学科4科目のうち「法規」だけが法令集という資料を持ち込みが可能です。
持込が可能だからといって、法規の問題を解いたことがある方は分かると思いますが、
一回引いてそのページだけで答えがさっと見つかるような問題はほとんどありません。
また、試験時間は計画と合わせて3時間です。
自分は法規に苦手だったこともあるのかもしれませんが、
計画は30分~40分で解き、法規には140分は費やすようにしました。
電卓を持っている方は叩いてみると分かりますが、法規の問題25問で5択とすると、140÷25÷5=1.12分。
計画の苦手な人で1時間かかる人なら、120÷25÷5=0.96分。
と一選択肢解くのに1分弱です。
短い時間を考えると、法令集を自分の引きやすいものにいかに作り上げていくかが大事だと思います。
ここで大事なのは「自分の引きやすい法令集」という点で、他人がどんなふうに作っていようが関係はないのです。
他の人が見たときに、全然わかんないやん。と言われても、自分が見たら無茶苦茶引きやすいというものならOKだと思います。
だから自分流が良いと思います。でも自分流を作るには他人の方法を知り、
その中から自分にあった物をピックアップして採用していくのが良いのではないでしょうか。
最初から自分流って言うのは難しいし、何から手を付けていいかわからないですからね。
--------------------------------------------------------------------------------
・線引きは定規を使用する
初受験の時、自分は線引きをフリーハンドで行っていました。
フリーハンドだと頑張ってきれいに引こうとすると時間がかかるし、
早く引こうとするとガタガタになってしまいます。
勉強を始めた頃、3月位はまだ良いかもしれませんが、
日が経ち、学科試験本番の7月中旬になると、汚い法令集をみると、
イライラしてしまいます。ただでさえうまくいかなくてあせっている時期なのに、
その法令集が追い討ちをかけてしまいます。
15センチ位の定規を利用して線を引くのが良いと思います。
自分はたまに二重線を引いたところもあります。たぶんフリーハンドではムリでしょう。
最初のうちは面倒と思うかもしれませんが、6月位になってくると効果がわかると思いますよ。
・インデックス貼り
市販の法令集は様々で、インデックスが付いているもの、ついてないものもあるようです。
自分はインデックスがあらかじめセットとして付いているものを利用してました。
自分で作る人もいるのでしょうが、自分にはそこまでの余裕がありませんでした。
まあどっちにしても、インデックス貼りは行ったことがある人は分かると思いますが結構時間が掛かります。
でも自分の場合は法令集を手に入れてすぐにインデックスを貼りました。
学校に行っている時、7月ごろ、自習室でインデックスをセッセと貼っている受講生がいましたが、
この人大丈夫なのかな?とこっちが不安になりました。
インデックス貼りをしていくことにより、細かい中身は分かりませんが、
法令集の作り、条文のつくりのようなものが見えてきます。
貼っている時にはこんなにいっぱい引かなくてはいけないの・・・・
と若干ブルーになりますが、インデックスを貼り終えたときには少し達成感を感じます。
そして法規の問題を解いていくわけですが、やはり自分の得意、不得意な部門というのが、
なんとなく分かってきます。
そういうとき自分はインデックス自体に色を付けたり、○を付けたりしました。
市販のものにセットされていたインデックスは法令集の右のスペースに貼りました。
法令集にはあと、上の部分と下の部分が有ります。ここを利用しない手もありません。
法令集の下部には法別表の部分に他より大きなインデックスを貼りました。
これは結構お薦めかもしれません。
あと自分の不得意分野は下部、上部に右側とダブルようでもインデックスを貼りました。
あと法規の一番最初の問題は用語問題です。建築基準法、施行令では最初に用語の条文がありますが、
よくそこではない部分から用語が出題されることが多いみたいです。
たとえば「避難階」などはいきなり出てきてもどこだか分かりません。
自分はそういった法規第1問に出そうな用語の部分にもインデックスを貼りました。
一問目からつまずくのは嫌ですからね。
基本のインデックス貼り → (問題を解きながら)インデックスの補足 → 弱点部にインデックス
の進め方が良いと思います。
・法別表部分を目立たせる
法令集の法別表の部分の小口に黒色を塗ります。
またインデックスの大きな物を貼る。
法別表は法規の問題を解く中で必ず1回は引きます。すぐに引きやすくしておくことが大事です。
また法別表は建築基準法と施行令の間にあるので、その区分けも一目で分かります。
・( )書きの中身を黄色蛍光ペンで塗る
法令に読みなれている人は良いかもしれませんが、条文は結構読みにくい文章になっています。
( )の中に( )があったりして、その上( )書きが5~10行もあったりして、
どこまでが( )の中身なのさ?と思ってしまうほどです。
自分はもともと文章を読むのが苦手であったせいもあるのですが、
( )の部分を黄色蛍光ペンで塗ってみると、どこまでが( )書きか分かりやすくなり、読み取りやすくなりました。
また( )の中の( )は緑の蛍光ペンで塗りつぶしました。
・問題を解いて、間違えた条文の横に印をうつ
問題集等を解いた時に、間違えた部分の横に・を付けます。
言葉を書くのはダメでしょうが、・を付けて文句を言われることはないと思います。
問題を解いた時に線引き+間違えた文に・を付けておくと、
後々自分の弱点となってくるところが見えてきます。
・線引きは細いペンを使う
よく赤鉛筆と青鉛筆で線引きを重ねていくことにより、その部分が濃くなって、
重要な部分が目立つを言われました。
確かにそれでよいのですが、自分は筆圧が高いほうなので、
重ねていくと多分紙が破れるだろうなーという怖さから鉛筆は使いませんでした。
自分の場合は特に細めのペン(0.3mm)を用意し、重ねるのではなく、
若干ずらしてもう一度線を引き、徐々に太くしていきました。
まあ塗り重ね方法と意味合いは同じなんですがね。笑
・関連条文は出発点も書き込む
自分の使っていた法令集には親切なことに関連条文のページが記載されていました。
それで十分なのかも知れませんが、自分の場合は、戻りのページも記載しました。
例えばAのページからBのページに飛んだとします。
Aのページには関連条文としてBのページ番号が書かれているとします。
こんどBのページからCのページへ飛びました。
それもBページからの関連条文としてCのページに飛んだとします。
そしてまたAのページに戻りたい時があるかもしれません。
そんなときにCのページに戻りとしてBのページ、そしてBのページには戻りとして、
Aのページを書いておくとスムーズに戻れますが、パージ数が書いてないと、
すんなり戻れないことが有ります。
法令集も引きなれてくると、5本の指を巧みに使い、A・B・Cの全てのページに指を挟みこみ、
Aのページを見失わないような対策が取れると思います。
しかし、ふとしたところで、Aのページの指が外れたことも考えて、
すぐに戻れるようにページをうっておくことをお薦めします。
持込が可能だからといって、法規の問題を解いたことがある方は分かると思いますが、
一回引いてそのページだけで答えがさっと見つかるような問題はほとんどありません。
また、試験時間は計画と合わせて3時間です。
自分は法規に苦手だったこともあるのかもしれませんが、
計画は30分~40分で解き、法規には140分は費やすようにしました。
電卓を持っている方は叩いてみると分かりますが、法規の問題25問で5択とすると、140÷25÷5=1.12分。
計画の苦手な人で1時間かかる人なら、120÷25÷5=0.96分。
と一選択肢解くのに1分弱です。
短い時間を考えると、法令集を自分の引きやすいものにいかに作り上げていくかが大事だと思います。
ここで大事なのは「自分の引きやすい法令集」という点で、他人がどんなふうに作っていようが関係はないのです。
他の人が見たときに、全然わかんないやん。と言われても、自分が見たら無茶苦茶引きやすいというものならOKだと思います。
だから自分流が良いと思います。でも自分流を作るには他人の方法を知り、
その中から自分にあった物をピックアップして採用していくのが良いのではないでしょうか。
最初から自分流って言うのは難しいし、何から手を付けていいかわからないですからね。
--------------------------------------------------------------------------------
・線引きは定規を使用する
初受験の時、自分は線引きをフリーハンドで行っていました。
フリーハンドだと頑張ってきれいに引こうとすると時間がかかるし、
早く引こうとするとガタガタになってしまいます。
勉強を始めた頃、3月位はまだ良いかもしれませんが、
日が経ち、学科試験本番の7月中旬になると、汚い法令集をみると、
イライラしてしまいます。ただでさえうまくいかなくてあせっている時期なのに、
その法令集が追い討ちをかけてしまいます。
15センチ位の定規を利用して線を引くのが良いと思います。
自分はたまに二重線を引いたところもあります。たぶんフリーハンドではムリでしょう。
最初のうちは面倒と思うかもしれませんが、6月位になってくると効果がわかると思いますよ。
・インデックス貼り
市販の法令集は様々で、インデックスが付いているもの、ついてないものもあるようです。
自分はインデックスがあらかじめセットとして付いているものを利用してました。
自分で作る人もいるのでしょうが、自分にはそこまでの余裕がありませんでした。
まあどっちにしても、インデックス貼りは行ったことがある人は分かると思いますが結構時間が掛かります。
でも自分の場合は法令集を手に入れてすぐにインデックスを貼りました。
学校に行っている時、7月ごろ、自習室でインデックスをセッセと貼っている受講生がいましたが、
この人大丈夫なのかな?とこっちが不安になりました。
インデックス貼りをしていくことにより、細かい中身は分かりませんが、
法令集の作り、条文のつくりのようなものが見えてきます。
貼っている時にはこんなにいっぱい引かなくてはいけないの・・・・
と若干ブルーになりますが、インデックスを貼り終えたときには少し達成感を感じます。
そして法規の問題を解いていくわけですが、やはり自分の得意、不得意な部門というのが、
なんとなく分かってきます。
そういうとき自分はインデックス自体に色を付けたり、○を付けたりしました。
市販のものにセットされていたインデックスは法令集の右のスペースに貼りました。
法令集にはあと、上の部分と下の部分が有ります。ここを利用しない手もありません。
法令集の下部には法別表の部分に他より大きなインデックスを貼りました。
これは結構お薦めかもしれません。
あと自分の不得意分野は下部、上部に右側とダブルようでもインデックスを貼りました。
あと法規の一番最初の問題は用語問題です。建築基準法、施行令では最初に用語の条文がありますが、
よくそこではない部分から用語が出題されることが多いみたいです。
たとえば「避難階」などはいきなり出てきてもどこだか分かりません。
自分はそういった法規第1問に出そうな用語の部分にもインデックスを貼りました。
一問目からつまずくのは嫌ですからね。
基本のインデックス貼り → (問題を解きながら)インデックスの補足 → 弱点部にインデックス
の進め方が良いと思います。
・法別表部分を目立たせる
法令集の法別表の部分の小口に黒色を塗ります。
またインデックスの大きな物を貼る。
法別表は法規の問題を解く中で必ず1回は引きます。すぐに引きやすくしておくことが大事です。
また法別表は建築基準法と施行令の間にあるので、その区分けも一目で分かります。
・( )書きの中身を黄色蛍光ペンで塗る
法令に読みなれている人は良いかもしれませんが、条文は結構読みにくい文章になっています。
( )の中に( )があったりして、その上( )書きが5~10行もあったりして、
どこまでが( )の中身なのさ?と思ってしまうほどです。
自分はもともと文章を読むのが苦手であったせいもあるのですが、
( )の部分を黄色蛍光ペンで塗ってみると、どこまでが( )書きか分かりやすくなり、読み取りやすくなりました。
また( )の中の( )は緑の蛍光ペンで塗りつぶしました。
・問題を解いて、間違えた条文の横に印をうつ
問題集等を解いた時に、間違えた部分の横に・を付けます。
言葉を書くのはダメでしょうが、・を付けて文句を言われることはないと思います。
問題を解いた時に線引き+間違えた文に・を付けておくと、
後々自分の弱点となってくるところが見えてきます。
・線引きは細いペンを使う
よく赤鉛筆と青鉛筆で線引きを重ねていくことにより、その部分が濃くなって、
重要な部分が目立つを言われました。
確かにそれでよいのですが、自分は筆圧が高いほうなので、
重ねていくと多分紙が破れるだろうなーという怖さから鉛筆は使いませんでした。
自分の場合は特に細めのペン(0.3mm)を用意し、重ねるのではなく、
若干ずらしてもう一度線を引き、徐々に太くしていきました。
まあ塗り重ね方法と意味合いは同じなんですがね。笑
・関連条文は出発点も書き込む
自分の使っていた法令集には親切なことに関連条文のページが記載されていました。
それで十分なのかも知れませんが、自分の場合は、戻りのページも記載しました。
例えばAのページからBのページに飛んだとします。
Aのページには関連条文としてBのページ番号が書かれているとします。
こんどBのページからCのページへ飛びました。
それもBページからの関連条文としてCのページに飛んだとします。
そしてまたAのページに戻りたい時があるかもしれません。
そんなときにCのページに戻りとしてBのページ、そしてBのページには戻りとして、
Aのページを書いておくとスムーズに戻れますが、パージ数が書いてないと、
すんなり戻れないことが有ります。
法令集も引きなれてくると、5本の指を巧みに使い、A・B・Cの全てのページに指を挟みこみ、
Aのページを見失わないような対策が取れると思います。
しかし、ふとしたところで、Aのページの指が外れたことも考えて、
すぐに戻れるようにページをうっておくことをお薦めします。













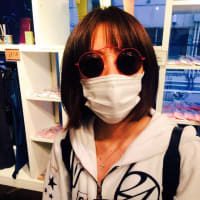






どうぞどうぞ
古い情報かもしれませんが、
是非参考にしてみて下さい!