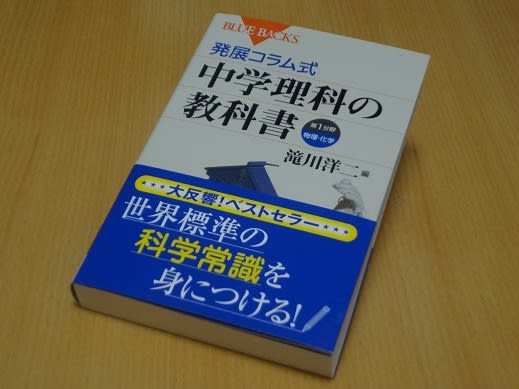
☆『発展コラム式 中学理科の教科書 第1分野(物理・化学)』(滝川洋二・編、講談社ブルーバックス)☆
中学の理科ってこんなにおもしろかったんだと思わせる本。とはいっても、曲がりなりにも大学理科系出身者の感想では説得力に欠けるかもしれない。しかし、中学時代、学校で習う理科がおもしろいと思ったことはなかった。とくに第1分野(物理・化学)は意味もわからずに公式を覚えさせられたり、計算問題ばかり解かせられたりした記憶だけが強く残っている。それでも、将来は大学の理科系に進み、いずれは科学者や技術者になりたいという夢だけは持ち続けていたように思う。それはやはり自然現象に興味があり、自然の神秘を解き明かすことや、口幅ったいが科学技術で世界に貢献することにロマンを感じていたからだろう。子どもは本来、自然現象や発明発見に興味を持っているものだと思う。そんな興味にこたえてくれる教科はもちろん理科であるはずだ。ところが、小学校までは理科好きだった子どもでも、中学生になって理科嫌いなる子どもが少なくないという。それはどうしてなのだろうか。
中学理科教師の情熱や力量はあえて問うまい。授業に創意工夫を試みる教師はきっと少なくないはずだから。やはりここで問われるべきは、いわゆる指導要領なのではないかと思う。この本には理科系出身者であっても、新たな発見や初めて腑に落ちたと思わせるような解説が少なくない。法則や原理が最新の科学技術とどのようにつながっているのか、その実例も多く紹介されている。恥ずかしながら一例を挙げれば、静電気とコピー機の関係などはまったく知らなかった。状態変化に関連して、地球とタイタン(土星の衛星)の比較なども興味深い。実際の授業でこのような話が紹介されないのは、時間的な制約も含めて指導要領のしばりがあるからではないかと推測する。
本書には「検定教科書をCHECK!」というコラムがところどころに挿入されている。小さいながらこのコラムこそが本書の核心をなす、いわば基本的な“哲学”を表現しているように思われる。たとえば、化学分野を理解する上で原子・分子などの粒子モデルは基本中の基本だと思うのだが、検定教科書ではかなり後にならないと出てこないという。また、電力を求める式が発展扱いになっていることや、エネルギーの概念が数式なしのため曖昧になっているとも指摘している。電力の簡単な計算やエネルギー概念の理解は、いまの時代にこそ必要不可欠なリテラシーであるはずだ。このような例を知ると、指導要領や検定教科書がどのような基準で作られているのか疑問に思われてくる。これを一歩進めれば、この不備を見直していくきっかけにもなるはずである。
国民の科学リテラシーを上げて、しいては国家の科学技術力を強化していくのは、中高生を理科系へと誘導させるよりも先に、高校どころか、中学レベルの理科に十分興味を持たせ徹底していくことこそ重要なのではないだろうか。この本にはその試みがよく表れているように思う。本書を読めば読むほど、自分が中卒だなんて恥ずかしくなってくる。中卒という学歴を揶揄しているのではない。中学レベルの理科さえも十分に身につけていないことが、とても恥ずかしく思えてくるのである。

中学の理科ってこんなにおもしろかったんだと思わせる本。とはいっても、曲がりなりにも大学理科系出身者の感想では説得力に欠けるかもしれない。しかし、中学時代、学校で習う理科がおもしろいと思ったことはなかった。とくに第1分野(物理・化学)は意味もわからずに公式を覚えさせられたり、計算問題ばかり解かせられたりした記憶だけが強く残っている。それでも、将来は大学の理科系に進み、いずれは科学者や技術者になりたいという夢だけは持ち続けていたように思う。それはやはり自然現象に興味があり、自然の神秘を解き明かすことや、口幅ったいが科学技術で世界に貢献することにロマンを感じていたからだろう。子どもは本来、自然現象や発明発見に興味を持っているものだと思う。そんな興味にこたえてくれる教科はもちろん理科であるはずだ。ところが、小学校までは理科好きだった子どもでも、中学生になって理科嫌いなる子どもが少なくないという。それはどうしてなのだろうか。
中学理科教師の情熱や力量はあえて問うまい。授業に創意工夫を試みる教師はきっと少なくないはずだから。やはりここで問われるべきは、いわゆる指導要領なのではないかと思う。この本には理科系出身者であっても、新たな発見や初めて腑に落ちたと思わせるような解説が少なくない。法則や原理が最新の科学技術とどのようにつながっているのか、その実例も多く紹介されている。恥ずかしながら一例を挙げれば、静電気とコピー機の関係などはまったく知らなかった。状態変化に関連して、地球とタイタン(土星の衛星)の比較なども興味深い。実際の授業でこのような話が紹介されないのは、時間的な制約も含めて指導要領のしばりがあるからではないかと推測する。
本書には「検定教科書をCHECK!」というコラムがところどころに挿入されている。小さいながらこのコラムこそが本書の核心をなす、いわば基本的な“哲学”を表現しているように思われる。たとえば、化学分野を理解する上で原子・分子などの粒子モデルは基本中の基本だと思うのだが、検定教科書ではかなり後にならないと出てこないという。また、電力を求める式が発展扱いになっていることや、エネルギーの概念が数式なしのため曖昧になっているとも指摘している。電力の簡単な計算やエネルギー概念の理解は、いまの時代にこそ必要不可欠なリテラシーであるはずだ。このような例を知ると、指導要領や検定教科書がどのような基準で作られているのか疑問に思われてくる。これを一歩進めれば、この不備を見直していくきっかけにもなるはずである。
国民の科学リテラシーを上げて、しいては国家の科学技術力を強化していくのは、中高生を理科系へと誘導させるよりも先に、高校どころか、中学レベルの理科に十分興味を持たせ徹底していくことこそ重要なのではないだろうか。この本にはその試みがよく表れているように思う。本書を読めば読むほど、自分が中卒だなんて恥ずかしくなってくる。中卒という学歴を揶揄しているのではない。中学レベルの理科さえも十分に身につけていないことが、とても恥ずかしく思えてくるのである。

























