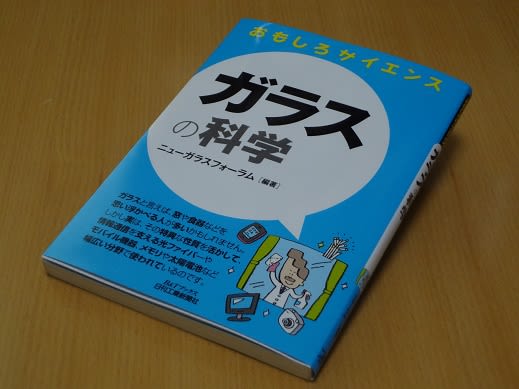
☆『ガラスの科学』(ニューガラスフォーラム・編著、日刊工業新聞社)☆
友人からご恵贈いただいた本。
一読して、語り口はやさしいのだが、内容を理解するのは相当むずかしいという印象をもった。高校生でも理解できる記述に努めていると「はしがき」に書かれているが、高校で履修する「化学」や「物理」の知識程度では、たぶん歯が立たないだろう。数式や化学式が羅列しているわけではない。むしろ、図や表も多用されていて、読者の理解を助けようとしている。しかし、本書に出てくる専門用語や図表と、高校で習う知識との隔たりはかなり大きく、本書を理解するには、その溝を埋めるための自分なりの勉強が必要になるだろう。やはり、これからガラスを専門的に研究しようという意欲をもった人が手に取るべき本であり、その人たちにとっては、良い指針になるかもしれない。
とはいえ、たまたまガラスとは何だろうと思い、本書を手にした人にとっても、益するところがないわけではない。第1章のガラスの科学的説明はたしかにむずかしい。しかし、第2章以降を読めば、正確な理解はできなくとも、ガラスが社会生活のあらゆる場面で使われていることに驚かされるし、未来に向けたガラスの高機能化は、われわれが持っているガラスのイメージを一新させる。
たとえば、光ファイバーやさまざまなディスプレイ装置へのガラスの応用は、よく知られていると思うが、ガラス製のハードディスクについては、知らない人が多いのではないだろうか。放射性廃棄物の固化にもガラスが用いられているが、原発の是非はともかくとして、タイムリーな話題といえるだろう。発電といえば、JAXAがSSPS(Space Solar Power Systems:宇宙空間での発電)の研究を行っているという。宇宙空間に設置された太陽電池に、鏡で反射した太陽光を照射し発電を行う。そのミラー(鏡)にもガラスが用いられるわけだが、さまざまな条件からフィルムのようにしなやかな超薄型のミラーが研究されているという。もし実現すれば、クリーンエネルギーの有力な候補になるかもしれない。これに限らず、ガラスは環境関連技術と関係が深いように思う。また、つい見逃してしまいそうだが、「Column」の記事もなかなかおもしろい。とくに歴史に関係したことなどは、ガラスについての雑学が増えそうで楽しく読める。
ふと立ち止まって考えてみると、ガラスのない生活など考えられないが、われわれはガラスのことをどれだけ知っているのだろうか。ガラスを知らない人などいないが、学校でガラスのことを習ったことがあっただろうか。手許に教科書がないので、最近の高校「化学」の参考書を見てみた。わずか数行の説明と、簡単な図表が載っているだけである。教科書はもっと少ない説明で終わっているかもしれない。そもそも授業でふれない可能性だってあるだろう。


だからといって、ガラスの説明をもっと増やすべきだとは思わない。金属の説明だって、電化製品や薬品の詳しい解説だってもっともっと必要かもしれない。しかしそんなことをいっていたら、どれだけの分量の本が必要になるか、どれだけの授業時間がいるのか、切りがなくなってしまう。高校までの「理科」ではやはり、科学の基本を身に付けさせることに重点をおくべきだろう。時間が許せば簡単な応用も射程において良いだろうが、具体的な応用例や最先端の話題については、研究者や技術者による出前授業などの活用がベストではないかと思う。社会人に対しては、サイエンスカフェなどの活用も同様である。
現職の研究者や技術者は各々の専門分野についての深い知識を有しているはずだが、その知識をわかりやすく(これは必ずしも程度を落とすことを意味しない)伝えるとともに、専門分野に対する「愛」を語ってほしいと思う。押し付けがましい「愛」ではなく、いわばふくよかな「愛」は、その分野の理解と裾野を広げることにつながるはずである。ちなみに、専門家は自らの専門について、「愛」の押し売りに陥りがちである。
この『ガラスの科学』は、ガラスについてわかりやすく説明しているとは必ずしも思わない。しかし、ガラスの応用例を広く紹介し、ガラスのもつさまざまな可能性にふれるなど、ガラスのことをもっと知ってもらいたいという意欲、すなわちガラスに対する「愛」は強く感じられるように思う。いま「ガラスのような」といえば、「固くて透明だが壊れやすい」といった意味にとることが多い。しかし、未来においてはこの意味が変わり、いまの意味は古語のようになるかもしれない。ガラスの研究者たちは、いわばガラスの意味を変えるべく日夜奮闘しているのだろうが、その「愛」はいまでも、「固くて透明」(純粋で断固としたもの)だが、けっして「壊れやすい」(もろい)「愛」ではない。本書には、少なくともそんな「愛」があふれている。

友人からご恵贈いただいた本。
一読して、語り口はやさしいのだが、内容を理解するのは相当むずかしいという印象をもった。高校生でも理解できる記述に努めていると「はしがき」に書かれているが、高校で履修する「化学」や「物理」の知識程度では、たぶん歯が立たないだろう。数式や化学式が羅列しているわけではない。むしろ、図や表も多用されていて、読者の理解を助けようとしている。しかし、本書に出てくる専門用語や図表と、高校で習う知識との隔たりはかなり大きく、本書を理解するには、その溝を埋めるための自分なりの勉強が必要になるだろう。やはり、これからガラスを専門的に研究しようという意欲をもった人が手に取るべき本であり、その人たちにとっては、良い指針になるかもしれない。
とはいえ、たまたまガラスとは何だろうと思い、本書を手にした人にとっても、益するところがないわけではない。第1章のガラスの科学的説明はたしかにむずかしい。しかし、第2章以降を読めば、正確な理解はできなくとも、ガラスが社会生活のあらゆる場面で使われていることに驚かされるし、未来に向けたガラスの高機能化は、われわれが持っているガラスのイメージを一新させる。
たとえば、光ファイバーやさまざまなディスプレイ装置へのガラスの応用は、よく知られていると思うが、ガラス製のハードディスクについては、知らない人が多いのではないだろうか。放射性廃棄物の固化にもガラスが用いられているが、原発の是非はともかくとして、タイムリーな話題といえるだろう。発電といえば、JAXAがSSPS(Space Solar Power Systems:宇宙空間での発電)の研究を行っているという。宇宙空間に設置された太陽電池に、鏡で反射した太陽光を照射し発電を行う。そのミラー(鏡)にもガラスが用いられるわけだが、さまざまな条件からフィルムのようにしなやかな超薄型のミラーが研究されているという。もし実現すれば、クリーンエネルギーの有力な候補になるかもしれない。これに限らず、ガラスは環境関連技術と関係が深いように思う。また、つい見逃してしまいそうだが、「Column」の記事もなかなかおもしろい。とくに歴史に関係したことなどは、ガラスについての雑学が増えそうで楽しく読める。
ふと立ち止まって考えてみると、ガラスのない生活など考えられないが、われわれはガラスのことをどれだけ知っているのだろうか。ガラスを知らない人などいないが、学校でガラスのことを習ったことがあっただろうか。手許に教科書がないので、最近の高校「化学」の参考書を見てみた。わずか数行の説明と、簡単な図表が載っているだけである。教科書はもっと少ない説明で終わっているかもしれない。そもそも授業でふれない可能性だってあるだろう。


だからといって、ガラスの説明をもっと増やすべきだとは思わない。金属の説明だって、電化製品や薬品の詳しい解説だってもっともっと必要かもしれない。しかしそんなことをいっていたら、どれだけの分量の本が必要になるか、どれだけの授業時間がいるのか、切りがなくなってしまう。高校までの「理科」ではやはり、科学の基本を身に付けさせることに重点をおくべきだろう。時間が許せば簡単な応用も射程において良いだろうが、具体的な応用例や最先端の話題については、研究者や技術者による出前授業などの活用がベストではないかと思う。社会人に対しては、サイエンスカフェなどの活用も同様である。
現職の研究者や技術者は各々の専門分野についての深い知識を有しているはずだが、その知識をわかりやすく(これは必ずしも程度を落とすことを意味しない)伝えるとともに、専門分野に対する「愛」を語ってほしいと思う。押し付けがましい「愛」ではなく、いわばふくよかな「愛」は、その分野の理解と裾野を広げることにつながるはずである。ちなみに、専門家は自らの専門について、「愛」の押し売りに陥りがちである。
この『ガラスの科学』は、ガラスについてわかりやすく説明しているとは必ずしも思わない。しかし、ガラスの応用例を広く紹介し、ガラスのもつさまざまな可能性にふれるなど、ガラスのことをもっと知ってもらいたいという意欲、すなわちガラスに対する「愛」は強く感じられるように思う。いま「ガラスのような」といえば、「固くて透明だが壊れやすい」といった意味にとることが多い。しかし、未来においてはこの意味が変わり、いまの意味は古語のようになるかもしれない。ガラスの研究者たちは、いわばガラスの意味を変えるべく日夜奮闘しているのだろうが、その「愛」はいまでも、「固くて透明」(純粋で断固としたもの)だが、けっして「壊れやすい」(もろい)「愛」ではない。本書には、少なくともそんな「愛」があふれている。

























