
数々のジャケット写真で知られていたウィリアム・クラクストンが、ドイツのジャズ評論家ヨアヒム・ベーレントから米国ジャズシーンの撮影を依頼される。それを一冊の写真集として出版した「Jazz Life」(Taschen 刊)にジョー・オーバニーのショットがあった。レスター・ヤングやパーカーと共演したピアニストだが、50年から60年代は重度の麻薬とアルコール中毒のため刑務所や療養所の生活が長く、シーンから忘れられた人である。
撮影されたのは1960年で一時的に体調が良かったときなのだろう。場所はフィル・スペクターが拠点として次々とヒット曲を生み出したハリウッドのゴールド・スター・スタジオなので、ポップスのレコーディングに呼ばれたのかもしれない。ピアノに向っている姿を斜め上からとらえたアングルで、1枚はピアノに向っていて音が聴こえてきそうなショットだが、もう1枚はカメラを上目遣いで睨み付けている。これが角度的にもパーカーと喧嘩をして歴史に残るダイアル・セッションに呼んでもらえなかったキレるジャンキーの心の闇をとらえているようで、その目は戦慄するほど怖い。これはホラー映画のワンシーンだと言われても疑わないだろう。
その恐怖映画の主人公が本格的にカムバックしたのは70年代に入ってからで、「Two's Company」は74年にベースのニールス・ペデルセンとデュオで録音されたものだが、空白の凡そ20年間のオーバニーは時間が止まっていたのかと思うほど完全なバップスタイルだ。タイム感覚に特色あるピアノで、ぎくしゃくした音とフレーズは不思議な魅力がある。完璧なベースを弾きこなすペデルセンとは異色の組み合わせのように思えるが、ペデルセンはベースを覚えた頃を思い出したかのようにバップのフレーズを刻む。ダメロン作の「If You Could See Me Now」というタイトルが二人の最高の出会いを表しているようだ。
クラクストンはその写真集でオーバニーを「The Elusive Pianist」と紹介している。捉えどころのないピアニストという意味だが、それはパーカーや、その前に参加したジョージ・オールドのバンドでも将来を嘱望されながら気性の激しさから喧嘩になり両バンドともクビになった才能あふれるピアニストを良く知っての表現だろう。パーカーはオーバニーを解雇したとはいえ、パウエルに次ぐ名ピアニストと賞賛している。
撮影されたのは1960年で一時的に体調が良かったときなのだろう。場所はフィル・スペクターが拠点として次々とヒット曲を生み出したハリウッドのゴールド・スター・スタジオなので、ポップスのレコーディングに呼ばれたのかもしれない。ピアノに向っている姿を斜め上からとらえたアングルで、1枚はピアノに向っていて音が聴こえてきそうなショットだが、もう1枚はカメラを上目遣いで睨み付けている。これが角度的にもパーカーと喧嘩をして歴史に残るダイアル・セッションに呼んでもらえなかったキレるジャンキーの心の闇をとらえているようで、その目は戦慄するほど怖い。これはホラー映画のワンシーンだと言われても疑わないだろう。
その恐怖映画の主人公が本格的にカムバックしたのは70年代に入ってからで、「Two's Company」は74年にベースのニールス・ペデルセンとデュオで録音されたものだが、空白の凡そ20年間のオーバニーは時間が止まっていたのかと思うほど完全なバップスタイルだ。タイム感覚に特色あるピアノで、ぎくしゃくした音とフレーズは不思議な魅力がある。完璧なベースを弾きこなすペデルセンとは異色の組み合わせのように思えるが、ペデルセンはベースを覚えた頃を思い出したかのようにバップのフレーズを刻む。ダメロン作の「If You Could See Me Now」というタイトルが二人の最高の出会いを表しているようだ。
クラクストンはその写真集でオーバニーを「The Elusive Pianist」と紹介している。捉えどころのないピアニストという意味だが、それはパーカーや、その前に参加したジョージ・オールドのバンドでも将来を嘱望されながら気性の激しさから喧嘩になり両バンドともクビになった才能あふれるピアニストを良く知っての表現だろう。パーカーはオーバニーを解雇したとはいえ、パウエルに次ぐ名ピアニストと賞賛している。










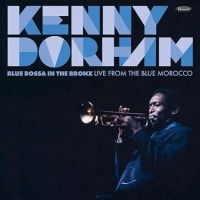

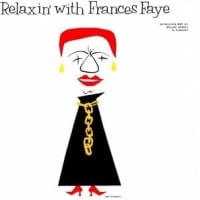

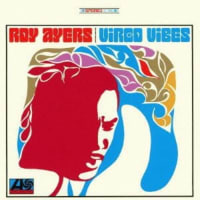

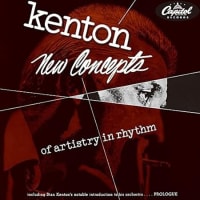


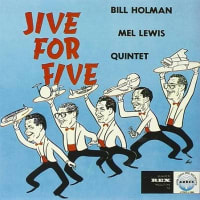
イフ・ユー・クッド・シー・ミー・ナウは、タッド・ダメロンがサラ・ヴォーンのために書いた曲ですが、その美しいメロディに魅せられて多くのプレイヤーが取り上げております。今週はピアノでお気に入りをお寄せください。ギターが入ったセッションも含みます。ホーンとヴォーカルはまたの機会に話題にします。
管理人 If You Could See Me Now Piano Best 3
Bill Evans / Moon Beams (Riverside)
Wynton Kelly - Wes Montgomery / Smokin' At The Half Note (Verve)
Kenny Drew / If You Could See Me Now (Steeple Chase)
他にもボビー・ティモンズをはじめジュニア・マンス、オスカー・ピーターソン、ローランド・ハナ、テテ・モントリュー、ジミー・コブ(ピアノはマッシモ・ファラオ)、マンハッタン・トリニティ、山下洋輔等々、多くのピアニストが演奏しております。持っておりませんが、寺井尚之さんは「Flanagania」で取り上げております。次回「OverSeas」を訪れたときにゲットしましょう。
Bill Evans Trio - If You Could See Me Now
http://www.youtube.com/watch?v=NXUxR4wunaE
今日はやられました。 それにしても、大谷くんの投手デビューは何時でしょうか?
dukeさんのベストはどれも素晴らしいですね!
僕はあと、ティモンズを挙げたいですね。
Easy Does It(Riverside)
これも、良いと思いますが、
一応、このティモンズとドリューとエヴァンスを聴きましたが、これベースを比較して聴くにも良いかと思いまして、 サムとペデルセンとイスラエルを中心に聴いてみました。
今日のところはサム・ジョーンズが一番と言うところで決定!
個人的には投手大谷くんが早く見たいのですが、そちらはどうなのでしょうか?
させたいところですね!
愚直なまでのバップへの拘り、感動的です。
初リーダー作「Blue High-land」から
なんと20年という悠久の時を経て、
満を持してリリースされたセカンド・アルバム。
ジョー・オーバニーの『TWO’S COMPANY』、久々に聴き返しながら書いておりますが、冒頭から引き込まれますね・・彼の世界に。もう片時たりとも耳を離せないと言いましょうか、ピアノの響きがジンジン胸に染みてきます。心がジャブジャブ洗われてゆくような、ヒンヤリとした清流に身を委ねてかのようなこの感覚・・こんな清らかな気持ちに浸らせてくれるジャズピアニストって他に思いつきません。僕にとっては神様のような存在です。
ご存じかと思いますが、ジョー・オーバニーが自身の演奏に乗せてジャズ半生を語った、それは素敵なドキュメンタリー・フィルムがYouTubeにありますので、リンクを貼らせて頂きます。未聴の方がいらしたらどうか51分56秒から始まる“Round Midnight”だけでもお聴きくださいませ、彼の「魂の籠ったピアノ」の凄みがヒシヒシと伝わってきます。
JOE ALBANY... A JAZZ LIFE 1980 Complete 60 min. Feature Documentary Film
http://www.youtube.com/watch?v=fnufLQMb6To
さてベスト3ですが、思いつきに乏しいので諸先輩方から借用させて頂きまして・・、
Joe Albany 『Two’s Company』(SteepleChase-1974)
Al Haig 『Invitation』(spotlite-1974)
Bobby Timmons 『Easy Does It 』(RIVERSIDE-1961)
それとWynton Kelly『Blues On Purpose』(Xanadu-1965)も。
ようやく中田君の一発でホーム白星を飾れましたのでホッとしております。
ティモンズも良い内容です。派手さはありませんがサム・ジョーンズのサポートは堅実でピアノに重みを与えているように聴こえます。
投手としての大谷君は2軍で実績を積んでからのデビューと思われます。もし投げるなら札幌ドームでしょうね。私も楽しみです。
太田寛二さんの貴重なアルバムのトップにありましたね。趣味が良いというのか、センスがあるというのか、実にバップなピアノです。
先日聴いた渡辺文男さんと小杉敏さんとも演奏しておりますので、機会があればこちらで聴きたいですね。札幌出身ですので燃えるでしょう。
オーバニーの「Two's Company」はストライクでしたか。あまり知られていないピアニストですので、熱心なファンがいるのは嬉しいことです。文学的な修辞句はさすがですね。オーバニーもオーバーとは言わんでしょう。(笑)
オーバニーのドキュメンタリー・フィルムのご紹介もありがとうございます。人間的には円くなっておりますね。若い頃はパーカーをはじめ全てのジャズ・プレイヤーが敵に見えた目も心も穏やかになったのでしょう。カムバック以降のピアノもバップ時と変わらぬ素晴らしいものですが、この円さが見えたならパーカーは使わなかったかもしれません。バップは戦場であることを良く知っている二人です。
トップにオーバニー、次いでのヘイグは奇しくも同じ年の録音でしたか。こちらもバップ・スタイルですが、ケニー・クラーク参加もあり流れを汲み取ったモダンな味付けです。タイトル曲の「Invitation」は幻想的ですね。近々話題にしましょう。
オーバニーのピアノを聴いていて「心がジャブジャブ洗われてゆくような、ヒンヤリとした清流に身を委ねているかのような感覚」になるというのは偽らざる正直な気持ちなんです。心の中のわだかまりが綺麗に洗い流されて浄化されていくような・・。
それは彼自身がそういう気持ちでピアノに向き合っているからなんじゃないかと僕は思うんです、まるで自身の救済のために弾いているみたい。先日、まん丸クミさまのブログ記事でお見かけしたような美しい教会の日曜礼拝でこんなピアノを奏でられたら、おそらく誰もが言葉を失うのではないでしょうか。
YouTubeのフィルムのラストの彼の表情、すごくステキな優しい笑顔でしょう?ああなるまでにどれほどの苦難があったことでしょう。そしてこの後、彼は脳梗塞で倒れてしまうんです。
> オーバニーもオーバーとは言わんでしょう。(笑)
いえ、そこは師匠的には「オーバニーもオーバーネーとは言わんでしょう。」のほうがよろしいかと・・笑。dukeさまと違って「思いつきに乏しい」僕が言うのもなんですけど^^;
1945年というバップの全盛期直前でバップにのめり込みながらも澄んだ曲なのだ。
歌モノが多いがピアノと制約がある、ソニー・ステイットと言いたいがダメだ!
Bobby Timmons /Easy Does It はアルバム全体が好きでよく聴く盤でこれが1位。
Bill Evans / Moon Beams (Riverside)
Wynton Kelly - Wes Montgomery / Smokin' At The Half Note (Verve)
ケリーはほかにも収録しているが、もうノリという意味でハーフノートライブ盤かな・・
エバンスが本当は一番この曲の本質を理解して弾いているような気がする。
ヘイグも良いが彼はいつも平穏無事な演奏にしてしまうのが・・聞くがわとしては消化不良になるのだ。
因みに私も以前この曲を弾いてみたが、この曲のコードチェンジを綺麗にやろうとすると難しくてやめた覚えがある。
ダメロンの好きな曲としては「グッドベイト」や「ダメロニア」が好きだ。
エバンスのように弾いてみたいもんだ・・・。
オーバニーは生粋のバップ・ピアニストですが、よく聴くとスウィング・ピアノの痕跡も見受けられます。そのスタイルがおっしゃる感覚につながるのかもしれませんね。
フィルムのラストの彼の表情と、記事で紹介した写真を比べますと、とても同じ人には見えません。年齢的な外見よりも大きく内側が変わったのでしょう。
>オーバーネー
こうきましたか。うまいですね。先日、スナックの帰り際、コートを出して、と言ったら年配のママはオーバーネーと言ったなぁ。