翌朝、我々の目の前には、広大なオレンジ色の甲板が出現していた。
「また、見事に錆びたねぇ…」
思わず感嘆するほど、昨日剥がした飛行甲板は鮮やかなオレンジ色になっている。
「さ、リブラ(Reブラスト)、リブラ!」
そのオレンジ色の飛行甲板で、我々はハイドロキャット-J(剥離用ロボット)を使い、幅300mmの銀色の帯を作って行く。
「どうですか、正男ちゃんは。すっかりキャットの操縦に慣れたみたいですね」
私は、腕組みをしながらホース台車を足で蹴っているハルに話し掛ける。
「そうだね、まあ正子は大丈夫だけど、ヨッシーは問題外だね」
ハルは六分(内径19mm)のエアホースを持って、キャットの側に立っている堂本を見て苦笑いをする。
「そう言えば正男ちゃん、日増しに臭くなってません?」
私の言葉を聞いたハルが、両手でホース台車を持つと一気に走り始める。私も他の台車に手をそえ、同じ様に走り出す。
「ガァあああああああ、ズガァあああああああ」
台車の樹脂製のタイヤが音を立て、甲板の上のサクションホースを大蛇のように移動させる。キャットを施行エリアの端でUターンさせる時は、一気にホースを移動させる方が仕事が速くなるからだ。
「木田さんは臭わないの?」
ハルはまた台車を足で軽く蹴りながら、須藤を顎でしゃくる。
「もちろん臭いますよ、行きも帰りも車の中が臭いし。あれは正男ちゃんの安全靴の臭いが凄いのかなぁ…」
「っちゃあ、木田さん、どうして俺がこんなに離れた場所でホースを動かしているか分かんないの?」
ハルがニヤリとする。
「は?」
「いや、は?じゃ無いって、正子の近くに行ってごらん」
ハルは満面の笑みを浮かべ、私に対して、手の甲をヒラヒラとさせている。
私はノンスキッド塗装(甲板のすべり止め塗装)の上を歩くと須藤に数メートルほど近寄り、なんとか臭いを嗅ごうとするが、特に過激な臭いはしない。
「ハルさん、そんなに臭わないけど?」
私はハルの元に戻ると、正直に言った。
「っちゃあ、そっちは風上でしょ、こっちからさぁ」
ハルはオレンジ色の錆をクリーニングした、銀色の鉄板を指差す。
「こっちね…」
私はホース台車の脇に積んであるシューズカバーを手に取り、安全靴に被せると、銀色のピカピカの鉄板の上を歩き始めた。
「ん?」
何かが私の鼻腔を刺激する。
「ウほっ、な、何か嗅いだ事がある臭いだ…」
私は急いでその場を離れると、ハルの元に戻った。
「大変、ハルさん、なんか新宿のガード下の、饐えた臭いがする…」
「でしょ、臭うでしょ、良かったよぉ、俺だけじゃ無くてさ!」
なぜかハルは大喜びをしている。
「やばくないですか、だって今の感じだと、5mくらいの距離でも臭いそうですよ」
私は自分で言いながら、顔をしかめた。
「何を言ってんの、風向きによっては、もっと離れていても臭うさぁ」
ハルは真顔で言っている。
「それってマジでヤバくないですか?」
「そうだよ、本当に臭いんだからさぁ、特に昼間に汗を掻き始めると本当に漂って来るんだから…」
ハルは口をへの字にして、首をブンブンと振る。
「S社の職人にばれると、『R社の奴等は臭いんだよ!』なんて言われちゃいますね」
「うひゃひゃひゃひゃ、そうさぁ、そんなこと言われたらたまんないよ!?正子をちゃんと風呂に入らせるのは、木田さんの仕事だかんね!」
私とハルが爆笑をしていると、なぜか堂本が我々のところにやって来た。
「どうしたの?」
「あの、自分、何か変でしたか?」
「…い、いや、何が?」
「うひゃひゃひゃひゃひゃ!」
ハルがしゃがみこんで笑い出す。
須藤も堂本も、我々には理解できない行動基準を持っているらしい。
「また、見事に錆びたねぇ…」
思わず感嘆するほど、昨日剥がした飛行甲板は鮮やかなオレンジ色になっている。
「さ、リブラ(Reブラスト)、リブラ!」
そのオレンジ色の飛行甲板で、我々はハイドロキャット-J(剥離用ロボット)を使い、幅300mmの銀色の帯を作って行く。
「どうですか、正男ちゃんは。すっかりキャットの操縦に慣れたみたいですね」
私は、腕組みをしながらホース台車を足で蹴っているハルに話し掛ける。
「そうだね、まあ正子は大丈夫だけど、ヨッシーは問題外だね」
ハルは六分(内径19mm)のエアホースを持って、キャットの側に立っている堂本を見て苦笑いをする。
「そう言えば正男ちゃん、日増しに臭くなってません?」
私の言葉を聞いたハルが、両手でホース台車を持つと一気に走り始める。私も他の台車に手をそえ、同じ様に走り出す。
「ガァあああああああ、ズガァあああああああ」
台車の樹脂製のタイヤが音を立て、甲板の上のサクションホースを大蛇のように移動させる。キャットを施行エリアの端でUターンさせる時は、一気にホースを移動させる方が仕事が速くなるからだ。
「木田さんは臭わないの?」
ハルはまた台車を足で軽く蹴りながら、須藤を顎でしゃくる。
「もちろん臭いますよ、行きも帰りも車の中が臭いし。あれは正男ちゃんの安全靴の臭いが凄いのかなぁ…」
「っちゃあ、木田さん、どうして俺がこんなに離れた場所でホースを動かしているか分かんないの?」
ハルがニヤリとする。
「は?」
「いや、は?じゃ無いって、正子の近くに行ってごらん」
ハルは満面の笑みを浮かべ、私に対して、手の甲をヒラヒラとさせている。
私はノンスキッド塗装(甲板のすべり止め塗装)の上を歩くと須藤に数メートルほど近寄り、なんとか臭いを嗅ごうとするが、特に過激な臭いはしない。
「ハルさん、そんなに臭わないけど?」
私はハルの元に戻ると、正直に言った。
「っちゃあ、そっちは風上でしょ、こっちからさぁ」
ハルはオレンジ色の錆をクリーニングした、銀色の鉄板を指差す。
「こっちね…」
私はホース台車の脇に積んであるシューズカバーを手に取り、安全靴に被せると、銀色のピカピカの鉄板の上を歩き始めた。
「ん?」
何かが私の鼻腔を刺激する。
「ウほっ、な、何か嗅いだ事がある臭いだ…」
私は急いでその場を離れると、ハルの元に戻った。
「大変、ハルさん、なんか新宿のガード下の、饐えた臭いがする…」
「でしょ、臭うでしょ、良かったよぉ、俺だけじゃ無くてさ!」
なぜかハルは大喜びをしている。
「やばくないですか、だって今の感じだと、5mくらいの距離でも臭いそうですよ」
私は自分で言いながら、顔をしかめた。
「何を言ってんの、風向きによっては、もっと離れていても臭うさぁ」
ハルは真顔で言っている。
「それってマジでヤバくないですか?」
「そうだよ、本当に臭いんだからさぁ、特に昼間に汗を掻き始めると本当に漂って来るんだから…」
ハルは口をへの字にして、首をブンブンと振る。
「S社の職人にばれると、『R社の奴等は臭いんだよ!』なんて言われちゃいますね」
「うひゃひゃひゃひゃ、そうさぁ、そんなこと言われたらたまんないよ!?正子をちゃんと風呂に入らせるのは、木田さんの仕事だかんね!」
私とハルが爆笑をしていると、なぜか堂本が我々のところにやって来た。
「どうしたの?」
「あの、自分、何か変でしたか?」
「…い、いや、何が?」
「うひゃひゃひゃひゃひゃ!」
ハルがしゃがみこんで笑い出す。
須藤も堂本も、我々には理解できない行動基準を持っているらしい。


















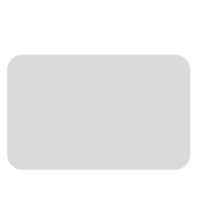

カミヤミさんの居住している県は、以前はデリすらほとんどありませんでしたねぇ。あとは怪しいピン○ロみたいな店と。
親方の性欲は、ヘルスで有名なA県N市で発散されていた模様ですね(笑)
しかし裁判って本当に疲れそうですね。私の感覚では、得られるお金(あるいは守るお金)が最低500万円くらいじゃないと割に合わない気がします。
訴えられたら、人生の貴重な時間の消耗って感じで、出来れば回避したいなぁ…。