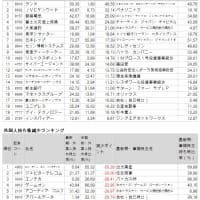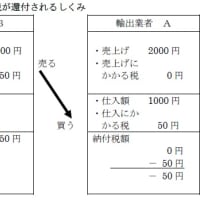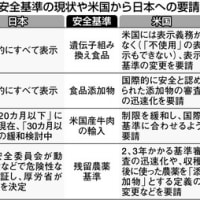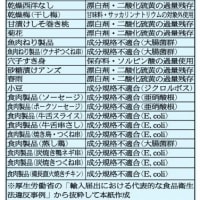なし崩し再稼動狙い 計画停電で「恫喝」 (東京新聞)
(東京新聞「こちら特報部」)
野田佳彦首相は八日、原発の再稼働方針をあらためて訴えた。
「暫定はない」と大阪市の橋下徹市長を追い込み、「国民生活が大切だ」と再稼働に慎重な民主党の小沢一郎元代表を皮肉った。主張の柱は、電力不足による計画停電の回避だ。
だが、関西の首長らが大飯原発再稼働で譲歩した後も「停電恫喝(どうかつ)」は続いている。
本当に原発抜きでは、計画停電は避けがたいのか。 (小倉貞俊、中山洋子)
「計画停電を回避するために最善を尽くす」。
野田首相は八日、記者会見でこう強調した。
「計画停電」は原発再稼働の切り札だ。政府が先月十八日に発表した今夏の電力需給対策にも、「実施しないことが原則」としつつも「大規模な電源脱落のために準備する」ことが示された。
再稼働阻止を訴えていた関西広域連合の首長たちが“腰砕け”になったのも、計画停電の恐れだった。
「環境派」で知られる滋賀県の嘉田由紀子知事ですら、「『計画停電は困る』という地元経済界からの強い要請」が容認をのむ最大の理由になった、と吐露した。
実際、滋賀経済同友会の小林正彦事務局長は「計画停電実施となれば、企業へのダメージは深刻だ。
『(計画停電が)実施されないなら、再稼働は仕方がない』という声は大きい」と話した。
それほどの不安感を与える計画停電は、そもそもどんなものなのか。
電力需要が供給を上回った際に起きる大規模停電を防ぐのが目的で、事前に地域や時間帯を予告する。
東京電力管内では昨年三月、計十日間にわたり実施された。
一回当たり三時間ほどの停電だが、市民生活に多くの混乱をもたらした。
だが、この時の計画停電が本当に必要だったのかについては議論の余地がある。
環境エネルギー政策研究所は当時、「大口契約者と結んでいる(電気料金を値引く代わりに電力使用を抑えてもらう)『需給調整契約』を生かせば、計画停電を強行しなくても電力は足りる」と試算していた。
ちなみに今夏の東電管内の電力供給力は、昨夏から柏崎刈羽原発の5~7号機が止まったにもかかわらず、約三百万キロワットも余裕が出る見通しだ。
不可解な部分もある。
政府は今夏の関西電力管内での電力不足で、“最終手段”である計画停電ばかりを持ち出すが、昨夏に東電と東北電力管内で発動された「電力使用制限令」については今回、見送っている。
企業に節電を義務付ける同制限令は昨年七月、政府が約二カ月にわたって発動。
大企業など大口需要家に電力使用量の15%削減を義務付けた。
それが今回は見送られ、最初から一般家庭や中小零細企業にしわ寄せが集中する計画停電が、前面に押し出された。
自然エネルギーの普及に取り組むエナジーグリーンの竹村英明副社長は「今夏の電力需給は、政府も関電も昨年から分かっていたはずだ。
にもかかわらず、火力発電の整備を意図的に避け、計画停電をちらつかせた。
再稼働ありきの『脅し』にしか見えない」と語る。
気になるのは、関西広域連合が大飯原発3、4号機の再稼働を容認した後も、計画停電の“合唱”が続いている点だ。
関電を含めた電力各社は、計画停電を大仰に準備。緊急時のマニュアル作りにすぎない「計画停電案」を振りかざす。
これほど「計画停電」が取り沙汰されること自体に違和感はないか。
政府は原発なしの夏を「節電努力」で乗り切れるとしていた。
夏の電力需給対策では、夏の約二カ月間、関西電力管内で猛暑だった二〇一〇年夏より、電力消費を15%程度抑えるよう企業や家庭に節電要請することになっている。
中部、北陸、中国、四国電力にも節電を求め、その浮いた分を関西に送るという支援策もまとめていた。
この間、関西電力は、改善策を小出しにしている。四月には不足分を16・3%と説明していたが、その後に14・9%に圧縮。
大阪府市エネルギー戦略会議で見積もりの甘さを再三追及され、五月中旬には、不足分を約5%にまで減らす試算を同会議に提示していた。
他の電力会社から最大百六十二万キロワットの供給を受けるほか、自社の水力発電で二十二万キロワット、卸電力取引所から十八万キロワットなどと供給を上積み。
企業との需給調整契約を広げて需要を減らし、緊急時に企業から節電分を買い取る「ネガワット入札」まで考慮した。
「再稼働なしを前提にして、なんとかなるはずだった」。
同会議のメンバーで富士通総研経済研究所の高橋洋主任研究員は振り返る。
「不足幅はまだ縮むはずだった」
高橋氏は需給見通しの前提になっている日本全体の最大需要の計算が、大きすぎる点にも着目。
「各電力会社の最大値を合算しているが、同じ日の同じ時間帯に全国のピークが一致することはない。
現実には存在しない数値で、西日本のピーク需要は下がるはずだ」 同会議で、関電の需給見通しの甘さを指摘していた環境エネルギー政策研究所の飯田哲也所長も「節電目標に向かって議論をしていた。
十分乗り切れるはずだった。
しかし、先月に入り、唐突に節電を無視した『計画停電』の回避に話がすり替わった」と説明する。
この転換が関西の企業を一気におびえさせた。
それが首長たちへの圧力となり、野田首相も会見で繰り返した。
首相は「期間限定」という妥協案については「夏場限定の再稼働では国民生活を守れない」と拒否した。
この一言は、関西における夏場の緊急時のための再稼働という大義名分を超え、その真意がなし崩しの原発再稼働であることを示唆している。
前出の竹村副社長によると、昨年三月の震災後、都内の企業の多くは十分な節電準備もできなかったにもかかわらず、照明を落とす程度で、一~二割の電力を削減できていたという。
「東電管内の企業は省エネでコストも削減できることを経験した。
節電は企業活動にとってマイナスばかりではない」と指摘しながら続ける。
「結局のところ、電気が足りるかどうかは、再稼働とは関係ない。
電力事業者が昨年、禁断の計画停電を強行して東日本にショックを与えた。
それを関西での再稼働への材料に使っている」。
この手法は関電管内にとどまらない恐れがある。
<デスクメモ>
野田首相は原発の安全に「絶対はない」と言った。
創意工夫による「原発ゼロの夏」という挑戦にも絶対はない。
では、どちらを取るべきか。
使用済み核燃料は処理できず、再稼働してもあふれるのは時間の問題だ。
道はこうある。
希望のある挑戦か。
絶望しかない安寧か。
敗北感に浸るにはまだ早い。
(牧)
(東京新聞「こちら特報部」)
野田佳彦首相は八日、原発の再稼働方針をあらためて訴えた。
「暫定はない」と大阪市の橋下徹市長を追い込み、「国民生活が大切だ」と再稼働に慎重な民主党の小沢一郎元代表を皮肉った。主張の柱は、電力不足による計画停電の回避だ。
だが、関西の首長らが大飯原発再稼働で譲歩した後も「停電恫喝(どうかつ)」は続いている。
本当に原発抜きでは、計画停電は避けがたいのか。 (小倉貞俊、中山洋子)
「計画停電を回避するために最善を尽くす」。
野田首相は八日、記者会見でこう強調した。
「計画停電」は原発再稼働の切り札だ。政府が先月十八日に発表した今夏の電力需給対策にも、「実施しないことが原則」としつつも「大規模な電源脱落のために準備する」ことが示された。
再稼働阻止を訴えていた関西広域連合の首長たちが“腰砕け”になったのも、計画停電の恐れだった。
「環境派」で知られる滋賀県の嘉田由紀子知事ですら、「『計画停電は困る』という地元経済界からの強い要請」が容認をのむ最大の理由になった、と吐露した。
実際、滋賀経済同友会の小林正彦事務局長は「計画停電実施となれば、企業へのダメージは深刻だ。
『(計画停電が)実施されないなら、再稼働は仕方がない』という声は大きい」と話した。
それほどの不安感を与える計画停電は、そもそもどんなものなのか。
電力需要が供給を上回った際に起きる大規模停電を防ぐのが目的で、事前に地域や時間帯を予告する。
東京電力管内では昨年三月、計十日間にわたり実施された。
一回当たり三時間ほどの停電だが、市民生活に多くの混乱をもたらした。
だが、この時の計画停電が本当に必要だったのかについては議論の余地がある。
環境エネルギー政策研究所は当時、「大口契約者と結んでいる(電気料金を値引く代わりに電力使用を抑えてもらう)『需給調整契約』を生かせば、計画停電を強行しなくても電力は足りる」と試算していた。
ちなみに今夏の東電管内の電力供給力は、昨夏から柏崎刈羽原発の5~7号機が止まったにもかかわらず、約三百万キロワットも余裕が出る見通しだ。
不可解な部分もある。
政府は今夏の関西電力管内での電力不足で、“最終手段”である計画停電ばかりを持ち出すが、昨夏に東電と東北電力管内で発動された「電力使用制限令」については今回、見送っている。
企業に節電を義務付ける同制限令は昨年七月、政府が約二カ月にわたって発動。
大企業など大口需要家に電力使用量の15%削減を義務付けた。
それが今回は見送られ、最初から一般家庭や中小零細企業にしわ寄せが集中する計画停電が、前面に押し出された。
自然エネルギーの普及に取り組むエナジーグリーンの竹村英明副社長は「今夏の電力需給は、政府も関電も昨年から分かっていたはずだ。
にもかかわらず、火力発電の整備を意図的に避け、計画停電をちらつかせた。
再稼働ありきの『脅し』にしか見えない」と語る。
気になるのは、関西広域連合が大飯原発3、4号機の再稼働を容認した後も、計画停電の“合唱”が続いている点だ。
関電を含めた電力各社は、計画停電を大仰に準備。緊急時のマニュアル作りにすぎない「計画停電案」を振りかざす。
これほど「計画停電」が取り沙汰されること自体に違和感はないか。
政府は原発なしの夏を「節電努力」で乗り切れるとしていた。
夏の電力需給対策では、夏の約二カ月間、関西電力管内で猛暑だった二〇一〇年夏より、電力消費を15%程度抑えるよう企業や家庭に節電要請することになっている。
中部、北陸、中国、四国電力にも節電を求め、その浮いた分を関西に送るという支援策もまとめていた。
この間、関西電力は、改善策を小出しにしている。四月には不足分を16・3%と説明していたが、その後に14・9%に圧縮。
大阪府市エネルギー戦略会議で見積もりの甘さを再三追及され、五月中旬には、不足分を約5%にまで減らす試算を同会議に提示していた。
他の電力会社から最大百六十二万キロワットの供給を受けるほか、自社の水力発電で二十二万キロワット、卸電力取引所から十八万キロワットなどと供給を上積み。
企業との需給調整契約を広げて需要を減らし、緊急時に企業から節電分を買い取る「ネガワット入札」まで考慮した。
「再稼働なしを前提にして、なんとかなるはずだった」。
同会議のメンバーで富士通総研経済研究所の高橋洋主任研究員は振り返る。
「不足幅はまだ縮むはずだった」
高橋氏は需給見通しの前提になっている日本全体の最大需要の計算が、大きすぎる点にも着目。
「各電力会社の最大値を合算しているが、同じ日の同じ時間帯に全国のピークが一致することはない。
現実には存在しない数値で、西日本のピーク需要は下がるはずだ」 同会議で、関電の需給見通しの甘さを指摘していた環境エネルギー政策研究所の飯田哲也所長も「節電目標に向かって議論をしていた。
十分乗り切れるはずだった。
しかし、先月に入り、唐突に節電を無視した『計画停電』の回避に話がすり替わった」と説明する。
この転換が関西の企業を一気におびえさせた。
それが首長たちへの圧力となり、野田首相も会見で繰り返した。
首相は「期間限定」という妥協案については「夏場限定の再稼働では国民生活を守れない」と拒否した。
この一言は、関西における夏場の緊急時のための再稼働という大義名分を超え、その真意がなし崩しの原発再稼働であることを示唆している。
前出の竹村副社長によると、昨年三月の震災後、都内の企業の多くは十分な節電準備もできなかったにもかかわらず、照明を落とす程度で、一~二割の電力を削減できていたという。
「東電管内の企業は省エネでコストも削減できることを経験した。
節電は企業活動にとってマイナスばかりではない」と指摘しながら続ける。
「結局のところ、電気が足りるかどうかは、再稼働とは関係ない。
電力事業者が昨年、禁断の計画停電を強行して東日本にショックを与えた。
それを関西での再稼働への材料に使っている」。
この手法は関電管内にとどまらない恐れがある。
<デスクメモ>
野田首相は原発の安全に「絶対はない」と言った。
創意工夫による「原発ゼロの夏」という挑戦にも絶対はない。
では、どちらを取るべきか。
使用済み核燃料は処理できず、再稼働してもあふれるのは時間の問題だ。
道はこうある。
希望のある挑戦か。
絶望しかない安寧か。
敗北感に浸るにはまだ早い。
(牧)