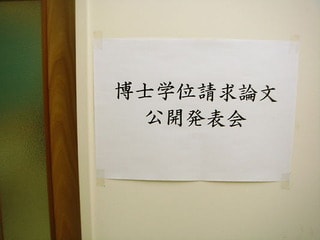
【経過】
勤務する大学に博士課程ができて、最初の卒業生が出ようとしています。
定員3名。3年間の課程を終えて、先週土曜日と、今週月曜日の口頭試問を終えたのが5名。
昨日と、今日、
「公開発表会」があります。
この公開発表会での発表と質疑を終えてから、来週、合否の投票があります。私が勤務する大学院では、すでに口頭試問で合格の結果を得た人だけが公開発表会で発表できる、という仕組みです。
【出席】
会場は、キャンパス内の会議室です。
博士課程の学生。
博士課程を指導する教員。
その他、日程を掲示してあるのですが、他のコース(国際文化研究科など)の院生。
総勢20名ほど。
この発表会の内容を踏まえて、聞いていた先生方のうち博士課程を担当する教員による会議が来週開催されて、投票によって最終的に合否が決定する。
参加人数は少ないのですが、来週の投票を行う教員が出席していて、発表内容を踏まえた審議と投票を控えているためか張り詰めた空気が漂います。
【ドイツから学ぶ】
昨日の発表会では、2件の発表が行われました。
持ち時間は60分。発表40分、質疑20分。
まだ、審査の途中ともいえるので、詳しくお伝えするというよりは、そのポイントを簡単にお伝えします。会場の写真も控えました。写真は、会場の会議室の入り口の張り紙。
「方面委員制度とエルバーフェルト制度の連繋に関する研究ー
大阪府方面委員制度源流考論ー」
「ドイツ介護保障の構造的研究」
と、2件とも、ドイツの研究を通じて、日本の課題を明らかにしようとしています。
いわゆる文献研究で、2件とも、膨大な、日本語、そしてドイツ語の文献を読んでの考察です。
2人とも、女性で、勤務する大学の修士課程の出身です。現在、勤務する大学の非常勤講師を務めている。
【福祉の担い手】
最初の研究は、
民生委員制度のもとになった戦前の「方面委員」制度の歴史を考察しています。
ドイツにおいては、
ハンブルグの制度→エバーフェルト制度→ストラスブルグ制度へと発展があった。
日本でも、
岡山の済生制度→大阪の方面委員→全国的な方面委員制度→民生委員
と、発展している。
このテーマの根本には、
「福祉の担い手は誰か?」という基本的な問題意識があります。
民生委員の評価は分かれるでしょうが、この研究には、鹿児島における民生委員の歴史的な評価が背景にあります。
関連して、
セーフティネット
社会福祉を管轄する行政
ソーシャルワーカーなどの専門職
といった重要なテーマがありますね。
ドイツ語ということもあって、先行研究が少ない分野ですが、この研究には、現在までの、日本の、そしてドイツでの研究の成果を踏まえています。
この研究の結論:
「日本では、ドイツの制度を参考にしたが、日本独自の制度を編み出している。この制度として歴史的に日本に蓄積されたものはこれからも重要である」
といったところでしょうか。
【介護保障の穴】
2番目の研究は、
ドイツの介護保険制度の構造を解明して、それが日本とはどのように違っているか
を明らかにしています。
この分野の先行研究はかなりあるのですが、
いま、改めて、ドイツの法制を学ぶ意味はどこにあるのか?
という問題意識に答えています。
「ドイツの介護保障の特色は、介護扶助にある」
という結論には力がこもっていました。
日本には、介護保険を受けられず、かといって、介護扶助でも救済されない・・
ということが起こりうる法制になっているからです。
私は、質疑の中で、
「何故そうなったのか?」
について感想を述べました。
【博士課程は違うなぁ】
2つの研究とも、質疑が緊迫していて勉強になりました。
先日、修士課程の審査を終えたばかりですが、さすがに博士課程の口頭試問、そして公開発表、その質疑応答は真剣勝負といった雰囲気で勉強になりました。
私は、聞いていただけなのに、夕方はぐったりして、何もしないで寝てしまいました。
今日の午後には、残る3件の発表があります。
勤務する大学に博士課程ができて、最初の卒業生が出ようとしています。
定員3名。3年間の課程を終えて、先週土曜日と、今週月曜日の口頭試問を終えたのが5名。
昨日と、今日、
「公開発表会」があります。
この公開発表会での発表と質疑を終えてから、来週、合否の投票があります。私が勤務する大学院では、すでに口頭試問で合格の結果を得た人だけが公開発表会で発表できる、という仕組みです。
【出席】
会場は、キャンパス内の会議室です。
博士課程の学生。
博士課程を指導する教員。
その他、日程を掲示してあるのですが、他のコース(国際文化研究科など)の院生。
総勢20名ほど。
この発表会の内容を踏まえて、聞いていた先生方のうち博士課程を担当する教員による会議が来週開催されて、投票によって最終的に合否が決定する。
参加人数は少ないのですが、来週の投票を行う教員が出席していて、発表内容を踏まえた審議と投票を控えているためか張り詰めた空気が漂います。
【ドイツから学ぶ】
昨日の発表会では、2件の発表が行われました。
持ち時間は60分。発表40分、質疑20分。
まだ、審査の途中ともいえるので、詳しくお伝えするというよりは、そのポイントを簡単にお伝えします。会場の写真も控えました。写真は、会場の会議室の入り口の張り紙。
「方面委員制度とエルバーフェルト制度の連繋に関する研究ー
大阪府方面委員制度源流考論ー」
「ドイツ介護保障の構造的研究」
と、2件とも、ドイツの研究を通じて、日本の課題を明らかにしようとしています。
いわゆる文献研究で、2件とも、膨大な、日本語、そしてドイツ語の文献を読んでの考察です。
2人とも、女性で、勤務する大学の修士課程の出身です。現在、勤務する大学の非常勤講師を務めている。
【福祉の担い手】
最初の研究は、
民生委員制度のもとになった戦前の「方面委員」制度の歴史を考察しています。
ドイツにおいては、
ハンブルグの制度→エバーフェルト制度→ストラスブルグ制度へと発展があった。
日本でも、
岡山の済生制度→大阪の方面委員→全国的な方面委員制度→民生委員
と、発展している。
このテーマの根本には、
「福祉の担い手は誰か?」という基本的な問題意識があります。
民生委員の評価は分かれるでしょうが、この研究には、鹿児島における民生委員の歴史的な評価が背景にあります。
関連して、
セーフティネット
社会福祉を管轄する行政
ソーシャルワーカーなどの専門職
といった重要なテーマがありますね。
ドイツ語ということもあって、先行研究が少ない分野ですが、この研究には、現在までの、日本の、そしてドイツでの研究の成果を踏まえています。
この研究の結論:
「日本では、ドイツの制度を参考にしたが、日本独自の制度を編み出している。この制度として歴史的に日本に蓄積されたものはこれからも重要である」
といったところでしょうか。
【介護保障の穴】
2番目の研究は、
ドイツの介護保険制度の構造を解明して、それが日本とはどのように違っているか
を明らかにしています。
この分野の先行研究はかなりあるのですが、
いま、改めて、ドイツの法制を学ぶ意味はどこにあるのか?
という問題意識に答えています。
「ドイツの介護保障の特色は、介護扶助にある」
という結論には力がこもっていました。
日本には、介護保険を受けられず、かといって、介護扶助でも救済されない・・
ということが起こりうる法制になっているからです。
私は、質疑の中で、
「何故そうなったのか?」
について感想を述べました。
【博士課程は違うなぁ】
2つの研究とも、質疑が緊迫していて勉強になりました。
先日、修士課程の審査を終えたばかりですが、さすがに博士課程の口頭試問、そして公開発表、その質疑応答は真剣勝負といった雰囲気で勉強になりました。
私は、聞いていただけなのに、夕方はぐったりして、何もしないで寝てしまいました。
今日の午後には、残る3件の発表があります。

























