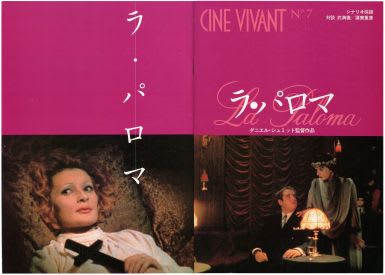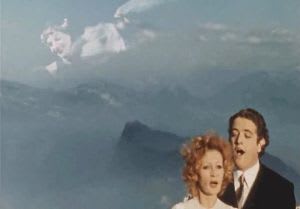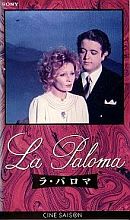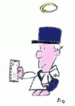ひょんなことから昔みた映画を見直しました。タイトルは「唇からナイフ」。 コメディアクション映画です。 貴方は観たでしょうか?

こんなんです。

 パンフレット/表紙
パンフレット/表紙


「唇からナイフ」 パンフレット A4 1966
「唇からナイフ」 原題 Modesty Blaise(モデスティ・ブレイズ) イギリス・1966年製作 カラー 118分

監督:ジョセフ・ロージー
出演:モニカ・ヴィッティ (女泥棒モデスティ・ブレイズ)
:ダーク・ボガード(国際犯罪組織の大物ガブリエル)
:テレンス・スタンプ(モデスティ・ブレイズの相棒ウイリー)

☆解説: 世界的に有名(らしい)なイギリスの漫画「モデスティ・ブレイズ Modesty Blaise」の映画化。『エヴァの匂い』や『召使』のジョセフ・ロージー監督がコメディアクションに挑戦。出演は女泥棒を演じるモニカ・ヴィッティ、 その相棒をテレンス・スタンプがつとめ、マザコンの悪漢を怪演する微笑ましいダーク・ボガード。コミックのヒーロー・ヒロインらしくどなたもあたりかまわずの大活躍!

☆あらすじ: (有って無いようなものですが・・・。)
イギリスは、中東マサラ国の石油をえる際、同国の元首シークの要望を聞き入れた見返りとして、ダイヤモンドを送ることにした。このことが国際犯罪組織の知るところとなり、イギリス秘密情報部長のタラントは女犯罪者・モデスティにダイヤの護衛を依頼する。その際、彼女は相棒のウィリーを協力者としてつけるという条件で引き受ける。 犯罪組織のリーダー・バシリオはモデスティをおびき寄せる形でウィリーを捕らえたうえで、ダイヤを盗んだ。モデスティは色仕掛けと変装でウィリーとダイヤを奪還するが、組織に見つかり窮地に陥る。・・(後略) ーウィキペディア(Wikipedia)よりー

どお?よ~分からないでしょ。 この僕でもよ~分からなかったんだから。 登場するこれらの大物スターが自分たちの役どころからかけ離れたコミカルな演技で、観るものを驚かせたり、戸惑わせたり。 おそらく演じる方もそれを観る方もどちらもワクワク・ドキドキ・ゾクゾクしながら楽しんでたんじゃないでしょうか?

そもそもジョセフ・ロージー監督のコメディ映画は珍しい。 そしてモニカ・ヴィッティがこのような映画に出るのって珍しい。 ダーク・ボガードやテレンス・スタンプもこんな役は珍しい。 これだけの珍しづくしも珍しい。 モニカのぶっ飛んだファッションやボガードのなんじゃこりゃ変身、モデスティ(モニカ・ヴィッティ)危うしで救援に突如現れる大軍団の唐突さ。思わず拍手!ギャグあり、涙なしの全編コレ突飛だらけ!これはもうゴボウあり、こんにゃくあり、人参、油揚げ、干し椎茸ありのまるで賑やかな役者ぞろいの五目ごはんと言うか、かやくご飯の大爆発。 (五目ごはんがお好き?)

こんな豪華絢爛な五目ごはんを更にポップでキッチュなキラキラの五目、いや天目茶碗にてんこ盛り。さあドぉだ!とばかりに愉しげなデュエットもふりかけて、これでもかのドンチャン騒ぎ。

少しお疲れが過ぎたのかペースダウンの処もありながら、ひたすらごちゃ混ぜのノー天気が煌めきわたった、笑っちゃうしかない実におかしな映画でありました。 登場する車はどれもウフフだったし、後半の舞台となる地中海を臨む絶壁にたつ悪漢どものアジトなんかは、 いかにも悪の巣窟あるあるです。ピッタリ!そのロケーションの素晴らしさは息を呑みます。とにもかくにも楽しい映画デス。 僕は好きです。(笑)



ジャ~ン、これが悪漢どものアジトだ!
(サンタレッシオ シークロ城 Castello di Sant'Alessio Siculo・伊)

今日の目線で見ればその出来栄えに物足りなさを言い言いしたいところかもしれませんが、それは曜変天目茶碗を偉大な失敗作だと言うようなものかもしれませんねエ。 (曜変天目茶碗もお好き?)
結果をどお愉しむかは受取る側次第なので大いに論じ合うのも楽しいですよね。
こんなヒッチャカメッチャカな作品を見てしまった当時の僕なんかはもう頭の中もスッカリ、すっちゃかめっちゃかになっちゃって、ただボ~ッとトランス状態になっていたのを思いだしたぞ!(今も変わりません。) 後半テンポがおちて残念なんて言わないけど、(言ってる) このようなよくわからない作品は二度と作れないでしょうし、作らないでしょうね。ってあの時さすがに思ってしまいました。
ついでに思いだしたんだけど、 あの頃世の中は高度経済成長期で僕は *♪ノッテけ、ノッテけ、ノッテけ♪って皆が誘うもんだから、よく分からずに、じゃあ僕も一緒にノッケて、ノッケて、ノッケてってノッケてもらい、オイルショックも何のその、またまたバブルで景気も良くなり勢いづいて遊びに遊び、皆でこのままノッとけ、ノッとけ、ノッとけと調子にノッてたら、 世の中 そおそお調子よいことばかりは続きません。とほほバブルがパッチンとハジけて一斉にひっくり返っちゃった。あとは散々。ご想像にお任せします。でも、ノリやすい僕が何んとか今日までやってこられたのも、ひとえに、僕の努力のおかげだったんデス。 僕って凄~い‼ (・・・長生きして下さい。)

* ♪太陽の彼方に♪ 曲:アストロノウツ。 1964年日本でシングルリリースされました。寺内タケシとブルージーンズをバックに藤本好一の歌でお馴染み(?)
と、言うことで (どう言うこと?) この映画は僕にとってあの大変だった時代のはしりの良き時代の気分を映し出した傑作・怪作でありました。ある意味ぼくにとって心地よい快作でもあったんです。

コレだけの破茶滅茶をやってのけられたのはさすがに良くも悪くもジョセフ・ロージー監督ならではかもしれません。 成功作だとか失敗作だとかを尽き抜けた、味の効いた豪華なハチャメチャ映画と言うしかないんじゃないのぉ? 最後に捕えられた悪漢ガブリエル(ダーク・ボガード)が銃口を突きつけられて言ったセリフなんゾ、ニクイねぇ~。 ダーク・ボガードなればこそですね。このように随所に蒔かれたギャグやしぐさには、唯、おもしろいだけじゃ終わらせないジョセフ・ロージー監督の企らみがあり、僕たちはまんまとノセられたって感じかな?

僕としてはまるで"アンニュイ"がそっくりそのまま女性になったようなモニカ・ヴィッティのカッコいい、生き生きと甦った はしゃぎっぷりを2時間弱たっぷり見られただけでも、もぉ~大満足です。 最初に観たのと今回で二度美味しかったというのが僕の至極他愛のない感想でありました。 (それだけ?) ハイ、それだけです。
こんなんです。
 パンフレット/表紙
パンフレット/表紙
「唇からナイフ」 パンフレット A4 1966
「唇からナイフ」 原題 Modesty Blaise(モデスティ・ブレイズ) イギリス・1966年製作 カラー 118分
監督:ジョセフ・ロージー
出演:モニカ・ヴィッティ (女泥棒モデスティ・ブレイズ)
:ダーク・ボガード(国際犯罪組織の大物ガブリエル)
:テレンス・スタンプ(モデスティ・ブレイズの相棒ウイリー)
☆解説: 世界的に有名(らしい)なイギリスの漫画「モデスティ・ブレイズ Modesty Blaise」の映画化。『エヴァの匂い』や『召使』のジョセフ・ロージー監督がコメディアクションに挑戦。出演は女泥棒を演じるモニカ・ヴィッティ、 その相棒をテレンス・スタンプがつとめ、マザコンの悪漢を怪演する微笑ましいダーク・ボガード。コミックのヒーロー・ヒロインらしくどなたもあたりかまわずの大活躍!
☆あらすじ: (有って無いようなものですが・・・。)
イギリスは、中東マサラ国の石油をえる際、同国の元首シークの要望を聞き入れた見返りとして、ダイヤモンドを送ることにした。このことが国際犯罪組織の知るところとなり、イギリス秘密情報部長のタラントは女犯罪者・モデスティにダイヤの護衛を依頼する。その際、彼女は相棒のウィリーを協力者としてつけるという条件で引き受ける。 犯罪組織のリーダー・バシリオはモデスティをおびき寄せる形でウィリーを捕らえたうえで、ダイヤを盗んだ。モデスティは色仕掛けと変装でウィリーとダイヤを奪還するが、組織に見つかり窮地に陥る。・・(後略) ーウィキペディア(Wikipedia)よりー
どお?よ~分からないでしょ。 この僕でもよ~分からなかったんだから。 登場するこれらの大物スターが自分たちの役どころからかけ離れたコミカルな演技で、観るものを驚かせたり、戸惑わせたり。 おそらく演じる方もそれを観る方もどちらもワクワク・ドキドキ・ゾクゾクしながら楽しんでたんじゃないでしょうか?
そもそもジョセフ・ロージー監督のコメディ映画は珍しい。 そしてモニカ・ヴィッティがこのような映画に出るのって珍しい。 ダーク・ボガードやテレンス・スタンプもこんな役は珍しい。 これだけの珍しづくしも珍しい。 モニカのぶっ飛んだファッションやボガードのなんじゃこりゃ変身、モデスティ(モニカ・ヴィッティ)危うしで救援に突如現れる大軍団の唐突さ。思わず拍手!ギャグあり、涙なしの全編コレ突飛だらけ!これはもうゴボウあり、こんにゃくあり、人参、油揚げ、干し椎茸ありのまるで賑やかな役者ぞろいの五目ごはんと言うか、かやくご飯の大爆発。 (五目ごはんがお好き?)
こんな豪華絢爛な五目ごはんを更にポップでキッチュなキラキラの五目、いや天目茶碗にてんこ盛り。さあドぉだ!とばかりに愉しげなデュエットもふりかけて、これでもかのドンチャン騒ぎ。
少しお疲れが過ぎたのかペースダウンの処もありながら、ひたすらごちゃ混ぜのノー天気が煌めきわたった、笑っちゃうしかない実におかしな映画でありました。 登場する車はどれもウフフだったし、後半の舞台となる地中海を臨む絶壁にたつ悪漢どものアジトなんかは、 いかにも悪の巣窟あるあるです。ピッタリ!そのロケーションの素晴らしさは息を呑みます。とにもかくにも楽しい映画デス。 僕は好きです。(笑)

ジャ~ン、これが悪漢どものアジトだ!
(サンタレッシオ シークロ城 Castello di Sant'Alessio Siculo・伊)
今日の目線で見ればその出来栄えに物足りなさを言い言いしたいところかもしれませんが、それは曜変天目茶碗を偉大な失敗作だと言うようなものかもしれませんねエ。 (曜変天目茶碗もお好き?)
結果をどお愉しむかは受取る側次第なので大いに論じ合うのも楽しいですよね。
こんなヒッチャカメッチャカな作品を見てしまった当時の僕なんかはもう頭の中もスッカリ、すっちゃかめっちゃかになっちゃって、ただボ~ッとトランス状態になっていたのを思いだしたぞ!(今も変わりません。) 後半テンポがおちて残念なんて言わないけど、(言ってる) このようなよくわからない作品は二度と作れないでしょうし、作らないでしょうね。ってあの時さすがに思ってしまいました。
ついでに思いだしたんだけど、 あの頃世の中は高度経済成長期で僕は *♪ノッテけ、ノッテけ、ノッテけ♪って皆が誘うもんだから、よく分からずに、じゃあ僕も一緒にノッケて、ノッケて、ノッケてってノッケてもらい、オイルショックも何のその、またまたバブルで景気も良くなり勢いづいて遊びに遊び、皆でこのままノッとけ、ノッとけ、ノッとけと調子にノッてたら、 世の中 そおそお調子よいことばかりは続きません。とほほバブルがパッチンとハジけて一斉にひっくり返っちゃった。あとは散々。ご想像にお任せします。でも、ノリやすい僕が何んとか今日までやってこられたのも、ひとえに、僕の努力のおかげだったんデス。 僕って凄~い‼ (・・・長生きして下さい。)
* ♪太陽の彼方に♪ 曲:アストロノウツ。 1964年日本でシングルリリースされました。寺内タケシとブルージーンズをバックに藤本好一の歌でお馴染み(?)
と、言うことで (どう言うこと?) この映画は僕にとってあの大変だった時代のはしりの良き時代の気分を映し出した傑作・怪作でありました。ある意味ぼくにとって心地よい快作でもあったんです。
コレだけの破茶滅茶をやってのけられたのはさすがに良くも悪くもジョセフ・ロージー監督ならではかもしれません。 成功作だとか失敗作だとかを尽き抜けた、味の効いた豪華なハチャメチャ映画と言うしかないんじゃないのぉ? 最後に捕えられた悪漢ガブリエル(ダーク・ボガード)が銃口を突きつけられて言ったセリフなんゾ、ニクイねぇ~。 ダーク・ボガードなればこそですね。このように随所に蒔かれたギャグやしぐさには、唯、おもしろいだけじゃ終わらせないジョセフ・ロージー監督の企らみがあり、僕たちはまんまとノセられたって感じかな?
僕としてはまるで"アンニュイ"がそっくりそのまま女性になったようなモニカ・ヴィッティのカッコいい、生き生きと甦った はしゃぎっぷりを2時間弱たっぷり見られただけでも、もぉ~大満足です。 最初に観たのと今回で二度美味しかったというのが僕の至極他愛のない感想でありました。 (それだけ?) ハイ、それだけです。










 パンフレット (表紙)
パンフレット (表紙)

 クルッ、クルッ、目がまわる~。
クルッ、クルッ、目がまわる~。
 ギロッ!
ギロッ!



 表
表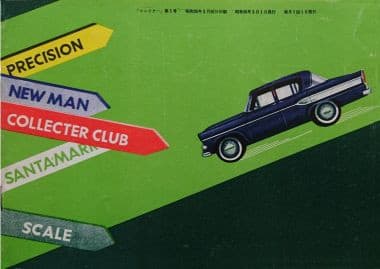 裏
裏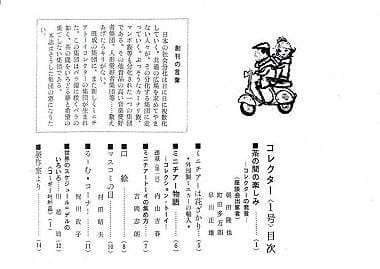

 表
表 裏
裏
 表
表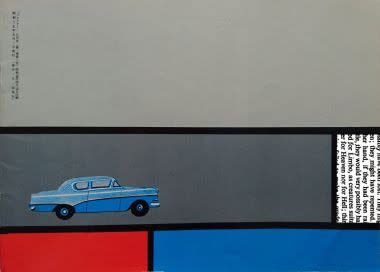 裏
裏