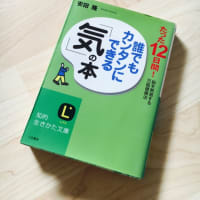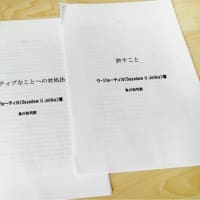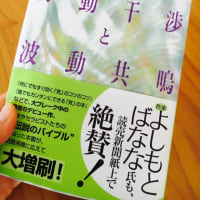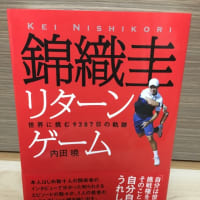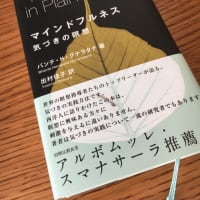心脳問題を研究する気鋭の科学者として注目を集める茂木健一郎の「脳と仮想」を読んだ。
きっかけは新潮社の雑誌「考える人」の編集長が書くメルマガだった。
そこには、この著書で第4回小林秀雄賞を受賞した茂木氏の、記者会見上でのエピソードが紹介されていた。
茂木氏は、東京大学理学部に入りながら途中で法学部に転部している。その理由をどこかの記者が質問すると、茂木氏は言いよどみながらも、話しはじめたのだとか。ようは、純粋培養の科学少年だった茂木氏が、あるとき恋に落ちた。
そしてその人は、茂木氏が学ぶ科学とは全く相容れない「法学部」的な価値観を信じる女性だった。
恋のとりこになった茂木氏は、その世界を深く知りたいと思い、そして、法学部に入りなおしたというのだ。
このエピソードを読んだだけで、もう普通に「いいなぁ」って思ってしまった。
恋に落ちるのは文学少年ばかりではない。科学少年だって恋に落ちるのだ。そこが面白い。
理性の世界で生きている人間が恋に落ちたとき、理詰めでは通らない出来事に遭遇して、一体何を悩み、苦しんだのだろう。
科学という自分が専門とするアプローチ方法ではあるもの、この本は、茂木氏が
若い頃に抱え込んだ課題を解き明かそうとする「あがき」が含まれているのでは、なんて、うがった見方をしてしまった。
文章は硬めで、専門用語が頻繁に登場し、茂木氏が研究テーマとする「クオリア」というキーワードもすんなり胸に入ってはこなかったけれど、でも、科学者でありながら科学周辺の領域に寛容に手を伸ばそうとするところには、茂木氏のやわらかさとか暖かさをを感じた。
本文中、心に残った文章を引いてみる。
【私たちが、他者の心を知ることは原理的にありえない。私たちは、ただ、他者の心が判ったことにするだけである。
そこに立ち現れる他者の心は、一つの仮想である。場合によっては、相手の実際の心とは似ても似つかないかもしれない仮想である。理解と誤解の間には、無限といっていいほどの諧調がある。
肝心なのは、理解ということを、世の中に確かに存在するはずの「他者の心」の把握という意味に捉えるならば、完全な理解など、決して存在しないということを認識することである。】
この手のことは、例えば心理学系や人生指南系の本などでは、よく書かれていることだ。
それは、大体は著書の直感であったり経験によって書かれており、脳よりも心の問題、人間関係の切り抜け方として扱われている。
茂木氏の文章は、あくまで脳科学という
科学から導かれた客観事実を基に書かれているので、また違った重みを感じる。
茂木氏は、科学という自分の使いなれた道具を使って、ここにたどり着いた人なんだな、という気がした。
そして・・・、
【押せば動くというような、単純な力学に従わない、やわらかい存在だからこそ、他者の心は自分にとって切実な意味を持つ。自らがコントロールできる対象ではない。相手には、相手の意志がある。価値判断がある。そのような、他者の心が、その独自の意志に基づいて自分に好意を寄せてくれる。だからこそ、恋愛の成就は、飛び上がるほどうれしい。】
この文章の中に、茂木氏をして心脳問題に深く関わらせ、この本を書かせた答えがあるように思えた。
恋愛エッセイのように甘かったり情緒的だったりはせず、あくまで冷たく硬い断定的な文体の中にだからこそ、茂木氏の生々しい体験とそこからもたらされた述懐がにじんでいるような印象を持った。
きっかけは新潮社の雑誌「考える人」の編集長が書くメルマガだった。
そこには、この著書で第4回小林秀雄賞を受賞した茂木氏の、記者会見上でのエピソードが紹介されていた。
茂木氏は、東京大学理学部に入りながら途中で法学部に転部している。その理由をどこかの記者が質問すると、茂木氏は言いよどみながらも、話しはじめたのだとか。ようは、純粋培養の科学少年だった茂木氏が、あるとき恋に落ちた。
そしてその人は、茂木氏が学ぶ科学とは全く相容れない「法学部」的な価値観を信じる女性だった。
恋のとりこになった茂木氏は、その世界を深く知りたいと思い、そして、法学部に入りなおしたというのだ。
このエピソードを読んだだけで、もう普通に「いいなぁ」って思ってしまった。
恋に落ちるのは文学少年ばかりではない。科学少年だって恋に落ちるのだ。そこが面白い。
理性の世界で生きている人間が恋に落ちたとき、理詰めでは通らない出来事に遭遇して、一体何を悩み、苦しんだのだろう。
科学という自分が専門とするアプローチ方法ではあるもの、この本は、茂木氏が
若い頃に抱え込んだ課題を解き明かそうとする「あがき」が含まれているのでは、なんて、うがった見方をしてしまった。
文章は硬めで、専門用語が頻繁に登場し、茂木氏が研究テーマとする「クオリア」というキーワードもすんなり胸に入ってはこなかったけれど、でも、科学者でありながら科学周辺の領域に寛容に手を伸ばそうとするところには、茂木氏のやわらかさとか暖かさをを感じた。
本文中、心に残った文章を引いてみる。
【私たちが、他者の心を知ることは原理的にありえない。私たちは、ただ、他者の心が判ったことにするだけである。
そこに立ち現れる他者の心は、一つの仮想である。場合によっては、相手の実際の心とは似ても似つかないかもしれない仮想である。理解と誤解の間には、無限といっていいほどの諧調がある。
肝心なのは、理解ということを、世の中に確かに存在するはずの「他者の心」の把握という意味に捉えるならば、完全な理解など、決して存在しないということを認識することである。】
この手のことは、例えば心理学系や人生指南系の本などでは、よく書かれていることだ。
それは、大体は著書の直感であったり経験によって書かれており、脳よりも心の問題、人間関係の切り抜け方として扱われている。
茂木氏の文章は、あくまで脳科学という
科学から導かれた客観事実を基に書かれているので、また違った重みを感じる。
茂木氏は、科学という自分の使いなれた道具を使って、ここにたどり着いた人なんだな、という気がした。
そして・・・、
【押せば動くというような、単純な力学に従わない、やわらかい存在だからこそ、他者の心は自分にとって切実な意味を持つ。自らがコントロールできる対象ではない。相手には、相手の意志がある。価値判断がある。そのような、他者の心が、その独自の意志に基づいて自分に好意を寄せてくれる。だからこそ、恋愛の成就は、飛び上がるほどうれしい。】
この文章の中に、茂木氏をして心脳問題に深く関わらせ、この本を書かせた答えがあるように思えた。
恋愛エッセイのように甘かったり情緒的だったりはせず、あくまで冷たく硬い断定的な文体の中にだからこそ、茂木氏の生々しい体験とそこからもたらされた述懐がにじんでいるような印象を持った。