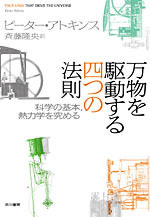
原題:Four Laws That Drives the Universe
~熱力学は科学の基本。文系で言うと、シェイクスピアの訳本が読めるレベルだ。熱とは、仕事とは、エントロピーとは何か……あらゆる自然科学に顔を出すこの分野の基本四法則を克明に解説した必読入門書~〈ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス〉
<目次>
1 第0法則 温度の概念(「系」とそのふたつの特性;「平衡」という概念と温度 ほか)
2 第1法則 エネルギーの保存(エネルギーと仕事;内部エネルギー ほか)
3 第2法則 エントロピーは増大する(熱力学第2法則の重要性;第2法則のふたつの表現 ほか)
4 自由エネルギー どれだけ仕事に使えるか(仕事にかんする熱力学的特性はないのか?;ヘルムホルツ・エネルギー ほか)
5 第3法則 ゼロには到達できない(第3法則の意義;有限のはしごを使っても、無限には到達できない ほか)
本書のタイトル「万物を駆動する四つの法則」に惹かれて、ろくに中身も確かめずに読み始めたのが私にとっては間違いだったかも。それでも、冒頭で著者が次のように記すると、少し頑張って読んでみようかと思えたのでした。
~第2法則は、深遠であるゆえに、難解なものとしてよく知られ、科学の素養を測るリトマス試験紙と言われている。現に、科学者から作家になったC・P・スノーが、『二つの文化と科学革命』のなかで、熱力学第2法則をしらないのは、シェイクスピアの作品を読んだことがないようなものだ、と言ったのは有名な話である。~
そもそもC・P・スノーという作家を知らない私は、本書のキャプションである「ポピュラー・サイエンス」が、自分にとって少しもポピュラーとは感じられないということにここで気づくべきでした。小説家としての彼の代表作は、現代の科学知と現代における政府設定について表現したシリーズ小説「他人と同胞」ということから既に、私には分相応でない分野であります。

<チャールズ・パーシー・スノー - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%8E%E3%83%BC
ページをめくりながら、何度も眠りに落ちた私でしたが、なんとか読み通せたのは、本書の160ページとういうコンパクトな分量の一言につきます。そんな私でも読んだ以上は、少なくとも本書に書かれた内容がどんなものであったかくらいは覚えておきたいと思うのですが、それは幸いにも、本書の「はじめに」で著者が次のように記してくれています。
~(この世界を動かしている)ひとにぎりの強大なものは四つの法則からなるが、ややこしいことに、0から始まり、3で終わる、初めの二法則(「第0」と「第1」)には、身近でありながら不可解なふたつの特性、温度とエネルギーが登場する。
~三つめ(「第2法則」)には、はるかに不可解な特性と一般に見なされるエントロピーが登場するが、これが、もっと身近に思える温度やエネルギーよりも実はわかりやすいことを本書で明らかにしたい。第2法則は、歴史を通じて屈指の重要な科学法則と言える。高音の物体が冷めることから、思考の形成に至るまで、どんな現象についても、そもそもなぜ起きるのかを説明してくれるからだ。
~四つ目の法則(「第3法則」)は、より専門性の高い役割を担っているが、本書を構成するテーマの締めくくりとなり、そこから応用として言えることがらの、可能性も制約も示す。第3法則は、温度が究極の寒さである絶対零度になることを阻む障壁となるが、そのゼロより下に、奇妙だが実現可能な鏡像の世界があることは、本書でいずれ明らかにしよう。~
<第0法則>
AがBと熱平衡をなし、BがCと熱平衡をなすとしたら、CはAと熱平衡をなす。
<第1法則>
独立系の内部エネルギーは不変である。
<第2法則>
熱源から取り出せた熱が、すべて仕事に変換されるような循環過程はあり得ない。
<第3法則>
循環過程を有限回繰り返しても、物体を絶対零度まで冷やせない。
<熱力学 - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E5%8A%9B%E5%AD%A6
そしてもう一つ、覚えておきたいのが、私たちが日頃耳にする温度の単位である摂氏、華氏、絶対零度にまつわる由来です。
私たちに馴染みの摂氏温度は、その制定者であるスウェーデンの天文学者アンデルス・セルシウス(1701-1744)の名前セルシウスから来ていたんですね。セルシウスを中国語で書いた「摂爾修」から摂氏なんだそうです。つまりセルシウス氏の温度単位ということなんですね。

<アンデルス・セルシウス - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%82%B9
次に、私たちに馴染みはありませんが、マイケル・ムーア監督の「華氏911」(2004)などのように欧米などで使われる温度の単位の華氏温度。制定者であるドイツの器械製作者ガブリエル・ダニエル・ファーレンハイト(1686-1736)のファーレンハイトを中国語に音訳した「華倫海特」から来ているそうです。ちなみに華氏911度は、摂氏約490度なんだそうです。

<ガブリエル・ファーレンハイト - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%88
この辺のことは次のサイトで詳しく書かれています。
<おじさん通信>
http://www.netricoh.com/contents/antenna/ojituu/data/0079.html
最後に、絶対零度の単位、ケルビン(記号: K)の名が冠されたのは、ケルヴィン卿(Lord Kelvin)という通称を持つ、イギリスの物理学者ウィリアム・トムソン(1824-1907)。

<ウィリアム・トムソン - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%A0%E3%82%BD%E3%83%B3
加えて、この機会に覚えておきたいのが、エントロピーです。悲しいかな本書の説明では理解できそうにもないので、「かつさん」という方のサイトから引用させてもらいます。
<エントロピーの法則>
http://www.gem.hi-ho.ne.jp/katsu-san/audio/entropy.html
~もともと、これは熱力学の第二法則(クラウジウスの法則 或いはカルノーの原理)から来ています。・・・話を簡単にするため、今、一方が熱くて一方は冷たい、二つの物体があると思って下さい。・・・おおざっぱに言って熱力学の第二法則とは、熱というモノは熱い方から冷たい方に向かって流れて逆はありませんよ、と言う誰でも知ってる経験則のことで、基本的には、これが積もり積もったものがエントロピーの増大です。・・・早い話が、熱量がδQ(熱量の変化)だけ熱い方から冷たい方に移動した、ただそれだけの事。負になるわけがない。だから必ずエントロピーは増大していく。もし減ったなら、それは時間が逆流した時です。~
<エントロピー - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%94%E3%83%BC
このエントロピーの概念を導入したのが、ポーランド出身の物理学者ルードルフ・クラウジウス(1822-1888)。エントロピーという言葉は、ギリシャ語で「変換」を意味するトロペー (τροπή)に由来しているそうです。

<ルドルフ・クラウジウス - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%82%B9
ピーター・アトキンス[Peter Atkins];1940年生まれ。オックスフォード大学化学教授、リンカーン・カレッジ・フェロー。専門は物理化学。世界的に著名な化学教科書の著者として知られるが、ポピュラー・サイエンスの書き手としても名高い。

<ピーター・アトキンス - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B9
訳者/斉藤隆央[サイトウタカオ]:1967年生まれ。東京大学工学部工業化学科卒業。
関連記事;
<つらつらぐさ: 万物を駆動する四つの法則>
http://mumrik.air-nifty.com/blog/2009/04/08_4ruledriveun.html
~熱力学は科学の基本。文系で言うと、シェイクスピアの訳本が読めるレベルだ。熱とは、仕事とは、エントロピーとは何か……あらゆる自然科学に顔を出すこの分野の基本四法則を克明に解説した必読入門書~〈ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス〉
<目次>
1 第0法則 温度の概念(「系」とそのふたつの特性;「平衡」という概念と温度 ほか)
2 第1法則 エネルギーの保存(エネルギーと仕事;内部エネルギー ほか)
3 第2法則 エントロピーは増大する(熱力学第2法則の重要性;第2法則のふたつの表現 ほか)
4 自由エネルギー どれだけ仕事に使えるか(仕事にかんする熱力学的特性はないのか?;ヘルムホルツ・エネルギー ほか)
5 第3法則 ゼロには到達できない(第3法則の意義;有限のはしごを使っても、無限には到達できない ほか)
本書のタイトル「万物を駆動する四つの法則」に惹かれて、ろくに中身も確かめずに読み始めたのが私にとっては間違いだったかも。それでも、冒頭で著者が次のように記すると、少し頑張って読んでみようかと思えたのでした。
~第2法則は、深遠であるゆえに、難解なものとしてよく知られ、科学の素養を測るリトマス試験紙と言われている。現に、科学者から作家になったC・P・スノーが、『二つの文化と科学革命』のなかで、熱力学第2法則をしらないのは、シェイクスピアの作品を読んだことがないようなものだ、と言ったのは有名な話である。~
そもそもC・P・スノーという作家を知らない私は、本書のキャプションである「ポピュラー・サイエンス」が、自分にとって少しもポピュラーとは感じられないということにここで気づくべきでした。小説家としての彼の代表作は、現代の科学知と現代における政府設定について表現したシリーズ小説「他人と同胞」ということから既に、私には分相応でない分野であります。

<チャールズ・パーシー・スノー - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%8E%E3%83%BC
ページをめくりながら、何度も眠りに落ちた私でしたが、なんとか読み通せたのは、本書の160ページとういうコンパクトな分量の一言につきます。そんな私でも読んだ以上は、少なくとも本書に書かれた内容がどんなものであったかくらいは覚えておきたいと思うのですが、それは幸いにも、本書の「はじめに」で著者が次のように記してくれています。
~(この世界を動かしている)ひとにぎりの強大なものは四つの法則からなるが、ややこしいことに、0から始まり、3で終わる、初めの二法則(「第0」と「第1」)には、身近でありながら不可解なふたつの特性、温度とエネルギーが登場する。
~三つめ(「第2法則」)には、はるかに不可解な特性と一般に見なされるエントロピーが登場するが、これが、もっと身近に思える温度やエネルギーよりも実はわかりやすいことを本書で明らかにしたい。第2法則は、歴史を通じて屈指の重要な科学法則と言える。高音の物体が冷めることから、思考の形成に至るまで、どんな現象についても、そもそもなぜ起きるのかを説明してくれるからだ。
~四つ目の法則(「第3法則」)は、より専門性の高い役割を担っているが、本書を構成するテーマの締めくくりとなり、そこから応用として言えることがらの、可能性も制約も示す。第3法則は、温度が究極の寒さである絶対零度になることを阻む障壁となるが、そのゼロより下に、奇妙だが実現可能な鏡像の世界があることは、本書でいずれ明らかにしよう。~
<第0法則>
AがBと熱平衡をなし、BがCと熱平衡をなすとしたら、CはAと熱平衡をなす。
<第1法則>
独立系の内部エネルギーは不変である。
<第2法則>
熱源から取り出せた熱が、すべて仕事に変換されるような循環過程はあり得ない。
<第3法則>
循環過程を有限回繰り返しても、物体を絶対零度まで冷やせない。
<熱力学 - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E5%8A%9B%E5%AD%A6
そしてもう一つ、覚えておきたいのが、私たちが日頃耳にする温度の単位である摂氏、華氏、絶対零度にまつわる由来です。
私たちに馴染みの摂氏温度は、その制定者であるスウェーデンの天文学者アンデルス・セルシウス(1701-1744)の名前セルシウスから来ていたんですね。セルシウスを中国語で書いた「摂爾修」から摂氏なんだそうです。つまりセルシウス氏の温度単位ということなんですね。

<アンデルス・セルシウス - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%82%B9
次に、私たちに馴染みはありませんが、マイケル・ムーア監督の「華氏911」(2004)などのように欧米などで使われる温度の単位の華氏温度。制定者であるドイツの器械製作者ガブリエル・ダニエル・ファーレンハイト(1686-1736)のファーレンハイトを中国語に音訳した「華倫海特」から来ているそうです。ちなみに華氏911度は、摂氏約490度なんだそうです。

<ガブリエル・ファーレンハイト - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%88
この辺のことは次のサイトで詳しく書かれています。
<おじさん通信>
http://www.netricoh.com/contents/antenna/ojituu/data/0079.html
最後に、絶対零度の単位、ケルビン(記号: K)の名が冠されたのは、ケルヴィン卿(Lord Kelvin)という通称を持つ、イギリスの物理学者ウィリアム・トムソン(1824-1907)。

<ウィリアム・トムソン - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%A0%E3%82%BD%E3%83%B3
加えて、この機会に覚えておきたいのが、エントロピーです。悲しいかな本書の説明では理解できそうにもないので、「かつさん」という方のサイトから引用させてもらいます。
<エントロピーの法則>
http://www.gem.hi-ho.ne.jp/katsu-san/audio/entropy.html
~もともと、これは熱力学の第二法則(クラウジウスの法則 或いはカルノーの原理)から来ています。・・・話を簡単にするため、今、一方が熱くて一方は冷たい、二つの物体があると思って下さい。・・・おおざっぱに言って熱力学の第二法則とは、熱というモノは熱い方から冷たい方に向かって流れて逆はありませんよ、と言う誰でも知ってる経験則のことで、基本的には、これが積もり積もったものがエントロピーの増大です。・・・早い話が、熱量がδQ(熱量の変化)だけ熱い方から冷たい方に移動した、ただそれだけの事。負になるわけがない。だから必ずエントロピーは増大していく。もし減ったなら、それは時間が逆流した時です。~
<エントロピー - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%94%E3%83%BC
このエントロピーの概念を導入したのが、ポーランド出身の物理学者ルードルフ・クラウジウス(1822-1888)。エントロピーという言葉は、ギリシャ語で「変換」を意味するトロペー (τροπή)に由来しているそうです。

<ルドルフ・クラウジウス - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%82%B9
ピーター・アトキンス[Peter Atkins];1940年生まれ。オックスフォード大学化学教授、リンカーン・カレッジ・フェロー。専門は物理化学。世界的に著名な化学教科書の著者として知られるが、ポピュラー・サイエンスの書き手としても名高い。

<ピーター・アトキンス - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B9
訳者/斉藤隆央[サイトウタカオ]:1967年生まれ。東京大学工学部工業化学科卒業。
関連記事;
<つらつらぐさ: 万物を駆動する四つの法則>
http://mumrik.air-nifty.com/blog/2009/04/08_4ruledriveun.html










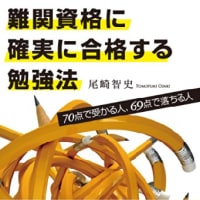
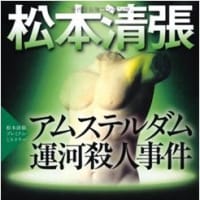
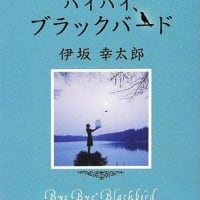

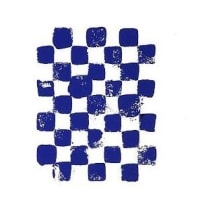
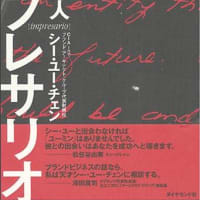



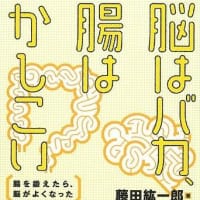
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます