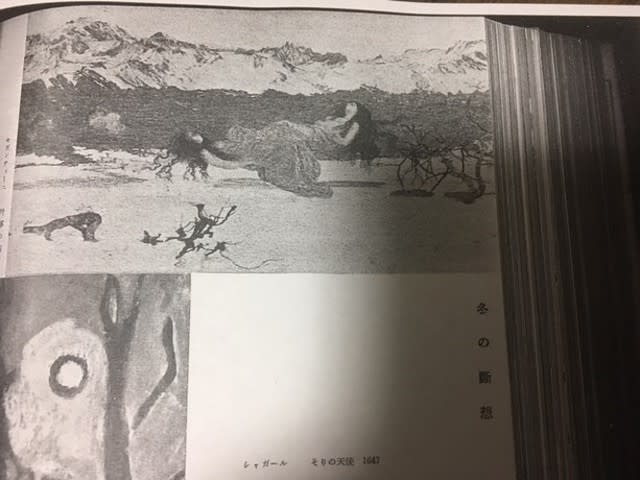「ユリイカ」2016年8月号「あたらしい短歌、ここにあります」が発行されてから、もう1年以上が過ぎたのですね。早いものです。
備忘のために、これもアップしておきます。短歌の現状分析として、どれくらい当たっているでしょうか?
文中で引用している大岡信さんの『うたげと孤心』は最近、岩波文庫で復刊されましたね。
============================================================
比較の詩型 そして比較できないもの
1 比較によって生み出される時間性
短歌は、つねに比較を誘う形式である。
比べるためには、何らかの共通性がなければならない。たとえば清少納言と紫式部を比較する、というのは、よくあることだが、〈平安時代を生きた女性文学者〉という暗黙の共通性があるからこそ、それは成立する。
短歌は、字余りや字足らずもあるけれど、およそ三十一音という共通性がある。そうであるから、今作られた歌と、千年以上前に作られた歌が対比されるということも、ざらに起きるのである。たとえば栗木京子の『うたあわせの悦び』(二〇一三年)では、
雪のうちに春は来にけり鶯のこほれる涙今やとくらむ
藤原高子『古今集』春上
ほんとうにおれのもんかよ冷蔵庫の卵置き場に落ちる涙は
穂村弘『シンジケート』(一九九〇年)
の二首を、小さな涙に注目した歌として、対照させながら論じている。まったく時代が異なる作品であるにも関わらず、ある一点において響き合うということが、短歌ではしばしばあるのである。
小説や詩では、形式や内容がそれぞれ違っているので、二つの作品を比べるのは慎重にならざるを得ないが、短歌では慣習的に容易(たやす)く行われている。これはある意味で乱暴なことである。時代状況を無視して並べるということも起こりやすいからだ。ただ、現在作られている歌は、過去の歌と地続きであるという時間認識を呼び覚まされるという良さもあるだろう。好むと好まざるとに関わらず、短歌は、古い歌と比較されることで歴史性を強く帯びる詩型である。
最近、ミステリ作家として著名な北村薫による『うた合わせ 北村薫の百人一首』が刊行された。「歌合(うたあわせ)」とは、二首の歌の優劣を議論しながら競い合う遊戯で、九世紀末から行われていたという。競い合うという短歌の性質は、時代を超えて、脈々と受け継がれているらしい。
比較する、ということは、〈何が新しいのか〉という問いを、いつも前景化させる。
ここで俵万智の『サラダ記念日』がベストセラーになったときの論調を振り返っておきたい。永田和宏の時評集『[同時代]の横顔』からの孫引きとなるが、次のような文章は、ある種の典型と言っていいだろう。
「新聞や週刊誌が、俵万智や歌集ブームをこれだけ大々的に扱っているにもかかわらず、わが歌壇はじつに奇妙である。その第一は、歌壇外でこれだけにぎやかな話題を提供しているにもかかわらす、本家本元の歌壇では、ピタリ音無しという点である」
(時評「奇妙な歌壇」細井剛、「岬」87年9月)
この文章について永田は、「『ピタリ音無し』などでは全くなく、少々はしゃぎすぎるくらい書かれている」と苦言を呈している。今読み直して興味深いのは、〈古い歌壇に対抗して、若い世代から新しい歌が生まれている〉という図式が明瞭にあらわれていることである。
『サラダ記念日』が刊行されて今年でちょうど三十年だが、伝統的な歌壇に対抗して新しい歌が登場してくる、という話型は、その後も繰り返し用いられてきた。枡野浩一のように、歌壇から認められないことを積極的にアピールする歌人もいる。もっと前に遡れば、与謝野晶子の『みだれ髪』も、旧弊な和歌に叛逆する歌集として、賛否両論を引き起こしたのだった。そして現在も、この図式に沿って、新しい歌が紹介されやすい――テレビなどで若い世代の短歌が取り上げられる場合、だいたい保守対革新のような語り方になる。
考えてみれば、三十年間もずっと変わらず、強固な伝統歌壇が存在しているはずはないのだが、非常に古い世界が一方にあって、それに対決する形で新しい短歌が生まれてくるという見方で論じられやすいのである。実際は、古い歌を継承することで優れた歌を生み出している歌人もたくさんいるのだけれど。
もちろん短歌には、宮中歌会始のように皇室とつながっている側面があり、伝統性がことさら強調されやすいのも事実である。旧来の短歌VSインターネット時代の短歌、というように、二項対立的にとらえたほうがおもしろいし、議論が盛り上がりやすいという側面もあるだろう。先にも書いたように、比較によって短歌は活性化するわけで、それが生み出している現象なのかもしれない。鴨長明が書いた十三世紀の歌論集『無名抄』にも、当時の旧派と新派の対立について書かれている。〈新旧の対立〉は、何度も繰り返されてきた、それ自体が歴史的なものなのだ、という視点を持っておくことも重要であろう。
よく言われることだが、短歌では歴史を知らなければ、ほんとうに新しい歌かどうか判断できない。自分は新しい歌と思っていても、じつは過去に何度も試されてきたものである、ということはよくあるからだ。そのため、短歌では、歴史的なまなざしを持つ読者の存在が非常に大切になる。もちろん、そうした読者に全員がなる必要はない。しかし少数であっても、過去から現在を見通そうとする読者が、つねに求められるのである。
2 短歌とは何か、という問い
これまでとは違った短歌が出てきたときに、〈これは短歌ではないのではないか〉という反応が生じることも、よく見られる風景である。『サラダ記念日』が出たときも、短歌以外の別物である、という批判はいくつも書かれた。短歌は五・七・五・七・七という型以外、何も制約がない。そのため、その型で書かれていれば何でも短歌と認められるのか、という問いが生じてくる。
最近、「偶然短歌」が話題になった。インターネット上の辞典、ウィキペディアから、たまたま五・七・五・七・七になった部分を抜き出すと、短歌のように見える、というものである。
西側にあったホームは撤去され、花壇に花が植えられている
福井県の「三方駅」の説明の中から抜き出されたもの。これは短歌といえるのだろうか? 短歌とはいえないと考える人も多いかもしれない。しかし一方で、
強風にリフト止めても可能ならすぐまた動かす「ガーラ湯沢」は
奥村晃作『都市空間』(一九九五年)
といった、事実だけを記す方法で作った歌も存在している。短歌か/短歌でないかの境界は、非常に曖昧なのである。
かつて穂村弘は、
たすけて枝毛ねえさんたすけて西川毛布のタグたすけて夜中になで回す顏
飯田有子『林檎貫通式』(二〇〇一年)
という一首を、「定型からは大きく外れた破調」であるが「切迫した孤独感のモチーフ」があり、「世界が酸欠状態にあるから、歌が喘いでいるのだ」と評価した(『短歌の友人』二〇〇七年)。三十一音を大幅にオーバーしているが、短歌として読むことで、定型に収めることのできなかった心情の激しさを読もうとする。
「たすけて」の繰り返しが、確かに印象的な作だが、一回的なインパクトなのか、それとも真に新しい表現なのか。当時、大きな話題になったけれども、あまり論議が深まることはなかったように記憶する。今考えると、これも「短歌か/短歌でないか」という枠組みの中での議論だった。それは「世界は酸欠である」という認識に賛同するか、賛同しないか、という問いにもつながっていた。もしもこの歌を認めないのなら、この息苦しい世界を肯定していることになる、と穂村は読者に迫ったのだった。
「現在の酸欠世界においては、愛や優しさや思いやりの心が、迷子になったり、変形したりして、そこここに虚しく溢れかえっている。」(『短歌の友人』)
という理由で、短歌の定型から逸脱していく表現を肯定する。
ただ、「枝毛ねえさん」という言葉はおもしろいとしても、「西川毛布のタグ」にどこまで短歌表現としての必然性があったのか。当時、世界は酸欠状態だったとして、十五年以上経て、大震災や原発事故を経験した現在、どうなっているのだろう。そうした過去を検証する議論があまりなされないのが、現代の短歌界の大きな問題点であると思う。「短歌とは何か」という問いはたしかに重要だが、話題作が次々に消費されるような形で、時間が流れてしまっているのが残念なのである。
3 「分かる/分からない」という議論
小さなものを売る仕事がしたかった彼女は小さなものを売る仕事につき、それは宝石ではなく
フラワーしげる『ビットとデジベル』(二〇一五年)
最近ではこうした歌が取り上げられることがある。「宝石ではなく」というところから、つつましい仕事をしているようであり、彼女は挫折感を抱いているのかもしれないが、それ以上どう読めばいいのか、よく分からない一首である。この歌も、定型を大きく外れているが、その意味をどう考えればいいのかも理解しにくい。「枝毛ねえさん」のような過去の歌を踏まえて批評する、ということもできない。過去の歌と現在の歌のつながりが見えなくなっているのである。
しかし、〈歌の分からなさ〉は、一つの価値となっている面がある。たとえば、フラワーしげるの「小さなものを」の作について、何人かで話し合う場があったとしたら、さまざまなストーリーをそれぞれが紡ぎだすことができるだろう。作品そのものを鑑賞することは難しいけれども、いろいろな会話を導き出すきっかけとなる。歌の意味が分からないことは、親しい間柄でコミュニケーションを楽しむための呼び水になるのである。
逆にいうと、価値観の違う人たちとの場では、こうした歌を論議の対象にするのは困難だろう。「これはそもそも短歌なのか」というところから、話し合いをはじめなければならない。作品が議論を引き起こすにしても、〈仲間内の議論〉になりやすいことは指摘しておかなければならない。
シャンデリアを梳くひとにしかできない頰ずりを雨の目の前でして
瀬戸夏子『かわいい海とかわいくない海end.』(二〇一六年)
鍵盤の白鍵、西暦二千年、なつかしくなる交通事故は
瀬戸夏子の歌集から、ランダムに選んだが、こうした意味の取りにくい歌が並んでいる。一首目の「シャンデリアを梳く」は、髪のようなシャンデリアに触れている感じなのだろうが、下の句とのつながりがよく分からない。二首目も、「白鍵」「西暦二千年」「交通事故」の関連がまったく理解できない。なぜ、こうした歌が現在作られているのだろうか。
おそらく瀬戸は、「分かってほしくない」ということを全力で伝えようとしている。現代は何でも分かりやすく透明化されていく時代である。どんな人間か、ということが分析されデータ化されていく。今、インターネットでは、これまで買ったものの履歴から、あなたが欲しいものはこれですね、と自動的に勧めてくるシステムも作られている。そういう現代社会の中では、自分のことを理解されたくない、自分はもっと混沌としたものでありたい、という欲求も生まれてくる。そうした「分からなさへの希求」が、こうした歌のバックボーンになっているのではないか。瀬戸の歌は、価値観の異なる人々には全く伝わらない表現だと思うが、感性や心情を共有するサークルの中では、高く評価をされているようである。
銀幕を膀胱破裂寸前の影が一枚ゆらゆらとゆく
木下龍也『きみを嫌いな奴はクズだよ』(二〇一六年)
逆にこんな歌はどうだろう。一見分かりにくいかもしれないが、映画の上映途中で、尿意をこらえられなくなった人が、ホールから出ていく様子を歌っているのである。その人の影が、映画の画面をゆらゆらと横切っていく。きっとあの人は「膀胱破裂寸前」だったのだろうなと作者は想像している。状況がうまく省略されていて、歌の意味に気づくと「なるほど!」という快感が生じる。切れ味のいい、おもしろい一首である。
瀬戸夏子の歌とは、真逆の方向で作られている歌と言っていいかもしれない。しかし、ある共通性を認めることもできる。木下の歌も、親しいサークルの中で楽しむことができる遊戯性が強いということである。もちろん、木下の歌のほうが、多くの読者へ広がっていく伝導性を持っていると感じるが、謎解きを楽しむという面が強い。こうしたハッと気づかされるおもしろさは、ツイッターとの相性もよいだろう。
集団の中で言葉を楽しむことを、大岡信は「うたげ」という語でとらえた。古典和歌の時代から、酒宴などの場で、機知に富んだ作品や人々の心を弾ませるような作品が生み出されてきたことを踏まえて、大岡はこう述べている。
「日本の詩歌あるいはひろく文芸全般、さらには諸芸道にいたるまで、何らかのいちじるしい盛り上りを見せている時代や作品に眼をこらしてみると、そこには必ずある種の「合す」原理が強く働いていると思われることに、興味をそそられるのである。」
(大岡信『うたげと孤心』一九七八年)
四十年近く前に書かれた文章だが、インターネット時代の詩歌にも確かに当てはまるのではないかと、私は考えている。一首の歌をめぐってさまざまな人が語りながら盛り上がる。それはインターネットが発達することで、直接に人と人が会わなくても、簡単に可能になった。インターネットを利用した歌会は、十数年ほど前から活発に行われている。また、インターネットを使った告知や宣伝が容易になったため、歌集の批評会や朗読会、文学フリーマーケットなど、実際に人が集まるイベントも盛んになっている。「合す」原理が強く働いており、今はまさに「うたげ」の時代だと言っていいのではないか。
4 「孤心」の必要性
けれども私は、この一節につなげて次のように大岡が書いていることに注目したいのである。
「もちろんただそれだけで作品を生むことができるのだったら、こんなに楽な話はない。現実には、「合す」ための場のまっただ中で、いやおうなしに「孤心」に還らざるを得ないことを痛切に自覚し、それを徹して行なった人間だけが、瞠目すべき作品をつくった。しかも、不思議なことに、「孤心」だけにとじこもってゆくと、作品はやはり色褪せた。「合す」意志と「孤心に還る」意志との間に、戦闘的な緊張、そして牽引力が働いているかぎりにおいて、作品は稀有の輝きを発した。」
(『うたげと孤心』)
「孤心」とは文字通り、孤独な心である。コミュニケーションが非常に発達している時代には、さらに強い「孤心」が重要となるだろう。鳥居という若い女性の歌集『キリンの子』が、多くの人々の心を揺さぶったのは、鮮烈な孤独感とともに、リーダビリティ(読み易さ)を持っていたからではないか。リーダビリティというのは、他者に「合す」ということにほかならない。鳥居の歌は、孤心だけに閉じこもるものではなかった。
目を伏せて空へのびゆくキリンの子 月の光はかあさんのいろ
鳥居『キリンの子』(二〇一六年)
透明なシートは母の顏蓋(おお)い涙の粒をぼとぼと弾く
理由なく殴られている理由なくトイレの床は硬く冷たい
鳥居は自殺した母の歌を繰り返し詠んでいる。二首目は、「ぼとぼと弾く」という表現に、まざまざと情景が浮かぶリアリティがある。三首目はいじめられた体験を歌っているが、「理由なく」の繰り返しに、どうしようもない無力感が漂っているし、「トイレの床」の触感が強く迫ってくる。こうした歌を背景とするとき、一首目の「キリンの子」の歌の、幼い美しさが、胸に沁みてくるのである。
鳥居の歌には、傷ついている自己を、外側から見ているようなまなざしがある。感情を殺して、非常に即物的に場面を見つめている。だから、母の自殺や虐待などの異常な体験を歌っているのにも関わらず、静かで明晰である。こうした分裂した自己のあり方も、論じられるべき価値があるだろう。
鳥居の歌は、境遇が特殊すぎるという意見もあるかもしれない。もちろん、そうした歌がすべてなのではなく、日常的な場を詠んだ歌にも「孤心」がくっきりとあらわれることはある。
これは君を帰すための灯 靴紐をかがんで結ぶ背中を照らす
大森静佳『てのひらを燃やす』(二〇一三年)
秋茄子を両手に乗せて光らせてどうして死ぬんだろう僕たちは
堂園昌彦『やがて秋茄子へと到る』(二〇一三年)
音もなく道に降る雪眼窩とは神の親指の痕だというね
服部真里子『行け広野へと』(二〇一四年)
金魚鉢をのぞく少女の眼球がガラス一杯に拡がりてゆく
楠誓英『青昏抄』(二〇一四年)
気の弱いせいねんのまま死ぬだらうポッケに繊維ごちやごちやさせて
吉田隼人『忘却のための試論』(二〇一五年)
「生きろ」より「死ぬな」のほうがおれらしくすこし厚着をして冬へ行く
虫武一俊『羽虫群』(二〇一六年)
近年の第一歌集から、こうした歌を挙げておきたい。四首目の「金魚鉢」の歌は、機知的な作だと感じられるかもしれない。しかし、どこか悪夢のようななまなましさがあり、暗い印象が残ってゆく。三首目も同様で、眼窩を「神の親指の痕」ととらえる発想に、いつかは失われる身体への恐れがにじむ。「孤心」とは、いつかは喪失するものに向き合う態度と言ってもいいだろう。生のはかなさが裏側に貼りついているために、秋茄子やポケットの中の繊維などの物が、確かな存在感をもって、指先に触れてくるのである。最後の虫武の歌からは、肉声のような響きが伝わってくる。短歌はやはり「うた」であり、リズムによって、作者の呼吸がいきいきと感じられることがある。そうした歌は、人の心を揺り動かす力を持つ。
短歌とは比較の詩型である、と私は書いた。しかし、どうしても比較できないものが、一首のなかに澱のように残る。それは死であり、死を帯びている生である。それはいくら「うたげ」が続いていても、消え去ることがないものであった。