
「伊万里・柿右衛門・鍋島 肥前磁器の華」
根津美術館 ※7月3日(日)まで
伊万里や鍋島の磁器の展覧会は随分見てきた。
東京にはトーハクのほか戸栗や出光など磁器に強い美術館も多い中、
どう見せてもらえるのかが鑑賞するのが楽しみ。
まず、染付の大皿から。
「国産の磁器の誕生」というタイトル。つまり、初期伊万里の頃。17世紀前半ぐらい。
次に17世紀半ばの磁器。絵柄が精巧になって、徐々に日本らいさがでてくる。
コーナーのタイトルが面白い。
色絵を「赤や緑、黄色も使える!」と紹介してるなんて、ユニーク。
陶磁器にあまり馴染みのない人にも引き込まれそうな文章。
片隅に「茶の湯の伊万里」を紹介するケースもあった。
肥前磁器は「茶味がない」とされていて、茶の湯の道具はあまり紹介されていない~と紹介文。
でも、染付や水指や白磁の平茶碗が涼しげな取り合わせを提案されている。
磁器ではないけれど、瓢形の風炉・釜はとてもお洒落でステキ
「いいなぁ」と思いつつ、代表的な柿右衛門や鍋島も堪能。
今回はある方(故人)から寄贈された肥前コレクションによる展覧会、かな。(という印象)
個人による収集は方針がハッキリしているから、見ていてとても面白い。
展示室6の茶道具の取り合わせは「雨を楽しむ」
青磁の下蕪花生や楽山の綴目水指。
掛物が瀟湘八景の中の瀟湘夜雨図。
瀬戸茶入の銘が「白雨」、薩摩耳付茶入の銘が「夜雨」。
高麗の雨漏茶碗。
利休作の茶杓が「浮橋」・
いずれも「水」に馴染み深い道具ばかり。
けっこう勉強になった。
ちょうど訪れた日が小雨が降る蒸し暑い午後だったのだけど、
こういう磁器や茶道具を鑑賞したことで、外に出ても湿った空気の不快感があまりなかった。

にほんブログ村
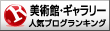 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
投票ヨロシク 致しマス
致しマス
★過去の根津美術館
2011.4月 『燕子花図屏風と初風炉の茶』→こちら
2010年10月『南宋の青磁 宙(そら)をうつすうつわ』→こちら
2010年1月『観るやきもの・使ううつわ 陶磁器ふたつの愉楽』→こちら
2009年11月『根津青山の茶の湯』→こちら
2009.10月『新・根津美術館展 国宝那智瀧図と自然の造形』→こちら
根津美術館 ※7月3日(日)まで
伊万里や鍋島の磁器の展覧会は随分見てきた。
東京にはトーハクのほか戸栗や出光など磁器に強い美術館も多い中、
どう見せてもらえるのかが鑑賞するのが楽しみ。
まず、染付の大皿から。
「国産の磁器の誕生」というタイトル。つまり、初期伊万里の頃。17世紀前半ぐらい。
次に17世紀半ばの磁器。絵柄が精巧になって、徐々に日本らいさがでてくる。
コーナーのタイトルが面白い。
色絵を「赤や緑、黄色も使える!」と紹介してるなんて、ユニーク。
陶磁器にあまり馴染みのない人にも引き込まれそうな文章。
片隅に「茶の湯の伊万里」を紹介するケースもあった。
肥前磁器は「茶味がない」とされていて、茶の湯の道具はあまり紹介されていない~と紹介文。
でも、染付や水指や白磁の平茶碗が涼しげな取り合わせを提案されている。
磁器ではないけれど、瓢形の風炉・釜はとてもお洒落でステキ

「いいなぁ」と思いつつ、代表的な柿右衛門や鍋島も堪能。
今回はある方(故人)から寄贈された肥前コレクションによる展覧会、かな。(という印象)
個人による収集は方針がハッキリしているから、見ていてとても面白い。
展示室6の茶道具の取り合わせは「雨を楽しむ」
青磁の下蕪花生や楽山の綴目水指。
掛物が瀟湘八景の中の瀟湘夜雨図。
瀬戸茶入の銘が「白雨」、薩摩耳付茶入の銘が「夜雨」。
高麗の雨漏茶碗。
利休作の茶杓が「浮橋」・
いずれも「水」に馴染み深い道具ばかり。
けっこう勉強になった。
ちょうど訪れた日が小雨が降る蒸し暑い午後だったのだけど、
こういう磁器や茶道具を鑑賞したことで、外に出ても湿った空気の不快感があまりなかった。
にほんブログ村
投票ヨロシク
 致しマス
致しマス
★過去の根津美術館
2011.4月 『燕子花図屏風と初風炉の茶』→こちら
2010年10月『南宋の青磁 宙(そら)をうつすうつわ』→こちら
2010年1月『観るやきもの・使ううつわ 陶磁器ふたつの愉楽』→こちら
2009年11月『根津青山の茶の湯』→こちら
2009.10月『新・根津美術館展 国宝那智瀧図と自然の造形』→こちら



























柿右衛門様式のお話を聞いて、帰る時に小雨が降っていましたが、嫌な気持ちにならなかったのは「雨を楽しむ」を観た後だったから
納得してしまいました。
講演会に参加されていらっしゃったのですねぇ。
ワタシは参加していないけど、時間的にはちょうど終わる時間に美術館にいました。
もしかすると、すれ違ったかもしれませんネ。
考えてみれば、青磁や染付、伊万里・鍋島の展覧会って、暑くなる時期に鑑賞した時の方が印象が強いです。