アイヌ民族を数千人調査 北大・ウタリ協会が初 生活実態把握へ(05/30 06:48)
北大アイヌ・先住民研究センター(センター長・常本照樹法科大学院教授)は本年度から三カ年計画で、道ウタリ協会(加藤忠理事長)と共同で、道内のアイヌ民族を対象に、初の大掛かりな実態調査を行う。調査を通じてアイヌ民族を取り巻く教育や就労、生活環境を把握する考えで、調査対象は少なくとも数千人規模に達する見通し。国会などでアイヌ民族の権利をめぐる議論が活発化する中、調査結果は今後の国や道の施策にも影響を与えそうだ。
調査は、北大で社会学を専攻する小内透教授とともに行う。初年度は、道内に約三千七百人いるウタリ協会会員をはじめ、その家族や親族など非会員の人も対象に、十月にアンケートで実施する。
二〇〇九年度は、調査対象を胆振や釧路管内などアイヌ民族が多く住む地域に絞り、生活相談員らが出向き、より詳細な項目について聞き取り方式で調査する。
最終年の一〇年度は、海外の先住民族の実態を調べ、アイヌ民族との比較などを行う。
調査結果は年度ごとに公表し、一一年度に最終報告書をまとめる考えだ。
これまでアイヌ施策の基礎データとなってきたのは、道がおおむね七年に一回実施してきたアイヌ民族の生活実態調査だった。
しかし、聞き取り調査の対象が全道で七百人程度と少ない上、調査地域や対象者選びにも偏りがあるなどとして、ウタリ協会や研究者から「実態を反映していない」と疑問視する声が出ていた。
実際、〇六年十月の道の調査では、生活が「とても苦しい」という回答が七年前の31%から0・3%に激減する一方で、生活保護世帯や年間所得が百万円未満の世帯の割合が増加するなど、相反するような結果が出ていた。
常本教授は「これまでアイヌ民族について、さまざまな研究がなされてきたが、基本的なデータが十分ではなかった。できる限り網を広げて調査、分析したい」と強調する。
ウタリ協会の阿部一司副理事長も「国や道に施策の充実を求めていくためにも、今回の調査は大いに意義がある」と期待している。
北大アイヌ・先住民研究センター(センター長・常本照樹法科大学院教授)は本年度から三カ年計画で、道ウタリ協会(加藤忠理事長)と共同で、道内のアイヌ民族を対象に、初の大掛かりな実態調査を行う。調査を通じてアイヌ民族を取り巻く教育や就労、生活環境を把握する考えで、調査対象は少なくとも数千人規模に達する見通し。国会などでアイヌ民族の権利をめぐる議論が活発化する中、調査結果は今後の国や道の施策にも影響を与えそうだ。
調査は、北大で社会学を専攻する小内透教授とともに行う。初年度は、道内に約三千七百人いるウタリ協会会員をはじめ、その家族や親族など非会員の人も対象に、十月にアンケートで実施する。
二〇〇九年度は、調査対象を胆振や釧路管内などアイヌ民族が多く住む地域に絞り、生活相談員らが出向き、より詳細な項目について聞き取り方式で調査する。
最終年の一〇年度は、海外の先住民族の実態を調べ、アイヌ民族との比較などを行う。
調査結果は年度ごとに公表し、一一年度に最終報告書をまとめる考えだ。
これまでアイヌ施策の基礎データとなってきたのは、道がおおむね七年に一回実施してきたアイヌ民族の生活実態調査だった。
しかし、聞き取り調査の対象が全道で七百人程度と少ない上、調査地域や対象者選びにも偏りがあるなどとして、ウタリ協会や研究者から「実態を反映していない」と疑問視する声が出ていた。
実際、〇六年十月の道の調査では、生活が「とても苦しい」という回答が七年前の31%から0・3%に激減する一方で、生活保護世帯や年間所得が百万円未満の世帯の割合が増加するなど、相反するような結果が出ていた。
常本教授は「これまでアイヌ民族について、さまざまな研究がなされてきたが、基本的なデータが十分ではなかった。できる限り網を広げて調査、分析したい」と強調する。
ウタリ協会の阿部一司副理事長も「国や道に施策の充実を求めていくためにも、今回の調査は大いに意義がある」と期待している。















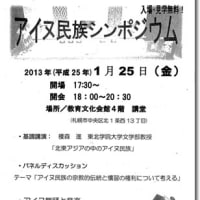

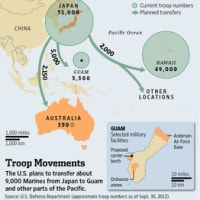


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます