 | 暮らしの哲学池田 晶子毎日新聞社このアイテムの詳細を見る |
大学生の頃、友人のひとりが、「毎年、春になると、とても憂鬱な気分になる」と言ったことを覚えている。
春は、寒い冬が終わり、暖かくなる季節。
桜が咲き、新入学の学生や、新入社員の姿は、とても初々しい。
明るい雰囲気が漂う季節に、どうして憂鬱になったりするのだろう?
当時の私は、友人の「春は憂鬱」発言を、不思議に思った。
池田晶子・著の「暮らしの哲学」のなかに、『春に思う「この感じ」』というエッセイが収められている。
これを読んで、「春は憂鬱」の理由を、少し理解できた気がする。
私自身について考えてみても、春は「憂鬱」まではいかないが、小さな痛みを感じる季節になりつつある。
池田晶子氏は、安岡章太郎氏の文章のなかに「春は残酷な季節だ」と書かれていたことについて触れる。学生時代には、「春は残酷な季節」の意味がよく分からなかった。しかし、年月が経ち、人生を積み重ねたとき、この言葉を実感した。
池田氏は、次のように書いている。
春を残酷と感じるのは、始まりは痛みであるからだ。
始まりが痛みであるのは、過ぎ去って還らないものを後ろに残して始まる、そのことが「痛い」のだ。
人生は過ぎ去って還らないけれども、春は、繰り返し巡り来る。
一回的な人生と、永遠に巡る季節が交差するそこに、桜が満開の花を咲かせる。人が桜の花を見たいのは、そこに魂の永遠性、永遠の循環を見るからだ。それは魂が故郷へ帰ることを希う(ねがう)ような、たぶんそういう憧れに近いのだ。
始まりを繰り返すことの痛みは、終わりへ向かうことの痛みでもあるだろう。花は儚いと人は言う、自分の人生がそうであるように。
「春は憂鬱」と言った友人は、おそらく、私よりもずいぶん大人だったのだろう。
過ぎ去った10代は戻らない。
あと数回、春が来たら、その後は、社会へ出なくてはならない。
私の友人は、すでに社会に出ている大人たちの姿に幻滅し、「春が来なければいいのに」などと考えていたのかもしれない。

















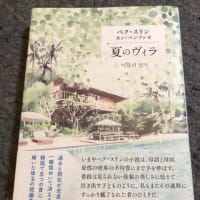


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます