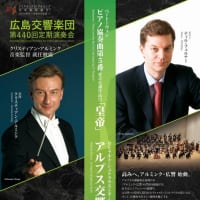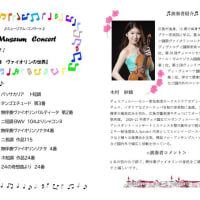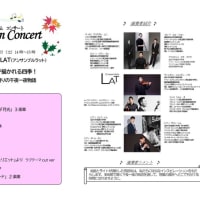マツダミュージアムに行ってきました。
マツダミュージアムに行ってきました。2023年11月
感想は正直う~んです。
ネットで予約をし、当日本社ビル1階に集合し、9:15分バスでマツダ宇品工場内にあるミュージアムまで移動します。本社ビルとミュージアムのある宇品工場は猿猴川をマツダ私設の橋を渡って10程度かかります。工場内の通路には何か所か交通信号機があり、数回停車して待たされます。バスは工場内の工員移動用のバスを使っているらしく、旧式で(さすがに製造メーカーの名前がわからないよう巧みに隠してある)座席が狭く、工場見学用に最新バスを備えることはコスト的に大きな負担とは思いますけど、客をもてなす姿勢が伝わりません。この時点で、かなりテンションが下がります。速谷神社(地元の著名神社で交通安全にご利益があるとされています)のお守りが運転席上部についていました。合理性を追求する近代産業の象徴である自動車工場でお守りとは、面白い組み合わせです。工場内の高台に「稲荷神社」が祭られていました。
移動時に見える工場敷地内は、さすがにメーカーらしくキチンと清掃されており、道路上に異物が全く見られません(異物が転がっていれば、それは即、部品の脱落・欠品等の事故ですから)。工場内の清掃は、製造メーカーにとってイロハのイですから当然といえば当然ですね。
ミュージアムにつくと所長が挨拶をし、所長と案内役の女性職員2名で引率開始です。
まずは、マツダ創業の歴史。まあ、関係者以外どうでもいい話ですよね。
次にマツダ車の変遷。オート三輪から初代の軽「マツダR360クーペ」、「キャロル」と懐かしい車が並びます。私の父が一番最初に軽トラの中古を買ってきた時の感動がよみがえります。姉と私が交代(軽トラですから二人乗りです)で父に乗せてもらい近所をドライブしました。世界が一気に広がったような、父が誇らしいような、本当にうれしい一日でした。
気になったのは、我が家の愛車だったマツダの大衆車「カペラ」や、カペラの高級化路線に位置づけられた後継者「クロノス」の展示がなかった点です。ちょっと悲しかったですね。「カペラ」は、当時マツダが提唱していた空気抵抗の低減(空気抵抗係数 CD値の低減)を図った車で、空気抵抗を抑えるシンプルなデザインながら、室内空間の最大化を目指した極めて合理的な設計でした。ボンネット高を抑えるために、エンジンはショートストローク化し、広い室内空間を確保したうえで走りも楽しめる名車だったと私は思います。
続く「クロノス」は、時代が高級化路線を歩むという前提で開発されたファミリーカーでしたが、バブル崩壊で瞬く間に消えてしまいました。2000CCV型6気筒エンジンは高トルクでともかく静か。4速ATはあくまでスムーズで、ドアは分厚く横方向からの衝突安全性を高めていました。室内の造りも上質で、これでやっと我家も中流家庭の仲間入りができたような気がしたものです。燃費もそんなに悪くはなく、10Km/L前後ははいっていたと思います。バブル崩壊が無ければ‥とは思います。その後、子どもが3人に増え、同居する両親と7人家族になりましたので、乗車定員8名にステップワゴンに乗り換えましたが、さすがに、エンジン音や走りの質など、明らかにクロノスとは劣りました。余裕があれば持ち続けたのに残念でした。「クロノス」は、バブルにのってマツダが高級路線に転換し経営危機を招いた象徴のような車。展示されないのは当然なのでしょうが、ちょっと寂しいですね。車そのもののは大変いいのですから。
次にル・マン24で総合優勝を果たした「マツダ787B」の展示です。マツダは何度かル・マンに挑戦していました。日本人ドライバ寺田陽次郎の活躍もうれしかったですね。そして、1991年のル・マン24時間レースにおいて総合優勝を果たします。展示されているのはまさにその車体です。一緒に回っている「所長」にちょっと訊ねてみましたが、あまり詳しくない様子。専門的?質問は思わず控えてしまいます。
続いて現在のマツダ車づくりのコーナーになります。マツダと言えば、EVや自動運転の開発には明らかに後れをとっているメーカー。その点を訊ねてみようというのが、私としては最大の見学目的でしたが・・。
EVについては、車を生産して廃車にするまでの総CO2排出量は、今の時点ではEVもガソリン車も変わらないという説明。その前提は、EVに供給する電力も化石燃料で発電しているからとのこと。えっ、今はそうだけど近い将来には自然エネルギーでの発電が大勢を占めるのではないの?と突っ込みを入れたくなります。
自動運転については、「マツダはあくまでも人車一体のドライブをする楽しさを求めており、技術はあくまでそれを補足するものと考えている。(略) 自動車の運転は認知症の予防になるとのデータもありますし・・。」とのこと。えっ、老人の誤操作による悲惨な交通事故をどうとらえているのでしょうか。ホンダなどのトップメーカーが自動運転が当然の機能となった後の差別化(車内での快適性や娯楽性)の研究投資を行っているのに、マツダはこの段階?と驚きます。
隣接している組立工場の見学は面白く観させていただきました。
続いては、マツダのデザインについてのコーナーです。ここで驚いたのはデザインの「ご神体」が展示されていることです。高校の生物で筋肉の電気反応で使った「カエルの足」のような筋肉の塊のようなステンレス製オブジェです。デザインに行き詰ったら、これを観てデザインの参考にするとのこと。えっです。私個人としては、デザインとは必然の末にあるものと考えています。我家の愛車だった「カペラ」や「クロノス」は、空気抵抗の減少や側面衝突安全性の確保のための必然的形であったと理解していました。車に求められる機能を最大限追求し、究極的に最後に残った形が最良のデザインだと思います。まず、車づくりをデザインから入るのは私の考えにはちょっと合いません。車を工芸作品に位置付ける考えもあるでしょうが、ユーザーはそのためのコストを払うことに納得しているのでしょうか。
ということで、2時間の見学は終了となりました。ちょっと不満顔の私たちに案内の女性が「月1回程度、時間制限のないフリーな見学の実施も予定しています。その際は、開発や現場の担当者も同席してゆっくり皆様のご質問にも応えられるかと思います。」と説明していました。ぜひ、開催してもらいたいものです。
以前、行きつけの飲屋さんで、マツダのブレーキ部門の技術者グループと同席したことがあります。ブレーキパッドの材料、耐摩耗性、踏んだ時の感触、コスト、放熱性など、1時間以上も楽しく?話をしたことを思い出します。自動車は技術、そして製造思想の塊で、いくら話をしても語りつくせない魅力が満載なのです。そうしたユーザーの期待に応える場をマツダミュージアムには提供してもらいたいですね。
窮屈な席に座らされてバスでマツダ本社ビルに帰って来て解散です。私たちは併設されているタリーズでちょっと遅い朝食をとりました。タリーズの内装も、う~んです。近所のホームセンターで買ってきたような安っぽい椅子。雑然とした店内。せっかくマツダ本社ビルなのですから、マツダで採用している地元内装部品メーカーの造った椅子をいれるとか、ロビー全体のデザインコンセプトを統一するとかしてもらいたいと思います。
まあ、楽しかった見学ですが、マツダが今後世界的自動車メーカーとして生き残れる先進性・独創性があるかという視点から見れば、う~んです。デザイン編重のクラフトマンシップも結構ですが、会社全体として次の時代を観る能力が欠けているような気がしてなりません。