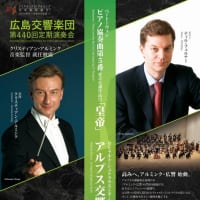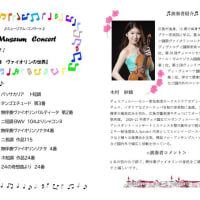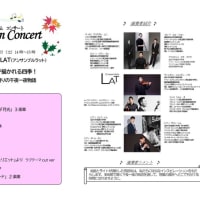2024年1月21日(日) 16時00分開演
ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール
■指揮/沖澤のどか
■ハープ/吉野直子
■管弦楽/京都市交響楽団
曲目
オネゲル:交響曲 第5番「三つのレ」
タイユフェール:ハープと管弦楽のための小協奏曲
イベール:寄港地
ラヴェル:ボレロ
会場
初めて入った会場。すごく豪華。エントランスホールは、まるでサンピエトロ大聖堂?のような高い円形ドームの上から天窓の光が降り注いでいました(福山にはちょっと似合わないかな・・)。ホール内部の壁面は木材で仕上げられ音響も良さそう。何より特徴的なのは席の配置で、宝塚劇場のように前列の観客の頭が重ならないように互い違いにずらして配置してあります。しかも、前列との段差が高い。さらに、席の配列の方向が微妙にずらしてあり、よくある会場のように席が前後に直線状に並んでいません。これはすごい配慮です。コンサートでいい席のチケットをゲットできたと喜んででかけても、前席にやけに体のでかい男性や、ヘアースタイルに凝った女性が座ると視界が妨げられてイライラすることがありますが、このホールなら安心して鑑賞できそうです(今回は前席が空いていました)。
入口近くには、飲食提供のスペースがあり当日もコーヒー等のソフトドリンクの提供をしていました。ちらっと見た感じでは、数もそんなに出ていない様子で人件費などを勘案すれば利益は出ていないのではないでしょうか。パリのオペラ座やウィーン国立オペラ座のような幕間にシャンパン片手の社交界という風になればいいのでしょうね。
スタッフの数や対応は特に問題ありません。席の誘導なども積極的にされていました。私たちは自家用車を使用したのですが、コンサート終了の時間に合わせて福山駅までの臨時バスを準備しているというアナウンスがありました(料金は確か170円)。こういう心遣い、いいと思います。
でも、肝心の客の入りは大目にみても6割程度。もったいない感じです。
沖澤のどか
彼女については、2019年6月20日の 広島交響楽団 Music for Peace コンサートにおいて、ペンデレツキ氏の代役としてベートーヴェンの交響曲第8番の指揮をしたのを聴いたことがあります(バーンスタインの代役をした大植氏の再来?)。その時は「だれ、この人?」という感じで、特に演奏内容に特徴もなく印象に残っていません。急な指揮者交代で「何か損をした感じだよね」と一緒にいった妻と話したと思います。その印象があったものでしたから、最近の彼女の人気を知らない私としてはあまり期待をしていませんでした。
オネゲル:交響曲 第5番「三つのレ」
聴いたこともない曲です。今回のプログラム、ボレロ以外極めてマイナーな曲の選択です(そう思うのは私だけ?)。しかも近現代ですから、構成も複雑で主題の展開もわかりづらく安心して心地よく聞けるというものではありません。どうしてマニア向けのプログラムにしたのでしょうか。しかも、福山という地方都市で。今も、曲の旋律とか印象を思い出せません。
タイユフェール:ハープと管弦楽のための小協奏曲
前曲と同様ですが、ハープの超絶技巧には驚かされます。私の理解が乏しくハープと言えばアルペジオを華やかに奏でる楽器というイメージでしたが、鍵盤楽器のように右手と左手で別々の旋律を弾いたり、違う和音の進行を奏でたりと多様な表現ができるのを目の当たりにできました。しかも、吉野氏は暗譜で弾いています。いったい、数にしたらい幾つの音符が頭に入っているのでしょうか。
イベール:寄港地
これは、船旅の際の各地の印象を曲にしたというだけあって判りやすい曲でした。地中海を船旅したということですから、曲全体にキラキラした華やかさがもっとあってもいいのでは? 民族音楽的リズムももっと強調してもいいかも。
ラヴェル:ボレロ
誰もが?聴いた馴染みのある曲で、オケの技量が問われます。曲終盤の盛り上がりの部分、あくまで破綻しないで弾き切るか、多少破綻しても観客とオケの興奮度を上げて終わるか、悩むところでしょう。もちろん、一番いいのは破綻せず観客の興奮度を上げれることですけど。
う~ん。私には今回も沖澤のどか氏の魅力が何なのかよく理解できませんでした。彼女の目指している音は何なのでしょうか。京都市交響楽団の常任指揮者として曲を仕上げる時間はたっぷりあったはず。もちろん、プロとして今回のプログラムの曲はソツなく完成度を上げていましたが、それ以上の「何か」を感じることはできませんでした。カラヤンの何を演奏してもついてくる「華やかさ」、小澤征爾の曲をいったんバラバラに分解して聴衆の前でそれを再構築してみせるような「構成力」、ドゥダメルの高齢な観客も思わず立ち上がらせる「楽しさ」など巨匠と比較するわけではありませんが、指揮者の個性・魅力が欲しいのです。
京都市交響楽団を初めて聴きましたが、レベル的には高いと思われます。第一バイオリンなどは、まるで一つの楽器を奏でているように聴こえ、各団員の技量の高さを感じます。ただ、他のパートについては改善の余地がありN響と比較するのはまだ早いようです。
初めて入ったリーデンローズのすばらしさや、演奏の完成度の高さ、知らない曲を聴いたことなど、満足度の高い演奏会でした。関係者の方々のお働きに感謝申し上げます。