山崎元が「未公開原稿」に綴った"お金を巡る真実"2025/04/04 12:30 様記事抜粋<
様記事抜粋<
2024年1月1日に65歳で世を去った経済評論家の山崎元氏。「余命3カ月」を宣告され闘病中だった山崎氏が書き下ろし、ベストセラーとなった『経済評論家の父から息子への手紙』には、実は未公開の原稿があったといいます。
惜しくも絶筆となってしまったその原稿の中で、山崎氏が伝えたかったメッセージの一端を、お届けします。
「これまでの人生設計」では適応できない
「世の中は変化している」とよく言われます。しかし、大事な変化が何なのかについて、われわれはしばしば無自覚です。単に、自分が世の中の変化に適応していると自認したいために、「世の中は変化している」と言ってみているだけなのかもしれません。
こうした場合、自分にとって重要な問題・目的に対して何がどう変化したのかをあらためて考えることが効果的です。人生をうまくやっていくための戦略やプランニングにとって重要な変化は何があったのでしょうか。
経済が「デジタル化」していることや、「グローバル化」していること、さらには働き方について「改革」が必要であることは、少なくとも過去20年くらいずっと言われ続けてきましたが、私の問題意識に関連するここ数年の変化を振り返ってみましょう。
まず、2016年に翻訳本が出版されて、2017年、2018年を通じたロングセラーになった『LIFE SHIFT』(リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット著、池村千秋訳、東洋経済新報社)という書籍は、「人生100年時代」というフレーズと共に、日本人の人生設計の考え方や金融資産の運用に大きな影響を与えました。
同書は、先進諸国の平均寿命が延びていて、とりわけ長寿国である日本人は、人生が100年あるというくらいの前提で人生のプランを考える必要があることを指摘しました。
そして、「大学まで勉強して」、「就職して会社で働き」、「引退して老後を暮らす」といった3ステージ・モデルの人生設計では、長寿化時代にうまく適応できないと警告しました。
ここまでの指摘はおおむね正鵠を射ていたように思えます。あなたが会社員だったとして、定年が近づいてきた時点で「さて、定年後はどうしようか」と考えるのでは、多くの場合、全く遅いからです。その後の人生選択の幅が狭くなりますし、経済的にも、精神的にも、「人生がもったいない」。
ただ、筆者は、『LIFE SHIFT』が提示した人生設計の考え方が、いくつかの点で、少なくとも現在及び近未来の日本にあっては不適切だと考えています。私が考える方法論とは重要な点でいくつか異なります。しかし、同書の問題提起自体は大いに評価したいと思います。
金融ビジネスにとっての「人生100年時代」
ところで、『LIFE SHIFT』から生まれた「人生100年時代」という言葉は、金融業界が大いに気に入ることになりました。
もともと金融業界にとっては、老後のお金の必要性は、将来のインフレ・リスクへの対処の必要性と並んで、運用商品販売のための「2大商材」と言っていい大事なテーマです。
彼らは、「老後にはお金が必要です。しかし、お金がないと寂しい老後になりますよ」と顧客に訴えて、金融商品を売りたい。顧客の心の中に「恐れ」の感情を喚起して商品へのニーズを煽るのはセールスの常道です。
ですが、老後の不安を長々と露骨に説明して顧客を脅すのはセールストークの構成が難しいし、金融マンもあまり気が進まない。しかし、「人生100年時代です」とひとこと言うと、キャッチーな言葉で、割合上品に「長い老後にあってお金が続くかどうかが心配ですね」と伝えることができます。
人生がかつてイメージされていたよりも長いことを意識することは重要ですが、「人生100年時代」を謳う運用商品(具体的には、外貨建ての生命保険、毎月あるいは奇数月分配型の投資信託、ラップ運用など)の広告やセールスは全て疑う方がいいと申し上げておきます。
端的に言って全て無視すればいいし、仮に現在持っている場合の正解は、ほとんどの場合、即刻解約です。
「つみたてNISA」が生まれた背景
さて、「人生100年時代」は老後の経済的な備えの重要性を想起させる言葉でしたが、2018年には、つみたてNISAという長期投資のための税制優遇の仕組みができました。この制度はなかなか優れています。
しかし、この制度ができた理由は、おそらく2014年に導入されたNISA(少額投資非課税制度)というもう少し柔軟性の高い制度が、金融機関の営業に悪用されて、制度導入の目的を果たせなかったことにあったと推測されます。
長期的な資産形成に適さない分配金の多い投資信託を売ったり、投資信託を頻繁に売り買いさせて手数料を稼いだり、対面営業の金融機関の多くが、端的に言って「行儀が悪すぎた」のです。
そうこうしているうちに、2019年になって、国民にお金の人生設計の問題を突きつける大問題が勃発します
それは、平均的な家計では、公的年金だけでは老後の資金が約2000万円不足すると指摘した、金融庁主催の有識者会議が発表した報告書を巡って大騒ぎになった、いわゆる「2000万円問題」でした。
この問題では、当時の麻生太郎金融担当大臣の対応が絶妙に悪く、連日、国会やワイドショーを賑わす「大炎上」となりました。
「悪い」と批判しているにもかかわらず、筆者が事後的に「絶妙」と書きたくなった理由は、この問題が資産運用ビジネスにとって特大の「炎上マーケティング」として機能したからです。
実際、この問題のメディア露出を広告費に換算すると、天文学的な数字になっただろうと想像できます。
金融業界が何十年にもわたって「貯蓄から、投資へ」というキャンペーンを続けてもサッパリ動かなかった人々の多くが、老後の資金の問題に目覚めて、投資に関心を持つようになり、投資信託の積み立て投資口座を新規に開設するなどの動きを見せました。
「2000万円問題」とは何だったのか
ところで、「2000万円問題」は、何が本質的な問題点だったのかというと、個々人の事情によって異なる問題を「平均」で語ろうとしたことでした。正しくは、個々人が「自分の数字」で自分にとって必要な貯蓄額や将来の資産額を計算する「方法」を伝えるべきでした。平均では、役に立ちません。
少し考えると分かっていただけると思いますが、現役時代に高所得な人は現役時代の支出額も大きいでしょうし、老後の支出の必要額も大きいでしょう。彼らは、「2000万円で足りるわけがない」という不安を抱えます。
逆に、相対的に低所得な人は、現役時代の支出も小さいし、その分老後の必要額も小さいでしょう。彼らは、リタイアまでに2000万円の資金を作ることが難しいと感じています。そして、「2000万円も必要だなんて、これは大変だ」と不安になります。
つまり、「平均」の数字は、参考になるというよりも、多くの人を不安にさせます。個々の人が安心するためには、「自分の数字」による計算方法を知る必要があります。
しかし、お金に関する多くの記事や書籍では平均のデータで老後を語ろうとするものが多く、率直に言って役に立ちません。
こうした本が多い理由は、1つには、論理や計算に弱く、語るべき内容を持たない専門家が著者である場合、データで紙面を埋めて格好を付けようとするからでしょう。
また、その種の数字のデータの出所や扱い方が、しばしば生命保険のセールスに近い売り手側の視点から来ているので、当事者である個人にとって不適切な場合が少なくありません。
必要な老後資金を「自分の数字」で概算することが大切なのです
自分自身を「マネジメント」しよう
まず、これからの個人は、これまでよりも「長い人生」を前提とした人生戦略が必要です。そして、変化に適応した「働き方」や「キャリア・プランニング」を身につける必要があり、「資産」や「お金」とうまく付き合う必要があります。
これらの要素の扱い方を、「幸せに生きるために」という価値観で統合して、あたかも自分自身を1つの会社であるかのように論理的にマネージする必要があるのです。
この「自分会社」は、自分が経営を決める「社長」であり、同時に管理の対象となる「唯一の社員」でもあります。
自分の「人材価値」の作り方・守り方・使い方、自由と時間とお金の交換法則、「資本家比率」の向上、例えば「45歳」くらいで気分良く人生を折り返す2ステップのキャリア・プランニング、などを考えていかなくてはならないでしょう。
かの文豪ゲーテは、「人間の最大の罪は不機嫌である」と言いました。その通りでしょう。
さあ、上機嫌な人生に向かって歩み始めましょう!著者:山崎 元氏












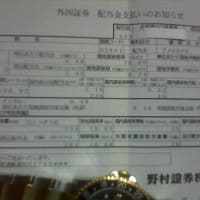

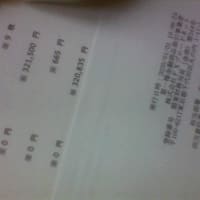
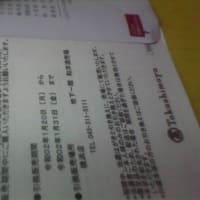

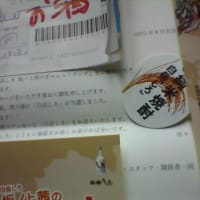

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます