
浜川崎から南武線を北上して、話は一気に府中本町に飛びます。
だって、鹿島田以外の川崎市内は「後回し」にしたから…空き時間にいつでも取材に行けるし…(^^;)
ということで、ターゲットは府中本町。
現在の駅の様子は、もちろん丹念に取材して記事に反映させましたけど。
もうひとつ、オマケとして下河原線の「東京競馬場前駅跡」を取材しておきました。
結局、記事には盛り込めませんでしたけど、ブログ用には活かせます(笑)
下河原線は国分寺と東京競馬場前、および貨物駅の下河原との間を結んでいた、中央本線の支線。
東京競馬場前駅は、1973(昭和48)年に武蔵野線が開業したのに伴い、役割を譲って廃止されました。
冒頭の写真が、東京競馬場前駅の跡。
現在は下河原線跡の多くの部分とともに、緑道になっています。
府中本町駅の西側に出て、線路沿いに南へ3~4分も歩くと、この場所に出ます。
1面2線だけの駅だったので、駅跡も狭いものですが、何となく雰囲気があります。

最初の写真の位置から、反対側を向いて1枚。
東京競馬場前駅は、南武線の線路に接する場所にありました。
写真の地下道が東京競馬場へと通じており、今も現役で使われています。

地下道を別の角度から。
左手が駅跡で、この駅から競馬場へ行く人は南武線をくぐって向っていました。

駅跡を反対側から見たところ。
奥が南武線の線路になります。

下河原線の跡も少し歩いてみました。
緑道には「電車ごっこ」の銅像もありました。

東京競馬場前駅からの線路跡の道は、いかにも鉄道らしいカーブを右へと曲がり、写真の地点で別の緑道と合流します。
まっすぐ進んでいるのが、下河原貨物駅への線路跡。
カーブして分かれているのが、東京競馬場前駅への線路跡です。

合流点から、さらに北府中方面へと緑道が続いていますが、時間の関係で、ここから府中本町駅へ引き返しました。
取材はまだまだ続きます。
だって、鹿島田以外の川崎市内は「後回し」にしたから…空き時間にいつでも取材に行けるし…(^^;)
ということで、ターゲットは府中本町。
現在の駅の様子は、もちろん丹念に取材して記事に反映させましたけど。
もうひとつ、オマケとして下河原線の「東京競馬場前駅跡」を取材しておきました。
結局、記事には盛り込めませんでしたけど、ブログ用には活かせます(笑)
下河原線は国分寺と東京競馬場前、および貨物駅の下河原との間を結んでいた、中央本線の支線。
東京競馬場前駅は、1973(昭和48)年に武蔵野線が開業したのに伴い、役割を譲って廃止されました。
冒頭の写真が、東京競馬場前駅の跡。
現在は下河原線跡の多くの部分とともに、緑道になっています。
府中本町駅の西側に出て、線路沿いに南へ3~4分も歩くと、この場所に出ます。
1面2線だけの駅だったので、駅跡も狭いものですが、何となく雰囲気があります。

最初の写真の位置から、反対側を向いて1枚。
東京競馬場前駅は、南武線の線路に接する場所にありました。
写真の地下道が東京競馬場へと通じており、今も現役で使われています。

地下道を別の角度から。
左手が駅跡で、この駅から競馬場へ行く人は南武線をくぐって向っていました。

駅跡を反対側から見たところ。
奥が南武線の線路になります。

下河原線の跡も少し歩いてみました。
緑道には「電車ごっこ」の銅像もありました。

東京競馬場前駅からの線路跡の道は、いかにも鉄道らしいカーブを右へと曲がり、写真の地点で別の緑道と合流します。
まっすぐ進んでいるのが、下河原貨物駅への線路跡。
カーブして分かれているのが、東京競馬場前駅への線路跡です。

合流点から、さらに北府中方面へと緑道が続いていますが、時間の関係で、ここから府中本町駅へ引き返しました。
取材はまだまだ続きます。











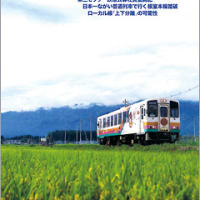

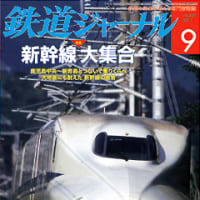






多摩川とかの砂利とかも運んでいたのでしょうね。
下河原というところは、名前の通り多摩川の側で、元は砂利を運ぶ線として建設されたそうです。
東京競馬場への観客輸送は、最初はいわば「おまけ」だったようです。
しかし武蔵野線がほぼ並行して建設されたので、廃止になりました。