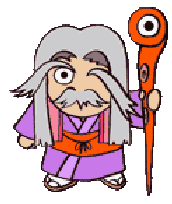景気は回復基調にあるという。トヨタ自動車が発表した2006年3月期連結決算の売上高は、日本の製造業として初めて20兆円を超えた。このところ景気のいい話が新聞紙上などで踊るが、果たしてそうなのか。
実感がわかないまま、江井ヶ島にある土木・建設会社の日置産業を訪ねた。
「確かに、業績がええ会社はあるね」。社長の日置大之さん(54)が柔和な表情で応対してくれた。
例えば、鉄骨や銅板を特殊加工している会社、という。取引先の電機・コンピューター業界が好調なのが主な理由だが、「これからは高度な特殊技術とノウハウがなければ、厳しい競争に生き残れない。中小・零細企業はなおさらだ」と話す。
こうした業績が好調な会社は、おう盛な注文をこなすために設備投資に積極的。その恩恵を受け、同社は工場の改修工事の仕事が増えている。
日置社長は「それだけじゃない」とした上で、こう付け加えた。「会社が伸びるためには優れた人材がいる。そこで、この際、食堂や女性の更衣室、シャワー室などを併せて新設する会社が少なくない」という。
父は同じ場所で牧場を営んでいた。ところが、近郊に住宅が増えてきたのに伴い、牛のふん尿がくさいと苦情が相次ぎ、建材の販売会社に業種転換。日置社長が26歳のときだった。その後、自ら一級土木施工管理者の免許をとり、先頭にたって土木・建設事業に打ち込んできた。
5年前までは売上高の8割を公共工事が占めていたが、市や県は財政難を背景に予算を大幅カット。仕事は激減し、同業者の中には倒産する会社が続出した。危機感を深めた同社は官公需の依存体質をあらため、民間の仕事に思い切ってシフト。今では比率は逆転し、8割が民間という。
「下水工事でいえば、明石市内は普及率が9割に達し、これからはやり変え工事ぐらいしかない。当社もそれをにらんで新しい工法を市に提案すべく準備しているが、やはり民間の活力が本格的に持ち直してほしい。そうなれば、店を改修しようかな、という動きが広がり、引いては業界も元気になる」
期待を込めた日置社長の大きな声が、事務所に力強く響きわたった。
実感がわかないまま、江井ヶ島にある土木・建設会社の日置産業を訪ねた。
「確かに、業績がええ会社はあるね」。社長の日置大之さん(54)が柔和な表情で応対してくれた。
例えば、鉄骨や銅板を特殊加工している会社、という。取引先の電機・コンピューター業界が好調なのが主な理由だが、「これからは高度な特殊技術とノウハウがなければ、厳しい競争に生き残れない。中小・零細企業はなおさらだ」と話す。
こうした業績が好調な会社は、おう盛な注文をこなすために設備投資に積極的。その恩恵を受け、同社は工場の改修工事の仕事が増えている。
日置社長は「それだけじゃない」とした上で、こう付け加えた。「会社が伸びるためには優れた人材がいる。そこで、この際、食堂や女性の更衣室、シャワー室などを併せて新設する会社が少なくない」という。
父は同じ場所で牧場を営んでいた。ところが、近郊に住宅が増えてきたのに伴い、牛のふん尿がくさいと苦情が相次ぎ、建材の販売会社に業種転換。日置社長が26歳のときだった。その後、自ら一級土木施工管理者の免許をとり、先頭にたって土木・建設事業に打ち込んできた。
5年前までは売上高の8割を公共工事が占めていたが、市や県は財政難を背景に予算を大幅カット。仕事は激減し、同業者の中には倒産する会社が続出した。危機感を深めた同社は官公需の依存体質をあらため、民間の仕事に思い切ってシフト。今では比率は逆転し、8割が民間という。
「下水工事でいえば、明石市内は普及率が9割に達し、これからはやり変え工事ぐらいしかない。当社もそれをにらんで新しい工法を市に提案すべく準備しているが、やはり民間の活力が本格的に持ち直してほしい。そうなれば、店を改修しようかな、という動きが広がり、引いては業界も元気になる」
期待を込めた日置社長の大きな声が、事務所に力強く響きわたった。