当然のことながら人はいつか死ぬ。どんな形でまたいつ死ぬのかそれはほとんどの場合は分からない。だから死は決して特別な事ではなく、人生の一つの通過点でしかないのかもしれない。
「おくりびと」
それはこの映画の場合は主人公である小林大悟(本木雅弘)の仕事である納棺師の事を指しているのではあるが、実は死んだ人を送る身内など全ての人が本当の”おくりびと”なのだ。いかに死に向き合いそれを受け入れて行くのか?誰かが死んだ瞬間にそれは家族など、その人に関わる人全てが行わなければいけない悲しくも厳かな儀式なのだ。
東京のオーケストラでチェロ奏者をしていた小林大悟(本木雅弘)は、突然そのオーケストラが解散となって仕事を失い、自分の才能の限界も感じて妻の美香(広末涼子)と共に故郷の山形に帰って再就職先を探す。そこでNKエージェントなる会社の求人広告を見た大悟は早速応募するが、まともな面接も無く社長の佐々木生栄(山凬努)採用されてしまう。どんな仕事かを聞くとそれは遺体を棺に納める「納棺師」の仕事だった。妻の美香には本当の仕事の内容も言えずに、大悟はいろんな納棺の現場に立ち会う。厳しい現場や、その仕事を決していいイメージに持たない人達の偏見に耐えられなくなっていきながらも、その納棺という儀式の愛情溢れる仕事にどんどん魅了されていく大悟。しかし、妻の美香にその仕事の内容がばれた時に、辞めるように言われた大悟は美香からつらい言葉を投げかけられる「汚らわしい!」。妻も出て行ってしまったが、それでも納棺師の仕事に意義を見いだした大悟は仕事に真摯に向き合って行く。やがて懐妊した美香も家に戻ってきて、知り合いの納棺の儀式に立ち会う事で大悟の仕事を理解していく。そして、そんな大悟の元に自分を捨てて家を出た父の死を伝える電報が届く・・・
死に向き合う映画ではあるが、冒頭から大悟が納棺の仕事を始めるまでは、かなりコミカルなシーンが多くて爆笑がわき起こるくらいだった。それが死をテーマにしながらもこの映画を暗くさせない事に成功している。死も様々。時には端から見ると、不謹慎ながらも滑稽な事も起きる。その辺をうまく不謹慎な感じにさせずに笑いにしているセンスが見事。
俳優陣では、何と言ってもコミカルな演技から、妻を愛する優しい顔、そして死に接して神聖なまでの丁寧な仕事を見せる本木雅弘の演技が素晴らしい。そして、その師匠である山崎努がやはり渋いいい演技を見せてくれる。また広末涼子はやはりかわいく、時に感情をぶつけながらも夫を心から支える素晴らしい妻を演じ切っている。
音楽は久石譲。主人公の大悟役の本木雅弘がチェロ奏者という事で印象的なチェロの素晴らしい音楽が映画を優しく包む。また舞台の山形の美しい自然。鳥海山の美しい山並みの前で本木雅弘がチェロを奏でるシーンが美しい。
納棺の儀式は実に厳かで美しい。初めに遺族の前に横たわる遺体は死んで間もなく、顔に乗せられた白い布を外したときに、その顔は死の苦しみを湛えるかのように疲れた顔立ちである。納棺の儀式はそこから故人を安らかに”旅立たせる”為にその身支度をする作業だ。まずは顔を整え、体を清める。儀式にあたっては遺族はそれを見ながら故人との別れの時間を過ごす。
体を清める時にはいったん来ていた服を脱がせてるが、肌を見せないように、布団を掛けて体を拭いていく。そして、やはり肌を見せないようにして死に装束を着せて行く。そして最後に顔に化粧をする。その時には女性であれば生前使っていた口紅などを塗ってあげる。納棺師は生前の遺影を見て、それに近づけるように丁寧に顔を整えていく。
この一連の作業が厳かでそして故人への愛情に満ちた作業なのだ。
印象深いシーンがあった。妻を亡くし動転して、少し遅れて来た納棺師を怒鳴りつける夫。やがて納棺の儀式が始まる、疲れたような妻の顔が段々と整えられ、納棺された時は綺麗な顔になる。そしてその儀式が終わった時に夫は先ほど怒鳴った事を詫びて、「あいつ今まで一番きれいでした。ありがとうございました。」ぐっと涙が止まらなくなってしまった。
つらい別れだが、生きているものはその死を乗り越えて生きていかなければならない。そのためにも故人との最後の別れの儀式はとても大切で愛情溢れるものでなければならない。いろんな別れが映画の中では描かれる、かなりキツイ現場の場合もあるが、亡くなったお婆さんが生前の希望だからとルーズソックス穿かせてあげたり、大往生したお爺ちゃんの顔に家族で一杯キスマークを付けて「今までお疲れ様でした」と泣きながらも笑って送ったり。
死を描きながら、この映画は生きる事への愛情に溢れていると感じた。それは”おくりびと”が一生懸命に生きていく姿ゆえではないか?初めて死に接した大悟が思わず美香を激しく抱きしめてその生を実感しようとする姿だったり、社長の佐々木が「死ぬ気にならなきゃ、生き物を食べなきゃいけない」と言って、美味しいモノをむさぼり食うシーンだったり。死を意識する事で人は生への執着を見せる。死に接する機会が多いからこそ”命”を大事に思う。
私は先日伯父を亡くした。伯父のいる本家に早朝に行ったときにはまだ伯父は仏間の前で白い布を顔に被されて横たわっていた。私はその後葬儀の事もありその場を離れたが、その時の顔は長い闘病で疲れた顔で見るのもつらかった。でもそこで恐らく納棺の儀式が行われた事だろう。その後棺の中の伯父は昔の伯父のような穏やかな顔になっていた。出棺の時、最後の別れで伯父の顔を見ていて、ついに涙がとどまらなくなった。その時伯母が一言伯父に向かって言った。
「長くつらい思いをさせてしまって・・・ご苦労様でした・・・」
伯母こそ大変だったろうに、この一言に夫婦の絆を強く感じた。伯母は「おくりびと」として最大限の愛情を「おくられびと」である伯父に注いでいたのだろう。
故人の思いを胸に、僕らは精一杯生きていく。主人公大悟の妻美香のお腹には新しい命が宿っている。最後に送った父親から受け継いだ”思い”をその子に託して、命は引き継がれていく。
「おくりびと」
それはこの映画の場合は主人公である小林大悟(本木雅弘)の仕事である納棺師の事を指しているのではあるが、実は死んだ人を送る身内など全ての人が本当の”おくりびと”なのだ。いかに死に向き合いそれを受け入れて行くのか?誰かが死んだ瞬間にそれは家族など、その人に関わる人全てが行わなければいけない悲しくも厳かな儀式なのだ。
東京のオーケストラでチェロ奏者をしていた小林大悟(本木雅弘)は、突然そのオーケストラが解散となって仕事を失い、自分の才能の限界も感じて妻の美香(広末涼子)と共に故郷の山形に帰って再就職先を探す。そこでNKエージェントなる会社の求人広告を見た大悟は早速応募するが、まともな面接も無く社長の佐々木生栄(山凬努)採用されてしまう。どんな仕事かを聞くとそれは遺体を棺に納める「納棺師」の仕事だった。妻の美香には本当の仕事の内容も言えずに、大悟はいろんな納棺の現場に立ち会う。厳しい現場や、その仕事を決していいイメージに持たない人達の偏見に耐えられなくなっていきながらも、その納棺という儀式の愛情溢れる仕事にどんどん魅了されていく大悟。しかし、妻の美香にその仕事の内容がばれた時に、辞めるように言われた大悟は美香からつらい言葉を投げかけられる「汚らわしい!」。妻も出て行ってしまったが、それでも納棺師の仕事に意義を見いだした大悟は仕事に真摯に向き合って行く。やがて懐妊した美香も家に戻ってきて、知り合いの納棺の儀式に立ち会う事で大悟の仕事を理解していく。そして、そんな大悟の元に自分を捨てて家を出た父の死を伝える電報が届く・・・
死に向き合う映画ではあるが、冒頭から大悟が納棺の仕事を始めるまでは、かなりコミカルなシーンが多くて爆笑がわき起こるくらいだった。それが死をテーマにしながらもこの映画を暗くさせない事に成功している。死も様々。時には端から見ると、不謹慎ながらも滑稽な事も起きる。その辺をうまく不謹慎な感じにさせずに笑いにしているセンスが見事。
俳優陣では、何と言ってもコミカルな演技から、妻を愛する優しい顔、そして死に接して神聖なまでの丁寧な仕事を見せる本木雅弘の演技が素晴らしい。そして、その師匠である山崎努がやはり渋いいい演技を見せてくれる。また広末涼子はやはりかわいく、時に感情をぶつけながらも夫を心から支える素晴らしい妻を演じ切っている。
音楽は久石譲。主人公の大悟役の本木雅弘がチェロ奏者という事で印象的なチェロの素晴らしい音楽が映画を優しく包む。また舞台の山形の美しい自然。鳥海山の美しい山並みの前で本木雅弘がチェロを奏でるシーンが美しい。
納棺の儀式は実に厳かで美しい。初めに遺族の前に横たわる遺体は死んで間もなく、顔に乗せられた白い布を外したときに、その顔は死の苦しみを湛えるかのように疲れた顔立ちである。納棺の儀式はそこから故人を安らかに”旅立たせる”為にその身支度をする作業だ。まずは顔を整え、体を清める。儀式にあたっては遺族はそれを見ながら故人との別れの時間を過ごす。
体を清める時にはいったん来ていた服を脱がせてるが、肌を見せないように、布団を掛けて体を拭いていく。そして、やはり肌を見せないようにして死に装束を着せて行く。そして最後に顔に化粧をする。その時には女性であれば生前使っていた口紅などを塗ってあげる。納棺師は生前の遺影を見て、それに近づけるように丁寧に顔を整えていく。
この一連の作業が厳かでそして故人への愛情に満ちた作業なのだ。
印象深いシーンがあった。妻を亡くし動転して、少し遅れて来た納棺師を怒鳴りつける夫。やがて納棺の儀式が始まる、疲れたような妻の顔が段々と整えられ、納棺された時は綺麗な顔になる。そしてその儀式が終わった時に夫は先ほど怒鳴った事を詫びて、「あいつ今まで一番きれいでした。ありがとうございました。」ぐっと涙が止まらなくなってしまった。
つらい別れだが、生きているものはその死を乗り越えて生きていかなければならない。そのためにも故人との最後の別れの儀式はとても大切で愛情溢れるものでなければならない。いろんな別れが映画の中では描かれる、かなりキツイ現場の場合もあるが、亡くなったお婆さんが生前の希望だからとルーズソックス穿かせてあげたり、大往生したお爺ちゃんの顔に家族で一杯キスマークを付けて「今までお疲れ様でした」と泣きながらも笑って送ったり。
死を描きながら、この映画は生きる事への愛情に溢れていると感じた。それは”おくりびと”が一生懸命に生きていく姿ゆえではないか?初めて死に接した大悟が思わず美香を激しく抱きしめてその生を実感しようとする姿だったり、社長の佐々木が「死ぬ気にならなきゃ、生き物を食べなきゃいけない」と言って、美味しいモノをむさぼり食うシーンだったり。死を意識する事で人は生への執着を見せる。死に接する機会が多いからこそ”命”を大事に思う。
私は先日伯父を亡くした。伯父のいる本家に早朝に行ったときにはまだ伯父は仏間の前で白い布を顔に被されて横たわっていた。私はその後葬儀の事もありその場を離れたが、その時の顔は長い闘病で疲れた顔で見るのもつらかった。でもそこで恐らく納棺の儀式が行われた事だろう。その後棺の中の伯父は昔の伯父のような穏やかな顔になっていた。出棺の時、最後の別れで伯父の顔を見ていて、ついに涙がとどまらなくなった。その時伯母が一言伯父に向かって言った。
「長くつらい思いをさせてしまって・・・ご苦労様でした・・・」
伯母こそ大変だったろうに、この一言に夫婦の絆を強く感じた。伯母は「おくりびと」として最大限の愛情を「おくられびと」である伯父に注いでいたのだろう。
故人の思いを胸に、僕らは精一杯生きていく。主人公大悟の妻美香のお腹には新しい命が宿っている。最後に送った父親から受け継いだ”思い”をその子に託して、命は引き継がれていく。
 | 「おくりびと」オリジナルサウンドトラック久石譲,サントラUNIVERSAL SIGMA(P)(M)このアイテムの詳細を見る |
 | So Special-Version AI-/おくりびと(初回限定盤)(DVD付)AI,ATSUSHI,久石譲UNIVERSAL SIGMA(P)(M)このアイテムの詳細を見る |















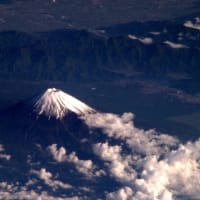


私も、この映画に注目をしていて、近くMIXで書こうかなと、思っておりました。
「人は、いつか、おくりびと、おくられびと」・・・・・・・
このフレーズが頭から、離れません。
まだ、実際に見たわけではないのですが、その映像の美しさ?日本らしさ?が伝わってくるようです。
めずらしく、あの、おずぎさんが、べた褒めしていたんです。おずぎさんって邦画の評価は・・・・・・・・・
なのにこの映画に関しては、すごかった。
そんなこともあって、私も是非映画館で見ようと決めております。実際に鑑賞したら、また感想を書きます。
日本人は、生と死に関して、非常に特異的な意識があるようです。最近は薄れてかも?
それが、証拠に四川大地震のときに、遅ればせながら、現地へ赴いた救援隊が、犠牲者に見せた姿勢が中国(現地)の人々に、感動を与えたそうです。中国では、死者にたいして、日本人のような扱いをしないのだそうです。
この映画では、日本人の日本人らしさが写されていると思います。
死生観というのは国民性もあるかもしれませんが、結局は人ぞれぞれです。最近は人の死に接する機会が多いせいか大いに考えさせられます。
まずは身近な親やもしかしてパートナーだっていつだっておくり、おくられる存在になるかもしれません。そんな事を感じさせてくれる映画でした。
モントリオール映画祭でも受賞し、米国アカデミー賞でも外国語映画賞でノミネートされているようです。日本のこの死生観が不偏なものとして受け入れられれば・・・何か救いを感じる思いがします。
実はモックンが苦手かも?と思っていた私でしたが、
いい表情を見せていて、古来からの日本人らしさの表現が
うまい役者さんなのかもしれないと再認識したりもしました。
テーマも斬新さには、驚きでしたが(いい意味で)、
多くの人が見たほうがいい映画かもしれませんね~
あっ、またしばらくチェロにハマりそうです(*^ー^*)
今もハイドンのチェロ協奏曲聴いてました♪
奏者はデュ・プレです☆
私も最近親戚を亡くし、とてもぐっと来る映画でした。
日本人らしい美しい表現ですよね。日本人の古くからの死への考え方とかも良く表している素晴らしい映画でした。
私はモックンは比較的好きな俳優さんでしたが、今回のチェロを弾く姿や納棺師としての演技はとても良かったですね。
私もやっぱり映画を観た後はチェロを聴きたくなって、ずっと聴いています。この記事を書いている時はヨーヨーマのバッハの無伴奏チェロ組曲を聴いてました
35年くらい、近親者との別れを経験していない私には、とても参考になる作品でした。
モックン、広末さん、納棺師の様式美、北国の自然、音楽等、作品の全てが美しかったですね。海外で評判が良いのも判る気がします。
それにしても、死に係わる仕事の中で、お坊さんや神父さんや医者には尊敬の想いを持つのに、納棺師や火葬場の仕事等の葬儀関係の仕事に対しては、劇中の広末さんや哲太さんと同じような感情を持ってしまうのはナゼですかね?。私も彼らと同じ感覚を持っているのに鑑賞中に気がつきました。
やはり実際に体験をしてみないと、その仕事の重要性って理解できないモノなのですかね?。
「自分の感覚を改める必要があるなぁ」と思いながら、映画館を後にしました。
今年みた「ぐるりのこと。」「歩いても歩いても」「おくりびと」の3作品は、色々と考えることが多い作品でした。
日本独自の様式美と死者への尊厳というものがきっと世界的にも評価される事だと思います。
日本で葬儀関係の仕事をしている人に差別意識を持ってしまうというのは歴史的な背景もあるようです。それと最もプライベートな部分に関わるので、あまり目立つような事をしないというのもあると思います。
それでもきっと身内の死に立ち会う機会があれば、その有り難さを感じる事もあると思います。
お互い自分が先に死ぬような事でも無ければ、恐らく近いうちに”身近な人”の死に立ち会う事になると思います。その時にどんな思いで送るのか?僕はあの火葬場で点火を努める職員の方の一言が全てだと思います。あそこが本当のクライマックスだったかもしれないですね。
それと主人公の父役で死者として映画に出演された峰岸徹さんが亡くなられたのは何か因縁深いものを感じました。元気な方とばかり思っていたので、病魔と闘っていたというのは驚きです。今改めてみればあのラストシーンはもっとぐっとくると思いますね。