ルワンダで起きたこのジェノサイド(虐殺)の事を私は最近まで詳しくは知らなかった。そもそも我々日本人は常にブラウン管の向こうに、世界のどこかで常に起きている紛争や戦争を押し込めて、その前で無関心を決め込むだけなのだ。私もそんな一人だ。
ルワンダのこの悲劇を詳しく知ったのは、昨年見た「ホテル・ルワンダ」だった。この映画は実在した、虐殺から1,200人もの人々を救ったルワンダ人ホテルマンの話だ。映画は彼の視点から描かれる。だからルワンダ人側の視点だ。
この映画を見てルワンダで何が行われたのかを知ったのだが、このルワンダでの事件で重要な点が2つある。
一つは同じルワンダ人でありながら、ツチ族とフツ族という二つの部族間で起きた虐殺事件だという事
そしてもう一つは現地に居た国連軍が多く居ながらも、この虐殺を防げなかった事、そして国連は西欧の諸国の思惑からこの国を見捨てた事が虐殺に拍車を掛けた事だ。
そしてこの映画は、白人であるイギリス人の青年ジョー・コナー(ヒュー・ダンシー)の視点で描かれたものだ。
この映画では重要なキーワードがある。それはもう一人の主人公の同じく英国カトリック教会のクリストファー神父(ジョン・ハート)がこの虐殺の中で葛藤する神の存在である。
神父はこの映画の舞台となった公立技術専門学校(ETO)を運営していて、その中でルワンダ人を集めてキリスト教のミサを行っていた。神父は彼らに神の存在を説き、いかなる時も神は我々を守ってくれているのだと説いていた。
そして、フツ族の民兵達による虐殺が始まると、神父を頼り、またこの学校を国連の平和維持軍として派遣されていたベルギー軍が駐屯地として駐留していたために、多くの避難民が学校に逃げ込んできた。
やがて、ジョーや神父は学校の外で行われている残虐なジェノサイドを目の当たりにしていく。そして、学校の周りにも虐殺を行っている過激派民兵達が集まり始める。ベルギー軍の存在でかろうじて彼らの流入を防いでいる学校である、実はその国連軍もルワンダ人を守る何の権限を持っていないのだ。彼らがその武器を使用するのは自衛の為のみであり、もしこの虐殺に介入するならば、国連安保理の理事長の許可が必要なのだが、この時、既に国連はルワンダを見捨てようとしていた。
刻一刻と生命の危機を感じる学校内のツチ族の人々。生徒である少女マリー(クレア=ホープ・アシティ)もその一人だった。彼女の事を特に案じていたジョーは「一緒にいるから」と約束し安心させる。
しかし、この学校に居た白人達だけがフランス軍の部隊に救助され、ベルギー軍以外は、神父とフランス軍のトラックに乗ることを拒否したジョーのみとなった。彼らにすがるように救いを求めるルワンダ人達。しかし、ついにベルギー軍にも撤退の命令が出て、この学校にいるルワンダ人達は完全に見捨てられる事になった。そこで神父とジョーは選択を決断を迫られ、神父はルワンダ人と運命を共にし、ジョーはベルギー軍と逃げる事を選択する。そして、完全にベルギー軍が撤退した学校に虐殺者達が流れ込む。僅か数時間で2,500名のルワンダ人が虐殺された。
言葉を失うシーンの連続だ。虐殺の中で白人であるジョーと神父の葛藤が描かれる。やがて彼らは神の沈黙に大きな疑問を抱き始める。
原題の「Shooting Dogs」は、ベルギー軍の隊長と神父のやり取りで出てくる。隊長は学校の周りに虐殺されたルワンダ人の死体を食べている野犬を衛生上の問題から撃ち殺してもいいか?と神父に尋ねた時に、虐殺のおぞましい現場を見て帰ってきた神父は怒り狂って言う「犬たちは君たちに発砲したのかね!国連軍は自衛の為にだけ武器の使用を許可されている。ならば犬が君たちに発砲したから、撃つんだろうね!」Shooting Dogs=発砲する犬。この言葉は白人社会のルワンダ人=黒人社会への無関心への比喩にもなっているのではないだろうか?目の前で非人道的な行為が行われているのに、何ら手出しが出来ない。それは軍隊だけではなく、神父としての自分が何も出来ない事への自らへの怒りにも繋がっていく。
映画の中でフランス人の女性ジャーナリストが呟く言葉にもその事が現れている。「ボスニアで虐殺された中年女性の死体を見ては泣いていた。それが自分の母親に重なったから。でもここでは全く無関心な事に気づいた。そこにあるのは”ただのアフリカ人の死体じゃない”って」自虐的にそう言った。
神の沈黙の前に神父は自問自答を繰り返す。ベルギー軍が秘かに撤退の準備を始める中で行われるミサのシーンが何とも言えないシーンになっている。神は沈黙している。少女マリーも「神は私たちの事は見守ってくれているの?」と神父に疑問を投げかける。やがて、ベルギー軍が撤退していく中で、神父はルワンダ人の中で、ジョーに伝える「私は今、この人々の中に神の存在を感じる。だから自分はここに残る事に至福を感じているんだよ」神父として極限状態の中で始めて得た神の存在。それは自分もキリストのように自己犠牲によってルワンダ人とともにある事で感じる事が出来た。
しかし、若いジョーはこの極限状態で「死ぬのが怖かった」ので、ベルギー軍とともに学校を去る。少女マリーに「一緒に居るんじゃなかったの?」といわれ、激しい心の痛みに苛まれながら学校を後にする。
ここで言葉を失うシーンがあった。学校内のルワンダ人の自治組織のリーダーがベルギー軍の隊長に懇願する。「ここを去る前に私たちを”銃殺”して下さい。ナタで殺されるのはつらい。出来ないなら責めて子供達だけでも苦しみの少ない形で殺して欲しい」それはベルギー軍にとっても出来る事では無かった。現場に居た国連軍でさえ、この辛い現実の中で厳しい決断を迫られていたのだ。ベルギー軍が最後に放った銃弾は空に向けたものだった。すがりつくルワンダ人を威嚇する為に・・・
神父は最後に子供達を数人トラックに隠して学校を後にする。学校はその後にすぐに虐殺が始まる。神父もトラックの子供達を逃がす為に命を落とす。その子供達の中に少女マリーも居た。
やがて、生き延びたマリーは神父が居たイギリスの学校で教師をしていたジョーに再会する。
彼女はジョーに問うた「なぜあの時に逃げたの?」。ジョーは絞り出すように答えた「死ぬのが怖かった」。マリーは彼を責める訳でも無く、こう呟いた「お互い運が良かったわね。これからも精一杯生きないとね」
神父によって生かされた2人。あまりに絶望的なこの映画の中で唯一と言っていい希望のシーンだった。
そして、エンドクレジットでは多くの虐殺の生き残りの人々がこの映画の制作に携わっている事が出ていた。
我々は神でも無いのに、まるで神のようにスクリーンの向こうで起きる事件を見ていないだろうか?ある映画でのセリフ
「この国では誰もが神様みたいなもんさ。いながらにしてその目で見、その手で触れることのできぬあらゆる現実を知る。何一つしない神様だ」
この映画は西欧社会、そして我ら日本も含めた先進国への痛烈な批判にもなっている。
ルワンダのこの悲劇を詳しく知ったのは、昨年見た「ホテル・ルワンダ」だった。この映画は実在した、虐殺から1,200人もの人々を救ったルワンダ人ホテルマンの話だ。映画は彼の視点から描かれる。だからルワンダ人側の視点だ。
この映画を見てルワンダで何が行われたのかを知ったのだが、このルワンダでの事件で重要な点が2つある。
一つは同じルワンダ人でありながら、ツチ族とフツ族という二つの部族間で起きた虐殺事件だという事
そしてもう一つは現地に居た国連軍が多く居ながらも、この虐殺を防げなかった事、そして国連は西欧の諸国の思惑からこの国を見捨てた事が虐殺に拍車を掛けた事だ。
そしてこの映画は、白人であるイギリス人の青年ジョー・コナー(ヒュー・ダンシー)の視点で描かれたものだ。
この映画では重要なキーワードがある。それはもう一人の主人公の同じく英国カトリック教会のクリストファー神父(ジョン・ハート)がこの虐殺の中で葛藤する神の存在である。
神父はこの映画の舞台となった公立技術専門学校(ETO)を運営していて、その中でルワンダ人を集めてキリスト教のミサを行っていた。神父は彼らに神の存在を説き、いかなる時も神は我々を守ってくれているのだと説いていた。
そして、フツ族の民兵達による虐殺が始まると、神父を頼り、またこの学校を国連の平和維持軍として派遣されていたベルギー軍が駐屯地として駐留していたために、多くの避難民が学校に逃げ込んできた。
やがて、ジョーや神父は学校の外で行われている残虐なジェノサイドを目の当たりにしていく。そして、学校の周りにも虐殺を行っている過激派民兵達が集まり始める。ベルギー軍の存在でかろうじて彼らの流入を防いでいる学校である、実はその国連軍もルワンダ人を守る何の権限を持っていないのだ。彼らがその武器を使用するのは自衛の為のみであり、もしこの虐殺に介入するならば、国連安保理の理事長の許可が必要なのだが、この時、既に国連はルワンダを見捨てようとしていた。
刻一刻と生命の危機を感じる学校内のツチ族の人々。生徒である少女マリー(クレア=ホープ・アシティ)もその一人だった。彼女の事を特に案じていたジョーは「一緒にいるから」と約束し安心させる。
しかし、この学校に居た白人達だけがフランス軍の部隊に救助され、ベルギー軍以外は、神父とフランス軍のトラックに乗ることを拒否したジョーのみとなった。彼らにすがるように救いを求めるルワンダ人達。しかし、ついにベルギー軍にも撤退の命令が出て、この学校にいるルワンダ人達は完全に見捨てられる事になった。そこで神父とジョーは選択を決断を迫られ、神父はルワンダ人と運命を共にし、ジョーはベルギー軍と逃げる事を選択する。そして、完全にベルギー軍が撤退した学校に虐殺者達が流れ込む。僅か数時間で2,500名のルワンダ人が虐殺された。
言葉を失うシーンの連続だ。虐殺の中で白人であるジョーと神父の葛藤が描かれる。やがて彼らは神の沈黙に大きな疑問を抱き始める。
原題の「Shooting Dogs」は、ベルギー軍の隊長と神父のやり取りで出てくる。隊長は学校の周りに虐殺されたルワンダ人の死体を食べている野犬を衛生上の問題から撃ち殺してもいいか?と神父に尋ねた時に、虐殺のおぞましい現場を見て帰ってきた神父は怒り狂って言う「犬たちは君たちに発砲したのかね!国連軍は自衛の為にだけ武器の使用を許可されている。ならば犬が君たちに発砲したから、撃つんだろうね!」Shooting Dogs=発砲する犬。この言葉は白人社会のルワンダ人=黒人社会への無関心への比喩にもなっているのではないだろうか?目の前で非人道的な行為が行われているのに、何ら手出しが出来ない。それは軍隊だけではなく、神父としての自分が何も出来ない事への自らへの怒りにも繋がっていく。
映画の中でフランス人の女性ジャーナリストが呟く言葉にもその事が現れている。「ボスニアで虐殺された中年女性の死体を見ては泣いていた。それが自分の母親に重なったから。でもここでは全く無関心な事に気づいた。そこにあるのは”ただのアフリカ人の死体じゃない”って」自虐的にそう言った。
神の沈黙の前に神父は自問自答を繰り返す。ベルギー軍が秘かに撤退の準備を始める中で行われるミサのシーンが何とも言えないシーンになっている。神は沈黙している。少女マリーも「神は私たちの事は見守ってくれているの?」と神父に疑問を投げかける。やがて、ベルギー軍が撤退していく中で、神父はルワンダ人の中で、ジョーに伝える「私は今、この人々の中に神の存在を感じる。だから自分はここに残る事に至福を感じているんだよ」神父として極限状態の中で始めて得た神の存在。それは自分もキリストのように自己犠牲によってルワンダ人とともにある事で感じる事が出来た。
しかし、若いジョーはこの極限状態で「死ぬのが怖かった」ので、ベルギー軍とともに学校を去る。少女マリーに「一緒に居るんじゃなかったの?」といわれ、激しい心の痛みに苛まれながら学校を後にする。
ここで言葉を失うシーンがあった。学校内のルワンダ人の自治組織のリーダーがベルギー軍の隊長に懇願する。「ここを去る前に私たちを”銃殺”して下さい。ナタで殺されるのはつらい。出来ないなら責めて子供達だけでも苦しみの少ない形で殺して欲しい」それはベルギー軍にとっても出来る事では無かった。現場に居た国連軍でさえ、この辛い現実の中で厳しい決断を迫られていたのだ。ベルギー軍が最後に放った銃弾は空に向けたものだった。すがりつくルワンダ人を威嚇する為に・・・
神父は最後に子供達を数人トラックに隠して学校を後にする。学校はその後にすぐに虐殺が始まる。神父もトラックの子供達を逃がす為に命を落とす。その子供達の中に少女マリーも居た。
やがて、生き延びたマリーは神父が居たイギリスの学校で教師をしていたジョーに再会する。
彼女はジョーに問うた「なぜあの時に逃げたの?」。ジョーは絞り出すように答えた「死ぬのが怖かった」。マリーは彼を責める訳でも無く、こう呟いた「お互い運が良かったわね。これからも精一杯生きないとね」
神父によって生かされた2人。あまりに絶望的なこの映画の中で唯一と言っていい希望のシーンだった。
そして、エンドクレジットでは多くの虐殺の生き残りの人々がこの映画の制作に携わっている事が出ていた。
我々は神でも無いのに、まるで神のようにスクリーンの向こうで起きる事件を見ていないだろうか?ある映画でのセリフ
「この国では誰もが神様みたいなもんさ。いながらにしてその目で見、その手で触れることのできぬあらゆる現実を知る。何一つしない神様だ」
この映画は西欧社会、そして我ら日本も含めた先進国への痛烈な批判にもなっている。
 | ホテル・ルワンダ プレミアム・エディションジェネオン エンタテインメントこのアイテムの詳細を見る |
 | 生かされて。PHP研究所このアイテムの詳細を見る |















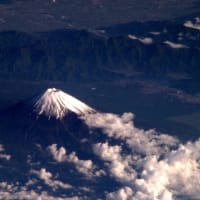


>この映画は西欧社会、そして我ら日本も含めた先進国への痛烈な批判にもなっている。
フツ族が人々を扇動するために利用したラジオ放送を妨害してくれるだけでも多くの命が救われたと、セサバギナの著書で読みました。
ルワンダという遠いアフリカで起きた出来事ではなく、とても身近にも起きつつある問題として、感じました。
大切な作品との出会いに感謝です。