遂に「のだめカンタービレ~最終楽章」の上映。これが本当に”最後の最後”の、のだめ実写版。まずはその前編。そして4月には本当に最後の後編が上映。これで終わるのかあ・・・何か寂しいけど早くみたい!
という事で上映初日に当然ながら行って参りました!(という事でソウル旅行記ちょっと休憩)
コミック版もついに終わって、既に千秋とのだめの壮大なる?恋の結末も終わってはいるんですが、ヨーロッパ編のクライマックスとも言える千秋のル・マルレ・オケでの常任指揮デビューが前編のクライマックス。そして、後編はいよいよのだめとシュトレーゼマンとのショパンのピアコンでの協演、そして衝撃の?!千秋とのだめの恋の結末へと向かう(ハズ)。
今回の映画化。前編、後編に分かれてじっくり描いてもらえるという事で期待してたけど、ドラマの映画化には「映画化の必要あるのか?」という不安も付きまとうもの。でもこの映画版「のだめ~最終楽章」は良い意味で裏切られた!そう、大画面のスクリーンと素晴らしいクオリティの音響設備のシネコンで観てこそ、この「のだめ」のクラシック演奏のシーンは更に際だつ。そのところ充分わかったストーリー展開と演出はさすがだ。
見所は、大爆笑の千秋のルー・マルレ・オケ初演の「”ボロボロ?”ボレロ」と、その後に再生したルー・マルレ・オケの定期演奏の第1曲「祝典序曲「1812」の演奏。特に「1812」の演奏はきっとクラシック音楽の演奏シーンを描いた映画の中でも屈指の名場面になったハズ。もう演奏のクライマックス、最後の”勝利の行進曲”では、思わず感動の涙が出てきて、体が震えるのを感じた。演奏が終わった瞬間、どれだけ「ブラボー!!!」と席を立ちたかった事か!(何とか抑えたけど)
ヨーロッパでプラティニ国際指揮者コンクールで見事優勝した千秋真一(玉木宏)は、シュトレーゼマン(竹中直人)の陰謀で、彼の事務所と契約させられ、しかも勝手に観たことも聞いた事も無い、パリのオケ、「ルー・マルレ・オーケストラ」の常任指揮者に任命させられてしまう。
一方の”のだめ”この野田恵(上野樹里)はコンセルヴァトワールに留学後の初めての進級試験に臨むべく猛レッスンをしながら、いつか千秋との協演を夢見ているのだった。
財政難から客離れとオケのレベルダウンで存亡の危機に瀕していた、ルー・マルレ・オケは千秋常任前の定演で指揮する事になった指揮者にドタキャンされ、やむなく就任前の千秋に指揮を任せる事に。しかし、まともに音合わせも出来ないまま、迎えた演奏会で、指揮した曲は「ラヴェル「ボレロ」」。オケのレベルがはっきりと分かってしまうこの曲で、ボロボロの演奏で聴衆の失笑を買ってしまったルー・マルレ・オケと千秋。ここからオケ再生の為の苦闘がはじまる。最初は反発されながらも、お互いの音楽性の一致で協力し合うコンマスのシモン(マンフレッド・ヴォーダルツ)と共にオーディションで、日本で千秋とライジング☆スター・オケで活躍したオーボエの黒木泰則(福士誠治)を初めとして実力のあるメンバーも揃い、千秋常任初演の定期演奏会に向け猛練習を行う。相変わらずの千秋の”オレ様”指導法に楽団員の反発も喰らいながらも、オケの実力は確実に高まっていく。
一方ののだめは進級試験で相変わらずの独創的なテンポの「モーツアルト「トルコ行進曲」」の演奏で「トレビアン」を獲得。千秋の初演成功の為に、のだめ独特のPR合戦を繰り広げる。
そうして迎えた定期演奏会。会場にはのだめの「ポケットティッシュ」PRの効果か(多分違う)、多くの観客が詰めかけ、期待と不安の中、重苦しい空気の中で演奏が始まる。1曲目のチャイコフスキー「祝典序曲「1812」」のタクトが遂に千秋によって振り下ろされる・・・
いや何が最高に面白かったって言って、あのコミック世界観を見事表現した、チープでコミカルなギャグのセンスが、映画版でCGも駆使しながらパワーアップしていたこと。
ヘタに映画だからって「フルCGで金掛けました!」って作りにすると、あのチープなコミック表現の世界観が崩れてしまいそうだったけど、パワーアップしながらもそのチープさはそのままというのがもう大爆笑!
あの”のだめ”人形をぶっ飛ばす千秋のシーンもまんまダミー人形を使うチープさ。それがこの”のだめ”の世界の面白さだけど、それをちゃんと描いている。うれしい限り!
最高に笑ったのはやはり、千秋との夢の”協演”が棚ぼたで巡って来た(結局ダメだったけど)時の、のだめの舞い上がり、あの”変態の森”へと誘うシーン。ベートーヴェンの第九のクライマックスの合唱をBGMに展開される、のだめと”変態の森”の住人達である、「プリごろ太」のキャラ達や動物たち、そして”のだめマングース!”。まあチープな感じの映像ながらもCGをうまく活かして、「あんたそこまでやるか!」ってくらいの変態ワールド展開!!!のだめ役のじゅりっぺがぶっ飛んでおります・・・
この”変態の森”のシーンを筆頭に、細かいギャグの息をもつかせぬ展開?は映画版でも健在、いや更にパワーアップしております。
そして、何と言っても演奏会のシーン。
冒頭のウィーン楽友協会での千秋の指揮での「ベートーヴェン交響曲第7番」の演奏シーンから、そのクオリティ高い音と映像はそのまんま、フル演奏をブルーレイで出して欲しいくらい。”のだめ”が始まったんだ、という期待感でいきなり一杯になってしまう。
”ボロボロ?”の「ラヴェルのボレロ」は、大爆笑の嵐。でもこれって、ボレロだから笑えた感じ。たった2つのメロディが楽器を変えて延々と演奏されるこの曲で、ルー・マルレ・オケはヘタな演奏者とうまい演奏者が交互に出てきて、最後はそれらが大合奏になって、もう何が何だか分からないような、トンでもない”ボレロ”に笑いが止まらない。松田さん(谷原章介)ならずとも腹がよじれて死んでしまいそう!いやうまくこのボレロの特性を活かした爆笑シーンにしてしまっていた。最後のハプニングのドラで笑い死ぬかと思った・・・
そして、何と言っても、そのルー・マルレ・オケが再生した千秋最初の定期演奏会の第1曲目。
チャイコフスキー「祝典序曲「1812」」
のだめファンで無くても、クラシックファンでなくても、このシーンを観るだけでもきっと大満足なハズ。映画館には不思議なくらいの緊張が走り、シーンとなった客席に、この荘厳なるシンフォニーが響き渡る。
冒頭の静かに始まる弦楽器の美しい音色で奏でられる正教会の古い聖歌のメロディ。実際にこの部分を聖歌の合唱に置き換えられる演奏もある(私はこの演奏版が結構好き)。そこから不安感を煽る不穏なメロディが差し込み、一気に音楽は波乱を見せ始める。
この曲はこの1812年にナポレオンのフランス軍がロシアに侵攻した、いわゆる「ナポレオンのロシア遠征」の時に、ロシア民兵が大きな犠牲を払いながらも、ナポレオン軍を撃退した史実に基づいて、その史実を追いながら音楽が進み、最後はロシアの勝利を祝う、壮大なる行進曲で最高潮に盛り上がって終わるフルオーケストラの音楽だ。クライマックスで、実際に本物の大砲を鳴らす指定がチャイコフスキーによって楽譜上に記されている珍しい曲でもあるが、実際に大砲を鳴らす演奏も多い。
今回の演奏も大砲を実際にホール外でぶっ放している。
演奏はたっぷり時間を使って、特にクライマックスはほぼ全曲フル演奏している。
曲の途中でフランス国家「ラ・マルセイエーズ」が主題として差し込まれるが、これはナポレオンのフランス軍を象徴している。「ラ・マルセイエーズ」が高らかになるとナポレオン軍の侵攻を表現して、途中からこの主題とロシア民謡風の主題とか激しく交互に鳴り響き、闘いが激しくなっていく模様が表現され、そして、ついにはロシア民兵が勝利して、意気昂揚とした行進曲へとなだれ込み、大砲や勝利の鐘の音の大合奏の中で最高潮のクライマックスを迎える。
ともかく迫力ある映像と、そして何より千秋役の玉木君の指揮の見事さが、この素晴らしい迫力のあるシーンにリアリティを与えている。華々しく復活したルー・マルレ・オケとヨーロッパデビューした千秋を祝福するが如くに最高に盛り上がる素晴らしい演奏。クライマックスの行進曲に入る瞬間に思わず、ぶるっと武者震いをしてしまい、千秋の堂々たる指揮ぶりに不覚にも涙が流れた。
最後の音が流れ演奏が終わった時に、「ブラボー!!!」と叫んで立ち上がろうとする自分を抑えるのに必死になったくらい(いやこれ本当に)。こんな素晴らしいクラシック演奏シーンはかつて無いくらいだ。自分の中でも一番。いや実際に映画のシーンの中でも出色じゃないだろうか。この曲のフル演奏の映像化をぜひ望みます!
それにしてもこの曲の選曲は見事としか言いようがない。コミック版ではこのシーンでは同じチャイコフスキーでも「幻想序曲「ロミオとジュリエット」」である(但し、初日の演目で無く、2日目。ルー・マルレ・オケの成功を決定付けたのは初日に演奏したニールセンの交響曲第4番「不滅」)。しかし、この「ロミオとジュリエット」は確かに甘美なメロディが素晴らしい名曲だが、オケの成功という華やかな曲としてはちょっと不向き。そこで差し替えられたと思われる、この「1812」だが、もちろんコミックでは登場しない曲なので、映画版のオリジナルである。でも、原作を思いっきりアレンジしたこの演出こそが、実写版ののだめの魅力だ。コミックの世界観を大事にしながらも映画ならではの演出の為に躊躇しない。素晴らしい演出だと思う。この演出にも「ブラボー!」だ(もっともナポレオン・フランス軍が負けてしまう「1812」をパリのオケでやるというのはちょっとご愛敬かな?)
と最高に盛り上がったところで映画もクライマックス・・・と思いきや、今回は前編。この後、千秋とのだめの間に流れる不協和音を表現するかのような、定期演奏の曲である、「バッハのピアノ協奏曲」や「チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」」の沈鬱なメロディーで見事に表現される。
そして、ラストシーン。
のだめがショックを受けて雨のパリの街をずぶ濡れで歩く、悲哀を感じるシーンで流れるのは、
マーラー「アダージェット」
私の最も好きなクラシック曲である、このマーラーの交響曲第5番の第4楽章の美しくも悲しいメロディがのだめの心を描く。
素晴らしいラストシーンだ。
そして、千秋がアパートを出て行く決心をして、失神してしまうのだめ。またもやチープなダミー人形がぶっ倒れる、衝撃(笑撃?)のラストシーンで前編は終了。
上映後には後編の予告編も流れたが、今回出演が少なかった日本組の峰(瑛太)や真澄ちゃん(小出恵介)や清良(水川あさみ)もかなり登場しそうな感じ。
そして、何より後編のクライマックスとも言えるのが、のだめとシュトレーゼマンの協演による、ショパン「ピアノ協奏曲第1番ホ短調」。あの独特のピアノ独奏の出だしも予告編で出てきて、期待してしまう。
もう今から4月の上映が楽しみ!どうなる千秋とのだめ!そして変態の森?!
という事で上映初日に当然ながら行って参りました!(という事でソウル旅行記ちょっと休憩)
コミック版もついに終わって、既に千秋とのだめの壮大なる?恋の結末も終わってはいるんですが、ヨーロッパ編のクライマックスとも言える千秋のル・マルレ・オケでの常任指揮デビューが前編のクライマックス。そして、後編はいよいよのだめとシュトレーゼマンとのショパンのピアコンでの協演、そして衝撃の?!千秋とのだめの恋の結末へと向かう(ハズ)。
今回の映画化。前編、後編に分かれてじっくり描いてもらえるという事で期待してたけど、ドラマの映画化には「映画化の必要あるのか?」という不安も付きまとうもの。でもこの映画版「のだめ~最終楽章」は良い意味で裏切られた!そう、大画面のスクリーンと素晴らしいクオリティの音響設備のシネコンで観てこそ、この「のだめ」のクラシック演奏のシーンは更に際だつ。そのところ充分わかったストーリー展開と演出はさすがだ。
見所は、大爆笑の千秋のルー・マルレ・オケ初演の「”ボロボロ?”ボレロ」と、その後に再生したルー・マルレ・オケの定期演奏の第1曲「祝典序曲「1812」の演奏。特に「1812」の演奏はきっとクラシック音楽の演奏シーンを描いた映画の中でも屈指の名場面になったハズ。もう演奏のクライマックス、最後の”勝利の行進曲”では、思わず感動の涙が出てきて、体が震えるのを感じた。演奏が終わった瞬間、どれだけ「ブラボー!!!」と席を立ちたかった事か!(何とか抑えたけど)
ヨーロッパでプラティニ国際指揮者コンクールで見事優勝した千秋真一(玉木宏)は、シュトレーゼマン(竹中直人)の陰謀で、彼の事務所と契約させられ、しかも勝手に観たことも聞いた事も無い、パリのオケ、「ルー・マルレ・オーケストラ」の常任指揮者に任命させられてしまう。
一方の”のだめ”この野田恵(上野樹里)はコンセルヴァトワールに留学後の初めての進級試験に臨むべく猛レッスンをしながら、いつか千秋との協演を夢見ているのだった。
財政難から客離れとオケのレベルダウンで存亡の危機に瀕していた、ルー・マルレ・オケは千秋常任前の定演で指揮する事になった指揮者にドタキャンされ、やむなく就任前の千秋に指揮を任せる事に。しかし、まともに音合わせも出来ないまま、迎えた演奏会で、指揮した曲は「ラヴェル「ボレロ」」。オケのレベルがはっきりと分かってしまうこの曲で、ボロボロの演奏で聴衆の失笑を買ってしまったルー・マルレ・オケと千秋。ここからオケ再生の為の苦闘がはじまる。最初は反発されながらも、お互いの音楽性の一致で協力し合うコンマスのシモン(マンフレッド・ヴォーダルツ)と共にオーディションで、日本で千秋とライジング☆スター・オケで活躍したオーボエの黒木泰則(福士誠治)を初めとして実力のあるメンバーも揃い、千秋常任初演の定期演奏会に向け猛練習を行う。相変わらずの千秋の”オレ様”指導法に楽団員の反発も喰らいながらも、オケの実力は確実に高まっていく。
一方ののだめは進級試験で相変わらずの独創的なテンポの「モーツアルト「トルコ行進曲」」の演奏で「トレビアン」を獲得。千秋の初演成功の為に、のだめ独特のPR合戦を繰り広げる。
そうして迎えた定期演奏会。会場にはのだめの「ポケットティッシュ」PRの効果か(多分違う)、多くの観客が詰めかけ、期待と不安の中、重苦しい空気の中で演奏が始まる。1曲目のチャイコフスキー「祝典序曲「1812」」のタクトが遂に千秋によって振り下ろされる・・・
いや何が最高に面白かったって言って、あのコミック世界観を見事表現した、チープでコミカルなギャグのセンスが、映画版でCGも駆使しながらパワーアップしていたこと。
ヘタに映画だからって「フルCGで金掛けました!」って作りにすると、あのチープなコミック表現の世界観が崩れてしまいそうだったけど、パワーアップしながらもそのチープさはそのままというのがもう大爆笑!
あの”のだめ”人形をぶっ飛ばす千秋のシーンもまんまダミー人形を使うチープさ。それがこの”のだめ”の世界の面白さだけど、それをちゃんと描いている。うれしい限り!
最高に笑ったのはやはり、千秋との夢の”協演”が棚ぼたで巡って来た(結局ダメだったけど)時の、のだめの舞い上がり、あの”変態の森”へと誘うシーン。ベートーヴェンの第九のクライマックスの合唱をBGMに展開される、のだめと”変態の森”の住人達である、「プリごろ太」のキャラ達や動物たち、そして”のだめマングース!”。まあチープな感じの映像ながらもCGをうまく活かして、「あんたそこまでやるか!」ってくらいの変態ワールド展開!!!のだめ役のじゅりっぺがぶっ飛んでおります・・・
この”変態の森”のシーンを筆頭に、細かいギャグの息をもつかせぬ展開?は映画版でも健在、いや更にパワーアップしております。
そして、何と言っても演奏会のシーン。
冒頭のウィーン楽友協会での千秋の指揮での「ベートーヴェン交響曲第7番」の演奏シーンから、そのクオリティ高い音と映像はそのまんま、フル演奏をブルーレイで出して欲しいくらい。”のだめ”が始まったんだ、という期待感でいきなり一杯になってしまう。
”ボロボロ?”の「ラヴェルのボレロ」は、大爆笑の嵐。でもこれって、ボレロだから笑えた感じ。たった2つのメロディが楽器を変えて延々と演奏されるこの曲で、ルー・マルレ・オケはヘタな演奏者とうまい演奏者が交互に出てきて、最後はそれらが大合奏になって、もう何が何だか分からないような、トンでもない”ボレロ”に笑いが止まらない。松田さん(谷原章介)ならずとも腹がよじれて死んでしまいそう!いやうまくこのボレロの特性を活かした爆笑シーンにしてしまっていた。最後のハプニングのドラで笑い死ぬかと思った・・・
そして、何と言っても、そのルー・マルレ・オケが再生した千秋最初の定期演奏会の第1曲目。
チャイコフスキー「祝典序曲「1812」」
のだめファンで無くても、クラシックファンでなくても、このシーンを観るだけでもきっと大満足なハズ。映画館には不思議なくらいの緊張が走り、シーンとなった客席に、この荘厳なるシンフォニーが響き渡る。
冒頭の静かに始まる弦楽器の美しい音色で奏でられる正教会の古い聖歌のメロディ。実際にこの部分を聖歌の合唱に置き換えられる演奏もある(私はこの演奏版が結構好き)。そこから不安感を煽る不穏なメロディが差し込み、一気に音楽は波乱を見せ始める。
この曲はこの1812年にナポレオンのフランス軍がロシアに侵攻した、いわゆる「ナポレオンのロシア遠征」の時に、ロシア民兵が大きな犠牲を払いながらも、ナポレオン軍を撃退した史実に基づいて、その史実を追いながら音楽が進み、最後はロシアの勝利を祝う、壮大なる行進曲で最高潮に盛り上がって終わるフルオーケストラの音楽だ。クライマックスで、実際に本物の大砲を鳴らす指定がチャイコフスキーによって楽譜上に記されている珍しい曲でもあるが、実際に大砲を鳴らす演奏も多い。
今回の演奏も大砲を実際にホール外でぶっ放している。
演奏はたっぷり時間を使って、特にクライマックスはほぼ全曲フル演奏している。
曲の途中でフランス国家「ラ・マルセイエーズ」が主題として差し込まれるが、これはナポレオンのフランス軍を象徴している。「ラ・マルセイエーズ」が高らかになるとナポレオン軍の侵攻を表現して、途中からこの主題とロシア民謡風の主題とか激しく交互に鳴り響き、闘いが激しくなっていく模様が表現され、そして、ついにはロシア民兵が勝利して、意気昂揚とした行進曲へとなだれ込み、大砲や勝利の鐘の音の大合奏の中で最高潮のクライマックスを迎える。
ともかく迫力ある映像と、そして何より千秋役の玉木君の指揮の見事さが、この素晴らしい迫力のあるシーンにリアリティを与えている。華々しく復活したルー・マルレ・オケとヨーロッパデビューした千秋を祝福するが如くに最高に盛り上がる素晴らしい演奏。クライマックスの行進曲に入る瞬間に思わず、ぶるっと武者震いをしてしまい、千秋の堂々たる指揮ぶりに不覚にも涙が流れた。
最後の音が流れ演奏が終わった時に、「ブラボー!!!」と叫んで立ち上がろうとする自分を抑えるのに必死になったくらい(いやこれ本当に)。こんな素晴らしいクラシック演奏シーンはかつて無いくらいだ。自分の中でも一番。いや実際に映画のシーンの中でも出色じゃないだろうか。この曲のフル演奏の映像化をぜひ望みます!
それにしてもこの曲の選曲は見事としか言いようがない。コミック版ではこのシーンでは同じチャイコフスキーでも「幻想序曲「ロミオとジュリエット」」である(但し、初日の演目で無く、2日目。ルー・マルレ・オケの成功を決定付けたのは初日に演奏したニールセンの交響曲第4番「不滅」)。しかし、この「ロミオとジュリエット」は確かに甘美なメロディが素晴らしい名曲だが、オケの成功という華やかな曲としてはちょっと不向き。そこで差し替えられたと思われる、この「1812」だが、もちろんコミックでは登場しない曲なので、映画版のオリジナルである。でも、原作を思いっきりアレンジしたこの演出こそが、実写版ののだめの魅力だ。コミックの世界観を大事にしながらも映画ならではの演出の為に躊躇しない。素晴らしい演出だと思う。この演出にも「ブラボー!」だ(もっともナポレオン・フランス軍が負けてしまう「1812」をパリのオケでやるというのはちょっとご愛敬かな?)
と最高に盛り上がったところで映画もクライマックス・・・と思いきや、今回は前編。この後、千秋とのだめの間に流れる不協和音を表現するかのような、定期演奏の曲である、「バッハのピアノ協奏曲」や「チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」」の沈鬱なメロディーで見事に表現される。
そして、ラストシーン。
のだめがショックを受けて雨のパリの街をずぶ濡れで歩く、悲哀を感じるシーンで流れるのは、
マーラー「アダージェット」
私の最も好きなクラシック曲である、このマーラーの交響曲第5番の第4楽章の美しくも悲しいメロディがのだめの心を描く。
素晴らしいラストシーンだ。
そして、千秋がアパートを出て行く決心をして、失神してしまうのだめ。またもやチープなダミー人形がぶっ倒れる、衝撃(笑撃?)のラストシーンで前編は終了。
上映後には後編の予告編も流れたが、今回出演が少なかった日本組の峰(瑛太)や真澄ちゃん(小出恵介)や清良(水川あさみ)もかなり登場しそうな感じ。
そして、何より後編のクライマックスとも言えるのが、のだめとシュトレーゼマンの協演による、ショパン「ピアノ協奏曲第1番ホ短調」。あの独特のピアノ独奏の出だしも予告編で出てきて、期待してしまう。
もう今から4月の上映が楽しみ!どうなる千秋とのだめ!そして変態の森?!
 | のだめカンタービレ 最終楽章 前編&後編のだめカンタービレERJこのアイテムの詳細を見る |















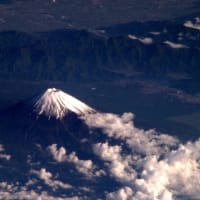


やはり「のだめ」は大きなスクリーンと大音響の映画館に合う作品ですね。テレビ版よりも数段良かったと思います。後編も観に行きます(ラストが原作と変わっていると嬉しいのですが・・)。
これで今年のマイアカデミー賞の音楽賞は「おっぱいバレー」と「のだめ」の2本でほぼ確定ですね。
コミックのラストはあっさりした感じもありますが、”のだめ”らしさが戻った感じで良かったと思います。
演奏シーンは本当に映画館で観るに限りますね。後編はのだめとシュトレーゼマンの協演がありますが、これが楽しみですね。千秋は孫Ruiとの協演があるでしょうか。
来年の4月まで待てないくらい楽しみです。