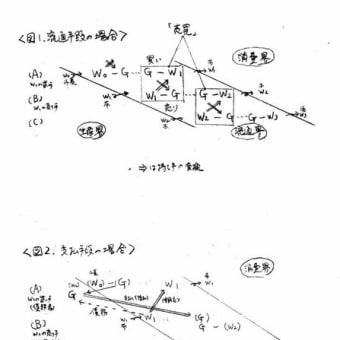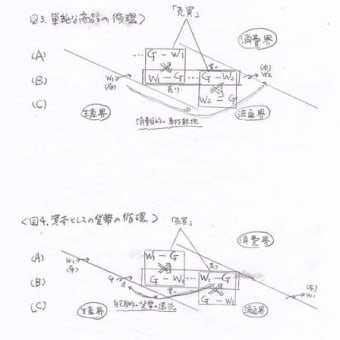「読む会」だより(22年7月用)文責IZ
《6月の議論》
6月の「読む会」は19日に開かれました。
《5月の議論》の所では、剰余価値率を利潤率と区別する意義は何か、という質問が出ました。チューターは、マルクスは利得(剰余価値)なり利潤は労働者からの搾取(必要労働を越える労働支出)から発生するということから、その度合を、賃金=支払部分である可変資本との比率(すなわち剰余価値率)で示している。これに対して、いわゆる近代経済学は、それを全投下資本(労働手段や原料等の費用を含めた)との比率である利潤率で示すことによって、なにか生産手段(“物”)の能力等々にも利得(剰余価値)の源泉があるかに示すのだが、これは結局、利得(剰余価値)の源泉を曖昧にするということに尽きるだろう、と述べました。
《説明》の部分では、まず、第2節のタイトルである「生産物の比例配分的諸部分での生産物価値の表示」という言葉が分かりにくい、という意見が出ました。チューターは、言葉は分かりにくいかもしれないが、本文で言っていることはそう難しいことではない。チューターは、生産物に含まれる価値の諸成分は、生産物の比例配分的諸部分として表示しうる、とまとめてみた、と述べ、了承されました。
また最後の部分で、ヤングの主張が「剰余生産物の狂信者」とあるが、どのような主張か、という質問が出ました。チューターは、少し調べてみたがしかるべき引用は見つからなかった。ここではマルクスがそう指摘しているということだけで、書いている。もう少し調べてみる、と宿題になりました。
この点について再度、ウィキペディアや剰余価値学説史などに何か引用やマルクスの指摘がないか調べてみましたが、イギリスの農業者で農業改善の専門家という以上には分かりませんでした。マルクスの指摘としてはここが一番長いようですので、岩波文庫版ですこし検討してみましょう。この注釈のある文章は次のようなものでした。
「剰余価値の生産が資本主義的生産の規定的な目的であるように、<資本主義的生産における>富の高さは、生産物の絶対的大きさによってではなく、剰余生産物の<必要労働が表示される生産物部分に対する>相対的大きさによって測られる(※注)。」この注釈にはこうあります。
(※注)「2万ポンドの資本をもち、年々2千ポンドの利潤をあげる個人にとっては、彼の資本が労働者を百人働かせるか千人働かせるか、生産された商品が1万ポンドで売れるか、2万ポンドで売れるかは、彼の利潤がいかなる場合にも2千ポンド以下には下がらないことを常に前提とすれば、全くどうでもよいことであろう。一国民の実質的な利益も同じではあるまいか? その国民の実質的な純所得、その地代および利潤が同じであると前提すれば、国民が1000万の住民から成るか、1200万の住民から成るかは、少しも重要なことではない」。(リカード『原理』<1817年>……)。リカードよりもずっと前に剰余生産物の狂信者アーサー・ヤングは、その他の点では饒舌無批判な著述家であり、その名声がその功績に逆比例しているのであるが、なかんづく次のように言った、「ある州全体の土地は、一体それが古代ローマ風に、小独立農民によっていかに良く耕作されようとも、近代的王国においては、何の役に立つだろうか? 人間を繁殖させるというただ一つの目的、それはそれ自体としては何の役にも立たないものであるが、このような目的以外には、何の役に立つだろうか?」。(アーサー・ヤング『政治算術』1774年……)。
「剰余生産物の狂信者」というヤングの評価それ自体の参考にはならないかもしれませんが、マルクスはここで、リカードが剰余価値の源泉を、流通を媒介とした労働者の搾取(必要労働を越える労働支出)に求めるのではなく、資本(貨幣の形態での)の純所得としてあるがままに無批判的に認め賛美するだけだと、批判しています。そのうえでリカードの半世紀ほど前の重農主義者と思われるヤングが、耕作労働の質の良し悪しではなくて、結果としての剰余農産物(人間の繁殖に役立つ)の量それ自体が重要だと言っていることを持ち出しているのだと思われます。
《説明》第7章「剰余価値率」の3回目第3節「シーニアの『最後の1時間』」
(5.シーニアの「最後の1時間」について)
次の第8章で詳論されるように、労働者たちの要求する10時間法に対抗して、1836年、マンチェスターの工場主らは当時オックスフォード大学の高名な経済学教授であったシーニアを招いて彼らが陥るであろう窮状を訴えました。翌年、シーニアは彼らの話を基に10時間法に関する小冊子『綿業に及ぼす影響から見た工場法についての手紙』をまとめました。その要旨はマルクスによれば次のようなものです。
・「われわれの紡績工は、彼の<12時間の>労働日の最初の8時間では綿花の価値<20シリング>を、次の1時間36分では消費された労働手段の価値<4シリング>を、さらにその次の1時間12分では労賃の価値<3シリング>を生産または補填し、そして、あの有名な「最後の1時間」だけを工場主に、剰余価値<3シリング>の生産に、ささげるのだ、と。」(第2節、P290)
この小冊子でのシーニアの主張に対して、マルクスは第3節の全部を割いてその批判を行っています。
今回は申し訳ありませんが、ほぼ引用だけになります。
・「……そのなかでは、とりわけ次のような有益なことを読むことができる。
「現行法のもとでは、18歳未満の人員を使用する工場は、1日に11時間半、すなわち週初の5日間は12時間、土曜は9時間よりも長く作業することはできない、。ところで、次の分析(!)は、このような工場では純益の全部が最後の1時間から引き出されているということを示している。……(※32への補足)シーニアの言うことは、内容の間違いはまったく別としても、混乱している。彼が本当に言おうとしたのは、次にようなことだったのである。工場主は毎日労働者を11時間半または23/2時間働かせる。1個の労働日と同様に、年間労働も11時間半または23/2時間(に年間労働をかけたもの)から成っている。このことを前提すれば、23/2労働時間は115,000ポンド・スターリングの年間生産物を生産する。<そこで>1/2労働時間は(1/23)×115,000ポンド・スターリングを生産する。<週前半の5日間で行われる>20/2労働時間は、(20/23)×115,000=100,000ポンド・スターリングを生産する。すなわち、それはただ前貸資本を補填するだけである。あとには3/2労働時間が残り、それは(3/23)×115,000=15,000ポンド・スターリング、すなわち総収益を生産する。この3/2労働時間のうち、1/2労働時間は(1/23)×115,000=5000ポンド・スターリングを生産する。すなわちそれは、それはただ工場や機械類の損耗の補填分を生産するだけである。最後の2つの半労働時間、すなわち最後の1時間は、(2/23)×115,000=100,000ポンド・スターリング、すなわち純益を生産する。……。」」(全集版、P291~)
・「そして、教授はこれを「分析」と呼ぶのだ! もし彼が、労働者は1日のうちの最良の時間を建物や機械や綿花や石炭などの価値の生産に、したがってまたそれらの価値の再生産または補填に浪費してしまう、という工場主たちの嘆きを信じたのであれば、およそ分析は余計だったのである。@
彼はただ単にこう答えればよかったのである。諸君! もし諸君が11時間半ではなくて10時間作業させるとすれば、ほかの事情が変わらない限り、綿花や機械などの毎日の消費は1時間半分だけ減るであろう。だから、諸君は諸君が失うのとちょうど同じだけを得るのである。諸君の労働者たちは、将来<の10時間で>は、前貸資本価値の生産または補填のために1時間半少なく浪費するであろう、と。@
もしまた、シーニアが工場主たちの言うことをそのまま信じないで、専門家としての分析が必要だと考えたのならば、なによりもまず、彼は、ただ労働日の長さに対する純益の比率だけの問題では、工場主諸君にお願いして、機械類や工場建物や原料と労働とをごちゃまぜにしないで、一方の側には工場建物や機械類や原料などに含まれている不変資本を置き、他方の側には労賃として前貸される資本を置くようにしてもらうべきだったのである。そこで、次に、工場主たちの計算では労働者は2/2労働時間、すなわち1時間で労賃を再生産または補填するということにでもなったら、分析家は次のように続けるべきだったのである。」(同、P294)
・「諸君のいうところでは、労働者は最後から2番目の1時間で自分の労賃を生産し、最後の1時間で諸君の剰余価値または純益を生産する。彼は同じ長さの時間では同じ大きさの価値を生産するのだから、<工場や機械類の損耗の補填分を生産する>最後から2番目の1時間の生産物は、<純益を生産する>最後の1時間の生産物と同じ価値をもっている。さらに、彼が価値を生産するのは、ただ彼が労働を支出する限りでのことであって、彼の労働の量は彼の労働時間で計られる。@
それは、諸君の言うところによれば、1日に11時間半である。この11時間半の一部分を彼は自分の労賃の生産または補填のために費やし、他の部分を諸君の純益のために費やす。そのほかには彼は1労働日のあいだ何もしない。ところが、陳述によれば、彼の賃金と彼の提供する剰余価値とは同じ大きさの価値なのだから、明らかに彼は自分の労賃を5・3/4時間<11.5/2=1労働日の半分>で生産し、そして諸君の純益を別の5・3/4時間で生産するのである。@
さらに、<最後の1時間と最後から2番目の>2時間分の糸生産物の価値は、彼の労賃・プラス・諸君の純益という価値額に等しいのだから、この糸価値は11・1/2労働時間<つまり1労働日>で計られ、最後から2番目の1時間の生産物<である糸の価値>は5・3/4労働時間で計られ、最後の1時間の生産物もやはりそれ<5・3/4労働時間>で計られていなければならない。@
われわれは、今、厄介な点に来ている。そこで、注意せよ! 最後から2番目の1労働時間も、最初のそれと同じに普通の1労働時間である。それより多くも少なくもない。それでは、どうして紡績工は、5・3/4労働時間を表わす糸の価値を1労働時間で生産することができるのか? 彼は実はそんな奇跡は行わないのである。@
彼が1労働時間で使用価値として生産するものは、一定量の糸である。この糸の価値は5・3/4労働時間によって計られ、そのうち4・3/4は、毎時間消費される生産手段すなわち綿花や機械類などのうちに彼の助力なしに含まれており、4/4すなわち1労働時間は彼自身によって付け加えられている。つまり彼の労賃は<11・1/2=23/2時間のうちの>5・3/4時間で生産され、また1紡績時間の糸生産物もやはり<生産手段の価値を含めれば?>5・3/4労働時間を含んでいるのだから、彼の5・3/4紡績時間の価値生産物が1紡績時間の生産物価値に等しいということは、けっして魔術でも何でもないのである。<生産物価値には生産手段の価値が含まれるから、1労働時間の生産物価値は(1+4・3/4)労働時間となる。これに対して、5・3/4労働時間の価値=価値生産物は、生産手段の価値=保存された価値を含まないから、そのまま5・3/4の価値をもつ。だから、両者は同量となる。>@
ところで、もし諸君が、綿花や機械類などの価値の再生産または「補填」のために労働者が彼の労働日のただの一瞬間でも失うものと考えるならば、それはまったく諸君の思い違いである。彼の労働が綿花や紡錘を糸にすることによって、つまり彼が紡績することによって、綿花や紡錘の価値はひとりでに糸に移るのである。これは彼の労働の質<有用労働としての>のおかげであって、その量<抽象的労働としての>のおかげではない。もちろん、彼は1時間では半時間でよりも多くの綿花価値などを糸に移すであろう。しかし、それはただ彼が1時間では半時間でよりも多くの綿花を紡ぐ<多くの労働を綿花に吸収させる>からに他ならない。@
そこで、諸君にもお分かりであろう、労働者が最後から2番目の1時間で彼の労賃の価値を生産し最後の1時間で純益を生産するという諸君の言い方の意味するものは、彼の労働日のうちの2時間の糸生産物<すなわち剰余労働対象化分>には、その2時間が前にあろうが後にあろうが、<1労働日である>11・1/2労働時間が、すなわち彼のまる1労働日とちょうど同じだけの時間が具体化されているということ以外の何ものでもないのである。@
そして労働者は前半の5・3/4時間では自分の労賃を生産し後半の5・3/4時間では諸君の純益を生産するという言い方の意味するところもまた、諸君は前半の5・3/4時間には支払うが後半の5・3/4時間には支払わないということ以外の何ものでもないのである。<ここで>私が労働への支払と言い、労働力への支払と言わないのは、諸君に分かる俗語で話すためである。@
そこで、諸君が代価を支払う労働時間と支払わない労働時間との割合を比べてみれば、諸君はそれが半日対半日、つまり100%であるのを見出すであろう。とにかく悪くないパーセンテージである。また、もし諸君が諸君の「働き手」を11時間半ではなく13時間こき使って、そして、いかにも諸君らしいやり方だと思われるのだが、余分の1時間半をただの剰余労働に付け加えるならば、剰余労働は5・3/4時間から7・1/4時間に増え、したがって剰余価値率は100%から126・2/33%に上がるだろうということにも、少しも疑う余地はないのである。ところが、もし諸君が、1時間半の追加によって剰余価値率が100%から200%に、また200%より高くさえもなるだろう、すなわち「2倍よりも多くなる」だろう、と期待するとすれば諸君はあまりにも度外れな楽天家である。反対に──人の気持ちはおかしなものだ、ことに財布に気を取られているときには──、もし諸君が、11時間半から10時間半に労働日を短縮すれば諸君の純益は全部なくなってしまうだろうと心配するとすれば、諸君はあまりにもうろたえて悲観屋である。決してそうはならない。他の事情はすべて元のままだと前提すれば、剰余労働は5・3/4時間から4・3/4時間に減るであろう。それでもなおまったく十分な剰余価値率、すなわち82・14/23%となる。ところで、あの宿命の「最後の1時間」について、諸君は千年説の信者が世界の没落について語る以上に作り事を言ったのであるが、それは「ただのたわごと」なのである。その1時間がなくなったからとて、諸君の「純益」がどうなるものでもなければ、諸君にこき使われている少年少女たちの「魂の純潔」がどうなるものでもないであろう。
いつか諸君の「最後の時」が本当に告げられたら、オックスフォードの教授を思い出されよ。ではまた、あの世でよろしくお願いする。さらば!……1836年にシーニアによって発見された「最後の1時間」の警報は、1848年4月15日、10時間法に反対して、経済高官の一人であるジェームズ・ウィルソンによって、『ロンドン・エコノミスト』誌上でまたもや吹き鳴らされたのである。」(同、~P298)