以前から不思議に思っていたことがありました。
総理大臣が会見する時など、その演台にかなり目立つ桐のマークがついていますが、あれはどういうことなのかと。

色がちがうこともあります。

官房長官の会見の時にはありません。

自民党政権のときもついていました。


大きいものもありました。

桐のマークといえば、豊臣家の家紋ではないか、何で豊臣家の家紋がついているのかと。
たまたま、慶応義塾大学の人間教育講座に出席し、そのときにいただいた2009年度の講演録の冊子を読んでいて、毎日新聞の岸井成格(きしい・しげただ)さんがこんなことを語っていました。
明治政府が日の丸と君が代をつくったときに、もうひとつ政府のマークを考えた。徳川幕府をなくなったのだから、葵の紋に代わる政府のシンボルが必要になる。それでは豊臣政権時代に使っていた豊臣家の家紋である「五七の桐」に戻そうと。
なるほど、そんなこともあったのかなと興味を持って少しネットで調べてみました。
首相官邸のWebサイトには以下のような回答が出ていました。(政府の回答)
Question
首相などが記者会見のときに「五七の桐」の紋章のようなものが付いた演台を使用しておりますが、その紋章の「由来」や「図柄の意味」また「いつからどのような理由で使用」しているのか教えてください。(平成16年8月5日)
Answer
桐花紋は政府において広く使われてきていますが、桐花紋がいつ頃から使われ始めたのか、また、その由来については定かではありませんが、従前から慣例により使われており、定着してきているものです。
なお、紋章について一般にいわれていることなどを記しますと、
1.桐花紋は、植物のゴマノハグサ科に属する白桐を紋様化したものといわれています。
2.桐は、聖天子の出現を待ってこの世に現れる鳳凰という瑞鳥(めでたい鳥)の宿る木だといわれており、天皇のお召しものにも桐や鳳凰などの紋様が使われるようになったといわれています(はっきりとはしていませんが、一説によれば嵯峨天皇(786~842年)の頃から使われているようです。)。
3.明治政府は、明治5年に大礼服(重大な公の儀式に着用した礼服)を定め(太政官布告「大礼服制」)、例えば勅任官(天皇が任命した官吏)は、その上着に「五七の桐」を用いることとされました。明治8年には、勲章の旭日章が制定され、デザインの一部に桐花紋が使われました。

4.総理大臣官邸では、以前から外国の賓客の接遇のための晩餐会等の招待状や食器、閣議室の大臣席の硯箱や大臣の表彰状などに「五七の桐」を使用しています。
平成15年10月から首相の記者会見の際にも「五七の桐」を付した演台を使うようになりました。
(参考)
「五七の桐」は桐花紋の代表的なもので、3枚の桐の葉の上に中央に7つの桐花を、その左右にそれぞれ5つの桐花を配した図柄となっています。
ついでに分かったことですが、パスポートにも「五七の桐」の紋章が使われていて、そのいきさつが外務省のWebサイトに出ていました。(外務省の回答)
Question
旅券の各ページの模様として「五七の桐」の紋章が使われるようになったのはいつからですか。
Answer
1938年(昭和13年)の旅券の改正によって、旅券の各ページに「五七の桐」が使われるようになりました。当時の改正の内容を示す記録は、外務省記録「外国旅券関係雑件」に収められています。
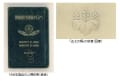
日本では、1920年(大正9年)10月にパリで開催された旅券に関する国際会議での決議に基づき、1924年(同13年)の改正時に現在のような手帳型の旅券が採用され、1926年(同15年)から使用されていました。
しかし、この旅券には、表紙に印刷された菊の紋章が法令に定める形と異なっていることや、表紙と内ページとの国号表記の不統一、携帯時に表紙の色が衣服に移る、といった問題点があったため、改正が必要となりました。
このうち、菊の紋章に関しては、表紙のほか、各ページの中央にも印刷されていたため、用紙の素地に入っている模様と一体化するおそれがあるとの問題点が指摘されました。そこで、ページ中央に印刷されていた菊は、皇室の御紋章として法律等で定められたものではない「五七の桐」に替えられることとなりました。
この改正を施した旅券は1938年8月頃から使用が開始されました。それ以後、旅券の内ページには「五七の桐」の紋章が模様としてあしらわれています。
調べてみて、なるほどと納得しました。
意外とこういうことは知らないもので、学校でも教えてくれなかったと思います。
各種の紋章の使われ方や歴史については、日本だけでなく海外(特にヨーロッパ)でも面白いことがたくさんありそうで、調べていくときりがなくて途中で切り上げてしまいました。
先日も、江戸東京博物館に見学に行った特に、「日光東照宮と将軍社参」という企画展示があり、葵御紋の大旗があったり、御供の方々の装束についても、羽織や旗に識別のための紋などが付けられていたことがわかりました。
古文書など字そのものや文章が難しくてなかなか近寄れませんが、見てわかる紋章などについては素人にもわかりやすいので興味を持っていきたいと思います。
【参考情報】
国章
菊花紋章
菊の紋章について(biyakusian8972さんの回答)
もともと菊の文様は平安期から鎌倉期(8~14世紀)に貴族に好まれていた”文様”で、衣服や手鏡・手箱などにつけられたもので、この時点では”紋章”ではなかったのですが、後鳥羽天皇(1180~1239)がとりわけ菊文様を好まれて衣服だけでなく車・刀にまで菊文様をつけられた。それが後宇多天皇(1267~1324)時まで受け継がれ”菊の花”は皇室の専用紋に制定されます{増鏡}
足利尊氏が後醍醐天皇から、また豊臣秀吉が正親町天皇から”菊紋”の使用を許されますが、この頃(天正9年{1581}と文禄4年{1595})に菊紋の権威保持のため禁制が出されています。しかし、徳川幕府が"葵紋”に対する厳重な保護を行なったのにひきかえ、規成が不徹底で菊紋は役者紋や商店紋(商標)として乱用され、天皇家の”菊花紋”が権威を復活させるのは明治政府樹立後です。
明治2年8月24日の布告で「菊花紋は皇族以外は使ってはいけない。また、親王家も十六葉のものは禁止」と示され、皇室(天皇・太皇太后・皇太后・皇后・皇太子・同妃・皇太孫・同妃)は”十六葉八重表菊”を御紋章とし、他の皇族{親王家}共通は”十四葉一重裏菊”とされ、各宮家は独自の菊の変形紋を使用された。
菊は花ぶさが放射状なので{日光に例えられ}日華(花)と賛美されていたことと、その強い香りも花の中で最も精気があり、”百草の王”といわれたことから菊花が特別視されたと考えられます。
また、菊は中国から移入された観賞花であり、中国では{重陽の節句:9月9日}に菊花酒を飲めば、延命・長寿のききめがあると信じられていて{延命草}とも呼ばれ、日本の宮中でも”重陽の節会”が催されて観菊などの菊花を大事にした行事などが開かれ、菊花の生命力を賛美していたので天皇家の文様に多用されて、ついで”紋様”として定着していったと考えます。
回答日時:2008/3/31 22:29:20