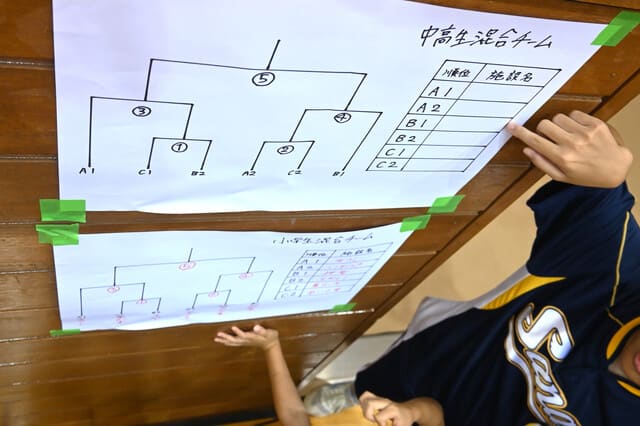一般の家庭と同様、児童養護施設でもこども達が日々の生活の中で自分で自由に使えるお金を持てるようお小遣いを渡しています。金額は同年代の子どもたちや地域の状況をみながら決められています。お小遣いは、子どもたちにとっては計算を覚える機会であったり、自分でお金を貯めて欲しいものにお金を使う計画力を養ったり、ひいては退所をして自立を始めるために経済観念を養っていくためのステップともなるものです。

さんあいでは毎月のお小遣いを施設長が直接、子どもたち一人ひとりに手渡しをするようにしています。

小学生になるとお小遣いもお札が混ざるようになります。今月はいよいよ新札が混ざるようになりました。
「あ、渋沢栄一だ!」いやいや、それは北里柴三郎さんです。

子どもたちのお小遣いを含む生活にかかる費用は、基本的に行政からの措置費によって賄われています。
10月も多くの品物の値段が上がりました。子ども会議では、子どもたちからお小遣いの額を引き上げて欲しい、という要望が出されています。施設単独の努力ではどうしようもないこともあることを子どもたちには説明、理解をしてもらい、たいせつに使おうね、と話しています。