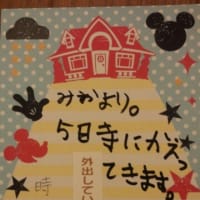例えば、「学力と精神」の向上を教育であると仮定しよう。しかし、あなたはどちらかを(学力か精神か)、あるいは場合によって使い分けるように両方を教育の根本と考えるだろう。やがて子供たちは「受験と思春期」を同時に迎え、親には本音を隠すようにそれを少しずつ受け入れる(あなたも経験があるだろう)。そして、たいていの親は「学力」を重視するだろう。その期間の知識とわかっていながら、いずれ役に立つと予測をするのだろう。しかしそれは、利益を得る、実在を守る、ための予備知識となるものがほとんどだ(これの経験があるはずだ)。けっこう軟弱な鎧であり、社会に出てからは実際、多様な面で「精神」の方を多大に必要とすることを、知っておきながら、学力向上を重視する。それは、いつまでも古い時代の中(思考)で暮らしている、我々の流動していることを知っておきながら、流動させたくない(馴染みある世界で安定していたい)という文化の中に根付いているものであり、「精神」とは、「若いうちの苦労」=「学力」という個人の「自由」と「時間」を奪うシステムを作り上げている。
人はある時期から「力(学力・体力・精神力など)」というものに対しある「時間的」差異が生じる。それは人の「見方」による看取性の「分岐」によるものであり、記憶への「記録の仕方」の違いであるものだと思っている。それを文化に浸った人たちは、「個人差」と呼んでいる。そして、それを個人がそのまま飲み込むことを「固執」と呼び、いつしか人は以前、受け入れられていたことを受け入れられなくなる。すると、コミュニケーション不足やいじめや恋愛ができないという問題にまで発展する。「時間的差異」は、我々が生んだ独特な文化であると私は言いたい。
「力」に関する時間の流れとは、複雑で感じ方や見方によって、個人と他では不正確なものだ。あることを理解し、主張する時間までを長く感じる者、理解するまでの間に、何度も記憶を確認し時間を短く感じる者、初めての対応に混乱し時間すら忘れる者、が存在する。しかし、我々の文化では(何であれ)「速さ」を追求する「力学」を必要としている。それゆえに、理解力を記憶力そのものとし、感覚で受け入れる記憶を技術力とした文化が発生した。そして、それぞれの能力に応じて差別をしてきたのである。しかし実際には、この「力」の差別も「見方」による「分岐」であり、「差別」という語ないし記号の下に押し込めてしまった条件づけられた反応という存在である。それゆえに、「力」を学ぶことを、我々は厄介で難しいことにしてしまった。