遅ればせながら、新年明けましておめでとうございます. 本年もどうぞ宜しくお願い致します。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。 皆様はどの様なお正月を迎えましたか?お正月の料理?と英会話の生徒達に尋ねると殆どの生徒がおせちとお雑煮と答えます。幾つになっても、万物改まった元旦の朝のお雑煮は良いものです。博多雑煮の味出しは焼アゴ(トビウオの干物)、シイタケ、カツオブシ、コブです。アゴではなく晩秋、能古島沖で釣れる大きなハゼを使う家も有ります。餅は丸餅を別なべで柔らかく煮て、すまし仕立てです。具はシイタケ、サトイモ、かつお菜、ぶりの切り身、家によっては焼き豆腐、銀杏等もいれます。明治以前の習慣ではスルメ、山芋、ごぼう、にんじんも入れて、ますますにぎやかな雑煮にします。父から聞いた話ですが、福岡の武家達は椀に大根の輪切りを敷き、子餅、ハマグリを各々二個入れたハマグリ雑煮で祝った事もあるそうです。
皆様はどの様なお正月を迎えましたか?お正月の料理?と英会話の生徒達に尋ねると殆どの生徒がおせちとお雑煮と答えます。幾つになっても、万物改まった元旦の朝のお雑煮は良いものです。博多雑煮の味出しは焼アゴ(トビウオの干物)、シイタケ、カツオブシ、コブです。アゴではなく晩秋、能古島沖で釣れる大きなハゼを使う家も有ります。餅は丸餅を別なべで柔らかく煮て、すまし仕立てです。具はシイタケ、サトイモ、かつお菜、ぶりの切り身、家によっては焼き豆腐、銀杏等もいれます。明治以前の習慣ではスルメ、山芋、ごぼう、にんじんも入れて、ますますにぎやかな雑煮にします。父から聞いた話ですが、福岡の武家達は椀に大根の輪切りを敷き、子餅、ハマグリを各々二個入れたハマグリ雑煮で祝った事もあるそうです。 魚の切り身には鯛、ぶり、アラと3通りの支持者があり、それぞれ正統派を主張します。鯛派は「鯛はめでたい、祝いごとにはタイ」と言えば、ぶり派は「ぶりこそ成長につれ呼び名が変わるめでたい出世魚。昔は台所にコモを巻いてぶら下げ、これを使った」と譲らない。これに対し、アラ派によれば姿も味も、値段もアラが魚の王者。「だいいち、竹グシを刺すとき、鯛だと身がぽろっと崩れるでしょう!その点、アラだと都合が良い」と追い討ちを掛けたそうです。戦前迄、未だ女性達が家事に手間と時間を掛けていた頃、博多の習慣では具を一人前ずつ竹グシに通しておいたのが特徴です。家族が多く、雑煮を食べた後、帰郷する住み込み店員を抱えた商家のごりょんさんの知恵でしょう。戦後は紅白歌合戦を観るのが忙しくて、とてもそんな暇などはありませんね。
魚の切り身には鯛、ぶり、アラと3通りの支持者があり、それぞれ正統派を主張します。鯛派は「鯛はめでたい、祝いごとにはタイ」と言えば、ぶり派は「ぶりこそ成長につれ呼び名が変わるめでたい出世魚。昔は台所にコモを巻いてぶら下げ、これを使った」と譲らない。これに対し、アラ派によれば姿も味も、値段もアラが魚の王者。「だいいち、竹グシを刺すとき、鯛だと身がぽろっと崩れるでしょう!その点、アラだと都合が良い」と追い討ちを掛けたそうです。戦前迄、未だ女性達が家事に手間と時間を掛けていた頃、博多の習慣では具を一人前ずつ竹グシに通しておいたのが特徴です。家族が多く、雑煮を食べた後、帰郷する住み込み店員を抱えた商家のごりょんさんの知恵でしょう。戦後は紅白歌合戦を観るのが忙しくて、とてもそんな暇などはありませんね。 お雑煮は栗の枝を削った新しい「栗はいバシ」で食べます。普通の箸では、引きの強い餅を食べる途中、ポキリと折れたりして縁起が悪いからです。それと新年も「くりあい」(やりくり)が良いようにと意味も有るそうです。2011年度は博多の歴史、行事、習慣、慣習等を加え、遠い日の出来事、春夏秋冬その日に関わる物を投稿出来ればと思っています。仕事の関係で福岡市に永住の居を構える迄、全国5都市に住みました。その都度、素晴らしい友人達が出来、今でも仲良く交流を続けています。その方々にも福岡の歴史を知って頂ければ大変光栄です。メインのNancy英会話から離れますが、時々は英語の話題も投稿して行きますので、引き続き読んで頂けると大変嬉しいです。それでは、今夜はこの辺で
お雑煮は栗の枝を削った新しい「栗はいバシ」で食べます。普通の箸では、引きの強い餅を食べる途中、ポキリと折れたりして縁起が悪いからです。それと新年も「くりあい」(やりくり)が良いようにと意味も有るそうです。2011年度は博多の歴史、行事、習慣、慣習等を加え、遠い日の出来事、春夏秋冬その日に関わる物を投稿出来ればと思っています。仕事の関係で福岡市に永住の居を構える迄、全国5都市に住みました。その都度、素晴らしい友人達が出来、今でも仲良く交流を続けています。その方々にも福岡の歴史を知って頂ければ大変光栄です。メインのNancy英会話から離れますが、時々は英語の話題も投稿して行きますので、引き続き読んで頂けると大変嬉しいです。それでは、今夜はこの辺で
 本年もどうぞ宜しくお願い致します。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。 皆様はどの様なお正月を迎えましたか?お正月の料理?と英会話の生徒達に尋ねると殆どの生徒がおせちとお雑煮と答えます。幾つになっても、万物改まった元旦の朝のお雑煮は良いものです。博多雑煮の味出しは焼アゴ(トビウオの干物)、シイタケ、カツオブシ、コブです。アゴではなく晩秋、能古島沖で釣れる大きなハゼを使う家も有ります。餅は丸餅を別なべで柔らかく煮て、すまし仕立てです。具はシイタケ、サトイモ、かつお菜、ぶりの切り身、家によっては焼き豆腐、銀杏等もいれます。明治以前の習慣ではスルメ、山芋、ごぼう、にんじんも入れて、ますますにぎやかな雑煮にします。父から聞いた話ですが、福岡の武家達は椀に大根の輪切りを敷き、子餅、ハマグリを各々二個入れたハマグリ雑煮で祝った事もあるそうです。
皆様はどの様なお正月を迎えましたか?お正月の料理?と英会話の生徒達に尋ねると殆どの生徒がおせちとお雑煮と答えます。幾つになっても、万物改まった元旦の朝のお雑煮は良いものです。博多雑煮の味出しは焼アゴ(トビウオの干物)、シイタケ、カツオブシ、コブです。アゴではなく晩秋、能古島沖で釣れる大きなハゼを使う家も有ります。餅は丸餅を別なべで柔らかく煮て、すまし仕立てです。具はシイタケ、サトイモ、かつお菜、ぶりの切り身、家によっては焼き豆腐、銀杏等もいれます。明治以前の習慣ではスルメ、山芋、ごぼう、にんじんも入れて、ますますにぎやかな雑煮にします。父から聞いた話ですが、福岡の武家達は椀に大根の輪切りを敷き、子餅、ハマグリを各々二個入れたハマグリ雑煮で祝った事もあるそうです。 魚の切り身には鯛、ぶり、アラと3通りの支持者があり、それぞれ正統派を主張します。鯛派は「鯛はめでたい、祝いごとにはタイ」と言えば、ぶり派は「ぶりこそ成長につれ呼び名が変わるめでたい出世魚。昔は台所にコモを巻いてぶら下げ、これを使った」と譲らない。これに対し、アラ派によれば姿も味も、値段もアラが魚の王者。「だいいち、竹グシを刺すとき、鯛だと身がぽろっと崩れるでしょう!その点、アラだと都合が良い」と追い討ちを掛けたそうです。戦前迄、未だ女性達が家事に手間と時間を掛けていた頃、博多の習慣では具を一人前ずつ竹グシに通しておいたのが特徴です。家族が多く、雑煮を食べた後、帰郷する住み込み店員を抱えた商家のごりょんさんの知恵でしょう。戦後は紅白歌合戦を観るのが忙しくて、とてもそんな暇などはありませんね。
魚の切り身には鯛、ぶり、アラと3通りの支持者があり、それぞれ正統派を主張します。鯛派は「鯛はめでたい、祝いごとにはタイ」と言えば、ぶり派は「ぶりこそ成長につれ呼び名が変わるめでたい出世魚。昔は台所にコモを巻いてぶら下げ、これを使った」と譲らない。これに対し、アラ派によれば姿も味も、値段もアラが魚の王者。「だいいち、竹グシを刺すとき、鯛だと身がぽろっと崩れるでしょう!その点、アラだと都合が良い」と追い討ちを掛けたそうです。戦前迄、未だ女性達が家事に手間と時間を掛けていた頃、博多の習慣では具を一人前ずつ竹グシに通しておいたのが特徴です。家族が多く、雑煮を食べた後、帰郷する住み込み店員を抱えた商家のごりょんさんの知恵でしょう。戦後は紅白歌合戦を観るのが忙しくて、とてもそんな暇などはありませんね。 お雑煮は栗の枝を削った新しい「栗はいバシ」で食べます。普通の箸では、引きの強い餅を食べる途中、ポキリと折れたりして縁起が悪いからです。それと新年も「くりあい」(やりくり)が良いようにと意味も有るそうです。2011年度は博多の歴史、行事、習慣、慣習等を加え、遠い日の出来事、春夏秋冬その日に関わる物を投稿出来ればと思っています。仕事の関係で福岡市に永住の居を構える迄、全国5都市に住みました。その都度、素晴らしい友人達が出来、今でも仲良く交流を続けています。その方々にも福岡の歴史を知って頂ければ大変光栄です。メインのNancy英会話から離れますが、時々は英語の話題も投稿して行きますので、引き続き読んで頂けると大変嬉しいです。それでは、今夜はこの辺で
お雑煮は栗の枝を削った新しい「栗はいバシ」で食べます。普通の箸では、引きの強い餅を食べる途中、ポキリと折れたりして縁起が悪いからです。それと新年も「くりあい」(やりくり)が良いようにと意味も有るそうです。2011年度は博多の歴史、行事、習慣、慣習等を加え、遠い日の出来事、春夏秋冬その日に関わる物を投稿出来ればと思っています。仕事の関係で福岡市に永住の居を構える迄、全国5都市に住みました。その都度、素晴らしい友人達が出来、今でも仲良く交流を続けています。その方々にも福岡の歴史を知って頂ければ大変光栄です。メインのNancy英会話から離れますが、時々は英語の話題も投稿して行きますので、引き続き読んで頂けると大変嬉しいです。それでは、今夜はこの辺で














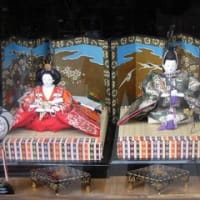



今年はせめて2カ月に1度のレッスンを
達成したいです (*^_^*)
年末はランチご馳走様でした。
いつもありがとうございます
次は春を考えています。
まだまだ寒いです、風邪に気をつけて下さい。