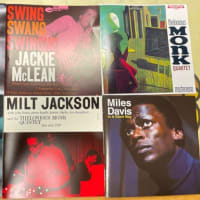2014年2月10日
障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会
昨年12月、厚生科学審議会「難病対策の改革に向けた取組について」(疾病対策部会難病対策委員会)および「慢性疾患をかかえる子どもとその家族への支援の在り方(報告)」(児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会)がまとめられた。
報告書では、「難病の治療研究を進め、疾患の克服を目指すとともに、難病患者の社会参加を支援し、難病にかかっても地域で尊厳を持って生きられる共生社会の実現を目指す」ことを基本理念として、①効果的な治療方法の開発と医療の質の向上、②公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築、③国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実の3つを柱とした新たな難病対策を確立していくことが述べられている。医療費助成においては、これまで裁量的経費により行われてきた特定疾患治療研究事業を、新たな法律にもとづいた制度として、対象疾患も56疾患から300疾患程度に拡大していくというものである。また、児童福祉法に位置づけられている小児慢性特定疾患治療研究事業においても、医療費助成を義務的経費化させ、対象疾患を514疾患から600疾患に拡大していく方向が出された。今回の難病対策の改革は、難病・慢性疾患をかかえる患者・家族にとっては、制度前進への一歩を踏み出したものと言える。
しかし同時に、今回の制度改革の議論が、医療費助成における患者負担の拡大無しには進めることが出来なかったことは、今後に大きな課題を残すことになった。患者の負担上限額には所得に応じた新たな負担上限額が設けられた。その中味を見ていくと、①既認定者の多くは従来よりも負担増となる②現在は自己負担が無い重症者へも一定の負担が課せられる③障害福祉サービスでは無料の住民税非課税世帯も有料となる④入院時食事療養費の全額給付が廃止される(小児慢性特定疾病では半額)、といった方向が出されている。
「他制度との均衡を図る」ということで導入されようとしているこれらの患者負担は、生涯にわたって医療を必要とする難病・慢性疾患患者にとっては大きな後退となるものである。また、負担上限額を決める所得の把握についても、本人所得ではなく健康保険上の世帯を単位としており、患者・家族の自立をさまたげるという問題も含んでいる。
対象疾患については、「難病」は、患者数が多い疾患は外すこととされており、新たな制度の谷間を生むのではないかということが懸念される。また、「難病」に含まれていない小児慢性特定疾患児においては、20歳を超えると医療費助成が途絶えてしまうという問題(成人期移行=トランジション問題)が指摘されてきたが、今回の報告書では、どの疾患が難病対策の対象になるのかは明確にされていない。障害者基本法の改正により、障害者の定義の中に「難病等」が含まれるようになったが、医療費助成だけが疾患名の枠にとらわれていることが、大きな矛盾を生み出している。新たに救われる患者がいる一方で、依然として制度の谷間で苦しむ患者が生まれていくということは、制度の根幹に関わる問題と言える。
難病、慢性疾患患者は、治療できる病院が専門医療機関に限定されており、症状が重いほど通院のための交通費や家族の付き添いなどの負担も負っており、せめて医療費の心配をせずに生活できるようにしていくことが最大の願いである。今後、通常国会において法案審議が行われるが、患者負担の在り方と対象疾患の範囲については、患者・家族の日常生活における実情を充分にふまえた慎重な議論を行うことが重要となっている。
また、今回の方の仕組みを検討する上で参考とされた自立支援医療についても、低所得者の無料化等の負担の在り方についてはいまだに検討課題となっているが、あわせて早急な改善が求められている。
私たち障全協は、誰もが健康に生きる権利を保障するために、今後も患者・障害者の医療を改善していくための運動を、患者団体とも共同しながら、展開していく決意である。
最新の画像もっと見る
最近の「日記・日常」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事