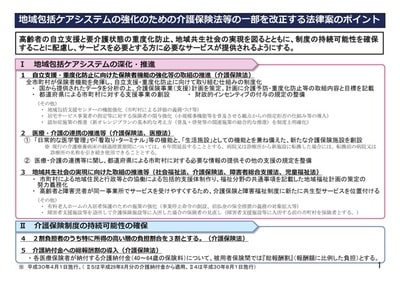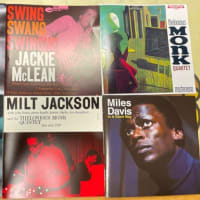すべての質問者をネット中継で見たわけではありませんが、示されている法案の重要な内容に関する質疑について政府が答えた内容をメモとしてまとめてみました。
<Q)が質問者、A)が政府回答>
拙速な取り扱いとならないよう、慎重で十分な議論を求めます。
Q)介護の社会化が図られず、介護離職、介護殺人(1週間に一度という統計もある)等の悲劇を生み出している現状に関する基本認識
A)悲劇は防がないといけないが、事案ごとに様々に状況は違うし負担についてもきめ細かな配慮がある。新総合事業は、介護保険の対象であるしこれによる実態の悪化は報告されていない
Q)未来投資会議等で示された方向「自立支援に軸足を置く」という流れがあるが、「高齢者の自立した生活」についての認識はどうか。
A)自立を助けていく方向であり、「サービスを使ってはいけない」とはいってない。
Q)利用者負担の見直し(3割負担の導入)。前回の検証もしていない。あまりに過酷なことではないか根拠はどこにあるのか。
A)所得の高い層においては能力に応じた負担をしてもらい。所得の低い人には配慮をしている。制度の対象者拡大につながっていく。
Q)地域共生社会について。我が事・丸ごとの方向が示されているが厚労省のめざす方向は何か。包括的な支援体制とは何か。相談支援窓口等の兼務を進めるだけになるのではないか。今後の社会福祉のあり方を変質させるもの。
A)相談支援体制は充実させていく方向だが、すべての努力をそこだけにゆだねることはない。包括支援体制の整備、地域住民に押し付けているわけではない。批判はあたらない。
Q)重度化防止等目標達成の指標は何を想定しているのか。サービス利用の阻害につながるのではないか。
A)保険者機能の強化していく。客観的な指標、インセンティブを与えられるように。サービス利用の阻害につながらない適正なものを想定。
Q)新設される介護医療院について。介護療養病床との違いは何か。(療養病床)の抜本拡充が必要ではないか。
A)介護・医療の役割の明確化が必要。日常的な医学管理だけでなく、看取り等生活施設の機能を兼ね備えたもの。具体的な基準は介護給付費分科会で議論。
Q)共生型サービスについて。介護サービス実施の基準緩和となるが、当事者が望んでいるのは介護保険優先原則の廃止。基本合意文書との関係はどうか。
A)共生型サービスは、65歳になった障害者がそのままサービスを継続できる内容。障害福祉との統合ではなく、基本合意文書に反するものではない。