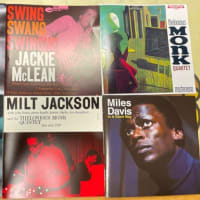辺野古への車中にて①(キャンプキンザー、キャンプハンセン)
・キャンプキンザー、僅かな土地返還(道路拡張のため)がされた。それを菅官房長官が、大々的に宣伝した。
・ここは、倉庫群。ありとあらゆる物質が保管されている。
・95年少女暴行事件、怒りの県民集会。その後、日米で結ばれた基地返還合意(SACO)。3点確認した。
①沖縄北部訓練場北側の返還。
②普天間を閉める。辺野古に基地を移す
③嘉手納から南側を返す。
・どれくらい減るのかと聞けば、わずか0.7%。県民の怒りを逆手にとっていくやり方。那覇軍港、返すと言って浦添に移す。キャンプキンザーもキャンプハンセンに。基地機能を強化するやり方。
・キャンプハンセン。ありとあらゆる状況に対応する訓練ができるようにされている。今の戦争は、対テロ。市街地の想定、都市型訓練施設。自衛隊との共同使用している。
・人を殺せる人間にしていく。人格が破壊される。そうして、戦場に送り込まれていく。
・実弾を使った訓練施設が住民に知らされたのは、ほとんど出来上がっての状態。訓練施設から500メートル先に保育園。3年抗議し続けて、何とか撤回させた。
・強襲上陸艦にオスプレイを載せて海外に出かける。艦は、基本的には佐世保にいる。今、分散している機能を集中させるのが、辺野古新基地。
・キャンプハンセン近くのいげい集落、流れ弾があった。監視小屋を立て、アピールをして。
・(下地さんの経験)…防空演習、小学校の時(朝鮮戦争時)にやっていた(下地さん)。両手の指10本を使って、鼻、目、耳を全て押さえる。これは、戦時中に爆風を押さえるやり方としてされていたこと。夜中には灯火訓練もあった。普天間第2は今もやっている。
辺野古への車中②・辺野古(テント・ゲート前・大浦湾・瀬嵩の浜)
・50年代の闘争、抵抗しても奪われた。抵抗し守り抜いて、そして取り返す闘いへ。米軍と一緒に攻撃してくるのが、日本政府。
・辺野古新基地建設、活断層があることがわかる。マヨネーズ状の軟弱な地盤があることもわかっている。変更するしかないが、その許認可権は県知事。デニーさんは認めない。
・さらに、以前の計画より陸地に近いところなったため、基地建設の基準にある周辺の建物などが高さ制限に引っかかる。例外措置で一部対応するつもりのようだが、やればやるほどぼろが出てくる
・祖国復帰まで27年、あきらめずに闘った。辺野古新基地反対は今で22年間。あきらめないことが変化をもたらす。日々の闘いは、変化のない毎日を継続することとなる。闘いで大切なのは、疲れないこと。暴力はダメ、闘いは鈍角で。鈍角とは、誰もが参加できる・いろんな闘い方があると言うこと。しなやかに、したたかに、粘り強く。
・ テントにて…護岸工事が始められた。埋め立てに必要な土砂は、東京ドーム180個。土砂は全国(7カ所)から入ってくる予定。土に含まれる生物などが入り、沖縄の環境が変わってしまう。土砂採取する方も同様。白い護岸で囲まれウミガメが来れなくなった。
・いのちを守る会、おじい・おばあの会があって、今のヘリ基地反対協議会につながる。戦争が終わった後、海に助けられた。その海が殺されようとしている。若者たちは暮らしがある。わたしたちががんばろうとの思い。いつまでやるのか、あきらめるのは相手より1日遅く。
・ゲート前にて…山城さんが逮捕・拘留された同時期に100日間、拘留された。現在、控訴し闘っている。
・今は、承認撤回してことで平日も工事してない。海上のフロートも撤去した。私たちは、護岸の撤去もしろと主張している。
・国は、行政不服審査法を使って、工事を再開しようとしている。シナリオは出来上がっているのではないか。
・始まれば人が集まるし阻止はしていけるが、国も船で土砂を運ぶ準備をしているので、土砂を積み込み場所での抗議行動も重要だろう。
・活断層が見つかったが、アメリカの法律ではできないことになる。40メートルに渡っての軟弱層等の問題も、デニー知事は計画変更を認めないサンゴの移植をしてない。高さ制限問題等、闘えば勝てる。
・国は、お金と力で黙らそうとしている。名護市長選は、その力が強大だった。今回の知事選も基礎票では向こうが断然大きいが、それを許さなかった。本土と沖縄の人が連帯した闘いを。
・大浦湾の浜辺から…この海は川が2本流れ込んでいて、陸と海のプランクトンがまじりあいとても豊か。高さが12mのサンゴは、3000年の歴史がある(縄文時代から)。クマノミ、日本にいる6種類が全ている。珍しい貴重な種があり、新種も多く発見されている(研究者が追いつかないというくらい)。それを調べないで埋め立てようとしている。
・夢と希望のある地域、自然とともに生きるか、基地とともに苦しみながら生きるのが、どちらがいいかわかっている。賛成派と言われる地元区長さん、基地に賛同してはいない。反対してもつくると国がいうから、せめて迷惑料としてもらいたいと言っただけ。
・本音は一緒。違いは、あきらめているか、あきらめられないか。基地が作られないと言う状況が出てきたら、一緒にできる。自らの判断で考えてもらえるような運動が大事。
・キャンプシュワブ、返還後には国民休暇村にしたい。弾薬庫は、泡盛貯蔵倉庫に。5年、10年の古酒にできたら、たくさんの人が訪れる。
沖縄愛楽園
・現在142名入所。平均年齢は84.1歳(親族関係を絶たれた人や偏見の目もまだある)
・患者立の療養所だった。開園当時は橋がなく、海上交通でのやり取りだった。
・明治40年のらい予防。隔離政策、その後内容が強化されたこと。
・園舎が整然と並んでいて、爆撃にあった歴史があったこと。
・堕胎や断種なども行われていたこと(声なき子供たちの碑)
・アメリカでは隔離政策はやめていた。アメリカ統治下で、やめようと思えばできていた。
・「家族と切り離され、人間の尊厳を奪われた入所者たちは、社会では生きていけないと烙印を押されたようなものだった。社会とは、どこの誰のことなのだろうか」(常設展展示説明文がら)
チビチリガマ・シムクガマ
・2つのガマの違い。遺族の思いに心を寄せて見つめていくことが大事。
・チビチリガマが荒らされた事件。少年4名、ほんとうにショックだった。4名(計画したのは12名)は、ネットでつながっていた子どもたち。複雑な環境で育ってきた子どもたちもいた。
・保護観察になった子どもたち。それを引き受けた金城実さんが出した課題。
①ここで何があったかのレメ[トを書くこと。
②平和の像に込めた地域の思いを踏まえたレメ[トを書くこと
③君たちは一生この事実を背負う。野仏を作る
・チビチリガマ、長いこと語られなかった場所である。「再び国家の名において、戦争への道を歩まさないこと」(碑文より)が大事。
・ガマの中での灯りをどうしたか。缶詰の空き缶を使い、そこに豚の脂を入れて芯を作った。薄ぼんやりした灯りでしかなかったが、そのことが生き延びることにつながる。仮にしっかり見えていたら、目を背けたくなる現実の中で気持ちが保てなかっただろう。
読谷村役場
・山内徳信さんの話しなど…。