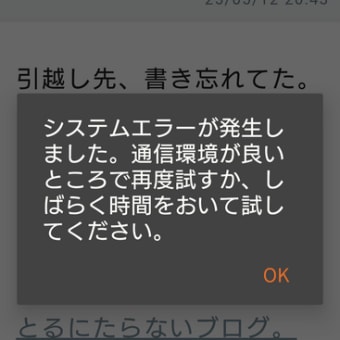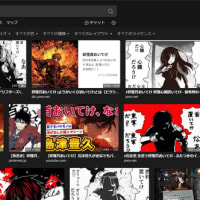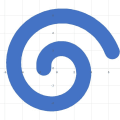NHKの聞き逃し配信から聞いてください。
間違いあれば、
私の聞き間違いか、理解不足です。
また、" " 内は感想だったり私が追記したものです。
3.X線がフェイズを変えた。進歩する日本の宇宙望遠鏡。
・銀河団はX戦で観測すると、高温のガスが全体を覆っていることが分かっている。
・分光観測すると、
物質の温度、
物資の組成、
運動、
が分かる。
・2025年2月、X線望遠鏡XRISM(クリズム)が1億光年のケンタウルス座銀河団を観測し、
銀河団の中心のプラズマ流の運動を解き明かした。
銀河団が合体、成長していくことが推測されるデータである。
・日本は16個の宇宙望遠鏡を打ち上げている。
全てISAS。
ほとんどがX線であり、日本が得意としている。
現在運用中のものは、XRISM、ひので、の2機。
・国立天文台は地上からの観測をしている。
・X線の波長は0.01~1nm。
・日本がX線望遠鏡に特化したのは、
高エネルギー天文学に関心が強い学者が多かったから。
・小田稔。
X線源の位置を特定する、
『すだれコリメータ』を発明した。
1964年にはくちょう座X-1を発見。
・可視光、赤外線観測で観測し、
1971年、はくちょう座X-1は、
ブラックホール(BH)であることを明らかにした。
・このことを契機に、日本ではX線天文学が発展してゆく。
・はくちょう(1979年)、てんま(1983年)が打ち上げられた。
最も成果を挙げたのが、ぎんが(1987年)で超新星を観測した。
その後も、あすか(1993年)、すざく(2005年)と打ち上げられていく。
国際的にも高い評価を得る、観測結果を出し続けてきた。
・BHから光は出れないが、
BH付近では物質が高密度に集まるので、
高温になりX線がでる。
・最近になり、BH付近の電波画像や、重力波の観測から、
小田らが発見した天体はBHであることが間違いないとされた。
・XRISMの特徴。
打ち上げ後1ヶ月で壊れた『ひとみ』の代替機がXRISMで2023年9月打ち上げ。
X線CCD、
X線マイクロカロリメータ分光撮像器
が搭載されている。
・宇宙の大規模構造のなりたち、
ダークマター、ダークエネルギー解明の手掛かり、
星の進化、
での成果が期待されている。
・太陽観測衛星について。
1981年ひのとり、1991年ようこう、
X線で太陽を観測した。
”『ひので』SOLAR-Bは観測中ですね。”
"『ようこう』SOLAR-Aについては昔、『今日の太陽』をよくダウンロードしてました。"
・2028年に赤外線望遠鏡JASMINE(ジャスミン)を打ち上げ予定。
SOLAR-Cも計画されている。