手
枕
に
花
火
の
ど
う
ん
ど
う
ん
哉
一
茶
一茶忌。
ということで、一茶をにわか勉強しました(;^_^A
一茶には名句がたくさんあります。
やせ蛙負けるな一茶これにあり
私はこの句を長いこと、一茶が自分のことを励ます句だと思っていたのですが
そういう解釈はまちがいではないかもしれないものの、
本来は、「これにあり」は「オレがここにいるぞ」という意で、
蛙への応援歌(応援句^^)なのだと知りました。
以来、この句を好きになりました。
手枕に花火のどうんどうん哉
夏の座敷にのびやかに花火を眺める姿が目に浮かぶようです。
畳についた肘に、花火の音とともに振動が伝わってでもくるかのよう。
一茶のことを調べると、その生涯は不遇であったとあります。
伝記を読むことは好きですが、
俳人の境遇と俳句は分けて考えたく思います。
俳句は十七文字で完結する世界。
それが全てであるべきです。
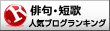

枕
に
花
火
の
ど
う
ん
ど
う
ん
哉
一
茶
一茶忌。
ということで、一茶をにわか勉強しました(;^_^A
一茶には名句がたくさんあります。
やせ蛙負けるな一茶これにあり
私はこの句を長いこと、一茶が自分のことを励ます句だと思っていたのですが
そういう解釈はまちがいではないかもしれないものの、
本来は、「これにあり」は「オレがここにいるぞ」という意で、
蛙への応援歌(応援句^^)なのだと知りました。
以来、この句を好きになりました。
手枕に花火のどうんどうん哉
夏の座敷にのびやかに花火を眺める姿が目に浮かぶようです。
畳についた肘に、花火の音とともに振動が伝わってでもくるかのよう。
一茶のことを調べると、その生涯は不遇であったとあります。
伝記を読むことは好きですが、
俳人の境遇と俳句は分けて考えたく思います。
俳句は十七文字で完結する世界。
それが全てであるべきです。













