
パイプオルガンには大きく分けて3つの形態があります。
1)大オルガン
2)ポジティフオルガン
3)ポルタティフオルガン
1)の大オルガンは、教会やホールに設置してあるもので、基本的に入れ物に入っていないため、または重量が大きいためそのまま移動する事ができないもの。
中でも、教会の西側、つまり正面入り口のすぐ上の壁にくっついている大オルガンでは、パイプのまわりを囲む木製の装飾部分が、どちらかというと壁と一体になっていて、いうなればオルガンの内臓を隠すついたてのように設置されている場合があります。
教会が作られた年代に、ほぼ同時に設置されたバロックオルガンでは、オルガンの外見的な「デザイン」は、オルガン制作者ではなく、教会の室内建築家が受け持っていたため、彫刻、金ぱくなどのスタイルが教会の内部と一致しています(フィニステール教会の場合もそう)。
2)のポジティフオルガンは、箱に入っていて、かなり大きいものでもいくつかの部分に分けると運べるもの。
3)は膝に乗せて演奏できるもの。つまり、ポルタティフオルガンはポルト、つまりポートできるオルガンなので、運べるオルガン、人が持ち歩けるオルガン、と意味が良くわかり納得がいきます。
が、先日、疑問が浮上した通り、ポジティフオルガンは何が「肯定的」なのか?わからない。
そこを追求してみたら、ポジティフは、写真のように「ネガティフの反対、肯定的」という意味ではなく、
ポーズできる、つまり好きなところに持って行って「置ける」
オルガン、という意味でした。
ポジティフオルガンはポルタティフよりは大きくて、四角い箱に入っているので、楽団の中にちょっと置いて他の楽器と一緒に弾く事もできる。ストップの数もたった1つの8フィートだけのものから1ダースを超えるストップを擁した楽器もある。演奏者を見る事ができる楽しみもあります。



さて、ここからは、ポジティフの発展した、大オルガンにおけるリュック・ポジティフの話。
教会の後ろの壁にくっついているタイプの大オルガンの手前にこのポジティフオルガンを置き、大オルガンの演奏台から弾けるように連動させたものが、リュックポジティフです。リュックの意味は、はリュックサックのように、オルガニストの背中部分に置いてあるから。演奏台のベンチに座った時、正面が大オルガンで鍵盤がついている。ベンチの背もたれのかわりのようにして、ポジティフオルガンが設置されているので、オルガニストは大小のオルガンに挟まれるかたちになります。
でも、このスタイルがはやりはじめたころの、17世紀のリュックポジティフ付き大オルガンを見ると、演奏台は連動しているのですが、ストップだけは大オルガン側ではなく、ポジティフの方についているため、演奏中に後ろを向いてストップをわしづかみしてさっ!と引き出すか押し込むかしたら、またおもむろに前を向いて演奏を続けなければならず、なかなか不便だし背中も痛くなるので、のちに全て演奏台の側でストップ操作できるように変わったようです。
リュックポジティフがはやった理由は、教会堂内部にいる会衆や聴衆からリュックポジティフの部分は距離的に近く、大オルガンよりも突き出しているので、
リュックポジティフさん=ソリスト
大オルガンさん=伴奏というかオケ役
という、バロック時代にとても人気のあった協奏曲様式、コンチェルトのような効果を、オルガニスト一人の演奏で表現する事が出来たのです。経済的!(弾くのは忙しいし大変ですが)
リュックポジティフは見た目も2層構えで迫力があって美しいし、演奏者がうまく隠れて教会にはふさわしい、などの視覚的な要因も人気の理由かもしれません。
バッハやそのいとこヴァルターは、ヴィヴァルディなどの管弦楽協奏曲を編曲して、オルガン1台で演奏するコンチェルトを残していますが、バッハの活躍した中部ドイツでは、リュックポジティフ付きのオルガンは数多くはありませんでした(現存しているもので有名なのはナウムブルグぐらい)。
このタイプの大オルガン発祥の地の一つであるフランスでは、「ティエルス・オン・タイイ」という、左手がリュックポジティフのソロパ-トを受け持つあまりに美しい効果のある曲種が生み出されました。
声楽的な片手のソロをもう一つの手とペダルで伴奏する曲の中でも、ティエルス・オン・タイイが特別なのは、身体的に低音側にある左手がソロで8フィート基本の音色、高音側の右手が16フィート基本の音色を使うため、基本的にソロが伴奏とほぼ同じ音域になるところです。
つまり右手は柔らかく深い音色のストップの組み合わせながら(16’+8’)、輝かしいストップの組み合わせ(8’+4’+22/3’+2’+13/5’+11/3’)で歌うソロパートを囲み込むような伴奏になります。下からペダルもサポートしてくるのでまさしくソリストを包み込む感じ。
というわけで、
ティエルス(8フィートに対し「1と3分の1」という長さのストップの名前。3度の音が出る、つまりまんなかのドを弾くと2オクターブ上のミの音が出る)
・オン(の場所にある、という前置詞)
・タイイ(「ウエストの辺り」にある声部。高音でもなく低音でもない、つまりテノール声部)
の作品は、フランス古典のオルガン組曲にはかならず入っています。左手で演歌歌手なみのメリスマ、装飾的な流れる音符群を弾くということは、右利きの人には意外に難しいけれど、柔らかく優しい左手が、中音域のテノールで弾くからこそ、こういう音楽になるんだ、と納得できる良さがあります。
リュックポジティフ付き大オルガンのコンサートでは、みんなが楽しみにしている、ソロのサビを聴かせるおいしいナンバーです。
(写真は、以前にもアップした事がある、エティエンヌ・ドベジュー氏制作のポジティフ・オルガンの写真。調律しているのはご本人)

1)大オルガン
2)ポジティフオルガン
3)ポルタティフオルガン
1)の大オルガンは、教会やホールに設置してあるもので、基本的に入れ物に入っていないため、または重量が大きいためそのまま移動する事ができないもの。
中でも、教会の西側、つまり正面入り口のすぐ上の壁にくっついている大オルガンでは、パイプのまわりを囲む木製の装飾部分が、どちらかというと壁と一体になっていて、いうなればオルガンの内臓を隠すついたてのように設置されている場合があります。
教会が作られた年代に、ほぼ同時に設置されたバロックオルガンでは、オルガンの外見的な「デザイン」は、オルガン制作者ではなく、教会の室内建築家が受け持っていたため、彫刻、金ぱくなどのスタイルが教会の内部と一致しています(フィニステール教会の場合もそう)。
2)のポジティフオルガンは、箱に入っていて、かなり大きいものでもいくつかの部分に分けると運べるもの。
3)は膝に乗せて演奏できるもの。つまり、ポルタティフオルガンはポルト、つまりポートできるオルガンなので、運べるオルガン、人が持ち歩けるオルガン、と意味が良くわかり納得がいきます。
が、先日、疑問が浮上した通り、ポジティフオルガンは何が「肯定的」なのか?わからない。
そこを追求してみたら、ポジティフは、写真のように「ネガティフの反対、肯定的」という意味ではなく、
ポーズできる、つまり好きなところに持って行って「置ける」
オルガン、という意味でした。
ポジティフオルガンはポルタティフよりは大きくて、四角い箱に入っているので、楽団の中にちょっと置いて他の楽器と一緒に弾く事もできる。ストップの数もたった1つの8フィートだけのものから1ダースを超えるストップを擁した楽器もある。演奏者を見る事ができる楽しみもあります。



さて、ここからは、ポジティフの発展した、大オルガンにおけるリュック・ポジティフの話。
教会の後ろの壁にくっついているタイプの大オルガンの手前にこのポジティフオルガンを置き、大オルガンの演奏台から弾けるように連動させたものが、リュックポジティフです。リュックの意味は、はリュックサックのように、オルガニストの背中部分に置いてあるから。演奏台のベンチに座った時、正面が大オルガンで鍵盤がついている。ベンチの背もたれのかわりのようにして、ポジティフオルガンが設置されているので、オルガニストは大小のオルガンに挟まれるかたちになります。
でも、このスタイルがはやりはじめたころの、17世紀のリュックポジティフ付き大オルガンを見ると、演奏台は連動しているのですが、ストップだけは大オルガン側ではなく、ポジティフの方についているため、演奏中に後ろを向いてストップをわしづかみしてさっ!と引き出すか押し込むかしたら、またおもむろに前を向いて演奏を続けなければならず、なかなか不便だし背中も痛くなるので、のちに全て演奏台の側でストップ操作できるように変わったようです。
リュックポジティフがはやった理由は、教会堂内部にいる会衆や聴衆からリュックポジティフの部分は距離的に近く、大オルガンよりも突き出しているので、
リュックポジティフさん=ソリスト
大オルガンさん=伴奏というかオケ役
という、バロック時代にとても人気のあった協奏曲様式、コンチェルトのような効果を、オルガニスト一人の演奏で表現する事が出来たのです。経済的!(弾くのは忙しいし大変ですが)
リュックポジティフは見た目も2層構えで迫力があって美しいし、演奏者がうまく隠れて教会にはふさわしい、などの視覚的な要因も人気の理由かもしれません。
バッハやそのいとこヴァルターは、ヴィヴァルディなどの管弦楽協奏曲を編曲して、オルガン1台で演奏するコンチェルトを残していますが、バッハの活躍した中部ドイツでは、リュックポジティフ付きのオルガンは数多くはありませんでした(現存しているもので有名なのはナウムブルグぐらい)。
このタイプの大オルガン発祥の地の一つであるフランスでは、「ティエルス・オン・タイイ」という、左手がリュックポジティフのソロパ-トを受け持つあまりに美しい効果のある曲種が生み出されました。
声楽的な片手のソロをもう一つの手とペダルで伴奏する曲の中でも、ティエルス・オン・タイイが特別なのは、身体的に低音側にある左手がソロで8フィート基本の音色、高音側の右手が16フィート基本の音色を使うため、基本的にソロが伴奏とほぼ同じ音域になるところです。
つまり右手は柔らかく深い音色のストップの組み合わせながら(16’+8’)、輝かしいストップの組み合わせ(8’+4’+22/3’+2’+13/5’+11/3’)で歌うソロパートを囲み込むような伴奏になります。下からペダルもサポートしてくるのでまさしくソリストを包み込む感じ。
というわけで、
ティエルス(8フィートに対し「1と3分の1」という長さのストップの名前。3度の音が出る、つまりまんなかのドを弾くと2オクターブ上のミの音が出る)
・オン(の場所にある、という前置詞)
・タイイ(「ウエストの辺り」にある声部。高音でもなく低音でもない、つまりテノール声部)
の作品は、フランス古典のオルガン組曲にはかならず入っています。左手で演歌歌手なみのメリスマ、装飾的な流れる音符群を弾くということは、右利きの人には意外に難しいけれど、柔らかく優しい左手が、中音域のテノールで弾くからこそ、こういう音楽になるんだ、と納得できる良さがあります。
リュックポジティフ付き大オルガンのコンサートでは、みんなが楽しみにしている、ソロのサビを聴かせるおいしいナンバーです。
(写真は、以前にもアップした事がある、エティエンヌ・ドベジュー氏制作のポジティフ・オルガンの写真。調律しているのはご本人)












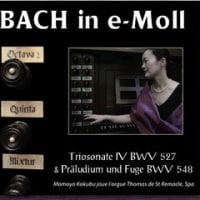







ブログを初めて拝見いたし、興味深く読ませていただきました。
オルガンを修行中のエルヴィンと申します。
私もオルガンが好きだし、勉強しているつもりですが、まだまだわからないことだらけです。
これからも、オルガンについて、いろいろ教えてください!
私は、前の人がオルガンに残したストップを使って弾いてしまいますが、それは、私自身が、どのストップでも「きれいな音」と満足してしまうからです。
曲によって、作曲家によるストップの指定はなかったとしても、一般的なストップがあったり、それぞれのストップに意味があったりするようですね。
折があったら、そんな話しも教えてください。
「世界一大きなオルガンを弾くこと」を夢見ています。
よろしくお願いします。