6月11日(月)、第344回目の“オルガンの月曜日”で、ルイ・ヴィエルヌ(フランス、ポワティエ1870年生まれ-パリ1937没)の"Pieces en Style Libre"2巻目を弾きました。
この曲集は、それぞれの曲の長さが3分から4分で、ペダルなしでもありでも、オルガンでもハーモニウムでも弾けるというものです。
ハーモニウムは、いわゆる足踏みオルガンのことですが、19世紀から20世紀初頭のフランスではそのちょっとものがなしい音色、送る空気の量を調節して音量のニュアンスをピアノみたいにつけられることから、わりと人気のあった楽器です。2段鍵盤、ペダル鍵盤付きのもの(その場合は空気はアシスタントが入れる、またはモーター付き)まであります。ストップも5個から15個くらい付いていて、オルガンのように音色が変えられます。でもパイプはなく、すべてリードです。
ヴィエルヌのこの小品集は、曲も長過ぎず、難度もそう高くないので、ピアノを弾いたことがある、オルガン初心者の方たちに好まれています。わたしもコンサートでポジティフを使うときなどに、弾いていました。
でも一度全曲順番通りに弾いたら、どうなるかな。と、思いつきました。調性も変化をつけながら、うまくならべられています。
昨日弾いた第2巻には、“子守唄”や、“パストラール”、“カリヨン”などよく演奏される曲が入っています。でも、全部で24曲の曲集の、第2巻なので12曲あるわけですが、あまり、というかほとんど弾かれていない曲もあります。わたしは1,2巻とも、ずっと前から持っていて、適当に選びながら弾いて来て、第2巻はあと2曲が残っていました。“Epithalame"と"Postlude"です。前者は題名の意味が分からないし、内容もどうとらえていいかピンと来ない。ロ長調(#が5つ)という調に、変化記号もたっぷりついてるので初見用ではないし...
まず身近にいる本読みっ子の娘に、
“Epithalame"って、どういう意味?
と訊いたら、
あっ、それ知らない。
...この半年、わたしが仏語の手紙(たとえ3行でも間違いが必ずある!)を書くたびに校正してくれて、頼りにしていた彼女が知らないのなら、私が知らないのは当然。と納得して夫に訊くと、やはり、知らない。となると、文語的表現なのか、詩に出てくることばかな。と考え、結婚式にいただいた背表紙10センチの“Le Robert"(Larousseみたいな辞書)で調べたら、ありました!
(語源Epithalamus、ラテン語):結婚式の際に、お祝いに贈る詩歌。
だそうでした。ははあ。第1フレーズが終わるなり第2フレーズに入ったと思えばすぐさま第3フレーズになだれ込んで行く不思議な出だし。どこへ向かっているのかわからないと思ったら、急にすごくスゥィートなカデンツ。これは意味わからないと弾けない!Emile Poillotに捧げる、と献辞がついていますが、この人の結婚式のためだったのかな。1913年出版の曲集なので、もう今は亡きこの人の人生はどんなだったかな。思いはふくらむのでした。
Postludeは、始まったと思ったら終わってるタイプの、展開部のない作品なので、これだけ弾くと、聴いてる人が困惑して拍手できなさそうな曲です。でも12曲の締めとして聴くならば...
そのような一曲一曲のキャラクターを掘り起こしながら、テンポ、曲想を練り、レジストレーションを決めて行き、順々に弾くと、曲を別々に弾くときより“チョコレート詰め合わせセット”のようで、気持ちが弾みました。ショパンのような、エレジー。赤ちゃんが最後に寝てしまう、子守唄。中でも、むかし試験で弾いてから大好きだったScherzettoをまた取り出して弾けたのが楽しく、練習していても飽きない体験でした。
ただ、一気に12曲なので、常に最初のページからさらうわけでもなく、練習し忘れが出そうだったので、しおりのような白紙を用意して、曲名、練習ok、レジストレーションok、と書いて、表の形でチェックしながら準備しました。折からの急激な歯痛に悩まされた週末だったので、このような目に見える、確かに準備できたという証拠物件が楽譜にはさまっていると、パニックが避けられ、気分的に落ち着いていられました。
演奏してみると、通常の昼コンサートの45分をオーバーして55分になってしまったので、1時半には教会を出てオフィスにもどらなければならない人たちなどが最後の2曲を聴けなかったようですが、最後まで残ってくれた人の中に、
最高に贅沢な時間だった!
と言ってくれた人がいて、あっこの人は曲の中のそれぞれのお話をちゃんとわかってくれたのだな。全部の“チョコレートの味見”ができたのだな。と感じました。ほかには、
こういう現代的なのは、変わってて不思議な感じ...
という感想の人がいて、これが現代って...19世紀生まれの作曲家なんだけどなあ、とびっくりしながらも、Vierne特有の、半音階でどこにでも行ってしまう超時間的なページは、たしかに古くならず、こちらにとっても、何回弾いてもまだわからない感じがして、飽きないのだと思います。
歯痛対策で、パラセタモル系のダファルガンという薬をエビアンのボトルに作っておいて、飲みながら弾いていたのでちょっと辛かったですが、一番こまったのは、最後に拍手があって、お辞儀する時に左の頬がはれていたことです。手で隠そうと思ったけれど、かえって目立ちそうなので、堂々と片おたふく顔でsalut-!してしまいました。
この曲集の録音してくれたら買う!と言ってくれた人が2人もいたので、ちょっといい気になってしまいました。たしかに、この小品集は宝石箱のようなのに、あまりCDは出ていません。
最後に12曲続けて弾いて思ったのは、エピタラーム=結婚のための歌、のような曲が、実は一番難しい、ということです。早いパッセージもないし、低音部もそんなに動かない。でも、メトロノームでは四分音符=42の、Adagio sostenuto e molto espressivo。楽な遅いテンポで、音を十分に保ち、最高に表情豊かに。結婚生活、のことかしら、と思わされます。
この曲集は、それぞれの曲の長さが3分から4分で、ペダルなしでもありでも、オルガンでもハーモニウムでも弾けるというものです。
ハーモニウムは、いわゆる足踏みオルガンのことですが、19世紀から20世紀初頭のフランスではそのちょっとものがなしい音色、送る空気の量を調節して音量のニュアンスをピアノみたいにつけられることから、わりと人気のあった楽器です。2段鍵盤、ペダル鍵盤付きのもの(その場合は空気はアシスタントが入れる、またはモーター付き)まであります。ストップも5個から15個くらい付いていて、オルガンのように音色が変えられます。でもパイプはなく、すべてリードです。
ヴィエルヌのこの小品集は、曲も長過ぎず、難度もそう高くないので、ピアノを弾いたことがある、オルガン初心者の方たちに好まれています。わたしもコンサートでポジティフを使うときなどに、弾いていました。
でも一度全曲順番通りに弾いたら、どうなるかな。と、思いつきました。調性も変化をつけながら、うまくならべられています。
昨日弾いた第2巻には、“子守唄”や、“パストラール”、“カリヨン”などよく演奏される曲が入っています。でも、全部で24曲の曲集の、第2巻なので12曲あるわけですが、あまり、というかほとんど弾かれていない曲もあります。わたしは1,2巻とも、ずっと前から持っていて、適当に選びながら弾いて来て、第2巻はあと2曲が残っていました。“Epithalame"と"Postlude"です。前者は題名の意味が分からないし、内容もどうとらえていいかピンと来ない。ロ長調(#が5つ)という調に、変化記号もたっぷりついてるので初見用ではないし...
まず身近にいる本読みっ子の娘に、
“Epithalame"って、どういう意味?
と訊いたら、
あっ、それ知らない。
...この半年、わたしが仏語の手紙(たとえ3行でも間違いが必ずある!)を書くたびに校正してくれて、頼りにしていた彼女が知らないのなら、私が知らないのは当然。と納得して夫に訊くと、やはり、知らない。となると、文語的表現なのか、詩に出てくることばかな。と考え、結婚式にいただいた背表紙10センチの“Le Robert"(Larousseみたいな辞書)で調べたら、ありました!
(語源Epithalamus、ラテン語):結婚式の際に、お祝いに贈る詩歌。
だそうでした。ははあ。第1フレーズが終わるなり第2フレーズに入ったと思えばすぐさま第3フレーズになだれ込んで行く不思議な出だし。どこへ向かっているのかわからないと思ったら、急にすごくスゥィートなカデンツ。これは意味わからないと弾けない!Emile Poillotに捧げる、と献辞がついていますが、この人の結婚式のためだったのかな。1913年出版の曲集なので、もう今は亡きこの人の人生はどんなだったかな。思いはふくらむのでした。
Postludeは、始まったと思ったら終わってるタイプの、展開部のない作品なので、これだけ弾くと、聴いてる人が困惑して拍手できなさそうな曲です。でも12曲の締めとして聴くならば...
そのような一曲一曲のキャラクターを掘り起こしながら、テンポ、曲想を練り、レジストレーションを決めて行き、順々に弾くと、曲を別々に弾くときより“チョコレート詰め合わせセット”のようで、気持ちが弾みました。ショパンのような、エレジー。赤ちゃんが最後に寝てしまう、子守唄。中でも、むかし試験で弾いてから大好きだったScherzettoをまた取り出して弾けたのが楽しく、練習していても飽きない体験でした。
ただ、一気に12曲なので、常に最初のページからさらうわけでもなく、練習し忘れが出そうだったので、しおりのような白紙を用意して、曲名、練習ok、レジストレーションok、と書いて、表の形でチェックしながら準備しました。折からの急激な歯痛に悩まされた週末だったので、このような目に見える、確かに準備できたという証拠物件が楽譜にはさまっていると、パニックが避けられ、気分的に落ち着いていられました。
演奏してみると、通常の昼コンサートの45分をオーバーして55分になってしまったので、1時半には教会を出てオフィスにもどらなければならない人たちなどが最後の2曲を聴けなかったようですが、最後まで残ってくれた人の中に、
最高に贅沢な時間だった!
と言ってくれた人がいて、あっこの人は曲の中のそれぞれのお話をちゃんとわかってくれたのだな。全部の“チョコレートの味見”ができたのだな。と感じました。ほかには、
こういう現代的なのは、変わってて不思議な感じ...
という感想の人がいて、これが現代って...19世紀生まれの作曲家なんだけどなあ、とびっくりしながらも、Vierne特有の、半音階でどこにでも行ってしまう超時間的なページは、たしかに古くならず、こちらにとっても、何回弾いてもまだわからない感じがして、飽きないのだと思います。
歯痛対策で、パラセタモル系のダファルガンという薬をエビアンのボトルに作っておいて、飲みながら弾いていたのでちょっと辛かったですが、一番こまったのは、最後に拍手があって、お辞儀する時に左の頬がはれていたことです。手で隠そうと思ったけれど、かえって目立ちそうなので、堂々と片おたふく顔でsalut-!してしまいました。
この曲集の録音してくれたら買う!と言ってくれた人が2人もいたので、ちょっといい気になってしまいました。たしかに、この小品集は宝石箱のようなのに、あまりCDは出ていません。
最後に12曲続けて弾いて思ったのは、エピタラーム=結婚のための歌、のような曲が、実は一番難しい、ということです。早いパッセージもないし、低音部もそんなに動かない。でも、メトロノームでは四分音符=42の、Adagio sostenuto e molto espressivo。楽な遅いテンポで、音を十分に保ち、最高に表情豊かに。結婚生活、のことかしら、と思わされます。












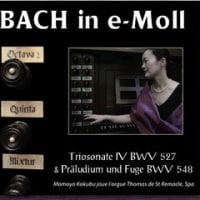







でも、まずは、全曲つづけて聴きたい。
録音はなさらなかったの?
好きだなあ。
この夏一週間空いているので、第一巻も準備して録音しちゃおうかなと思っています。去年はデュルフレのレクイエムで力尽きたので、今度は小品集でお金をあまりかけずに作って安価な2枚組にして...クリスマスあたりにいろとりどりの表紙で出すのはどうかな。いやまったくの思いつきなのでどうなることやら。
コンサートは教会で出入り自由なので、雑音が多いから(ろうそくを買った人のお金ちゃりーん、とか)録りませんでした。