5日間の穴窯焼成が、無事に終わりました。今回の助っ人は笠間陶芸大学校の生徒さんで、先輩陶芸家さんの息子さんです。はじめての1人窯焚きに不安そうでしたが、一生懸命やってくれて、本当に感謝です!
窯の調子はというと、後ろの部屋を空にしていたのを忘れていて、気がついた時は1000度を過ぎていて、止めるわけにも行かず、そのまま焚いていたのですが、その影響が1150度からあきらかに出て、2日間横ばいになってました。今回は窯奥の棚は釉薬ものを詰めていて、1000度過ぎて止めると動き始めた釉薬が剥離してしまうのです。
前回、友人が後ろの部屋を使ったので、きれいに片付けてくれていて、通常は棚を空組みしてました。
大きなエアダンパーを利かせた状態で、粘りました。益子の友人ものぞきに来てくれて、色々やってみました。
2月の浜田窯のとき、見せてくれた、後ろの部屋に薪を落として、前の部屋に熱を溜める、もやってみましたが、効果は有りませんでした。
結局、完全に酸化になるくらい、空気を入れながら9番ゼーゲル錐を倒して、その後攻め焚きに入りました。
引きの悪い状態の攻め焚きは、薪入れも火が噴いて、過酷なものになってしまい、助っ人さんも衝撃を受けていたようです。
なんとか、反省点を確認して、5日目の朝に窯焚き終了しました。
窯のまわりの満開の桜も、煙突からの黒煙で煤けてしまいました。

窯の調子はというと、後ろの部屋を空にしていたのを忘れていて、気がついた時は1000度を過ぎていて、止めるわけにも行かず、そのまま焚いていたのですが、その影響が1150度からあきらかに出て、2日間横ばいになってました。今回は窯奥の棚は釉薬ものを詰めていて、1000度過ぎて止めると動き始めた釉薬が剥離してしまうのです。
前回、友人が後ろの部屋を使ったので、きれいに片付けてくれていて、通常は棚を空組みしてました。
大きなエアダンパーを利かせた状態で、粘りました。益子の友人ものぞきに来てくれて、色々やってみました。
2月の浜田窯のとき、見せてくれた、後ろの部屋に薪を落として、前の部屋に熱を溜める、もやってみましたが、効果は有りませんでした。
結局、完全に酸化になるくらい、空気を入れながら9番ゼーゲル錐を倒して、その後攻め焚きに入りました。
引きの悪い状態の攻め焚きは、薪入れも火が噴いて、過酷なものになってしまい、助っ人さんも衝撃を受けていたようです。
なんとか、反省点を確認して、5日目の朝に窯焚き終了しました。
窯のまわりの満開の桜も、煙突からの黒煙で煤けてしまいました。












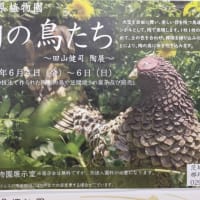
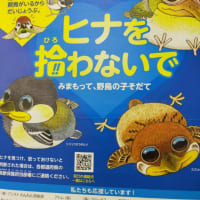


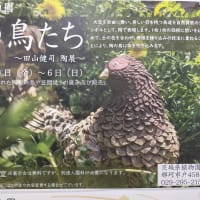





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます