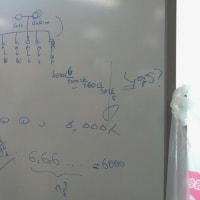個人差というのは、同じ人類と言えどかなり激しいもので、大人になってしまうと自分の属する集団からあまり外に出なくなるので、他の集団について思いをめぐらす機会も減っていく。その集団がいかに世間一般の目で見て偏っているにしても、属するものにとっては標準なのである。
例えば、医学の学会が行われている会場に行けば、石を投げたら医師に当たるという状況になるし、自動車メーカーにいけば、工学部出身者のオンパレードになる。鍼灸師は鍼灸学校出身者で占められているし、白百合女子大出身ならしっかりした職業の夫の妻である確立が高いだろう。ん、最後の例は飛びすぎか。
それぞれが、あまり階層を意識しないくらいきっちり職業で分別されているのが日本社会なのではないかと思う。同じ階層でしか交流がないから自分がアホかそうでないかも全対的には意識できないというか。
違う階層に属するもの同士が出会い互いを理解しようとするプロセスーこれって結婚では起こりうる。日本で階層(教育レベルぐらいの大雑把なくくりで)の違う者同士が結婚するということが多く起こったのは1970年代なんだそうだ。確かに、国立大学卒のエンジニアが地方から出てきた高卒女子と結婚なんてことは結構よく起こっていた。そして生れた子供がより良い教育を受けることを当然とする前提で育って、より自己選択度の高い人生を歩むことができれば、幸福度の高い状態といえる。そういったことを、日系D青年が語ってくれた。
社会科学のある分野を研究する彼は、貧乏人の子が貧乏という社会のパターンを刷り込みの一種で、教育の重要さにある一定数の人口が気付けば通念を覆すことも可能と語る。「随分前向きなんですね。やっぱり現実は暗かったですなんてよくある終わり方はしないんですね。」とワタス。
「暗いなら、なぜ暗いか、どういう風に暗いか、どうすれば明るくなって良くなるかという考え方をしないと論文は書けませんよ。だって、そのままじゃ何も変わらないでしょう?社会が良くならないじゃないですか。」
本当の学問は前向きで社会貢献を前提とするものなのだ。
博士課程後期では多くの人がそういう発想をする傾向が顕著にある。
で、そういう発想をする集団が実際にあるという事実は、かなり気持ちを明るくしてくれるものなのだ。
例えば、医学の学会が行われている会場に行けば、石を投げたら医師に当たるという状況になるし、自動車メーカーにいけば、工学部出身者のオンパレードになる。鍼灸師は鍼灸学校出身者で占められているし、白百合女子大出身ならしっかりした職業の夫の妻である確立が高いだろう。ん、最後の例は飛びすぎか。
それぞれが、あまり階層を意識しないくらいきっちり職業で分別されているのが日本社会なのではないかと思う。同じ階層でしか交流がないから自分がアホかそうでないかも全対的には意識できないというか。
違う階層に属するもの同士が出会い互いを理解しようとするプロセスーこれって結婚では起こりうる。日本で階層(教育レベルぐらいの大雑把なくくりで)の違う者同士が結婚するということが多く起こったのは1970年代なんだそうだ。確かに、国立大学卒のエンジニアが地方から出てきた高卒女子と結婚なんてことは結構よく起こっていた。そして生れた子供がより良い教育を受けることを当然とする前提で育って、より自己選択度の高い人生を歩むことができれば、幸福度の高い状態といえる。そういったことを、日系D青年が語ってくれた。
社会科学のある分野を研究する彼は、貧乏人の子が貧乏という社会のパターンを刷り込みの一種で、教育の重要さにある一定数の人口が気付けば通念を覆すことも可能と語る。「随分前向きなんですね。やっぱり現実は暗かったですなんてよくある終わり方はしないんですね。」とワタス。
「暗いなら、なぜ暗いか、どういう風に暗いか、どうすれば明るくなって良くなるかという考え方をしないと論文は書けませんよ。だって、そのままじゃ何も変わらないでしょう?社会が良くならないじゃないですか。」
本当の学問は前向きで社会貢献を前提とするものなのだ。
博士課程後期では多くの人がそういう発想をする傾向が顕著にある。
で、そういう発想をする集団が実際にあるという事実は、かなり気持ちを明るくしてくれるものなのだ。