最近とみに聞く言葉に「アンチ・エイジング」(anti-ageing)というものがある。
anti(アンチ)は「反」「反対」の意味の接頭語で、ageing(エイジング)は「加齢」「老化」か?とするとこの言葉は「老化・加齢に反対する」もしくは「老化・加齢に抵抗する」ということ?
念のために、この言葉でネット検索してみたら、あるはあるは・・・その一つを紹介すると
『「時計の針を止めること」ではなく、「針を少し戻して、その進みを遅らせること」なのです。時計の場合、針自体に指をかけて逆戻りさせたり、裏のネジ部分を操作して、針の進みを遅らせることが出来ます。それと同様の取り組みが、私たちが考える「アンチエイジング」です。例えば、肌の若返りは、スキンケアや医学的治療により、外部から皮膚そのものをケアすることであり、「針自体を逆戻りさせる」ことに当たります。また、サプリメントやホルモン補充療法などの、内部から全身的に若返りを図る方法、つまり全身的な老化防止策が、「針の進みを遅らせる」方法として最近脚光を浴びてきました。」』
もともとアンチは、その後に「嫌なもの」「悪いもの」を置き、それに対してアンチ・反対や抵抗するという場合に使われる言葉。たとえば「アンチ巨人」とか・・・。
で、このアンチエイジングの場合は「老化」「加齢」を、「悪いもの」「嫌いなもの」とし、私たちが年齢を重ねることを嫌なこと悪いこととし、そこから逃げだそう。嫌そこまではいわなくても「少しでも若く見られよう」(陰の声『無駄な抵抗です』)という魂胆が丸見えで、何かしら現代人の即物的・短絡的・快楽追求的物の考え方を代表するような言葉と見える。(考えすぎで、穿ちすぎか?)
「上は大聖世尊より、下は悪逆の堤婆に至るまで、逃れがたきは無常なり」であって「老い」は喜ばしいことではないにしても、最近頓に「老い」を実感している身にしてみれば、抵抗しようにもどうにもならないもの。
おそらくアンチエイジングなるものを提唱している方々には「老熟」「長老」「郷老」「老練」等ということは、ヘソが茶を沸かすほどに笑えるほど馬鹿馬鹿しく有り得ないことなのだろう。ましてや
「年々に 我が悲しみは深くして いよよ華やぐ 命なりけり」(岡本かな子)
の心境など、わかって欲しいけど、わからないだろうなあ・・・。
このような感覚で生きている人々が増えたこの時代で、どう仏教を伝えるか?
気が重くなるほどの道のりであるが、岐阜の畏友S師がいつも言っているように「ご法義の直球勝負」しかないのだろう。
anti(アンチ)は「反」「反対」の意味の接頭語で、ageing(エイジング)は「加齢」「老化」か?とするとこの言葉は「老化・加齢に反対する」もしくは「老化・加齢に抵抗する」ということ?
念のために、この言葉でネット検索してみたら、あるはあるは・・・その一つを紹介すると
『「時計の針を止めること」ではなく、「針を少し戻して、その進みを遅らせること」なのです。時計の場合、針自体に指をかけて逆戻りさせたり、裏のネジ部分を操作して、針の進みを遅らせることが出来ます。それと同様の取り組みが、私たちが考える「アンチエイジング」です。例えば、肌の若返りは、スキンケアや医学的治療により、外部から皮膚そのものをケアすることであり、「針自体を逆戻りさせる」ことに当たります。また、サプリメントやホルモン補充療法などの、内部から全身的に若返りを図る方法、つまり全身的な老化防止策が、「針の進みを遅らせる」方法として最近脚光を浴びてきました。」』
もともとアンチは、その後に「嫌なもの」「悪いもの」を置き、それに対してアンチ・反対や抵抗するという場合に使われる言葉。たとえば「アンチ巨人」とか・・・。
で、このアンチエイジングの場合は「老化」「加齢」を、「悪いもの」「嫌いなもの」とし、私たちが年齢を重ねることを嫌なこと悪いこととし、そこから逃げだそう。嫌そこまではいわなくても「少しでも若く見られよう」(陰の声『無駄な抵抗です』)という魂胆が丸見えで、何かしら現代人の即物的・短絡的・快楽追求的物の考え方を代表するような言葉と見える。(考えすぎで、穿ちすぎか?)
「上は大聖世尊より、下は悪逆の堤婆に至るまで、逃れがたきは無常なり」であって「老い」は喜ばしいことではないにしても、最近頓に「老い」を実感している身にしてみれば、抵抗しようにもどうにもならないもの。
おそらくアンチエイジングなるものを提唱している方々には「老熟」「長老」「郷老」「老練」等ということは、ヘソが茶を沸かすほどに笑えるほど馬鹿馬鹿しく有り得ないことなのだろう。ましてや
「年々に 我が悲しみは深くして いよよ華やぐ 命なりけり」(岡本かな子)
の心境など、わかって欲しいけど、わからないだろうなあ・・・。
このような感覚で生きている人々が増えたこの時代で、どう仏教を伝えるか?
気が重くなるほどの道のりであるが、岐阜の畏友S師がいつも言っているように「ご法義の直球勝負」しかないのだろう。










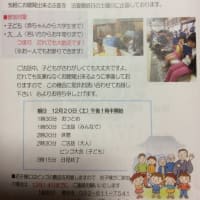









6月と10月。直球楽しみにお待ちしております。