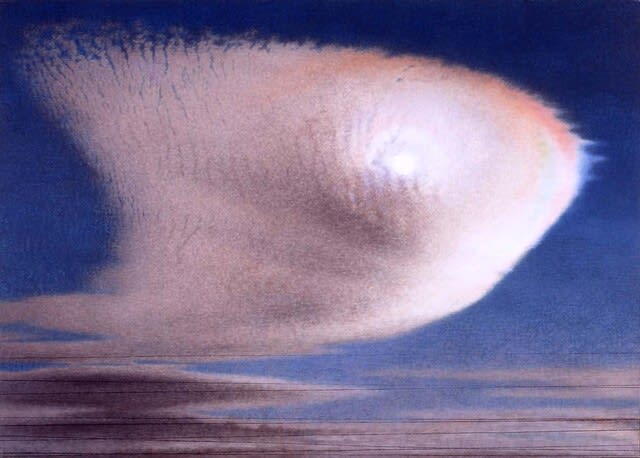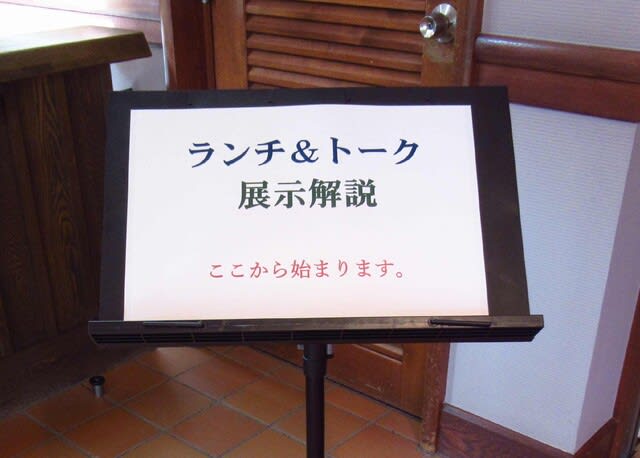8月2日(土)「第2回 芸術館夏まつり」を開催しました。
去年大好評だった芸術館夏まつり。今年も「くしろ港まつり」の賑わいに、当館も参加しました!
この日はどなた様も展覧会の観覧料100円引きの特別料金で観覧できるお得な1日としました。
また、展覧会を観覧していただいたお客様に、過去の展覧会図録をなんとワンコイン100円の格安販売!
お宝ゲットしたお客さまもいらっしゃったのではないでしょうか!?
今年もスタンプラリーを実施しました。
芸術館をゴールに近隣の2施設(MOO郵便局、国際交流センター)にスタンプと台紙を設置し、3つのスタンプ全てを集めた方に、オリジナル缶バッジをプレゼント!(缶バッジはMOOさん提供と当館のモノ)


当館のボランティア団体SOAの皆さんによるオープンカフェでは冷たいドリンクを1杯100円のワンコインで販売しました。
前庭のオープンガーデンではパラソルを設置したスペースで涼んでいたお客さんも多数!


現在開催中の夏のキッズ・アトリエ「夏まつりスペシャル」では、アトリエ内での特別アニメ上映に加えてテラスを開放し、館内外にカプラで遊べるスペースも設置しました。
蒸し暑い外から涼を求めてきてくれた子供さんたちも工作に夢中になっていましたよ♪
テラスでは当館のマスコットキャラクターももちゃんの顔出しパネルを用意しました。開催中の展覧会にちなみ、さんまとももちゃんの手持ちパネルもご用意。
(画像は見本を実演してくれたSOAさんと当館のアテンダントスタッフTさんです。みんなよい笑顔♪)
ほかにもももちゃんと写真を撮れるスポットを設置しました。SNS映えにピッタリです!


夏のキッズ・アトリエは8月24日(日)まで開催しています。道具や材料を用意していますので、工作好きの子供たちは芸術館へぜひお越しください。
そして!!
行列ができたほどの大人気だった「さかなつりゲーム」
わかくさ保育園の園児さんたちが描いてくれたかわいいおさかな(の絵)を釣るゲーム。
「つり名人」には記念品をプレゼント!
大人も子供もみんな「つり名人」を目指して楽しく熱中!
ず~~っとにぎわっていました♪♪


夏まつりの締めはパフォーミング・シアター。ヒートボイス前庭ライブ!
曇天から霧、そして小雨へと変化する天気でしたが、ヒートボイスのお二人の熱唱に会場は大盛り上がり!
ヒートボイスさん。ありがとうございました。

最後の最後に雨が降り出した芸術館夏まつり。無事終了することができました。
改めて、来館してくださったお客様。協力してくださった近隣施設の方々。SOAの皆さんに感謝申し上げます。
次は9月13日(土)のくしろ大漁どんぱくで「芸術館秋まつり」です。
パフォーミング・シアターは「ザ・プロジェクト前庭ライブ」を開催予定です。
皆さんに楽しんでいただけるように只今、絶賛準備中!ぜひ来てください!!
詳しくは当館のHP、SNSをご覧くださいませ~~。
さて、当館では2011年よりこちらのgooブログを利用していましたが、11月にサービスが終了するとの知らせを受け、hatenaブログへと引越しをしました。
過去の記事ごとhatenaブログへ移動しましたので、新ブログへのブックマークの変更をお願いいたします。
また、過去にいただいた「いいね!」などの反応は引き継げません。今までリアクションいただきありがとうございました。
新ブログを応援いただけますと幸いです。