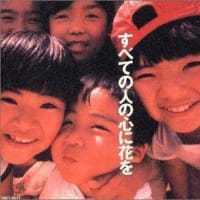戸隠の観光地として有名なのは巨大な杉並木です。
日蔭のおかげさまというものを、目に見える姿で現しているところは、戸隠の真骨頂と言える場所かもしれません。
日を隠して影を成す。
ジメジメして暗いのかといえばそうではなく、明るさというものをむしろ日なたに居る時よりも強く感じる場所でした。
「戸」というのを天岩戸の意味で捉えると、神話では洞窟にこもった天照大御神の光を隠すものとされます。
この場合「戸隠」とは「日隠し」、すなわち「日蔭」と同じものとなります。
あらためて戸隠の杉並木を観てみますと、日蔭とはかがやきそのものであることを感じられるのではないかと思います。

「物陰」(ものかげ)と聞きますと私たちは暗く狭いところをイメージしてしまいますが、実際にそちら側に身や心を置くと、
そこにはとても大きな世界が広がっているのを感じられるわけです。
杉並木に広がる世界というのはこの世の一端を現しています。
つまり、現実のあらゆる物事も、その陰には広大無辺な広がりがあることを示唆しています。
戸隠の杉並木の中に居ると、まるでミクロの決死圏です。
それはまた、日なたの世界の縮尺と、日蔭の縮尺が全く違うことを暗示するものでもあります。
見た目の世界と、目に見えない世界とは、そもそものスケールが根本的に違うということです。
見える世界を氷山の一角と表現したりしますが、そんな程度の比率ではなく、私たちの想像を遥かに超えた気の遠くなるほどの
広がりが水面下には存在しているわけです。
ふと立ち止まり、身のまわりを一つ二つ見渡しただけでもそれは明らかです。
たとえば、私たちの肉体がこの世に存在するのも、その水面下には何十億人、何千億人ものご先祖様がいらっしゃいます。
その途轍もないピラミッドの頂上のわずか1点だけが今こうして目に見えているということです。
あるいは、目の前に存在する様々な物であっても、その背後、見えない蔭には幾千万もの材料や工程がネズミ算式に広がって
います。
はたまた、目の前で起きた些細な出来事にしても、網の目に広がる無数のご縁の、たった一つの結晶であるのです。
もちろん、そうしたことをいちいち振り返っていては目の前がおろそかになってしまいますので、日頃そこまでする必要はない
でしょう。
ただ、目に見えないおかげさまが山ほどある、万事そういうものであるのだと承知しておくことが極めて大事ということになります。
目には見えない、日蔭の世界の存在によって、日なたの世界が確実なものとなっています。
一つ一つの現実とは、無限に詰まり詰まった非現実がついに飽和しきった末の、結晶のカケラであるわけです。
見えないようにさせといたというのも一つの神意です。
ジロジロとガン見して歩くのではなく、そのような御心があると知っておくだけでいい。
私たちの足もとに広く深く、たとえ見えなくともそこに無限のおかげさまが広がっていると承知しておく。
それだけで、黙っていても私たちの心はその先々にまで広がり開いていくわけです。
この日本において、戸隠は「日蔭のおかげさま」であったわけですが、それはその先に訪れた土地にも広がっていました。
今回の旅は、半分は真面目な目的でしたが、残り半分は気晴らしのバカンスのつもりでいました。
初日のお参りが終われば、2日目は森の中、水辺の高原で1日ゆったりとブルジョワチックに涼もうと考えていました。
翌朝、そうした場所を探す前に、まずは気になっていた池だけ行っておこうと軽い気持ちで出かけたのでしたが、そのフラッと
立ち寄った場所にいきなり願望以上のものがポーンと現れてしまいました。
喩えるなら、まだ寝ぼけたまま顔を洗いに行ったら、そこに豪華メインディッシュが用意されてたような唐突感でした。
心の準備もないまま、バーンと出されてしまったものですから心がまったく追いつかなかったのですが、やはり肉体というのは
凄いものです。
皮膚から入ってくる感覚は頭や心を即座にねじ伏せ、急速充電のごとく満たされていったのでした。
身体の感覚にすべてを任せてしまいますと、頭も心も天地へと溶け出していきます。
そうして時間も忘れて景色と一体となっていると、その景色とともに自他の区別など消えてなくなっていきます。
そのままブルジョワチックに1日お茶しているのも良かったのですが、そうやって全身で満喫しきってしまうと、来る前の空腹感も
すっかり満たされまして、さて何か他のことをやろうかという気持ちになるのでした。
今一度、旅の前に気になっていたところを思い返すと、諏訪大社が浮かんできました。
ただ土日2日で戸隠に行って諏訪も行くとなるとこれは結構な強行軍になります。
弾丸ツアーのように時間に追われて駆け回るのでは意味ありませんので、諏訪はカットして旅に臨んだのでしたが、時刻表を見ると
それが行けなくも無い状況になっていました。
実は諏訪大社そのものはこれまで行ったことがありませんでした。
諏訪周辺には過去に何度か訪れたことがありましたが、正直なところ空気感としてはピンと来るものが無い場所でした。
正直ついでに言ってしまうと、今回も地鎮の意味合いとして行かないといけないかなという、まさしく人間考え100%でしたので、
今にして思えばこれほど失礼な話も無いものです。
さて、在来線の鈍行の長旅を終えて駅を降りましたが、車を走らせていてもやはり空気感は変わることもなく、すんなり大社に
到着しました。
昔のイメージのままでしたので、ある意味、構えることもなく自然体のまま敷地内へと入って行けたと言えます。
すると、そこにはまさに1週間前に神事が終わったばかりの御柱が天高く祀られていました。
不思議なことにこの御柱自体から発するものは特に何も感じられなかったのですが、しかしそこから進んだ先の境内の空気感が
半端ないものでした。
なんと表現すればいいのか、本当に言葉すら浮かばない。
頭も心も真っ白。
言葉にならない言葉。
茫然自失。立ち尽くすのみ。
超然というか「凄い」という思い、感覚、全身それ一色です。
そして、それとともに心の奥底からねじ上がる「ありがたい」という思い。
でも、何がありがたいのか理屈としては分からない。
とにかく、細胞の奥深くから全身がそのように感じてしまっている。
まさか、こんな場所が諏訪にあるとは思いもしませんでした。
大地的といえば大地的ですし、宇宙的といえば宇宙的。
大地なんだけども宇宙。
それがごく自然に一体となっているのですから、言葉では表現できない。
とにかく湧き上がる思い、ありがたさに震え、涙をこらえるのが大変なのでした。
覚えているのは、深い深い納得感です。
「あぁ…こうして護られてきたのだなぁ」という。
陰(かげ)というものには、いくつもの意味があります。
この世のすべてに共通する、天地の理としての陰。
そして、この国を平安たらしめている陰というのもそうです。
戸隠は前者に当てはまるかと思いますが、諏訪大社というのは後者なのかもしれません。
九州阿蘇から続く中央構造線は、四国、紀伊を通って、ここ諏訪から鹿島へと抜けていきます。
そのエネルギーは、諏訪を転換点として裏表バランスが取られているのではないかと感じました。
阿蘇も鹿島も日なたの表であるのに対して、やじろべえの支点となっているのが諏訪。
エネルギーバランスの裏にあたるわけです。
この地がそのようにあるからこそ、そうあり続けるためにも幾千年もの間ご先祖様たちは御柱という天地垂直方向へのアースを
立て続けてこられたのではないか。
私たち人間こそは天と地とを繋ぐ柱ですが、その私たちが大勢集まり、御柱を引いて大地を練り歩くことで、祓いとともにそこに
凄まじいエネルギーが練り込まれていき、天と地とを繋ぐ依り代となっていきます。
命を落とす人があとを絶たなくとも、氏子の方々は全身全霊でそれを続けてこられました。
出雲を追われてこの地に引きこもったなどトンデモない嘘っぱちでしょう。
実際は、この地、この国を蔭から護るために命懸けの祭祀を行なってきたということではないでしょうか。
しかし、蔭はあくまで蔭でなくてはその務めを果たせない。
蔭が表に出てしまっては、日なたを支えるという天地の理が根底から崩れてしまう。
だからこそ、あえて日蔭となるような言い伝えを甘んじて受け入れて来たのではないかと思います。
実際、日なたのために頑張ると思った瞬間、そこにはたちまち我心が現れてしまいます。
理屈など関係なく、ただ無心でそれをやるところに神宿るということです。
そうした無我の結晶、天地合一の御柱に囲まれている。
諏訪大社には境内の四方に御柱が立てられていました。
そんなところでは言葉を失ってしまうのも当然のことだと言えるでしょう。
そして諏訪大社というのはこの上社(本宮)の他に三社がありまして、合計四社で成り立っています。
それらの社もそれぞれ御柱4本に囲まれています。
そうして、その四社が諏訪湖を取り囲むように建てられています。
結果は推して知るべしです。
これほどの土地であるのに、そのエリアに普通に立ち寄っただけでは全くそれとは感じさせない空気であることが逆に驚きです。
正直、どの駅で降りても、盆地特有の空気感しかありませんでした。
中央線沿線に住む身としては、他の土地よりも比較的身近な場所で、子供の頃から行くような場所でした。
言葉は悪いですが、あまり風通しが良くない、空気がピタリと止まったような肌感だったわけです。
しかし、それこそは日蔭に対する私個人の感覚、思いの現れだったということです。
何故ならば、そうした日蔭にこそ、これほどの凄まじいものが存在していたからです。
見えない世界にしても、これまで私は「日なた」しか見えていなかったのかもしれません。
伊勢にせよ阿蘇にせよ、熊野にせよ、あるいは出雲にせよ、それらはどれも「日なた」であったわけです。
しかし、日なたというものはそれ単独のものではありません。
必ず、その背後、その足元に途轍もなく広大な日蔭が広がっている、支えているのです。
そうしたことを知り、そうしたものへ心を広げる。
言葉を超越した有り難さ。感謝。
諏訪大社で全身それ一色に包まれた感覚というのは、そういうことだったのではないかと思います。
実際、私たちの身体を振り返ってみましても、頭上や足下の遥かなる遠く、高く深く、見えない先の先まで心を大きく広げることで、
全体は自然に大きく安定していきます。
それは全てのことに通じる根本原理であるわけです。
天地というのはもとより一つのものです。
しかし私たちは、天は天、地は地、と分けて考えてしまいます。
すなわち、日なたと日蔭もそうであるということです。
日なたと日蔭は同じ一つのものであり、裏表ですらない。異質のものではないわけです。
天地の柱たる私たちが、そうした心を持ち、分け隔てなく同じ心を向けることが、天地自然のこの世界の全ての在り方に合致する
ことになります。
量子論的にも明かされているように、私たちの思いというのは、そのままこの世界の現れ方に反映されていきます。
私たちが、心を分けることなく、片寄らせることなく、天地自然の本来の姿の通りに心を向けることで、この世界の精妙なバランス
が現われ、裏表なく等しく輝き溢れかえるのではないでしょうか。
真のバランスというのは互いの力が拮抗して現れるものではありません。
彼我の分け隔てなく、合一することで現れるものです。
それは日なたと日蔭とのことであり、また私たちと天地自然とのことでもあります。
壁がなくなれば、自然に優しい風が吹き抜けていきます。
それは天地が為すものではなく、私たちが為すものなのです。
(おわり)

にほんブログ村
日蔭のおかげさまというものを、目に見える姿で現しているところは、戸隠の真骨頂と言える場所かもしれません。
日を隠して影を成す。
ジメジメして暗いのかといえばそうではなく、明るさというものをむしろ日なたに居る時よりも強く感じる場所でした。
「戸」というのを天岩戸の意味で捉えると、神話では洞窟にこもった天照大御神の光を隠すものとされます。
この場合「戸隠」とは「日隠し」、すなわち「日蔭」と同じものとなります。
あらためて戸隠の杉並木を観てみますと、日蔭とはかがやきそのものであることを感じられるのではないかと思います。

「物陰」(ものかげ)と聞きますと私たちは暗く狭いところをイメージしてしまいますが、実際にそちら側に身や心を置くと、
そこにはとても大きな世界が広がっているのを感じられるわけです。
杉並木に広がる世界というのはこの世の一端を現しています。
つまり、現実のあらゆる物事も、その陰には広大無辺な広がりがあることを示唆しています。
戸隠の杉並木の中に居ると、まるでミクロの決死圏です。
それはまた、日なたの世界の縮尺と、日蔭の縮尺が全く違うことを暗示するものでもあります。
見た目の世界と、目に見えない世界とは、そもそものスケールが根本的に違うということです。
見える世界を氷山の一角と表現したりしますが、そんな程度の比率ではなく、私たちの想像を遥かに超えた気の遠くなるほどの
広がりが水面下には存在しているわけです。
ふと立ち止まり、身のまわりを一つ二つ見渡しただけでもそれは明らかです。
たとえば、私たちの肉体がこの世に存在するのも、その水面下には何十億人、何千億人ものご先祖様がいらっしゃいます。
その途轍もないピラミッドの頂上のわずか1点だけが今こうして目に見えているということです。
あるいは、目の前に存在する様々な物であっても、その背後、見えない蔭には幾千万もの材料や工程がネズミ算式に広がって
います。
はたまた、目の前で起きた些細な出来事にしても、網の目に広がる無数のご縁の、たった一つの結晶であるのです。
もちろん、そうしたことをいちいち振り返っていては目の前がおろそかになってしまいますので、日頃そこまでする必要はない
でしょう。
ただ、目に見えないおかげさまが山ほどある、万事そういうものであるのだと承知しておくことが極めて大事ということになります。
目には見えない、日蔭の世界の存在によって、日なたの世界が確実なものとなっています。
一つ一つの現実とは、無限に詰まり詰まった非現実がついに飽和しきった末の、結晶のカケラであるわけです。
見えないようにさせといたというのも一つの神意です。
ジロジロとガン見して歩くのではなく、そのような御心があると知っておくだけでいい。
私たちの足もとに広く深く、たとえ見えなくともそこに無限のおかげさまが広がっていると承知しておく。
それだけで、黙っていても私たちの心はその先々にまで広がり開いていくわけです。
この日本において、戸隠は「日蔭のおかげさま」であったわけですが、それはその先に訪れた土地にも広がっていました。
今回の旅は、半分は真面目な目的でしたが、残り半分は気晴らしのバカンスのつもりでいました。
初日のお参りが終われば、2日目は森の中、水辺の高原で1日ゆったりとブルジョワチックに涼もうと考えていました。
翌朝、そうした場所を探す前に、まずは気になっていた池だけ行っておこうと軽い気持ちで出かけたのでしたが、そのフラッと
立ち寄った場所にいきなり願望以上のものがポーンと現れてしまいました。
喩えるなら、まだ寝ぼけたまま顔を洗いに行ったら、そこに豪華メインディッシュが用意されてたような唐突感でした。
心の準備もないまま、バーンと出されてしまったものですから心がまったく追いつかなかったのですが、やはり肉体というのは
凄いものです。
皮膚から入ってくる感覚は頭や心を即座にねじ伏せ、急速充電のごとく満たされていったのでした。
身体の感覚にすべてを任せてしまいますと、頭も心も天地へと溶け出していきます。
そうして時間も忘れて景色と一体となっていると、その景色とともに自他の区別など消えてなくなっていきます。
そのままブルジョワチックに1日お茶しているのも良かったのですが、そうやって全身で満喫しきってしまうと、来る前の空腹感も
すっかり満たされまして、さて何か他のことをやろうかという気持ちになるのでした。
今一度、旅の前に気になっていたところを思い返すと、諏訪大社が浮かんできました。
ただ土日2日で戸隠に行って諏訪も行くとなるとこれは結構な強行軍になります。
弾丸ツアーのように時間に追われて駆け回るのでは意味ありませんので、諏訪はカットして旅に臨んだのでしたが、時刻表を見ると
それが行けなくも無い状況になっていました。
実は諏訪大社そのものはこれまで行ったことがありませんでした。
諏訪周辺には過去に何度か訪れたことがありましたが、正直なところ空気感としてはピンと来るものが無い場所でした。
正直ついでに言ってしまうと、今回も地鎮の意味合いとして行かないといけないかなという、まさしく人間考え100%でしたので、
今にして思えばこれほど失礼な話も無いものです。
さて、在来線の鈍行の長旅を終えて駅を降りましたが、車を走らせていてもやはり空気感は変わることもなく、すんなり大社に
到着しました。
昔のイメージのままでしたので、ある意味、構えることもなく自然体のまま敷地内へと入って行けたと言えます。
すると、そこにはまさに1週間前に神事が終わったばかりの御柱が天高く祀られていました。
不思議なことにこの御柱自体から発するものは特に何も感じられなかったのですが、しかしそこから進んだ先の境内の空気感が
半端ないものでした。
なんと表現すればいいのか、本当に言葉すら浮かばない。
頭も心も真っ白。
言葉にならない言葉。
茫然自失。立ち尽くすのみ。
超然というか「凄い」という思い、感覚、全身それ一色です。
そして、それとともに心の奥底からねじ上がる「ありがたい」という思い。
でも、何がありがたいのか理屈としては分からない。
とにかく、細胞の奥深くから全身がそのように感じてしまっている。
まさか、こんな場所が諏訪にあるとは思いもしませんでした。
大地的といえば大地的ですし、宇宙的といえば宇宙的。
大地なんだけども宇宙。
それがごく自然に一体となっているのですから、言葉では表現できない。
とにかく湧き上がる思い、ありがたさに震え、涙をこらえるのが大変なのでした。
覚えているのは、深い深い納得感です。
「あぁ…こうして護られてきたのだなぁ」という。
陰(かげ)というものには、いくつもの意味があります。
この世のすべてに共通する、天地の理としての陰。
そして、この国を平安たらしめている陰というのもそうです。
戸隠は前者に当てはまるかと思いますが、諏訪大社というのは後者なのかもしれません。
九州阿蘇から続く中央構造線は、四国、紀伊を通って、ここ諏訪から鹿島へと抜けていきます。
そのエネルギーは、諏訪を転換点として裏表バランスが取られているのではないかと感じました。
阿蘇も鹿島も日なたの表であるのに対して、やじろべえの支点となっているのが諏訪。
エネルギーバランスの裏にあたるわけです。
この地がそのようにあるからこそ、そうあり続けるためにも幾千年もの間ご先祖様たちは御柱という天地垂直方向へのアースを
立て続けてこられたのではないか。
私たち人間こそは天と地とを繋ぐ柱ですが、その私たちが大勢集まり、御柱を引いて大地を練り歩くことで、祓いとともにそこに
凄まじいエネルギーが練り込まれていき、天と地とを繋ぐ依り代となっていきます。
命を落とす人があとを絶たなくとも、氏子の方々は全身全霊でそれを続けてこられました。
出雲を追われてこの地に引きこもったなどトンデモない嘘っぱちでしょう。
実際は、この地、この国を蔭から護るために命懸けの祭祀を行なってきたということではないでしょうか。
しかし、蔭はあくまで蔭でなくてはその務めを果たせない。
蔭が表に出てしまっては、日なたを支えるという天地の理が根底から崩れてしまう。
だからこそ、あえて日蔭となるような言い伝えを甘んじて受け入れて来たのではないかと思います。
実際、日なたのために頑張ると思った瞬間、そこにはたちまち我心が現れてしまいます。
理屈など関係なく、ただ無心でそれをやるところに神宿るということです。
そうした無我の結晶、天地合一の御柱に囲まれている。
諏訪大社には境内の四方に御柱が立てられていました。
そんなところでは言葉を失ってしまうのも当然のことだと言えるでしょう。
そして諏訪大社というのはこの上社(本宮)の他に三社がありまして、合計四社で成り立っています。
それらの社もそれぞれ御柱4本に囲まれています。
そうして、その四社が諏訪湖を取り囲むように建てられています。
結果は推して知るべしです。
これほどの土地であるのに、そのエリアに普通に立ち寄っただけでは全くそれとは感じさせない空気であることが逆に驚きです。
正直、どの駅で降りても、盆地特有の空気感しかありませんでした。
中央線沿線に住む身としては、他の土地よりも比較的身近な場所で、子供の頃から行くような場所でした。
言葉は悪いですが、あまり風通しが良くない、空気がピタリと止まったような肌感だったわけです。
しかし、それこそは日蔭に対する私個人の感覚、思いの現れだったということです。
何故ならば、そうした日蔭にこそ、これほどの凄まじいものが存在していたからです。
見えない世界にしても、これまで私は「日なた」しか見えていなかったのかもしれません。
伊勢にせよ阿蘇にせよ、熊野にせよ、あるいは出雲にせよ、それらはどれも「日なた」であったわけです。
しかし、日なたというものはそれ単独のものではありません。
必ず、その背後、その足元に途轍もなく広大な日蔭が広がっている、支えているのです。
そうしたことを知り、そうしたものへ心を広げる。
言葉を超越した有り難さ。感謝。
諏訪大社で全身それ一色に包まれた感覚というのは、そういうことだったのではないかと思います。
実際、私たちの身体を振り返ってみましても、頭上や足下の遥かなる遠く、高く深く、見えない先の先まで心を大きく広げることで、
全体は自然に大きく安定していきます。
それは全てのことに通じる根本原理であるわけです。
天地というのはもとより一つのものです。
しかし私たちは、天は天、地は地、と分けて考えてしまいます。
すなわち、日なたと日蔭もそうであるということです。
日なたと日蔭は同じ一つのものであり、裏表ですらない。異質のものではないわけです。
天地の柱たる私たちが、そうした心を持ち、分け隔てなく同じ心を向けることが、天地自然のこの世界の全ての在り方に合致する
ことになります。
量子論的にも明かされているように、私たちの思いというのは、そのままこの世界の現れ方に反映されていきます。
私たちが、心を分けることなく、片寄らせることなく、天地自然の本来の姿の通りに心を向けることで、この世界の精妙なバランス
が現われ、裏表なく等しく輝き溢れかえるのではないでしょうか。
真のバランスというのは互いの力が拮抗して現れるものではありません。
彼我の分け隔てなく、合一することで現れるものです。
それは日なたと日蔭とのことであり、また私たちと天地自然とのことでもあります。
壁がなくなれば、自然に優しい風が吹き抜けていきます。
それは天地が為すものではなく、私たちが為すものなのです。
(おわり)
にほんブログ村