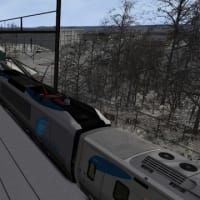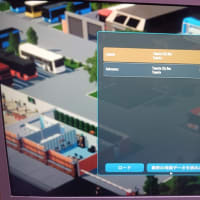市電保存館では今年1月末のリニューアルオープン以来、しでんホール連続講座として月1~2回程度の講演会を開催しています。横浜市電に限らず横浜の都市発展や過去には「ハマっ子」をテーマとした講座も開催されたようで・・・。
今回は第7回として市電OBの方々を講師として当時の思い出話を語ってもらう。という回となりました。
ちなみに私が参加するのは初めて。過去の講演で興味ある会もあったのですが、私のところから市電保存館は結構遠いもので・・せめて「みなとぶらりチケット」で市電保存館に行ければ交通費的にありがたいのですが・・

写真正面の建物が昨年2016年8月に新築された講演・イベント用のしでんホール。右の団地の1階が市電保存館本館。本館入口の受付で入場券を買ってからホールの方で受付をする形です。
なお講座参加料金は入館料のみで特別な代金は必要ありません。
お手洗いはホールの方にもあるようですが保存館本館の方で済ませておいた方が無難そうです。
今回の講師の方は、斉藤章三先生(市電運転手から廃止後は地下鉄駅員など)、河島弘先生(市電車掌から運転手?)、相原正行先生(車掌のちに地下鉄運転手)

こちらが講演風景。
空調機器の配置の都合か後ろの方は暑かったです

「集客に苦慮している」という話を聞いていたので予約しないで行ったのですが、今回は約50名ほどと盛況。もう少し多かったら立ち見が出るかも。という状態でした。
以下に当日の講演の内容を箇条書きで紹介しますが、話の流れや前後関係の都合上、実際の講演での順番と違っている部分あるので了承願います。
 まずは講師の紹介に続いて市電運転手の免許の紹介に
まずは講師の紹介に続いて市電運転手の免許の紹介に
斉藤先生の免許証。
交通局は免許を預かる癖?があって在職中は実物を見たことはなく、市電廃止で営業所解散の際に初めてみたとか・・。乗務中の事故の際に警察官から免許証の提示を求められて困ったこともあるそう。
戦後になって免許制度が改定されたそうで、横浜では運輸省の定める基準を満たさないとのことで、東京都交通局(都電)で免許を取得する形になったそう
また相原先生は地下鉄運転手1期生となったが、その際は営団地下鉄で免許を取得したとのこと。
さらに市電廃止時に路面電車が存続した他都市に移籍した乗務員はいない。市の職員という形なので地下鉄や市の他部署に転属したとのこと。
免許そのものは全国で有効(ただ実際の乗務前には一定の研修が必要)なので、当時の冗談話として「夏は北海道・冬は九州辺りで運転手をやれば暑さ寒さに苦労しなくていい」なんていうのもあったとか。
また地下鉄など普通鉄道と市電では市電の方がブレーキのかけ方など運転が難しいといった話も
当時給料は基本給を月に2回、さらに手当を1回支給で給料日は月に3回あったそう。
他の仕事比較して「給料が良い」というほどはなかったような話も
 まず車両面として・・
まず車両面として・・ちんちん電車の名前の由来は、運転手と車掌の連絡用合図ベルとする説とフードゴングと呼ばれる運転席下にあり足踏みで警笛のように使用されていたものの2つがあるそう(一般的には合図ベル説が有力だけど・・)

こちらがフードゴング。これは小学校等での出張説明用に台に固定しているとのことで・・
間接制御車の1500形は決定版。加速・減速がよく振動も少なくと高性能で素晴らしい車両だったよう。
全車が滝頭に集中配置されていたのは他車よりも複雑な構造なので保守の都合ではないか?
1600形は最新鋭にも関わらずワンマン対応されず早々に廃車になったが・・
→ワンマン対応されなかったのは、中扉からの降車客が後部車輪に轢かれるなど接触事故を恐れた。が定説だが、ドア位置が異なることでの乗客の混乱防止。根本的には「車体は新造だが機器流用車でモーターは小型で非力」だった。という複合理由だったのではないか?とのこと。
単車とボギー車どちらが良かったか?に関しては
→横浜は橋が多いため単車だとよく揺れて車掌泣かせだった。一方でボギー車は直角カーブでの自動車との接触事故が多かった。車掌も確認してくれるが・・
 実際の乗務・運転に関して
実際の乗務・運転に関して急加速が多いなど運転が荒い運転手は車掌泣かせであまり組みたくない。一方で運転手・車掌兼務の人は両方の気持ちが分かるのでやりやすい。
運転手と車掌のペアはローテーションで決まっているが実際には似た時刻に出庫する組同士で変えることも多かった。運転が荒い運転手の相方役は若手車掌がよく押し付けられていた。時にはジャンケンをすることも。
相方との相性が悪いと実に悲惨。停留所で折り返す場所は他に乗客がいるからまだしも、三渓園など折返し線で待機する場所では、車内で二人っきりの空間になり実に苦痛だった。
運転が荒い運転手の中には、過電流でブレーカーが落ちないように手で押さえながら、ノッチを一気に入れて加速する人もいた。
名物乗務員としては、例えば横浜駅での乗換え案内で「平塚・熱海方面お乗り換え」のように単に「国鉄線」ではなく遠くを言う車掌。東北方面を言う人もいた。
雪での運休は殆どなかった。
運行ダイヤは停留所には初電終電時刻の掲出程度だったが、乗務員のスタフでは主要電停の時刻まで厳密に決まっていた。ただ自動車の軌道敷内乗り入れ許可後は遅延が酷くなり、一度出庫したらいつ戻れるかわからない状態になった。
後年の車両1500・1600などの着席での運転は立ちでの運転に較べて格好よく感じた。という話も

これは当時のスタフ。この写真は保存館展示車両内のもの
 質疑応答中に変わった質問をした方がいて・・
質疑応答中に変わった質問をした方がいて・・「昭和36年10月頃に馬車道~尾上町間(駅間が短く速度が出ない)で500形の車軸折損事故があったが理由は」
→あったとすれば知ってないといけないはずだが記憶にない
「1300形1323号は運転台のブレーカーの仕様が違ったが理由は?」
→不明。何らかの試験車だった可能性
「1500形は当初5000形と呼ばれていたが・・」
→前回講師の市電研究家八木氏も含め「それはない」と否定
(可能性があるとすれば1200形がデビュー時に2600形だった流れでの計画時の仮称??)
といったところで15時に一旦終了しましたが、聞き足りない・質問があるという人は残って2次会のような形で講師の近くに集まりなおして座って続きを・・・
こちらでは質疑応答を中心に進行
 まずは「乗務員のトイレ問題」
まずは「乗務員のトイレ問題」一度出庫すると交代するまでが長いのでトイレ問題はかなり切実だったそう。どうしても我慢できない時など横浜駅(東口)停車中に交番のトイレに駆け込むが・・・そんな時に限ってお巡りさんが使用中で最悪
 といったエピソードも。
といったエピソードも。(話の感じから折返し点にもあまりトイレがなかったような雰囲気ですね)
またトイレ問題に関連して、バキュームカーとの衝突事故もあって、当時のバキュームカーは木製の箱に下肥を積載していたので悲惨なことになった→消防車の出動を依頼して水で流して処理した。といったエピソードも
また乗務環境として、夏は風の吹き込みがあって天然の冷房のようだが、冬は寒くて当時は車両に暖房もなくとにかく悲惨だったそう。今のバス運転手が冬でもワイシャツ1枚で乗務しているのを見ると信じられないぐらいだとか。
車掌は寒さで手がかじかんで切符がうまく切れないとか、ボーナスが出たらまず防寒着(トレーナーのようなもの?)を買っていたとか・・。
 思い出深い話として、元町から4系統に乗ってきた高齢の女性が「浜松町に行きたい」というので「行きます」と案内し浜松町に到着して教えると「ここじゃない」と・・。よく聞くと東京の浜松町だと。保土ヶ谷駅で単に降ろすのも可愛そうなので改札口まで連れて行き駅員に引き継ぎたいが、そうこうしているうちに、「1系統」「次の4系統」といった具合に後続車がどんどん来る。
思い出深い話として、元町から4系統に乗ってきた高齢の女性が「浜松町に行きたい」というので「行きます」と案内し浜松町に到着して教えると「ここじゃない」と・・。よく聞くと東京の浜松町だと。保土ヶ谷駅で単に降ろすのも可愛そうなので改札口まで連れて行き駅員に引き継ぎたいが、そうこうしているうちに、「1系統」「次の4系統」といった具合に後続車がどんどん来る。保土ヶ谷橋に帰る途中だという若い女性客が、駅までの案内して駅員への引き継ぎを買って出てくれた。あの時ほどお客さんに感謝したことはない。といった出来事。
今にして思えば、元町から東京の浜松町なら根岸線開業後だったから石川町から京浜東北線に乗ればよかったのに・・
考えてみると「浜松町」のみならず、横浜には他都市と同じ地名が多い。電停名になはなっていないが「軽井沢」「池袋」「青砥」などなど・・・
 他には名物運転手の話も
他には名物運転手の話も後にベイスターズ(現在の名称)に入団した?イケスギ運転手は、生麦営業所所属で人身・衝突・脱線などあらゆる事故を起こしたことで当時局内でも有名。交通局の事故処理の緊急自動車が走っているのを見ると「またイケスギか!?」と噂になるぐらい。
運転も荒く車掌の間では一緒に組みたくない運転手ナンバーワンクラスでよく車掌同士でジャンケンをしていたとか。(本人は「そんなに俺と一緒に組みたいのか?」と思っていたとか・・)
深夜1時30分過ぎまで野球選手たちと飲んで翌朝初電時間の乗務につくこともあって眠くないわけがない。冬でもサングラスをかけていたのは眠い目を隠すためでは?といった時代を感じる話なども・・
このイケスギ運転手の話は色々思い出があるようで盛り上がっていたような

 「はまれぽ」の記者氏からは、市電の塗装が末期の黄色ベース(市バスに類似)になったのは昭和30年代だが市バスの塗装は昭和3年からのもの。「市電の塗装を市バスに合わせた」という明確なソースが知りたい。といった趣旨の質問がありましたが、これは不明。
「はまれぽ」の記者氏からは、市電の塗装が末期の黄色ベース(市バスに類似)になったのは昭和30年代だが市バスの塗装は昭和3年からのもの。「市電の塗装を市バスに合わせた」という明確なソースが知りたい。といった趣旨の質問がありましたが、これは不明。 私は最後に、「横浜市電は晩年まで単車が多かったがその理由」「混雑路線には大型車、閑散路線は単車のような使い分けはあったのか??」「京急と並走する生麦線は実際どの程度の利用だったのか?」を質問
私は最後に、「横浜市電は晩年まで単車が多かったがその理由」「混雑路線には大型車、閑散路線は単車のような使い分けはあったのか??」「京急と並走する生麦線は実際どの程度の利用だったのか?」を質問→9系統の浅間下に急カーブがありボギー車の入線は出来なかった。3系統の山元町は外人墓地などの観光客もありドル箱路線で乗客が多かった。大型車中心の運用で補充で中型車などを運用していた。混雑時はホームに係員を出して集改札していたほど
→生麦線は戦時中の軍需工場の行員輸送で賑わい、生麦でのバス乗り換えがパンクしていたので鶴見線を急遽敷設。生麦線自体も戦後は利用客数も振るわず、早々に廃止になったのも納得。だそう
鶴見線に関しては、戦時中に軍隊を動員して急遽敷設するも戦後すぐにGTQの命令で一夜にしてアスファルトで埋設し運行終了。言及されることも少なく、自分(講師の先生)も勤務当時に生麦営業所の助役から思い出話として聞いて知ったぐらい。

参加者氏が持参した横浜市電各形式のHOゲージ模型
都市発展記念館で横浜市電の方向幕や側面系統板を模したマスキングテープを売っているが、都市発展記念館オリジナルで、現状市電保存館では販売できないのは残念といった話も・・
といったところで、今回の講座は終了となったわけですが、横浜市電に限りませんが鉄道の過去の出来事・事象は車両面では諸元表・概要などが書物によくまとめられるなど記録に残りやすいですが、それ以外の運転・運用面、また思い出話のように公式記録になりづらいものは、残念ながらなかなか知る機会もないうちに歴史の闇に消えていきがちです。
そういった中で当時のOBの貴重な話を聞けた今回の講演は、横浜市電の当時の実際の状況を知るうえでとても有意義なものであったと思います。
横浜市電の1500形はPCCカーとも呼ばれ(実際はPCCではなく準PCCカーと呼んだ方が適切)横浜市電の決定版と紹介されますが、今回の講演での性能の良さに触れられやはり当時から一目置かれる存在だったようですね。一方で特徴あるスタイルで最後の新型車1600形は見た目はともかく実際は・・とやはり不遇さを感じます。
この記事では車両形式では「形」と表記しましたが、講演中講師の先生方は「1500代はなんとか~~」のように一貫して「だい」(恐らく「代」)と表現していました。
鉄道趣味界では「形系論争」などもありますが、少なくても当時の現場では「代?」が一般的に使われていたのではないか?ということで、特筆すべき点かと思います。
なお一部内容が聞き取りづらい部分、前後関係がわかりづらい部分もあったので、記載内容に多少の誤りがある可能性もあります。ご了承願いいます。
【PR】楽天市場で「横浜市電」を検索
2017/6/26 00:30(JST)