
母屋の奥の部屋にも、雛人形が、部屋いっぱいに飾ってありました。
雛人形の歴史は古く、平安時代の貴族の子供たちの人形遊びに由来するといわれています。
江戸時代の初めまでは、紙の雛を雛びょうぶの前に2~3対、それに白酒や菱餅を供えるという簡素な祭りでした。
中期になると、雛壇に段を設け、内裏雛や調度類などを飾るようになっていきます。
内裏雛の男雛と女雛の位置は、向かって右が男雛、左が女雛でしたが、大正期から今日のように男雛が左、女雛が右側という飾り方になります。
雛人形の歴史は古く、平安時代の貴族の子供たちの人形遊びに由来するといわれています。
江戸時代の初めまでは、紙の雛を雛びょうぶの前に2~3対、それに白酒や菱餅を供えるという簡素な祭りでした。
中期になると、雛壇に段を設け、内裏雛や調度類などを飾るようになっていきます。
内裏雛の男雛と女雛の位置は、向かって右が男雛、左が女雛でしたが、大正期から今日のように男雛が左、女雛が右側という飾り方になります。

















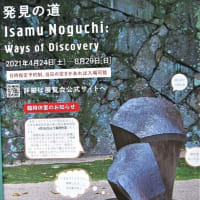
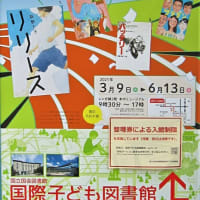

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます