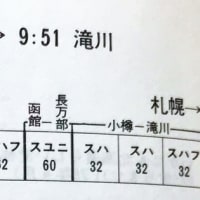まず、近代のフレンチフルートの歴史のおさらいから。
1847年に一定の完成をみた、テオバルト・ベームによる、いわゆるベーム式フルートは、音響について、最も合理的に改良されたシステムであった。
音孔を大きく、完全排気型のキーメカニズムとし、形状はコニカルボア(円錐形)から円筒形へ、材質は木製のみならず銀製へと、近代のフルートの基本を確立する革命といえた。
しかし、この画期的なシステムは、当地のドイツでは保守的な教授陣や奏者に受け容れられず、なかなか普及しなかった。
音孔を大きく、完全排気型のキーメカニズムとし、形状はコニカルボア(円錐形)から円筒形へ、材質は木製のみならず銀製へと、近代のフルートの基本を確立する革命といえた。
しかし、この画期的なシステムは、当地のドイツでは保守的な教授陣や奏者に受け容れられず、なかなか普及しなかった。
むしろ、開花したのは、印象派の時代を迎えるフランスにおいてゞあった。色彩感のある華やかな音が好まれ、この新しいシステムと銀製のフルートは覿面であったのかもしれない。
そこで、パリの工房で次々とベーム式の新しいフルートが製作されるようになる。最初に製作のライセンスを取得したのはGodfroyの工房で、同時期にイギリスのRudall & Carteも得ている。
Godfroyと協業していたLouis Esprit Lotは、1855年に独立し工房を開く。Godfroyの工房で仕上げを担当していたであろうBonnevilleも、独立した。
また、1888年には、Louis Lotから、Louis Leon Joseph Lebretが独立している。
ほか、モイーズ先生の独特の楽器を製作したCouesnonなど、よく知られた工房がパリに揃い、さらにそれらから派生して多くの工房があった。フルートの専門の工房もあれば、他の木管楽器の工房が兼業で製作していた例も窺える。現在はクラリネットの代表的なメーカであるBuffet Cramponも、優れたフルートを製作していた。
近代のフレンチフルートの魅力とされるのは、金属とくに銀素材の板を巻いて管を作る、巻管工法によるところが第一であろう。これは、当時は圧延式のパイプを作る技術がなかったからでもある。心棒に巻きつけて、木槌で叩き鍛えながら整形し、継ぎ目をロー付けすることでパイプとするが、これによって、密度の濃い美しい倍音が醸し出されてくる。
そこで、パリの工房で次々とベーム式の新しいフルートが製作されるようになる。最初に製作のライセンスを取得したのはGodfroyの工房で、同時期にイギリスのRudall & Carteも得ている。
Godfroyと協業していたLouis Esprit Lotは、1855年に独立し工房を開く。Godfroyの工房で仕上げを担当していたであろうBonnevilleも、独立した。
また、1888年には、Louis Lotから、Louis Leon Joseph Lebretが独立している。
ほか、モイーズ先生の独特の楽器を製作したCouesnonなど、よく知られた工房がパリに揃い、さらにそれらから派生して多くの工房があった。フルートの専門の工房もあれば、他の木管楽器の工房が兼業で製作していた例も窺える。現在はクラリネットの代表的なメーカであるBuffet Cramponも、優れたフルートを製作していた。
近代のフレンチフルートの魅力とされるのは、金属とくに銀素材の板を巻いて管を作る、巻管工法によるところが第一であろう。これは、当時は圧延式のパイプを作る技術がなかったからでもある。心棒に巻きつけて、木槌で叩き鍛えながら整形し、継ぎ目をロー付けすることでパイプとするが、これによって、密度の濃い美しい倍音が醸し出されてくる。
現代の金属の精錬技術と違い、坩堝を何度も使い回すため、ごちゃごちゃとわけのわからない不純物(他の金属分子)が混入しているのも、倍音に効果的にはたらいているか。
また、素材は、銀だけでなく、1819年に開発されたマイショー(maillechort…MailletとChorierの二人の冶金学者の名を合わせてこう呼ぶ)も盛んに使われた。銅、亜鉛、ニッケルの合金で、洋白と訳される。明るく華やかな響きが、フレンチに好まれたのであろう。たいていは銀メッキの施されている。
また、素材は、銀だけでなく、1819年に開発されたマイショー(maillechort…MailletとChorierの二人の冶金学者の名を合わせてこう呼ぶ)も盛んに使われた。銅、亜鉛、ニッケルの合金で、洋白と訳される。明るく華やかな響きが、フレンチに好まれたのであろう。たいていは銀メッキの施されている。

No.1772、Louis Esprit Lotの作、銀製
衆目の一致する代表的な工房は、Louis Lotである。フレンチフルートの代名詞といってもよい。フレンチスクールの歴代の教授や、奏者によって、高い評価を得て、プロから趣味者にまで広く愛用されてきた。
創業から100年近くを経た1952年に他社に吸収されるまで、6代の工場長によって経営され、銘器を生み出してきた。
創業から100年近くを経た1952年に他社に吸収されるまで、6代の工場長によって経営され、銘器を生み出してきた。
(SML社に買収された後も、1974年頃までは技術を継承する職人さんが細々と製作を続けていたらしい。但し、全て手作業による工程が前近代的であると、社内では白眼視されていたよう。音質よりも音量を求めたクーパーカットがもて囃される頃、完全にLouis Lotの銘柄は消えていったか。)
歴代の工場長(在職期間)と、シリアルナンバーとの関係は、およそ次のとおりとされる。1877年から、木製を奇数番、金属製を偶数番に振り分けている。
Louis Esprit Lot (1855~1875年) No. 0~2000
H. D. Villette (1876~1882年) No.2150~3390
Debonneetbeau de Coutelier (1882~1889年) No.3392~4750
M. E. Barat (1889~1904年) No.4752~7350
Ernest Chambille (1904~1922年) No.7352~9210
G. Chambille (1922~1951年) No.9212~10442

No.2687、Villetteの作、コーカスウッド製、円筒形



初代の作に格別のものがあるという声の強い一方、三代目のDebonneetbeauの作が最も充実しているという愛好家も多い。
パイプを作る技術の発展に伴い、およそ6000番を境として、シームレス(圧延式)の管体に移行していく。

以前、所有していたNo.3772、Debonneetbeauの作、銀製、K18金製L&R

No.4155、Baratの作、コーカスウッド製、円錐形
Louis Lot n° 2980 , Par H. D. Villette, directeur d'usine de deuxième génération a 1881.
Dans le passé, je détestais les plaques à lèvres sculptées, mais maintenant, considérez cela comme une bonne idée car cela empêche de glisser.
Dans le passé, je détestais les plaques à lèvres sculptées, mais maintenant, considérez cela comme une bonne idée car cela empêche de glisser.
DONJON - Elégie-Etude - Alexis Kossenko (LCDP #5)
さて、本題はこゝからで、Louis Lotの歴史が六代目のChambilleで終わったといえるのか、という挑戦的な問いかけをしてみたい。
《参考》
ことは、一通の匿名の手紙から始まったという。
奇しくも、2000年5月にJ.P.ランパル先生の亡くなられてから一月後のこと、差出人は、Louis Lotの最後の職人さんとゆかりのある方と自称し、こと細かに製作の秘訣が記されていたという。Louis Lotの継承者として相応しいフルート職人の現れたら、その者に伝授すべし、との旨。時を置かずして、同一差出人から確認のために二通目の手紙の届いたという。
そして、この手紙の受取人、則ち、その時に白羽の矢を立てられたのが、日本の秋山好輝氏であった。
文面によると、やはり、音作りの最たる要は、巻管工法にあるとのこと。
以来、秋山氏は、この手紙をランパル先生の「遺言」と捉えられ、アキヤマフルートのコンセプトの起点となった。
以来、秋山氏は、この手紙をランパル先生の「遺言」と捉えられ、アキヤマフルートのコンセプトの起点となった。
たしかに、差出人と秋山氏とを結びつける仲介人は、ランパル先生と考えるのが最も合理的ではある。
ちなみに、秋山氏が、最後に生前のランパル先生にお会いになったのは、1998年のこと。アキヤマフルート創業の翌年。
その後、故ランパル先生夫人宅で保管されている、世界で最初の、かつLouis Lot現存唯一の金製(K18)の巻管フルート(初代作No.1375、1869年製)をご覧になり、撮影されている。僕も、その写真をキャビネ版で頂戴している。
ちなみに、秋山氏が、最後に生前のランパル先生にお会いになったのは、1998年のこと。アキヤマフルート創業の翌年。
その後、故ランパル先生夫人宅で保管されている、世界で最初の、かつLouis Lot現存唯一の金製(K18)の巻管フルート(初代作No.1375、1869年製)をご覧になり、撮影されている。僕も、その写真をキャビネ版で頂戴している。

掃除棒までK18金製というのに驚く。

尚、ランパル先生がその楽器を入手されたのも偶然のことで、演奏に使用されていたのは、1948年から1958年頃まで。それ以降は、W.S.HaynesのK14金製を使われていた。さすがに、金製のLotは、歴史的価値からお蔵入りとされたよう。
そして、ランパル先生の存命中には間に合わなかったが…ついでながら僕がご相談した頃にはまだ夢物語であったが(笑)、ついに、10年ほど前であったか、Louis Lotを悉く模したK18金製の巻管フルートの製作に成功されている。1869年から、実に約140年を経ての再現であった。
このような試みは、一つに画期的ではある。
今日、ご当地のフランスには、往年の巻管工法の技術を継承するフルートの工房はない。やがて、バリに、Louis Lotの「七代目」といえる継承者が現れ、工房を再興する日を期待したい。それは、国境を問わず、黎明期のヤマハをはじめ、Louis Lotの修理や研究に携わってこられた、日本の製作者たちから、エッセンスや技術を還元していく、さらに、経営を支援していく形でも可能ではないか。
ちょうど印象派の時代、ジャポネスクよろしく、笛好きの文化もフランスと日本とで通じる縁がある。
現代に至っては、ランパル先生も、大の日本好きで、頻繁に来日されては演奏会を開かれ、肥えられてからは和装も粋な旦那ぶりで(笑)、子供たちにフルートの魅力を教えて下さった。その門下から今日のプロの奏者も何人か輩出されている。
ちょうど印象派の時代、ジャポネスクよろしく、笛好きの文化もフランスと日本とで通じる縁がある。
現代に至っては、ランパル先生も、大の日本好きで、頻繁に来日されては演奏会を開かれ、肥えられてからは和装も粋な旦那ぶりで(笑)、子供たちにフルートの魅力を教えて下さった。その門下から今日のプロの奏者も何人か輩出されている。
謂うなれば、半世紀を経て、Louis Lotのフルートのエッセンスと技術は、たまたま、パリから練馬にもたらされ、その再現は、阿波出身の職人によって試みられたということであろう。
しかし、大切なことは、単に昔の製法を再現するだけでなく、その佳さをさらに活かすために、改良すべきは改良に努められていること。
オーケストラ奏者の中にも、愛用される方が出てきた。フレンチフルートの伝統を継承する楽器の製作の試みが、これからも受け継がれ、次代の優れた製作者によって、より確かな楽器として再現され、多くの奏者や愛好家に伝えられていくことを願う。
19世紀と同じくほとんどが手作り。
オーケストラ奏者の中にも、愛用される方が出てきた。フレンチフルートの伝統を継承する楽器の製作の試みが、これからも受け継がれ、次代の優れた製作者によって、より確かな楽器として再現され、多くの奏者や愛好家に伝えられていくことを願う。
19世紀と同じくほとんどが手作り。
現存する世界唯一の手巻き管での楽器作りは、体が資本(笑)。

さて、もう一つの本題。
かくいう僕も、突然の告白ながら、今週から完全なるアキヤマフルート・ユーザーとなった。工房から拙宅への到着は、2月8日(月)。

新(左)旧(右)で刻印の異なる。旧の方が彫りの深く、字体も小綺麗。
顧みると、初めてヴィンテージのフルートを手にした折、そこにスペアで添えられていたのが、秋山氏の製作された木製の頭部管であった。本体は、NHK交響楽団の菅原潤先生から、山野楽器を介して頂戴した、ボストンのBettoneyの木製フルートであった。時に20年前。
もっとも、菅原先生は、W.S.Haynesの名だゝる愛好家でいらっしゃる。
やがて、Louis Lotをはじめ、オールドフレンチ・フルートのメンテナンスは、オリジナルに忠実に、かつ適切な改良を加えられた修理をされる秋山氏に、依頼するようになった。
実に長い間、そのような細々とした修理の依頼ばかりであったのが、近年になって、ようやく、リップヽ゚レートとライザーだけとか、歌口の内側だけとか(笑)、秋山氏に作って戴いたものに。
一昨年の暮れには、僕の提案で、JEUGIA三条本店APEXにて、京都で初めて、本格的にアキヤマフルートの展示試奏会を開催。秋山氏ご夫妻に、二日間、在洛して戴いた。僕も、言い出した手前、ボランティアのスタッフのようにお手伝いして、たいへん有意義な機会をご一緒させて戴いた。
関西フィルハーモニー管弦楽団の首席フルート奏者の沼田陽一先生と知己を得て、なぜか僕が「接客」をさせて戴き、さらに、この元日に急逝されたルカス・ロレンツィ先生と、ご内儀さんの笠原純子先生(ピアニスト)とも、貴重なご縁を戴いた。
それからしかし、頭部管一本を中古で入手するにしても、ネット詐欺に遭遇したり、巻管と紹介されていた製品がシームレスであったりとか、故・ロレンツィ先生からお譲り戴く話も、試奏の結果、見送ったりと、紆余曲折。
昨秋、ようやく、偶然、弦楽器工房の臼井功先生からAg950製の巻管を譲って戴いた。但し、以下の事情により、これは申し訳なくも再び譲渡へ。

かく苦労に苦労を重ねた結果(笑)、この一年をかけて、俄に実現に向け話が進展を始め、現状の予算の範囲で、目をつけていた新古品の胴体が工房に回収されるのを待って、楽器全体をあつらえることに。


頭部管は、秋山氏の強い奨めもあり、自信の最新作。といってもよりLouis Lotの古態に復したタイブ。先週の土曜日に作って戴いたばかり。OFSことOld French Silver(19世紀のフランスの銀食器を溶解して板材に仕立て直した)製の手巻管。リップ・プレートとライザー、さらに反射版は、例によってK18金製。
美音の秘訣は、巻きライザーのハンマー叩き製法とか。やはり、力仕事(笑)。


歌口の形状は、フレンチレクタンギュラという、オーバルとスクエアの中間的なものを模しているか。ライザーは、無論、低い。
ちなみに、クラウン(ヘッド・キャップ)は、外側はLouis Lotの美しいデザインに倣っているが、見えない内側は丸面加工をされていない。マニアとしては(笑)、その方が好みながら、音響のためには感心しないそう。重量が軽くなるからとか。
胴輪(リング)は、巻きリングにして下さった。

胴体は、既製のNo.137。これは本来は、ロンドンのある若手のプロ奏者(Louis Lotユーザー)の発注になる作品とか。やゝあって、この胴体はご帰国なされ、他の日本の奏者に貸し出されていた後に、僕のところへ。「3」と「7」の入るのは、僕のメインの楽器の伝統(笑)。
19世紀のフランスの銀素材の組成を擬したAg944製、手巻管。キーメカニズムなどはAg925製。
バネは、発注者の意向で、SP-1(金とプラチナの合金)としてある。但し、秋山氏は、Louis Lot以来の、先端を細く加工した硬質鋼の針バネを推奨されている。
スケールは、クーパースケールに近いとのこと。英国とあって、W.ベネット先生によって完成されたスケールへの指向の強いか。ゆゑに、些かモダンな性能も加味されており、これもアキヤマフルートのLouis Lotモデルの標準とは少し異なるものゝ、それはそれで貴重とあって、しばらくは使わせて戴く。
Disレバーも、僕の好みのティアドロップとは違う(後日、それに交換)。
製作は、2005年9月の由。



例によって、磨きの仕上げは僕自身の手による。
尚、ありがたいことに、ケースも新調して戴いた。
ほんで、何でやねん(笑)。広報用のチラシの束が同梱されていた。
杉江先生のご訳書及び音符グルーピングよろしく、アキヤマフルートの布教活動にも、引き続き精進しなあかん(笑)。


僕の駄弁はともかく、どうぞ工房のサイトをご覧下さい。
akiyamaflutes 1 French 720
akiyamaflutes 2 French 720
巻き管フルートの饗宴 アキヤマフルートによるアンサンブル
さて、秋山氏の復刻された楽器が、フランスに里帰りする日は、いつのことか。
追記
創業200年を迎えるBuffet Crampon社を出資者として、秋山氏監修の許、パリでLouis Lot工房を復活することを提案したい。
追記。

Louis Lotを超えたLouis Lotとは、言い得て妙。綺麗によう鳴る。妙味。
追記。
秋山師匠に我が儘を申しまして、Disキーを、古式のティアドロップのレバーのものに作り換えて戴きました。
(英国の奏者によって発注されたオリジナルの同キーは保管してあります。)
(英国の奏者によって発注されたオリジナルの同キーは保管してあります。)


追記
ふとした思いつきながら、いっそう、K18金製の音のまろやかさの加味され、Louis Esprit Lot No.1375の音のニュアンスを思わせる。
反射板とクラウンは、同一材質とすると、響きの安定するよう。


追記
JTB大阪第二事業部がスポンサーについているらしい、日本室内楽振興財団(大阪市中央区)が編集・発行をしている『SOU 奏』VOL.56に掲載された、アキヤマ・フルートの記事。♫
非売品で、JTBや駅や車内で頒布してる冊子やろか。