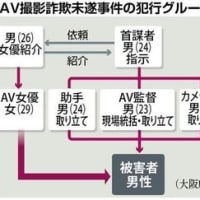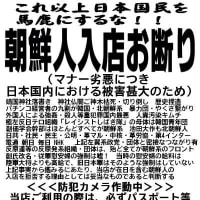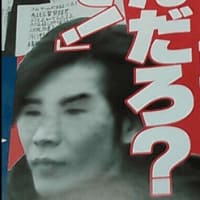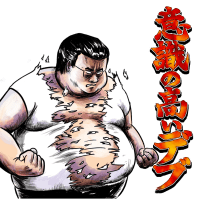2015年(平成27年)の春のお彼岸はいつからいつまででしょうか。お彼岸の期間についておさらいしましょう。
お彼岸は年に2回、春彼岸と秋彼岸がありますが、一体お彼岸とはどのように決められる日なのでしょうか?
お彼岸の由来や意味、お墓参りの文化
彼岸という言葉は、サンスクリット語の「パーラミター」の漢訳「到彼岸」の略だといいます。
元々仏教の用語で、「煩悩に満ちた現世である此岸(しがん)を離れて修行を積むことで煩悩を脱して、悟りの境地に達した世界(彼の岸)に到達する」という意味をもちます。
現代の私たちが普段使っている「お彼岸」という言葉は、修行を経て悟りの世界に達したというよりも、彼岸の期間に寺院で行われる彼岸会と呼ばれる法要や、先祖供養の意味で用いられることのほうが多いです。
「お彼岸にお墓参り」という文化は、仏教徒が多い他の国と比べても日本だけの独特の風習です。
お彼岸の中日である春分の日の意味が「自然をたたえ、生物をいつくしむ」、秋分の日が「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」という意味をもち、昔から先祖崇拝や豊作に感謝してきた日本らしい文化が影響しているのでしょう。
仏教においては、お彼岸の時期に真西へ沈む夕陽の向こう側にある此岸・浄土の先祖を偲び、夕陽に拝み供養する仏事です。
春のお彼岸の日程の決め方は?
秋のお彼岸
お彼岸とは、毎年「春分の日」と「秋分の日」を中日として、前後3日間を合わせた7日間のことをさします。お彼岸に入る日のことを「彼岸入り・彼岸の入り」といい、お彼岸が終わる日のことを「彼岸明け・彼岸の明け」といいます。
お彼岸の中日である春分の日と秋分の日は日付で決まっているわけではないため、お彼岸の時期(彼岸入り・彼岸明け)も確定しているわけではありません。
そもそも「春分・秋分」とは、太陽が春分点・秋分点に達した日のことをいいます。この日は、太陽は天の赤道上にあり、ほぼ真東から出てほぼ真西に沈みます。
そして「春分の日」と「秋分の日」は国立天文台が作成する「暦象年表(れきしょうねんぴょう)」に基いて閣議によって決められます。毎年2月1日付で翌年の該当日が発表されます。国民の祝日であるため、官報にも掲載されます。
※2年後以降の春分の日・秋分の日は天文学で推測することはできますが、確定ではありません。
2015年・2016年のお彼岸はいつから?いつまで?お彼岸期間は?
春のお彼岸(春彼岸)の時期
お彼岸の期間は、春分の日を中日として前後3日間を合わせた7日間です。お彼岸はいつから始まり、いつまでお彼岸なのかチェックしましょう。
年
彼岸入り
中日
春分の日
彼岸明け
2015年
平成27年 3月18日(水) 3月21日(土) 3月24日(火)
2016年
平成28年 3月17日(木) 3月20日(日) 3月23日(水)
秋のお彼岸(秋彼岸)の時期
お彼岸の期間は、秋分の日を中日として前後3日間を合わせた7日間です。いつからお彼岸で、お彼岸はいつまでなのかチェックしましょう。
年
彼岸入り
中日
秋分の日
彼岸明け
2015年
平成27年 9月20日(日) 9月23日(水) 9月26日(土)
2016年
平成28年 9月19日(月) 9月22日(木) 9月25日(日)
春の初彼岸とは?
故人が亡くなってから初めて迎えるお彼岸を「初彼岸(はつひがん)」と呼びます。普段のお彼岸と同じように、彼岸入りには仏壇・仏具を清め、お彼岸の期間は、お花やお供え物を供えましょう。
初彼岸だからといって特別なことはないですが、家族みんなでお墓参りに行って故人や先祖を供養できるといいですね。
秋のお彼岸 お墓参り
彼岸法要や施餓鬼法要もおすすめ
またお彼岸の期間に、お寺では彼岸会・お彼岸法要や施餓鬼法要・施餓鬼供養が行われる場合が多いです。
お墓参りだけでなく、お彼岸法要に参加してお坊さんと共に先祖を供養するお彼岸を過ごしてみるのもいいでしょう。
☆あつさも、さむさも、彼岸までといいますが、すごいあたってます、今日の朝は朝もやまで出て、あたたかいですね。