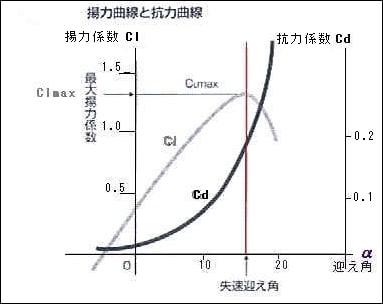私たちが飛行の足場にしている空気・大気について少し整理してみましょう。
“大気”と“空気”という言葉は、一般的にはほとんど同じ意味で使われていて明確な区別はなされてないようですが、およそ大気とは“地球をとりまいている気体の層全体”のことであり、その“大気の下層部分=対流圏”のことを空気と呼ぶことが多いようです。大気のうち私たちの生活に特に縁の深い部分が空気であるとして不都合はないでしょう。
大気は、対流圏、成層圏、中間圏、熱圏・・・というように温度分布によって鉛直方向に幾つかの層をなしてながら宇宙空間に広がり、ここでおしまいという地点はありません。地球の重力によって地面に引き付けられている気体は、地面から離れるほど気圧が下がり薄くなって、この4区分では最後の熱圏の初め辺りの地上100kmを超えると宇宙空間と呼ばれる領域になります。ついでに、圏と圏との境目を圏界面(けんかいめん)と呼びます。

地表に最も近い対流圏は、極地上空と赤道上空ではその厚さに2倍近くも開きがあって、両極では9kmほど、赤道では17kmほど(季節変化あり)ですが、およそ10km(10000m)として話を進めます。この高度は多くのジェット旅客機がフライトするレベルだし、積乱雲の上部がカナトコ型に変形する場所でもあるので、地上から見ても分かりやすい高さだと思います。
大気が活発に“対流”する対流圏は、私たち人間にとっての生活の場であり、雲が湧き雨が降り風が吹くなど、あらゆる気象現象もここで生まれます。この空気の層はまさに生命の世界と言っていいでしょう。しかし、この厚さはわずか10kmで、時速60kmの車で10分という地上での距離感覚で捉えると、私たちの生活圏である対流圏がどれほど薄く限りあるものであるかが良く分かります。
この大気の組成は、窒素が約78%、酸素が約21%、アルゴンが0.9%・・・この3つの気体で99.9%を占めます。その他の0.1%の中に他の幾つかの微量気体が含まれるわけですが、地球温暖化で問題になっているCO2などはわずか0.035%程度に過ぎません。この0.035の中のさらに数%の変動が気温上昇や海面上昇など地球環境の深刻な問題を引き起こすわけですから、大気の組成だけをとってみても、私たちの自然世界がいかに絶妙な調和とバランスの上に成り立っているか良く分かります。更に忘れてはならないのが、水蒸気という気体としての水で、これは常に変動しながら、およそ0~3%の範囲でこの空気という混合気体に潤いを与えています。
さて、この空気、何気なく地上でじっとしているとその存在を意識することはほとんどありません。しかし、山に登れば徐々に、海に潜ればたちまち、その存在感が目の前に現れてきます。気象の変化に敏感な方は、身体の変調具合で低気圧や高気圧の接近による大気圧変動や湿度変化を感じ取ります。私の場合は、低気圧の接近と湿度の上昇が重なると、腹の調子がおかしくなったりします。
また横方向や縦方向に移動しても空気は“風”として感じられます。そもそも風とは“空気の運動”のことだから当然のことかもしれませんが、この風が私たちの飛行世界だけでなく、あらゆる生命にとってどれほど大切なものであるかについては、また徐々に考えてみたいと思います。
今回は、日常的には存在感の薄いこの空気をもっと量的に実感するために、幾つかの数字を見てみましょう。まず、空気の質量・・・これが案外重いのです。比重は水の約1000分の1などというと「やっぱり軽いな~」となるでしょうが、標準大気1㎥で1.2kgもあると言ったらどうでしょうか。6畳間の部屋は約30㎥ありますからこの中の空気を秤にかけると、36kg、子供一人分ぐらいの重さにはなる。

さらにこの中に、水蒸気つまり水がどれくらい含まれているかというと、もちろん温度・湿度によって違いますが、もし気温30℃、湿度100%の飽和状態だとすると900g・・・1リットルのペットボトル一本分くらいにはなります。現在の私の6畳部屋の温度が20℃、湿度が65%ですから、ここの水蒸気を全部水にすると540ml程度にはなるということです。
空気は決して空っぽの何かではなく、中身が相当ぎっしり詰まった、しっかりした物体であるということが少しはピンとくるでしょうか。私たちは空気という変動してやまない物体のいわば海の底に住んでいる生き物であり、空気中を滑空するということは、この濃密な物体の中を滑りながら落ちていくことを意味するのだ、などということはまた次回のお話にします。