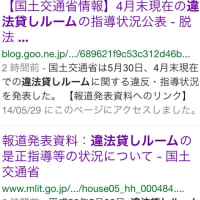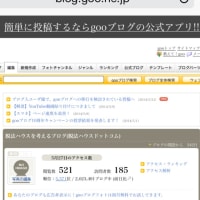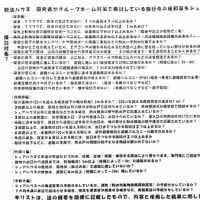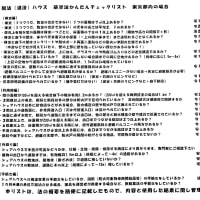このカテゴリーでは、シェアハウスの開設と運用に必要な建築法規について解説していきます。
通常、シェアハウスを開設するにあたり、
新たに新築する事例は極めて少ないと思います。
多くは既存の建物(それも格安物件)を活用し、
内装の改修を行ってシェアハウスのオーナーに
なられるのではないでしょうか?
そして、多くのオーナー様が、不動産屋や内装業者に
任せたきりになり、結果として怠ってしまうのが、
この「用途変更」の手続きであります。
では、どのような場合に用途変更の手続きが必要なのか?
条文をあたっていきましょう!
(用途の変更に対するこの法律の準用)
第八十七条 建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項及び第五項から第十二項までを除く。)、第六条の二(第三項から第八項までを除く。)、第六条の三(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十二項から第十四項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
2 建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第四十八条第一項から第十三項まで、第五十一条、第六十条の二第三項及び第六十八条の三第七項の規定並びに第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項及び第五項並びに第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定を準用する。
3 第三条第二項の規定により第二十四条、第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条から第三十五条の三まで、第三十六条中第二十八条第一項若しくは第三十五条に関する部分、第四十八条第一項から第十三項まで若しくは第五十一条の規定又は第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これらの規定を準用する。
一 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合
二 当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
三 第四十八条第一項から第十三項までの規定に関しては、用途の変更が政令で定める範囲内である場合
4 第八十六条の七第二項(第三十五条に係る部分に限る。)及び第八十六条の七第三項(第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条の三又は第三十六条(居室の採光面積に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、第三条第二項の規定により第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条、第三十五条の三又は第三十六条の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用する。この場合において、第八十六条の七第二項及び第三項中「増築等」とあるのは「用途の変更」と、「第三条第三項第三号及び第四号」とあるのは「第八十七条第三項」と読み替えるものとする。
またもや分かりにくいですね。
端的に言うと
「用途を変更して特殊建築物になるものは手続きが必要」という事です。
もう一つは
「類似の用途間での用途変更は、改修などを併せて行われなければ手続きは要りませんよ」
という事です。
ここで大事なポイントは、「手続き不要とは、法規を守らなくてよい」
ではないことです。
変更(改修)する部分には変更(改修)する時点で適用される法規を守る義務はあるということです。
そして、類似の用途間での変更でない場合、もしくは
新たに特殊建築物になる場合、
具体的には
★事務所ビルをシェアハウスにする
★倉庫をシェアハウスにする
★一戸建てをシェアハウスにする
★共同住宅の一室をシェアハウスにする
★ビルの上部のオーナー住戸をシェアハウスにする
★飲食店をシェアハウスにする
など
いずれの事例も変更する部分(シェアハウスの部屋だけでなく、
避難階までの階段やリビング、便所などの共用部分全てを合わせた合計)が
100m2を越えれば、用途変更の手続きが必要です。
元々が寄宿舎であるか、下宿であれば類似用途間での変更ということで、
改修を伴わなければ申請手続きは原則として不要です。
ちなみに、120m2の一戸建て住宅のうち、
1月1日に40m2をシェアハウスにし、その後1月2日に40m2をシェアハウスにし、
最後の1月3日に残り40m2をシェアハウスにすれば
それぞれ100m2を超えないので手続きを免れられるとお考えの皆さん!
残念でした。
特殊建築物になる部分の累計が100m2を超える時点で手続きが必要です。
例が2013年で、その10年後20年後でも同じです。
同様に、例えば70m2×3階建ての事務所ビルがありました。以前に1階を店舗にしています。
今回3階をシェアハウスにする時は、3階だけでなく1階が
も、さらに階段部分について用途変更手続きが必要という事です。
ただし、同じ例で既に2階をシェアハウスにしていた場合、
3階をシェアハウスに用途変更する申請は受付してもらえません。
2階を用途変更した時点で手続きを怠っているからです。
このように既に違反がある建物の申請は受付してもらえないので注意が必要です。
従って、用途変更に限らず、完了検査が行われていないなど
手続き違反のある物件では色々不利になります。
そして、新築時や途中で正当な手続きができないから、シェアハウスの手続きも申請なし
で行かざる得ないという悪循環に陥るのです。
(このあたりの考え方・手続き書類は役所によって異なります)
【管理人の意見】
この用途変更の考え方が、脱法ハウスを産み出す要因の一つである事を、
国は認識すべきです。
これからシェアハウス事業を始めようという方は、
寄宿舎や共同住宅からの改修を強くお勧めします。
それは、用途変更の手続き面ばかりではなく、
法規上寄宿舎系にだけ必要な規定である、○○○○、○○○○○○○、
○○○○を設け、○○○○や○○○○を確保するのが、
寄宿舎や共同住宅以外の用途からの改修の場合、
(郊外でもない限り)ほぼ100%実現不可能だからです。
次回以降はこの○○○○について見ることにいたしましょう。
通常、シェアハウスを開設するにあたり、
新たに新築する事例は極めて少ないと思います。
多くは既存の建物(それも格安物件)を活用し、
内装の改修を行ってシェアハウスのオーナーに
なられるのではないでしょうか?
そして、多くのオーナー様が、不動産屋や内装業者に
任せたきりになり、結果として怠ってしまうのが、
この「用途変更」の手続きであります。
では、どのような場合に用途変更の手続きが必要なのか?
条文をあたっていきましょう!
(用途の変更に対するこの法律の準用)
第八十七条 建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項及び第五項から第十二項までを除く。)、第六条の二(第三項から第八項までを除く。)、第六条の三(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十二項から第十四項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
2 建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第四十八条第一項から第十三項まで、第五十一条、第六十条の二第三項及び第六十八条の三第七項の規定並びに第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項及び第五項並びに第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定を準用する。
3 第三条第二項の規定により第二十四条、第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条から第三十五条の三まで、第三十六条中第二十八条第一項若しくは第三十五条に関する部分、第四十八条第一項から第十三項まで若しくは第五十一条の規定又は第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これらの規定を準用する。
一 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合
二 当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
三 第四十八条第一項から第十三項までの規定に関しては、用途の変更が政令で定める範囲内である場合
4 第八十六条の七第二項(第三十五条に係る部分に限る。)及び第八十六条の七第三項(第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条の三又は第三十六条(居室の採光面積に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、第三条第二項の規定により第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条、第三十五条の三又は第三十六条の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用する。この場合において、第八十六条の七第二項及び第三項中「増築等」とあるのは「用途の変更」と、「第三条第三項第三号及び第四号」とあるのは「第八十七条第三項」と読み替えるものとする。
またもや分かりにくいですね。
端的に言うと
「用途を変更して特殊建築物になるものは手続きが必要」という事です。
もう一つは
「類似の用途間での用途変更は、改修などを併せて行われなければ手続きは要りませんよ」
という事です。
ここで大事なポイントは、「手続き不要とは、法規を守らなくてよい」
ではないことです。
変更(改修)する部分には変更(改修)する時点で適用される法規を守る義務はあるということです。
そして、類似の用途間での変更でない場合、もしくは
新たに特殊建築物になる場合、
具体的には
★事務所ビルをシェアハウスにする
★倉庫をシェアハウスにする
★一戸建てをシェアハウスにする
★共同住宅の一室をシェアハウスにする
★ビルの上部のオーナー住戸をシェアハウスにする
★飲食店をシェアハウスにする
など
いずれの事例も変更する部分(シェアハウスの部屋だけでなく、
避難階までの階段やリビング、便所などの共用部分全てを合わせた合計)が
100m2を越えれば、用途変更の手続きが必要です。
元々が寄宿舎であるか、下宿であれば類似用途間での変更ということで、
改修を伴わなければ申請手続きは原則として不要です。
ちなみに、120m2の一戸建て住宅のうち、
1月1日に40m2をシェアハウスにし、その後1月2日に40m2をシェアハウスにし、
最後の1月3日に残り40m2をシェアハウスにすれば
それぞれ100m2を超えないので手続きを免れられるとお考えの皆さん!
残念でした。
特殊建築物になる部分の累計が100m2を超える時点で手続きが必要です。
例が2013年で、その10年後20年後でも同じです。
同様に、例えば70m2×3階建ての事務所ビルがありました。以前に1階を店舗にしています。
今回3階をシェアハウスにする時は、3階だけでなく1階が
も、さらに階段部分について用途変更手続きが必要という事です。
ただし、同じ例で既に2階をシェアハウスにしていた場合、
3階をシェアハウスに用途変更する申請は受付してもらえません。
2階を用途変更した時点で手続きを怠っているからです。
このように既に違反がある建物の申請は受付してもらえないので注意が必要です。
従って、用途変更に限らず、完了検査が行われていないなど
手続き違反のある物件では色々不利になります。
そして、新築時や途中で正当な手続きができないから、シェアハウスの手続きも申請なし
で行かざる得ないという悪循環に陥るのです。
(このあたりの考え方・手続き書類は役所によって異なります)
【管理人の意見】
この用途変更の考え方が、脱法ハウスを産み出す要因の一つである事を、
国は認識すべきです。
これからシェアハウス事業を始めようという方は、
寄宿舎や共同住宅からの改修を強くお勧めします。
それは、用途変更の手続き面ばかりではなく、
法規上寄宿舎系にだけ必要な規定である、○○○○、○○○○○○○、
○○○○を設け、○○○○や○○○○を確保するのが、
寄宿舎や共同住宅以外の用途からの改修の場合、
(郊外でもない限り)ほぼ100%実現不可能だからです。
次回以降はこの○○○○について見ることにいたしましょう。