「くりぼう」です。だいたい9月いっぱいは残暑に苦しみ、それが一段落したところで学会シーズンやらハロウィーン商戦やらで何となく時間が過ぎ、気が付いたら今年もあと少しという例年とおりの展開です。
ブログの方ですが、まっちい先生の孤軍奮闘を黙って見ているわけにはいきません。忙しさにかまけてなおざりの投稿ですが、忙しい師走のひととき、しばしお付き合い下さい。
さて、写真はこの時期に街でよく見かけるクリスマスのイルミネーションですが、これは私が通っていた大阪府の某歯科クリニックの外観です。酷暑・猛暑の夏から木々が色づく頃までの約4ヵ月間、十数回の通院で5本の虫歯を治療しました。治せど治せど指摘される虫歯、正しくは齲歯(うし)と呼びますが、その語源は「憂し」ではなかろうかと半ば本気で思ったものでした。
ちなみに写真のクリニックですが、大阪での勤務先から徒歩圏内にあります。激戦とされる業界で患者を確保するための方策なのでしょうか、年中365日、土曜日曜祝日はおろか、盆も正月も無関係に午前10時から夜の10時まで昼食休憩も一切関係なく診療がなされます。「忙しいから通えない」などという言い訳は一切通用しない、まさにぐうの音も出ない診療体制です。
5本目の虫歯の治療が終わったとき、「虫歯はこれで終わりましたが、親知らずは抜いておいたほうが良いかもしれません」と、予想もしない一言がありました。どうやら、下の親知らずは埋もれているため上の親知らずとは噛み合っておらず、その「上側の親知らず」が無用の長物となっているとのこと。現在その親知らず自体も虫歯となっており、さらに、隣接する歯との境界も歯ブラシが届きにくくなり結果的にはその隣の歯も虫歯になりやすいでしょう、との説明でした。なるほど、それなら親知らずの抜歯も止むなしか。
ただし最後に補足で、「レントゲン上は、おそらくすんなり抜歯できますが、例外もあります。また、どうしても今すぐに抜かないといけないというわけでもありません。」
まさに医療現場における常套句というか、逆にこのように言うしか他にないというか、「どうせ邪魔しかしない歯が虫歯なんだから、さっさと抜いたらいい」という医学的見解をダイレクトに言えない、そんな現代を象徴しているようでした。患者の自己判断による医療といえば聞こえはいいですが・・・自分も含めた大半の患者では、おそらくそれは最善ではないのでしょう。結局、思わしくない経過を辿ったときに、仮にそれが不可抗力であっても事が荒立ってしまう一部のケースのためのもの、本質的には契約書に付いてくる誰も読まないような長々しい約款なんかと大差ないのかもな、との思いを禁じ得ませんでした。
しかし、自分自身が行ってきた説明も、まさに全く同じ類のものであったことに気が付くのです。「手術したほうが良いとは思うが、こういう合併症もある。」手術した方が良い根拠、手術しなかった場合に想定される経過、合併症の頻度、あらゆる医学的見解を限られた時間に説明し、もうこれ以上言うことはない、どうだ、とばかりに、「手術なさるかどうかはあなたの判断です」と締めくくる。
最善の説明をした、言うべきことは言ったという自己満足とは裏腹、大半の患者さんは、結局どうしたらいいのかという迷いを拭いきれぬまま診察室を後にしていたことでしょう。結局のところ、後々あれこれ言うような患者さんが「最小限」になる方法を「最善の説明」と決め付けていただけなのかもしれません。
再診日、担当医から発せられた一言。「親知らず、抜いておきましょうね」
ポンと背中を押してもらって、気持ちが軽くなった瞬間でした。他の患者さんはどうか知らないけど、自分の場合はそれでいい、それがいい。極力担当医の言われた通りに治療したい。どうしますか、の問いは一度で十分だよな、と。
これがmajorityと判っていながら、minorityに左右される診療の姿勢。ジレンマでもあり、腕の見せ処でもあります。
虫歯の治療よりやや多めの(と感じた)局所麻酔薬を施されました。
「痛かったら言って下さいね」
十分麻酔が効いているから痛いはずはないだろうと思いながらも、普段から無意識のうちに発していたこのセリフ、今度は患者として全く同じように言われます。次の瞬間には、相棒に恵まれなかった哀しき運命の親知らずが無抵抗に引き抜かれ、「あれ、もう終わったんですか?」という患者すなわち私の問いかけに「まあ、こんなもんですよ」と微笑む担当医の姿は、同じ日に術後の患者さんに抜糸をした、己の日常そのもの。歪んだ口角は、キシロカインの作用だけではなかったはずです。
医療行為に際しては、やはり言うべきことは言っておく必要があります。当然です。最初のうちは、言い漏れを減らすように、統計学的に言うなら感度を高める検診的スタンスが無難でしょう。しかし、その時点で最善の説明に到達しているケースはむしろ例外のはず。そこから先は、己の臨床経験とコミュニケーション力で、患者さんの不安を削いでやる努力をせねばならないと思います。今回のケースであれば、「抜いてしまいましょう」と背中を押してもらったことが、それに相当するような気がします。
この不安を削ぐという作業ですが、度を超すと今度は「こんなはずじゃなかった」ということになり、線引きが難しいところでもあるため軽視あるいは敬遠されがちです。しかし、自分や肉親が患者になればその重要性は良く分かります。患者にとっての唯一の救いといっても良いかもしれません。こういう姿勢が潤滑油になると信じて、残り少ない今年の診療に臨みたいと思っています。



















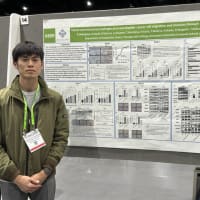

親知らずも確かに無い方が快適かも。