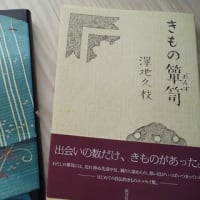ソテツ染の久米島紬が、仕立て上がりました!

創った方は高坂エミ子さんという、
大ベテランの伝統工芸士さん。
大き目の、伸び伸びした絣が持ち味だと聞いた。
袖を裏返すと……

こんな風に、袖口だけ裏地がついている。
単衣にありがちな「手首にくけた端があたる」のを防ぎ
袷のようにも単衣のようにも、見える。
裏地は……

赤い矢印の高さまでが、本来の八掛。
いわゆる「胴抜き」の場合は、この高さまでしか裏がない。
「そうすると、膝上くらいで色の段差が」と山本秀司さん。
そこで、緑の矢印まで羽二重を同じ色に染めてもらい、付け足すことに。
裾の一部をクローズアップ。

このように「フキ」が出ず、表と裏がぴったり
合わさっている(ほんの少し、表地が出ているかな)。
だから八掛をつけても、表からは単衣に見える。
でも、裾が翻ると裏地が見えるから、
「あれ? 袷? 単衣?」 どちらにも見える、というワケ。
今までにない、新しい仕立て方。
名前をつけましょうということで、
山本さんがはざま仕立て
と命名した。
袷と単衣の特徴を備えて、どちらの季節にも合う、という意味もあるし、
袷か単衣か悩む「はざま」の時期に、迷わず着られる、という意味もある。
昔ながらの更衣のルールが、そぐわなくなってきている昨今。
この仕立てだったら、盛夏以外はいつでもOK

どうしても胴裏をつけたい、
あるいは表から見たとき、フキで色のアクセントをつけたい、という
場合はともかく、
気楽に着られて体温調節もしやすいという点で、
とても有用な仕立て方だと思うのですが、いかがでしょうか。

雑になってしまいましたが、
先にご縁をいただいた、芽生え帯と合わせて。
これは着物友 キモトモTさんのお見立て。
この一揃いで早速、彼女とお出かけしました

レポートは、イベントスケジュールの都合により、
順番を後送りして週末にアップしますね。