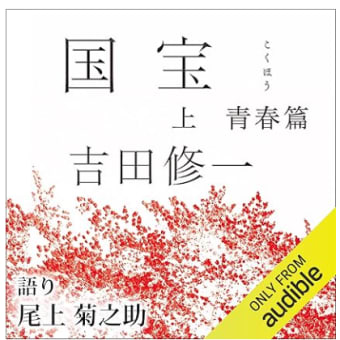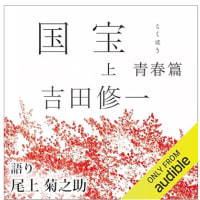1月末に、銀座で染織家・吉岡幸雄さんのご講演を聴いたことは、
以前ブログに書いたが、
その内容を後日…と、含みを持たせておきながら、
ずいぶん長いこと書けなかった。
今、当日いただいたレジュメを
読み直しているところだけど、記憶が薄れてしまって…。
源氏物語や、当時の文化に詳しい人にとっては、すでにご存じのことばかりに
なってしまうと思うが、
私の覚書程度、とご容赦いただければ…。
もっとも心に残ったのは次の2点。
1点目は、「権力が大きくなるほど、色の文化は発達する」ということ。
奈良、平安時代とも、蘇芳など輸入した原料も多かったそう。
絹もラオスや中国などから輸入していたとか。
日本国内にこだわるのではなく、むしろ「どこどこ(国の名前)に
とてもきれいな色を出す植物があるらしい」という話が伝わってくれば
ときの権力者は積極的に取り寄せたそうだ。
2点目は、
端的にいうと「襲の色目にマニュアルはない」ということ。
例えば、桜の季節をあらわすのに

こんなような取り合わせでもよし

これもあり、で、あくまで着る人や見立てる人のセンスに任されていたとのこと。
源氏物語の「玉鬘」の中に、「桜の細長(貴婦人の表着)」という表現が出てくるが、
これは表が白で裏が紫、または蘇芳とのことで、
桜の花が咲く直前に、葉が紫色を帯びる様子を表現しているそう。
桜ひとつとっても、さまざまだ。
源氏物語の時代の貴族は、
季節を感じられない=教養がない と見なされてしまうそうだが
感じているかいないかを襲のセンスで判断されるというのも
マニュアルがないだけに、なかなかシビアだったのではないだろうか?
結局、二人のフィーリング次第ということか。

これは「若紫」の途中、源氏が美しい少女(後の紫の上)を垣間見る場面で
「白き衣、山吹などのなれたる着て、走り来たる女子、
あまた見えつる子どもに似るべうもあらず、
いみじくおひさき見えて、うつくしげなる容貌(かたち)なり。」の
山吹はこんな感じだったのでは、と吉岡さんのお話から色を想像し、
合成してみたもの。
山吹といっても、当時はおそらく梔子で染めていただろうと
吉岡さんはお話しされていた。
桜が散った後は、山吹の季節。
その季節感を子どもの着物にまできちんと表現しているとは、
この家は教養があり、子どもも大事にされているのだろう、と、
源氏は思うわけである。
こうしてみると、色に対する感性は、昔はさぞ豊かだったのだろう。
今はどうか。人工のまぶしい光にいつも照らされているような環境では、
微妙な色の違いや季節による移ろいなど、わかりたくてもわからなかったり、
わかったつもりでいても本質はそうでなかったり、…なのかもしれない。
そこまでしなくても、今は「顔」を普通に見せられる時代。
季節を表現するセンスなど二の次で良いのだ。
それが例え、メイクやプチ整形などで「つくられた」ものであっても。
結局、ものごとの本質は、わかりたくてもわからなかったり、
わかったつもりでいても、そうではなかったり、…の繰り返しなのかもしれない。

 確かに昔は草木や虫など自然のもので染めていたわけですから、発色は化学染料のものとは違いますよね。どんどん褪せたり、変色したりしますし…。
確かに昔は草木や虫など自然のもので染めていたわけですから、発色は化学染料のものとは違いますよね。どんどん褪せたり、変色したりしますし…。 たいへんためになる、そしてイマジネーションが広がる奥の深いお話しをありがとうございます
たいへんためになる、そしてイマジネーションが広がる奥の深いお話しをありがとうございます
 ご著書たくさんお持ちなのですね、いいなあ…私も購入しようかな…
ご著書たくさんお持ちなのですね、いいなあ…私も購入しようかな…
 そうなんです、少なくとも源氏物語の時代にはそういうルールやマニュアルはなかったそうですよ。
そうなんです、少なくとも源氏物語の時代にはそういうルールやマニュアルはなかったそうですよ。 わぁ吉岡先生のご著書お持ちなのですね。どうしようかな、私も購入しようかしら。
わぁ吉岡先生のご著書お持ちなのですね。どうしようかな、私も購入しようかしら。