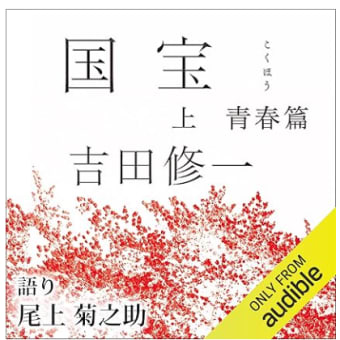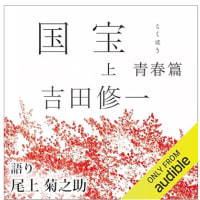20年以上前から
流行が生活に溶け込んだ、オシャレ感度の高い街として知られている。
その中心部にあるイベントスペース「ヒルサイドテラス」の一角で……

京都・西陣きっての実力派
「おび弘」「帯屋捨松」「織楽浅野」の三社展「織三蹟(せき)」が
開かれた(会期は終了しています)。
この日の私は……

ソテツ染めの白系の久米島紬に、読谷山花織の帯。初めてのコーデだ。
帯締めに青の入った一本を選んだので、
帯揚げも青に。明るすぎると、春先にしては“浮いて”しまうので、
滅多に使わない、少し渋みのある青にした。
--------------------
さてこの展示、販売をともなわず、
「西陣の最高峰の技術を見ていただきたくて」(おび弘さん)
さながら「織の美術展」といったところ。
写真撮影もご自由にどうぞ、とのことで、印象に残った作品を
あれこれ、カメラに収めてきた。
例えば、おび弘さんの展示では……

ティファニーのステンドグラスをモチーフにした、この本袋帯は
右の拡大図でいうと、地と白い葉が綴れ、黄色の葉が唐織、
紫の地にところどころ入っている銀の雲が箔、と
技の複合で織り出されている。
しかも、地の部分の綴れと、白い葉の綴れでは、経糸の本数を変えている。
(そのため、白い葉の方は組織がやや粗い)
織り方も違えば、糸の太さも違ってくるから、
素人考えでは、とうてい同じ帯幅に織れそうにない、と思ってしまうが、
そこは熟達した職人さん、織りながら「ここはきつめに打ち込もう、こっちはゆるめに」
と調節しているそう。

これは、ブルックリン橋をモチーフにした本袋帯(部分)。
このとき、複数の人が帯の周りにいて、いくら撮影OKといっても
堂々とカメラを取り出すのは憚られたので、
撮ったのはお太鼓部分のアップだけだったが、
実は裏面にはビッグアップルをもじった「リンゴ柄」が織り出されていて
とても洒落ていた。
これも、紺の地(夜空)部分は80枚綴れという、経糸が一定幅に80本ある細かい織地。
それに対し、白い塔は20枚綴れで、地よりは組織がやや粗く見える。
これを織れる人は、おび弘さんの中で4人しかいないそう。
高齢化が進んでいて、最年少でも51歳、上は70代と聞いた。
ちなみに……

源氏物語をモチーフにしたこちらの本袋帯は、
同じ柄の繰り返しではなく、上から下まで絵がつながっている。
「これ、デザインを起こす人が、たいへんですよね?」訊ねたところ、
写真右のような“紋紙”(織りの型紙)をつくるのに、半年はかかると
おっしゃっていた。
「織るのに要するのは2カ月くらい。それより紋紙をつくる方が、時間がかかるんです」
-----------------
場所は変わって、こちらは帯屋捨松さんの会場。

記念に撮っていただきました。
後ろの唐織、カラフルで芸術的ですね!
「単色で見ると、紫や青は派手できついのですが、
デザインに溶け込ませると、程よくうちらしさが出る。
それを考えながら、色を決めるのです」(捨松さん)
捨松さんのコーナーには、博物館級の展示もあり

こちらは古い金唐革。
(私の記憶では、なめした革に型で凹凸をつけ、金箔を貼り打ち込む…だったような。
コチラの過去記事が参考になるかも)
写真では見難いですが、この柄を帯に再現したのが右の一本。

こちらは捨松さんに伝わる古裂。時代はさまざまだそう。
これらを復元したり、ヒントを得て新たな図案を起こしたりして、
帯のデザインにすることも多いと、捨松さんはおっしゃっていた。
------------------
そして、この展示のご案内をくださった織楽浅野さん。
何と言っても目を惹いたのは

フレッシュな萌黄にガーゼのようなパウダリーな白を重ねた帯。
写真ではなかなか、洗練されたたたずまいが伝わりませんが……。
「藤田嗣治の描く“白”にインスパイアされたんです」(浅野さん)
写真左に見きれてしまったが、乳白色ですべらかな質感。
私にとっても藤田の白は、昨年ブリヂストン美術館で見て以来、とても好きな色の一つ。

フラッシュなしなので写りが悪いですが……
この、ラベンダー色の葉っぱのような凹凸が連なった帯も
とーってもスタイリッシュ。
確か、浅野さんがルーマニアに行ったときに見かけた、フランスのフライパンの柄、
と聞いたような(違っていたらスミマセン)。
世界を旅して、鋭い感性でデザインのエッセンスを持ち帰る、
浅野裕尚さんは今回の、お三方の中でもアーティストの気風がとても強い方だと思う。

「息子を紹介します」
何と、浅野さん親子とスリーショット。光栄です!
「ま、2年くらいしたら、俺の代わりにぺらぺらしゃべりよるな」
今はお父様の元で修業中だそうですが、
にこやかで人当り良く、織楽浅野の次代として頼もしい限り。
-----------------
こんな風に、百貨店でもそう何本も置いていない逸品が
一堂に会する展示は、
一般の人にとって「佳き物を見る目を養う」意味でとても貴重。
加えて、この三社は特色がかっちり分かれていたので、展示内容にも変化があり
西陣と一言でいってもさまざまなアプローチ、たくさんの技があるんだなあと
思わせるのに十分だった。
なかなか、こうした逸品には、個人的には縁がないけれど、
日本にはこんな優れた伝統工芸があることを誇りに思い、伝えていきたいなと
心から思った。