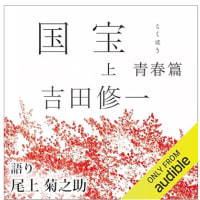ここは関東平野の北限。
父の介護認定のための調査が入る日、
私も立ち合うために、再び帰省しました。

父は昨年から何度か転倒しており、
幸い大事には至っていないのですが
先週も、玄関先で尻もちをついたそうで
以降、家の中でも杖が手放せなくなってしまいました。
健康な若い人なら、取るに足らない程度のアクシデントでも
高齢になるとあっと言う間に、運動機能のレベルが落ちてしまいます。
認定調査を受けたことがない人向けに、
概要をお話ししますと
うちの場合は女性の調査員が1名いらして
約75項目、1時間にわたり、質問をしながらチェックしていきます。
「今日の日付はわかるか」「生年月日は言えるか」
「急に怒りだしたり泣いたりするか」「見えないものを見えるといったりするか(!)」
などの認知症関連の項目や
「着替えは一人でできるか」「顔は自分で洗えるか」「足の爪を自分で切れるか」
「買い物はどうしているか」
などの日常生活動作の項目が中心で
足やひざがどのくらい上がる(曲がる)か、腕はどうか、といった
簡単な身体状態チェックもありました。
家の中の視察は行いません。
私としては、うちの浴室が古い造りで浴槽が深いのも
見ていただきたかったのですが、そういう役目はないようです。
調査員さんは高齢者の対応に慣れていて、
とても親切に接してくださり、
和やかなムードで話が進みました。
父も、(人によっては他人に弱いところを見せたくなくて
強がりを言ってしまうケースもあるようですが)
私が介護認定のために帰省の時間をつくったことをわかっているし
実際、足が不自由になりつつあり困っているので
出来ないことはできない、と、やや強調気味に主張してくれたので
あとは自治体の判断に任せるしかないです。
この調査結果と、主治医の意見書(認定を受ける本人が
医療機関でもらってくる必要があります)をもとに
自治体で審査会議が行われ、約1カ月後に認定結果が出ます。
下された認定は、原則最低1年間は継続しますが、その間に
病気や怪我などで要介護の度合いが強まれば1年を待たず再認定を
受けることはできます。
うちは、浴室と階段に手すりをつけるのが希望なので
要支援1さえとれればいいのですが…どうなるでしょうか。
→受けられるサービスは、おもに福祉用具の貸与、屋内工事、
リハビリ指導で(年金)所得に応じ1~3割の自己負担
それにしても、たまたまここ2年程、
書籍の仕事で地域包括ケアシステムや介護制度の勉強をする機会があったおかげで
地域包括支援センターの方や、市の福祉課の方ともスムーズに話ができ
良かったです。
とても堅苦しい話になってしまいましたが
記録の意味合いも兼ねてアップしました。